デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくる
工藤青石
宣伝会議
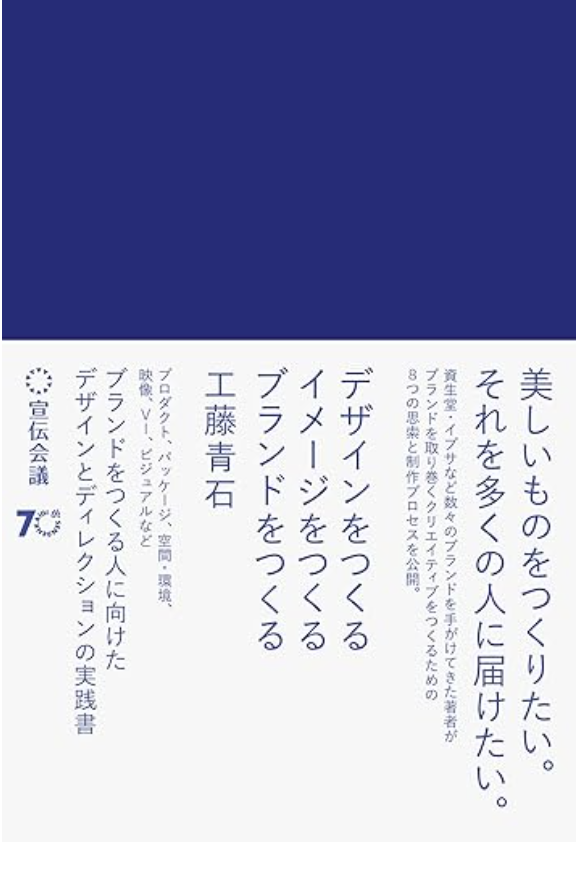
デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくる(工藤青石)の要約
『デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくる』は、工藤青石氏の豊富な経験に基づき、「つくるとは何か?」を多様な視点から探究した一冊です。「イメージは創る」「ブランドは造る」という言葉に象徴されるように、ブランドは表面的な演出ではなく、信念と美意識を積み重ねた結果として形づくられます。本書のデザイン論は人生にも応用できます。良い人生を「つくりたい人」に深い気づきと行動のきっかけを与えてくれます。
スタイリングではなくデザインを──“本物”をつくるための思考の型
「つくる」ということは、人が得た最大の能力の一つではないかと考えます。ですから生きていく上で「つくる」ということは誰にとっても魅力的なことであり、多くの人がそれを欲するのではないかと感じています。(工藤青石)
「つくる」という行為は、誰にとっても本質的な欲求であり、生きる力の源泉である——そう語るのは、デザイナーとして長年第一線を走り続けてきた工藤青石氏です。デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくるは、そんな氏の豊富な経験と深い洞察、そして独自の美意識が凝縮された一冊です。
本書は単なる実務書にとどまりません。デザインとは何か、ブランドとは何か、そして「つくる」とはどういう営みなのか。そうした根源的な問いに対して、工藤氏は自らの体験と実践をもとに丁寧に向き合い、読者に思考のきっかけを与えてくれます。 そこにあるのは、工藤氏の成功事例の羅列でもなければ、テクニックの紹介でもありません。「どう見せるか」ではなく、「どう考え、どう生み出すか」に焦点を当てた、本質的なデザイン論なのです。
本書の特徴は、デザイン、イメージ、ブランドといった一見すると異なる概念を、「つくる」という共通の行為によって貫いている点にあります。ビジュアルやマーケティングのテクニック論ではなく、それらの根底にある“意志”や“姿勢”に焦点を当てています。表層的なデザイン論ではなく、目的に向かって何をどう考え、どう表現し、どうかたちにしていくか。そのプロセスこそが、「つくる」という行為の本質であると工藤氏は語ります。
工藤氏は23歳で資生堂に入社し、化粧品のパッケージデザインを皮切りにキャリアを積み上げてきました。その後、パリへの駐在を経て欧米・アジアでのプロジェクトに携わり、40歳で独立。以来20年以上にわたり、自らの会社で実務に取り組みながら、国内外のブランドのクリエイティブに深く関わり続けてきました。
本書の随所で印象的なのは、「美しさ」とは何かという問いです。著者はデザインを「ものことを、結果として美しくすること」と定義しています。この「結果として」という言葉に、デザインに対する深い哲学が表れています。美しさは、意識的な選択と緻密な設計の積み重ねによってのみ生まれるものであり、単に見た目が整っているだけでは、決して“美”とは呼べないと著者は指摘します。
美しさとは、つくり手の誠実な姿勢と、時間をかけた思考の積み重ねから生まれるものです。著者は、見た目の装飾ではなく、「どのように考え、どう実現したか」というプロセスこそが、美をかたちづくると語っています。
たとえば、あるプロジェクトが実際に社会の中で機能し、多くの人に支持され、長く継続されるのであれば、それは「美しい結果」と言えます。そしてそれは、しっかりと「デザインされたもの」とも言えるのです。
真のデザインは、目に見える表面だけにとどまりません。むしろ、プロジェクトの目的や設計、進め方、成果の出し方といった“見えにくい領域”こそが、デザインの本質的な対象になります。著者は、こうした見えない部分を丁寧に設計することこそが、プロフェッショナルに求められる本当の仕事だと述べています。
表面的な見栄えだけではなく、「なぜそれをやるのか」「どうすれば持続可能なのか」を考え抜き、かたちにしていく。その積み重ねこそが、本物の美しさを生み出すのです。
近年、SNSやAIの進化により、誰でも「それっぽく」見えるものを手軽につくれるようになりました。しかし著者は、こうした表層的な見栄えに頼る行為を「スタイリング」と定義し、デザインとは区別します。スタイリングは模倣やアレンジの範疇であり、本質を捉えた「つくる」とは一線を画すものだと指摘します。
世界には、「本当にデザインされたもの」はごくわずかしか存在しないと著者は述べています。その理由は明快です。現代のものづくりの現場では、スピードやコストが優先され、「本当に考えて、時間をかけてつくる」ことが難しい状況にあるからです。けれども、そうした中でも一握りの「本物のデザイン」は、人々の心を動かし、長く愛され、社会に価値を与え続けるのです。
著者はまた、「つくること」は決してデザイナーやクリエイターだけの特権ではないと語ります。日常の中で、私たちは無意識のうちに、言葉をつくり、人間関係をつくり、時間の使い方をつくっています。つまり、誰もが「つくる人」であり得るという視点です。この考え方は、ビジネスやデザインの専門家だけでなく、すべての生活者に対して「自分の生き方を主体的につくる」という視点を促してくれます。
本書を読み進めるうちに、私たちは次第に、目に見える結果よりも、その思考のプロセスや他者とのコミュニケーションにこそ価値があることに気づかされます。見えない部分へのこだわりが、やがて見える成果につながる。それは言い換えれば、日々の選択や姿勢の積み重ねが、未来の美しい結果を形づくるということです。
真のブランドの8つの要素が教えてくれるブランドの本質
デザインがイメージを創る。イメージがブランド造る。ブランドがイメージを発する。
工藤氏のブランド論に触れて、もっとも印象的だったのは「つくる」という行為に対する深いこだわりです。氏は、ブランドとは単に商品やロゴを整えることではなく、「イメージ」をどう創り出し、どう社会と共有していくかの営みだと語ります。 ブランドには、強いイメージが必要です。
そしてそのイメージは、表層的な広告やマーケティングではなく、本当のデザインや本当のアートからしか生まれないと工藤氏は言います。美意識と思想に裏打ちされた創造だけが、人の心を動かし、記憶に残るブランドを生み出すのです。
ここで特筆すべきは、工藤氏が「イメージは創る」「ブランドは造る」と明確に言葉を使い分けている点です。この使い分けには、ブランド構築に対する深い哲学が込められています。「創る」は、感性や美学をもとに、まだ形になっていないものに命を吹き込む行為です。
一方、「造る」は、創られたイメージをもとに、社会に根づく構造を築いていく営みです。つまり、ブランドとは、創られたイメージをもとに“造り込まれていく”ものであり、表面的な装飾では成立しないというメッセージがそこに込められているのです。
工藤氏は、「つくる」という言葉に終わりはないと述べています。ブランドは完成して終わるものではなく、育て続けるものです。時代や社会の変化に応じてアップデートされながらも、根底には揺るがない信念と世界観が存在し続けなければなりません。その意味で、ブランドとは“続ける覚悟”を問われる存在とも言えます。
このようにブランドとは、単なる「名前」でも「ロゴ」でもありません。それは、見る者の心に残る“イメージの結晶”です。そして、この結晶が磨かれていく過程には、厳しい美意識と、一貫した哲学があります。 フランスの名門ラグジュアリーブランドが加盟するコルベール委員会は、ブランドに求められる8つの条件を挙げています。
フランスの コルベール委員会が唱えるブランドの定義は次の通りです。
1 歴史や物語があること
2 研究や技術の蓄積があること
3 高品質で、それにふさわしい価格設定であること
4 人から人へ手渡しされるものであること
5 ブランドのポジショニングを高めるために、マーケティングが厳しい自己規制を行っていること
6 創業者、経営者の人間性が見えること
7 伝統を大切にしながら、絶えざる革新を行うバイタリティがあること
8 世界的であること
これらはただのチェックリストではありません。ブランドの「魂」を形成する8つの精神的支柱とも言ます。 一流のブランドは、曖昧さを拒みます。すべての判断は「美」に通じており、表現、製品、サービスの隅々にまでそのこだわりが貫かれています。
「何を伝えたいのか」ではなく、「何を感じさせたいのか」にまで意識が及んでいるのです。たとえば、エルメスのオレンジの箱を見ただけで、多くの人が“美意識と格式”を想起します。メルセデスのボディラインには、単なる工業製品を超えた「誇り」や「伝統」が投影されています。それは、長い時間をかけて積み重ねられた物語が、形や色や質感を通じて伝わってくるからです。
こうしたブランドの力には、「時間を超えて関わろうとする意志」が込められています。商品そのものというよりも、それを手に取る人の人生そのものに深く寄り添おうとする姿勢があるのです。
だからこそ、「創業者や経営者の人間性」が問われるのです。人間の顔が見えないブランドは、いずれ顧客の心からも消えていきます。 そして、伝統に寄りかからず、革新を恐れない。それが一流ブランドの共通点です。古典に学び、現代に挑む。まさに、時間軸を自在に往来するような柔軟さと覚悟が、ブランドの未来を切り拓いていきます。
最終的に顧客が惹かれるのは、そのブランドの一貫した世界観です。商品を超えた「美の体験」「文化の共有」「生き方への共鳴」こそが、ブランドへの信頼を生むのです。
ブランド構築において本当に問われるのは、マーケティングのテクニックではありません。揺るぎない美意識と、時間という名のフィルターを通してなお残り続ける哲学こそが、ブランドの本質です。 一時的なトレンドに流されるのではなく、「何を守り、何を捨てるのか」を問い続ける姿勢が欠かせません。そこにこそ、そのブランドらしさが宿ります。
経営者に求められるのは、目先の反応ではなく、10年後にどう語られていたいかという視点です。ブランドとは、短期的な成果を積み上げるものではなく、顧客との長期的な約束をかたちにしていく営みなのです。 だからこそ、ブランドは一貫性と覚悟の証でもあります。「今、この瞬間の最適」ではなく、「時間に耐えうる価値」をどう造り出すか。その問いと向き合うことが、ブランドを築く最初の一歩になるのです。
本書は、ものづくりやブランドづくりに携わる方だけでなく、「自分の人生をどのように設計していくか」を考えたいすべての人にとって、大きな気づきと考えるきっかけを与えてくれる一冊です。 工藤氏の言葉に触れることで、自分の中にある価値観や信念の輪郭が少しずつ浮かび上がり、思考の軸が整っていくのを感じます。
さらに、本書は私たちの思考や行動にも影響を及ぼします。何を選ぶのか、どんな美学に従うのか、何を「創り」、何を「造って」いきたいのか。日々の選択や働き方、生き方そのものに、「つくる人」としての意志が宿りはじめるのです。
ブランドは特別な人だけが語るものではありません。私たちは皆、日々の営みの中で、自分という存在を“つくり続けている”のだと気づかされます。プロダクトであれ、関係性であれ、自分のキャリアであれ、すべては「創造」の対象です。
だからこそ、「自分は何をつくりたいのか」と問い続けることが、すでにひとつの“デザイン”であり、未来のブランドにつながっていくのだと、本書は教えてくれます。




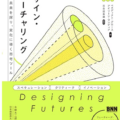









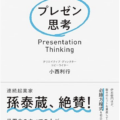
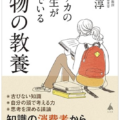
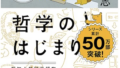

コメント