だれもわかってくれない 傷つかないための心理学
ハイディ・グラント・ハルヴァーソン
早川書房
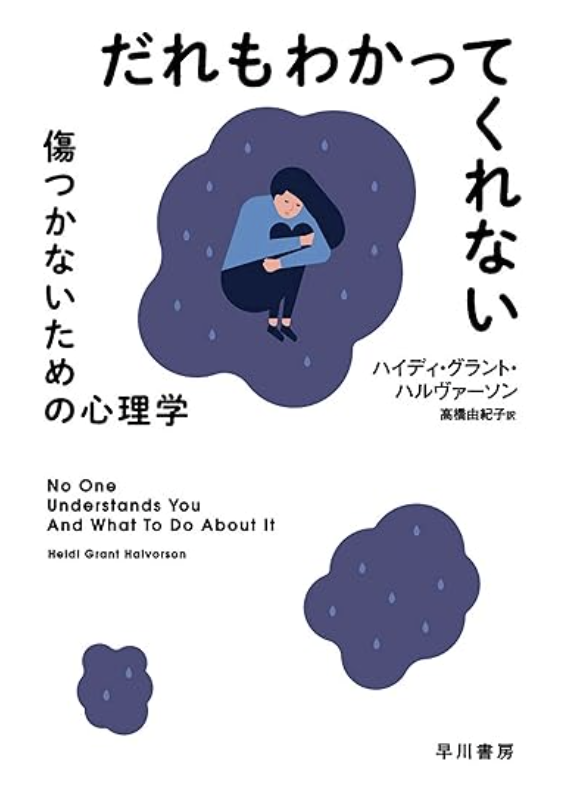
だれもわかってくれない 傷つかないための心理学 (ハイディ・グラント・ハルヴァーソン)の要約
人との誤解は、自己認識と他者認識のズレから生まれます。本書では、私たちが無意識にかけている「認知のレンズ」がその原因であることを、科学的根拠とともに明らかにしています。促進型・予防型といった思考傾向の違いや、信頼・権力・エゴといった視点が、どのように相手の評価や反応を左右するのかが丁寧に解説されています。自分の意図を正確に伝え、信頼関係を築くためには、相手の見ている世界を理解し、それに合わせて表現を選ぶ必要があります。
人が誤解される理由
認めたくない事実ですが、私たちは自分がこう見られたいと思うようには、他人から見られていません。人間は、自分を完全に客観的に見ることも、他者を客観的に見ることもできないからです。私たちには、他者の自分に対する反応を自分の見方に合うように歪めてしまう強い傾向があります。このことは、たとえ頭でわかっていても、それが実際に起きているときに気づくことはまずありません。(ハイディ・グラント・ハルヴァーソン)
私たちは日々、誰かとのコミュニケーションに悩みながら生きています。職場で一生懸命に提案したのに、返ってきたのは冷ややかな反応だった。良かれと思って動いたことが裏目に出て、関係がぎくしゃくしてしまった。そんな経験、きっと一度や二度ではないはずです。
実は、自分が「こう思われているだろう」と信じているイメージと、他者から実際にどう見られているかの間には、想像以上に大きなギャップがあるのです。人間は、自分自身を完全に客観的に見ることも、他者を正確に理解することもできません。さらに私たちは、他者の反応を自分の望むイメージに合うように無意識のうちに歪めてしまう傾向があるのです。
社会心理学者のハイディ・グラント・ハルバーソンは、この認識のギャップがもたらす問題を科学的に解明し、その解決策をだれもわかってくれない 傷つかないための心理学で明らかにしています。本書を読むことで、私たちは自己認識と他者認識のズレを理解し、より効果的なコミュニケーションができるようになります。(ハイディ・グラント・ハルバーソンの関連記事)
私たちは、思っている以上に「伝わっているつもり」で毎日を過ごしています。「こんなに一生懸命やっているのに、なぜ伝わらないんだろう」「どうして、わかってもらえないんだろう」——そんなモヤモヤを感じたこと、きっと誰にでもあるはずです。もちろん、私にもあります。
自分の意図や感情は、言葉や態度に乗せればきちんと相手に伝わっている——そう信じたい。でも現実には、その多くが伝わっていないのです。相手には見えているはずだ、わかってくれているはずだ、という思い込みが、誤解を生み、人間関係のズレをつくります。
この錯覚こそが、コミュニケーションにおける多くの問題の根源となっています。キャリアの停滞、チームの不和、ビジネスチャンスの逸失といった、深刻な結果を招くことさえあるのです。
もう一つの理由は、人が他人を、自分が見たいように見てしまうという点です。他者の本質や意図を正しく理解することは、簡単ではありません。そのためには、以下の4つの条件が満たされる必要があります。
・認識する側に、情報が与えられること
・その情報が、意味を持つものであること
・認識する側が、その情報に気づいて注目すること
・認識する側が、その情報を正しく使うこと
これらが揃って初めて、私たちは他者を正確に理解することができるのです。
人間は認識にエネルギーをケチる。
脳は非常に多くの情報を処理しなければならないため、できるだけ少ないエネルギーで認識を済ませようと、無意識に「省エネモード」に入ります。その結果、他者を理解する際にも、ショートカットや憶測を多用する傾向があります。私たち人間は「認知倹約家」なのです。
このような認識の努力をケチる私たちが好んで使う手抜きツールのひとつが、「ヒューリスティクス=思考のショートカット・経験則」です。これは、「すぐに思い浮かぶことは、より頻繁に起こっているように感じられる」といった思考のパターンを指します。
ヒューリスティクスは多くの場合、妥当な結論を導きますが、時に私たちを見当違いの方向に導くこともあります。 もうひとつの代表的な手抜きツールが「憶測」です。これは、相手があなたのどこに注目するか、その情報をどう解釈するか、そしてそれをどう記憶に残すかという一連のプロセスに影響を与え、認識の重要な部分を形づくるものです。
思考のショートカットや憶測には、以下のような具体例があります。
・確証バイアス(Confirmation Bias) 自分がそこに見出すだろうと予測しているものだけをみる
・初頭効果(Primacy Effect) 第一印象に引きずられる
・ステレオタイプ 出自や性別、外見、所属、社会経済的階層などのカテゴリーに基づく思い込み
・ハロー効果 一つの長所が他の面まで優れていると思わせる
・偽の合意効果 本当は意見が分かれている場面でも、「みんな自分と同じはず」と思い込んでしまう
・偽のユニークネス 自分は他人とは違う、よりユニークで優れている」という思い込みや錯覚
これらの認知バイアスは、誰にでも起こりうるもので、知らず知らずのうちに他人の考えや行動を正しく理解できなくなる原因となります。そのため、自分がどう見られているかも、このバイアスによって歪められてしまうのです。
わかりやすく言うと、誰もが「自分の考えや感じ方が普通で、多くの人も同じだろう」と無意識に思い込みやすいので、その思い込みが他者との誤解やすれ違いを生みやすいのです。
人間の認知を歪めてしまう3つの「レンズ」
「フェーズ1」では、認識する側の人間は自分が見ると予期していること(何を予期しているのか意識しなくても)しか見ないのです。
本書では、人間が他者を判断するプロセスとして、「認識の第1段階(フェーズ1)」と「認識の第2段階(フェーズ2)」の2段階モデルが提示されています。
フェーズ1は、思い込みや直感に基づいて自動的に判断する段階であり、以下のような特徴があります。
・本人が気づかないうちに起こる
・意識的な意図なしに起こる
・特に努力を必要としない
・コントロールが難しい
多くの認知はこのフェーズ1で止まってしまい、ショートカットや憶測に支配されます。つまり、認知的倹約家としての人間の性質がここで強く現れるのです。これはダニエル・カーネマンのファスト&スローのシステム1に当たります。
フェーズ2では、最初の印象を努力して修正します。
・意識的に考え、修正する
・注意力とモチベーションが必要になる
フェーズ2に進むことで、ようやく文脈や個別事情を考慮した、より正確な認知が可能となりますが、残念ながら多くの人がこの段階までたどり着けていないのが現実です。カーネマンのシステム2に当たります。
本書の中盤では、人間の認知を歪めてしまう3つの「レンズ」について解説されています。「信用レンズ」は、相手が味方か脅威かで評価が変わるバイアスです。信用できる相手、自分に利益をもたらす相手は高く評価され、そうでない相手は低く評価される傾向があります。
判断の基準は「温かみ」と「能力」に関わると、ハーバード大学の心理学者のエイミー・カディは指摘します。温かみは「相手の味方になろうとしていることの現れ」、能力は「その意図を実行できる力があるか」という観点です。
「温かみ」を伝えるには、相手に注意を払うことが大切です。話している間に目を合わせる、微笑む、うなずいて理解を示すといった基本的な態度が効果的です。状況によっては共感を示したり、相手を気遣ったりすることも大切です。一番大事なのは、誠実さとウソのない姿勢です。こちらが先に相手を信用し、安心させることも有効な手段です。
また、「能力」を示すためにも、目を合わせることが効果的です。加えて、背筋を伸ばして座ること、個人的な心配事を過度に話さないこと、そして卑下も自慢もしすぎないことが求められます。やや謙虚な姿勢を保つことで、相手に良い印象を与えることができます。
「パワーレンズ」は、上司や権力者など、力を持つ人が変わるというバイアスです。力のある人は、弱い立場の人に対する見方が歪む可能性がある一方で、弱い立場の人が強い人に対する見方を歪めることはめったにありません。もちろん、弱い立場の人が力のある人に対して怖れや妬みを抱くことはありますが、それはしばしば一時的な感情にとどまります。
パワーを持つ人は、多くの場合あなたのことを正確に認識してくれません。その理由は、彼らが自分の目標達成に集中しており、他者の問題や考えにまで注意を払う余裕がないからです。そのため、彼らはショートカットを用いて大まかに理解し、他者の複雑で微妙な側面までは見落としがちになります。
彼らが本気で人を理解しようとするのは、目標を達成するために必要なときだけなのです。 他者のエゴレンズに対応するには、謙虚に振る舞い、相手を事実に基づいて褒め、「自分たちは同じ側の人間だ」と伝えることが有効です。
「エゴレンズ」とは、自己肯定感を守るために働く心理的バイアスです。人は誰しも、自分が他者より優れていると信じたがる傾向があり、それが脅かされると防衛的な態度を取りやすくなります。容姿や能力、経済力など、自負している部分が否定されそうになると、「エゴレンズ」が強く作用します。
このレンズは、自己肯定感を保ち、自信を持たせる役割を担います。通常の人であれば(極端に落ち込んでいない限り)、自分に対して基本的にポジティブな見方をしており、一定の自己肯定感を持っています。
自己肯定感とは、自分の評価や記憶、強みと弱みを含む総合的な自己イメージです。中でも、自分の本質に深く関わる要素は特に重要視されます。 他人もそれぞれ異なる自己肯定感を持っており、それは「何を大事にしているか」によって左右されます。
相手の「エゴレンズ」がどのようなバイアスを生むかを知りたいなら、その人が重視している価値観を探ってみましょう。多くの人は、仕事や知性、地位、外見などを大切にしています。 もし、相手の自己肯定感を脅かすような言動をとると、「エゴレンズ」が働きやすくなります。それを避けるには、謙虚な姿勢を示し、相手に肯定的な態度を伝えることが有効です。
プロモーションフォーカスレンズとプリベンションフォーカスレンズ
「促進」に焦点が合うメガネをかけた人は、身のまわりにある達成、報酬、成功などの機会に目が留まります。経済の言葉を借りれば、人生にとって大事なことは「利益を最大にし、機会を逃さない」ことだと思っています。
人の性格や傾向に応じて、私たちは「プロモーションフォーカスレンズ」と「プリベンションフォーカスレンズ」という2種類のレンズを通して世界を見ています。前者は希望やチャンスを重視し、前向きなアプローチを好みます。達成や成功といったキーワードに心を動かされ、利益を最大化することや、チャンスを逃さないことに価値を見出します。起業家のリチャード・ブランソンのような人物は、その典型例と言えるでしょう。
一方で、プリベンションフォーカスレンズをかけた人は、損失や失敗を避けることに意識が向きます。安定や安全を守ることを重視し、義務や責任を果たすことに価値を見出します。これは、利益を追求するというよりも、損失を最小限に抑えるという考え方に近く、現状を維持することが最優先となるのです。
どちらのレンズで物事を見るかに正解はありません。実際、数十年にわたる研究でも、促進型と予防型のどちらが優れているという結果は出ていません。どちらのタイプも同じように有能であり、満足した人生を送っていることがわかっています。
違うのは目標に向かうアプローチの方法であり、使う戦略、強み、好み、そして陥りやすい落とし穴がそれぞれ異なるという点です。
促進レンズをかけた人は、称賛によってやる気が高まる傾向があり、逆に予防レンズをかけた人は批判によってモチベーションが上がります。また、予防型の人は失敗の兆しが見えるとすぐにあきらめることが多く、促進型の人は逆に引き際を見失いやすいという特性もあります。
このように、人がかけているレンズによって、説得されやすい言葉や納得する根拠が異なります。ですから、同じアイデアであっても、それをどう伝えるかによって、相手の受け取り方は大きく変わってきます。 たとえば、自分の意見や考えを正しく理解してほしいと思うなら、相手がどのレンズを通して世界を見ているかを意識することが重要です。
促進レンズの人には、提案を「潜在的な利益」や「前向きな変化」として伝えると効果的です。「これをすれば、もっと良くなる」といったポジティブな未来を描くことで、相手の感情を動かすことができます。
反対に、予防レンズの人には「リスク回避」や「失敗防止」の視点で話すと伝わりやすくなります。「これをしないと危険です」といった具合に、現実的で慎重なトーンが必要になります。
人間関係においては「愛着レンズ」も影響します。育った環境によって、人は他者への信頼や距離感に違いが生まれます。安定した愛情を受けて育った人は、他人を信じやすく、不安の少ない関係を築こうとします。
逆に、不安定な愛情を経験した人は、他者への依存や不安を感じやすく、また愛情を得られなかった人は、人と距離を取ろうとする傾向が強くなります。 もし誤解を与えてしまったときには、圧倒的な証拠を示したり、相手が自然と意見を修正したくなるように働きかけることが有効です。
また、相手にとって欠かせない存在となる努力をしたり、自分に非があるなら素直に謝る姿勢も大切です。信頼関係を築くには、感情的な共鳴だけでなく、現実的なアプローチが必要なのです。
この本には、対人関係に悩んでいる人が、一歩踏み出すためのヒントが数多く詰まっています。コミュニケーションのすれ違いに頭を抱えたとき、自分の価値が正しく伝わっていないと感じたとき、どう行動すればいいのか。その答えが、科学的な知見とともに、わかりやすく丁寧に示されているのです。
他者から評価されたいなら、ただ待っているだけではダメなのです。自分の考えや意図を届けたいなら、伝わるように言葉を選び、相手の立場や見え方を想像しながらアプローチしていく必要があります。誤解されることを恐れるより、正しく理解されるための工夫を重ねていくことが大切なのです。
人生もビジネスも、最後は人とのつながりで決まります。だからこそ、自分をどう見せるかだけでなく、相手がどんなレンズでこちらを見ているのかを知ることで、コミュニケーションの質を根本から変えられるのです。
あなたの言葉が、きちんと届くようになることで、世界との関係が変わりはじめます。本当の自分を理解してもらいたいと願うすべての人に、この本は心強い味方になってくれるはずです。












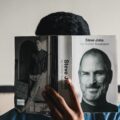




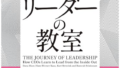
コメント