Learning: 知性あるリーダーは学び続ける
デヴィッド・ノヴァク, ラリー・ビショップ
ダイヤモンド社
Learning: 知性あるリーダーは学び続ける(デヴィッド・ノヴァク, ラリー・ビショップ)の要約
変化の激しい時代において、過去の成功体験に頼ることはリスクです。「Learning」の著者デヴィッド・ノヴァクは、学び続ける姿勢こそがリーダーの成長に不可欠だと説きます。学びには「周りから学ぶ」「方法を学ぶ」「実践して学ぶ」の3要素があり、行動を通じた気づきが自己成長とリーダーシップを強化します。
学び続ける姿勢が重要な理由 アクティブラーナーの3つの要素
私がこれまでに出会ってきた成功者たちは皆、学ぶことを習慣にしていた。彼らは、それが自分や他人の可能性を広げる唯一の方法であると信じていた。(デヴィッド・ノヴァク)
インターネット上には大量の情報が更新され、時間の流れが日々加速する中、過去の成功体験や知識だけに頼ることはとてもリスクが高くなっています。昨日の常識や正解が今日には通用しなくなっている、そんな時代を私たちは生きているのです。 だからこそ、重要なのは「学び続ける姿勢」です。
Learning: 知性あるリーダーは学び続けるの著者であるデヴィッド・ノヴァクは、世界的な企業ヤム・ブランズ(ケンタッキーフライドチキン、タコベル。ピザハット)を成功に導いた実績を持ちながら、常に「自分はまだまだ学ぶべきことがある」と語っています。
肩書きや経験にあぐらをかかず、常に新しい情報・考え・人から刺激を受け続ける。そのような「学び続けるリーダー」こそが、どんな時代でも信頼され、成長し続けることができるのです。 学びの習慣は「あったらいい」という程度のものではなく、成功に不可欠なものなのです。
過去の延長線上で続ける仕事、今までの常識にとらわれた思考、そして既存の人間関係だけに頼ったネットワーク――こうしたものは、無意識のうちに自分の視野を狭めてしまいます。
しかし、成功しているリーダーたちは、自らの思い込みやバイアスを壊すことを恐れていません。 むしろ、それを壊すことでこそ、新たな学びや成長があることを知っているのです。 彼らはまさに、アクティブ・ラーナーとして、日々学び続ける姿勢を貫いています。
アクティブ・ラーナーとは、自らアイデアや知恵を探し求め、それを行動や実行に結びつけようとする人のことだ。
彼らは、むしろ、自分のわからなさや間違いを認めることこそが、次の学びへの扉だと知っているのです。 アクティブラーナーは目的を持って学ぶことで、結果として自分や周りに大きな可能性をもたらすのです。
アクティブラーナーになる第一歩も、まさにこの「学び続ける」と決意することにあります。著者は、学びを深めるために重要な3つの要素を明らかにしています。
①周りから学ぶ(Learn from)
新しいもの、興味深いもの、価値のあるものを与えてくれる人物や経験から学ぶ姿勢を持つことが大切です。 ここで重要なのは、学びが特別な場面や専門家からしか得られないわけではないということです。
私たちは、身の回りの人や環境、そしてこれまでの成功・失敗体験からも、多くの気づきを得ることができます。たとえば、日々の何気ない会話の中にある一言、失敗からの反省、同僚の振る舞いや考え方などにも、貴重な学びの種が隠れています。
アクティブ・ラーナーは、教訓やアイデアが目の前に現れるのをただ待っていたりはしません。どこにいても、誰といても、今すぐにポジティブな変化を起こすために、自ら学びの機会を探しているのです。 「何かを学べるとしたら、今この瞬間から何が得られるだろう?」という視点を持つこと。これが、「周りから学ぶ」力を育てる第一歩です。
②方法を学ぶ(Learn to)
アクティブ・ラーナーには、優れたアイデアを生み出すためのオープンマインド(開かれた心)と、アイデアを適切に分析・評価するための批判的思考(クリティカルシンキング)を磨くことが求められます。 そのために必要なのは、日々の小さな習慣です。たとえば、異なる意見に触れたときにすぐに否定せず、一度受け止めてから考えてみること。
自分の考えにも疑問を持ち、「本当にそうだろうか?」と問い直す習慣を持つこと。他者と建設的な対話を重ねながら、新しい視点を得ていくこと。こうした習慣が、アイデアを生む柔軟性と、それを実行可能なかたちに育てる力につながっていきます。
また、人との関係性の中で「信頼を築く力」や「感情を適切に伝える力」を磨くことも、学びの一部です。学びとは、知識を増やすことだけではありません。よりよい人間関係を築く方法を学び、行動に移していくこともまた、大切な成長の一歩です。
③実践して学ぶ(Learn by)
実際にやってみることでしか得られない学びがあります。これは、喜びの追求やシンプルな思考への切り替え、問題解決、人間関係における優先順位のつけ方、そして目的を持った他者との関わり方など、非常に実用的で応用力のある内容へとつながります。
実践を通じた学びでは、体験に基づいた深い知見が得られます。その知見は、自分自身に関すること、他人に関すること、そして自分を取り巻く社会や世界についての理解にまで広がります。単なる知識にとどまらず、自分の行動と結果を結びつけることで、より実感を伴った学びとなるのです。
この方法は、成長の最大のチャンスをもたらします。たとえば、新たな課題を自ら探し、困難なことにあえて挑む。あるいは、学んだことを誰かに教えることで、自分の理解をより深めていく。このような行動を積み重ねることで、知識や能力は大きく伸びていきます。
そして、実践に伴う不安や不快感に向き合う力も、学びの一部です。失敗や違和感から逃げずに受け止めることで、精神的な柔軟性や忍耐力が養われていきます。それこそが、リーダーとしての成長を加速させる鍵となるのです。
アクティブ・ラーナーは変化を楽しむ!
アクティブ・ラーナーは、ワクワクした気持ちで学ぼうとする。学んだことが、自らの成長に役立つことを知っているからだ。
「激変する時代において、未来を受け継ぐのは学ぶ者である。知識ある者ではなく、学び続ける者だ」とアメリカの哲学者のエリック・ホッファーは述べています。
この言葉は、まさにアクティブ・ラーナーの本質を表しています。アクティブ・ラーナーは、学ぶことを義務や手段としてではなく、「喜び」や「可能性の源泉」として捉えているのです。
新しいアイデアを発見することが待ち遠しくてたまらない。そして、その次のアイデアも、さらにその次のアイデアも早く見つけたくて仕方がない――そんな熱量を持ちながら、日々を生きているのです。
「学ぶ者」が未来をつくる――これは単なる比喩ではなく、これからの時代を生き抜くための真実です。学び続けることでこそ、変化の波に乗り、自分らしい未来を切り拓く力が育まれていきます。
アクティブ・ラーナーになるためのもうひとつの鍵は、「自分自身を深く知ること」です。 私たちの生い立ちは、情報の金鉱ともいえる存在です。まずは、そこから学び始めてみてもいいかもしれません。 生い立ちは、良い経験も悪い経験も、そして日々の生活の中にある普通の体験も含めて、私たちを形づくっています。
自分のこれまでの歩みに目を向けることで、自分という人間をより深く理解できるようになります。たとえば、自分の強みや弱み、独自の視点、見落としがちな盲点に気づくことができるのです。
アクティブ・ラーナーになるということは、自分自身の人生の「歴史家」になることだという著者の言葉に共感を覚えました。 幼い頃の経験、ビジネスで影響を受けた人物、本や出来事などを振り返ることで、 新たな気づきを得られます。
自分の価値観や思考パターン、無意識に抱いている先入観と、どのような経験が結びついているのかを探っていくうちに、なぜ自分が特定の人や考え方に惹かれるのかが見えてくるかもしれません。
こうした自己認識は、あなたの今の学習能力を広げてくれる土台になります。 外の世界から学ぶだけでなく、自分の内側からも学ぶこと。これが、真のアクティブ・ラーニングにつながるのです。
本書では、インディラ・ヌーイ(ペプシコCEO)やジェームス・ゴーマン(モルガン・スタンレー元CEO)、コンドリーザ・ライス(アメリカの元国務長官)など、世界のトップリーダーたちが登場します。彼らに共通しているのは、驚くほどの「学びに対する執着」です。
たとえば、インディラ・ヌーイは向上心と競争力の重要性を母から学んだと言います。彼女は業界以外の知識にも貪欲で、日々新しい分野を学ぶことを欠かさなかったそうです。
ゴーマンは厳しい父親から謙虚さや自立する力を学んだと言います。彼の父親は18歳の時に自立を求められ、3つの仕事を掛け持ちしながら、自ら学費を払い、大学を卒業したのです。
ライスは、困難な環境で育ったにもかかわらず、被害者意識にとらわれることはありませんでした。 自分でコントロールできることに意識を向けることで、周囲の状況に左右されず、自らの人生を切り開いていったのです。
アクティブ・ラーナーは、変化よりも停滞を嫌う。
著者は、「環境を変えなければ成長できない」と述べています。しかし実際には、多くの人が新しいことへのチャレンジをついつい先延ばしにしてしまいます。
新しい環境には、人間が本能的に避けたがる2つの要素が伴います。 それは、「何が起きるかわからないこと」と、「リスクと隣り合わせであること」です。 私たちの脳には、何かを得る機会よりも、何かを失う危険のほうを重視するという特性があります。
たとえば、引っ越しや転職など、新しい環境に身を置いたとき、そこにどんな人がいるのか、どんなカルチャーなのか、自分がうまくやっていけるのか――そうしたことは事前にはわかりません。 そのため脳は、「慣れ親しんだ環境にとどまっていたほうが確実で、リスクが少ない」と判断しやすくなるのです。 けれども、それが常に正しい選択とは限りません。
アクティブ・ラーナーは、学ぶべきことを見つけ、学んだことを実際に活用しながら、新しい環境で成果を出していきます。 そして、その環境での学習や成長が行き詰まりを見せたとき、次の新しい環境を探し始めるのです。 もちろん、やみくもに飛び込むわけではありません。
アクティブ・ラーナーは、リスクを最小限に抑え、自信を高めて飛躍するために、新しい環境を慎重に評価し、選択します。 これは特別な人だけができることではありません。あなたにも、同じことができるのです。
私自身も、かつて広告会社を辞め、ベンチャー企業の社外取締役に就くという選択をしました。 それによって、マーケティングだけでなく、経営全体に関する知識を学ぶ機会を得ることができました。 その後、その会社が上場することになり、資金調達や監査に関する知識は、現在のビジネスや、大学での講義にも大いに役立っています。
このアクションは、もう10年以上も前のことですが、私の人生を大きく変えるきっかけとなりました。 そしてその後も、意識的に環境を変え続けることで、人生はより豊かになっていると実感しています。 だからこそ、著者の「環境を変えることでこそ学びが生まれる」というメッセージは、私にとって非常に心に響きました。
若さを保ち続ける人たちに共通しているのは、アクティブ・ラーナーであることだと著者は指摘します。 彼らは常に、新しい環境、特に未来を見据えた環境を自ら選び、そこに身を置くことを恐れません。私も若さを保つために、今後も新たな環境に身を置きたいと思います。
仕事を前進させる6つの力
自分の強みや、行動の傾向、性格的な特性について学ぶ度に、他人にどんな弱点を補ってもらえばいいかを把握しやすくなる。
仕事を前に進めるためには、次の6つの力が欠かせません。
・好奇心
物事の可能性や、潜在的なチャンスについて前向きに考える力です。常に「もっと良くできることはないか?」と問いかける姿勢が、成長や変化の原動力になります。
・発明力
斬新なアイデアや、既存の枠にとらわれない解決策を生み出す力です。創造性を活かして、新たな価値を提案することが求められます。
・判断力
アイデアや状況を冷静に評価・分析し、最適な選択を導き出す力です。直感と論理のバランスが問われる力でもあります。
・励ます力
人やチームの行動を促すために、組織をまとめ、ビジョンを示し、仲間を鼓舞する力です。リーダーシップの中核となる能力の一つです。
・実現力
目標達成に向けて、人を励まし、支援しながら、現実に物事を前に進める力です。チーム全体の力を引き出す役割も担います。
・粘り強さ
自分の強みや行動の傾向、性格的な特性について学ぶことで、どんな弱点を他人に補ってもらえばよいのかが見えやすくなります。 自己理解が深まれば深まるほど、自分ひとりで何とかしようとするのではなく、適切な協力を得るための判断力が養われるのです。
理想の自分と現在の自分との間にあるギャップを埋めるためには、自分のスキルや特性を一度棚卸しすることが欠かせません。 そして、前述の「仕事を進める6つの力」の中で、自分に足りていないと感じる要素があれば、それを意識的に身につけていく必要があります。
誰に相談するかを迷ったときには、著者が勧めているように、「自らの考えを現実の世界で実践し、それがうまくいくことを証明している人」を選ぶことが、私にとっても非常に大切だと感じています。 理論だけでなく、行動と成果によって信頼を得ている人からのアドバイスは、実践的で再現性が高く、自分自身の学びに直結しやすいからです。
アクティブ・ラーナーになりたいのなら、まずは「他人は自分よりも物事を知っている」と考えることが大切です。 そして、毎日、誰かから何かを学ぼうと意識して過ごすこと。
それによって、求めている目標や解決策への近道が見えてくるようになります。 決断し、行動を起こすときが来たときには、専門家レベルの知識がなければ得られないような自信を持って、しっかりと前に進むことができるようになるのです。
私自身もこれまで、取締役会のメンバー、大学の教授、士業やコンサルタントの方々など、周囲の多様な専門家たちから学びを得ることで、自分に足りない力を一つひとつ補ってきました。
たとえば、困難な状況や長期にわたるプロジェクトの中でも、諦めずに前に進み続ける力は、そうした学びの中で特に意識して磨いてきた力のひとつです。 成果が出るまでやり抜く姿勢は、やがて周囲の信頼を生み、さらに新たな学びの機会へとつながっていく。 私はそれを、実体験として強く実感しています。
アクティブ・ラーナーは、危機からも成功からも学びを得る!
アクティブ・ラーナーは、危機の中でも正しいことをしようとする。 成長や改善、 学習の機会を見つけるのに役立つからだ。
アクティブ・ラーナーは、どのような状況であっても、危機を学びの場に変える力を持っています。 成功よりも、むしろ危機や失敗から多くを学べると考えているのです。著者自身も、最大の危機の中で、最大の学びを得てきたと語っています。
新たな危機が訪れると、アクティブ・ラーナーは自らの「学びのギア」を入れ、できる限りのことを吸収しようとします。 どの危機にも固有の学びがありますが、すべての危機から共通して得られる普遍的な教訓も存在します。
私たちには、どのような危機であっても乗り越える力が備わっています。 一見すると困難にしか思えない状況であっても、その中にこそ、自分の中に眠る強さや可能性を見つけるきっかけがあるのです。
そして、危機を経験することによって、将来同じような状況を回避するための知恵や備えを学ぶこともできます。 一度困難を乗り越えた経験があれば、次に同じような状況に直面したとき、落ち着いて対処することができるようになります。 過去の経験が、未来の自分を守ってくれるのです。
また、危機をくぐり抜けることによって、ただ元に戻るのではなく、以前よりも強く、しなやかになった自分に出会うことができます。 成長とは、失敗や困難を避けることではなく、それらをどう乗り越え、そこから何を学び取るかによって決まるものなのです。
アクティブ・ラーナーは、そうした価値を理解しています。 だからこそ、危機の中にあっても、自分が正しいと信じることを選び取ろうとします。 苦しい状況であるからこそ、そこには必ず「成長の種」があると信じているのです。 学び、改善し、進化するチャンスは、実はそうした局面にこそ多く隠れています。
また、過去に困難を乗り越えた経験は、次に同じような状況に直面したとき、力強い味方になってくれます。 「前にもこういう経験があった」「あのときも乗り越えられた」と思えることは、自分自身への信頼につながります。 危機を乗り越えた経験の積み重ねが、自分に対する肯定感や安心感となり、次の一歩を支えてくれるのです。
このように、アクティブ・ラーナーは、危機をただの問題としてではなく、未来の自分をつくる学びの場として捉えています。 そして、その姿勢こそが、どんな環境でも前に進み続けるための原動力になっているのです。
アクティブ・ラーナーは日々、他人の成功から学び、自分が知らないことを知っている人やチームからできる限り多くのことを吸収しようとします。そして、自分自身の成功や勝利から学ぶ機会も、決して見逃しません。
成功している企業には、次の5つの共通点があるとされています。
・従業員全員を大切にする企業文化
社員一人ひとりを尊重し、心理的安全性を確保することで、高いエンゲージメントと生産性を実現しています。
・顧客と販売を重視する姿勢
顧客のニーズを的確に捉え、販売の現場を重視することで、市場の変化に柔軟に対応しています。
・他社と明確に差別化された価値
単なる価格や機能の勝負ではなく、自社にしか提供できないユニークな価値を打ち出すことに成功しています。
・従業員とプロセスの継続性
人材の定着と業務プロセスの安定化を両立させ、持続的なパフォーマンスを発揮しています。
・安定した対前年比の業績
一時的な成果にとどまらず、毎年の積み重ねとしての業績改善が継続されているのです。
このような企業は、表面的な成功要因だけでなく、「どのように学び続けているか」という視点にも共通点があります。 実際に、学びを続けている企業は、競合他社や、さらには自社よりもはるかに成長している企業の取り組みを積極的に研究し、その中から優れた要素を選び取って、自社に取り入れる柔軟性を持っています。
彼らは「自分たちのやり方に固執しない」ことを学んでおり、成功事例に対して素直であり、模倣や改善に対しても前向きです。 だからこそ、変化の激しい時代においても、学習を武器に競争優位を維持し続けているのです。
これまでの道のりと、自分が積み重ねてきた勝利を振り返ることで、自分には能力があること、自分の直感や過去の経験から得た学びを信じてよいことを思い出せるはずです。 前進し続けている限り、私たちは常に何かを学んでいます。
勝利からは、喜びや爽快感を学ぶことができます。 立ち止まって成果を祝い、その感情にしっかり浸ることで、その勝利が私たちを次の挑戦へと導いてくれるのです。
一方で、傲慢な人は、自分にはもう学ぶべきことがないと思い込みます。 自分だけで答えを導き出せると考え、他人から学ぼうとしなくなるのです。 このような姿勢は、自信ではなく「恐れ」を生みます。なぜなら、すべてが自分一人にかかっていると感じてしまうからです。
ターゲット社のCEOのブライアン・コーネルは、チーム内の「主語の使い方」を「私たち」に変えることの大切さを語っています。 主語を私たちに変えることで、チームに謙虚さと一体感が生まれます。
このようにチームにフォーカスすることで、私たちは自分の周りの世界をより深く理解できるようになります。 そして結果として、自分自身の理解も深まっていきます。
自分の弱さを正直に見せることができれば、相手もまた自分の弱さを見せてくれるようになります。 そうした関係の中では、表面的ではない、深くて価値あるアイデアや視点が共有されるようになるのです。
アクティブ・ラーナーは、人生を進行中の“傑作”と捉える画家であり、アーティストのような存在だと著者は言います。 学び続けることで、その作品は日々、より良いものへと進化していきます。自分の人生という作品をより良くするために、私も学び続けたいと思います。
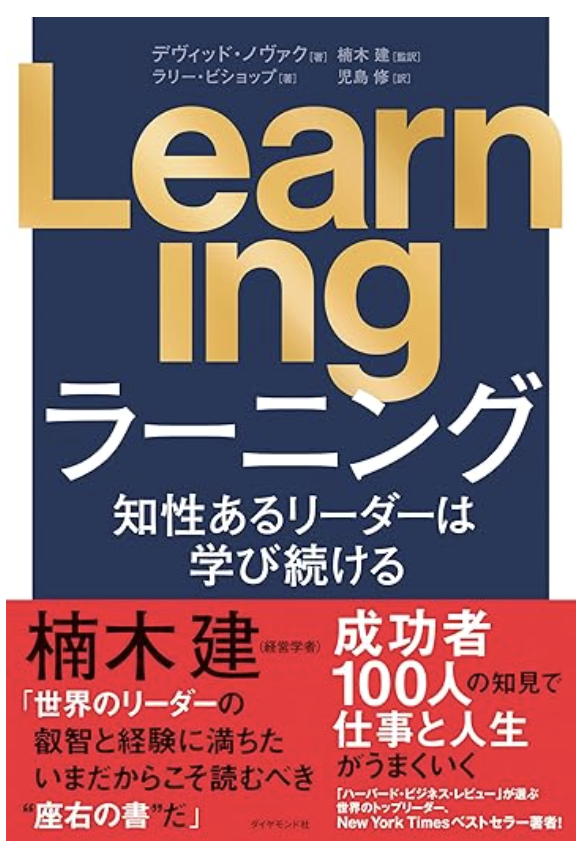





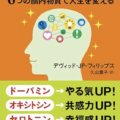












コメント