「偶然」はどのようにあなたをつくるのか: すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味
ブライアン・クラース
東洋経済新報社
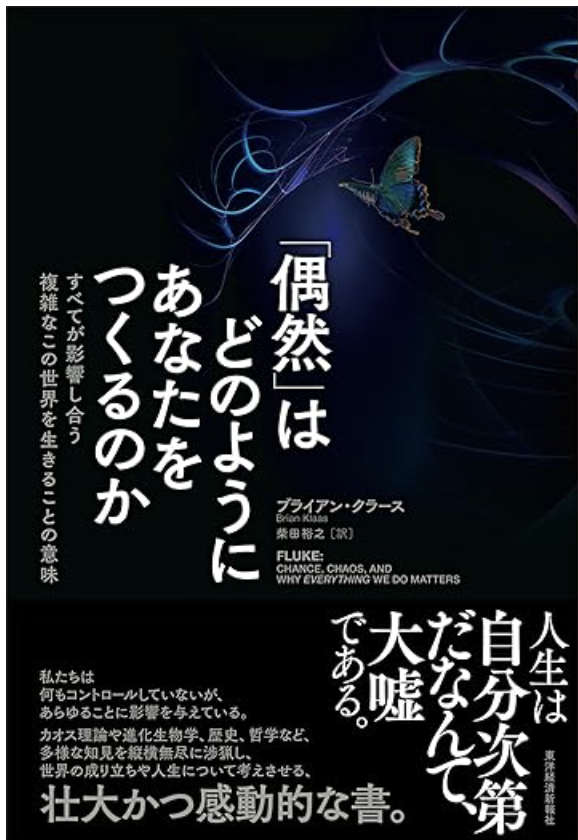
「偶然」はどのようにあなたをつくるのか: すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味(ブライアン・クラース)の要約
人生や社会は、予測不能な偶然や複雑に絡み合う出来事の連鎖によって絶えず形作られています。ブライアン・クラースは、こうした偶発性を単なる不運として排除するのではなく、意味づけと受け入れの姿勢によってそれを味方に変えることの重要性を語ります。不確実性の高まる現代において、私たちはすべてをコントロールすることはできなくても、小さな選択や行動に意味を見出すことで、しなやかに未来を切り開いていけるのです。
偶然の力を活用すべき理由
ほんのわずかでも何かが変われば、異なる世界で異なる人々が生まれ、異なる人生を送ることになる。(ブライアン・クラース)
私たちは毎日、数え切れないほどの選択を無意識のうちに積み重ねています。朝、何時に起きるか、どの服を着るか、どの道を通るか。そのひとつひとつは取るに足らないように見えるかもしれませんが、もしもそのうちのどれかが少し違っていたら?たとえば、あの日5分早く家を出ていたら?あるいは、偶然出会ったあの人とすれ違っていなかったら?──そんな偶然の積み重ねが、人生の構造そのものを決定づけている可能性があるのです。
政治学者のブライアン・クラースの「偶然」はどのようにあなたをつくるのか: すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味は、こうした偶発性と予測不能性に正面から向き合う一冊です。
クラースは、人生や歴史は自分の意思や努力によってコントロールできるという一般的な信念に対し、明確な疑問を投げかけます。人は物事に一貫した因果関係を求めがちで、自分の成功を「選択」と「計画」の結果と信じたくなるものです。
しかし彼は、そのような成功神話こそが、実のところ偶然の力を過小評価した危うい幻想だと指摘します。 クラースの議論は、端的に言えば「あなたの成功は、本当にあなたの手柄なのか?」という問いを突きつけるものです。
自己責任論に陥りがちな現代社会において、これは不快に感じられるかもしれませんが、だからこそ価値があります。彼は、偶然がいかに人生に決定的な影響を及ぼしているかを、歴史的事例や科学実験を用いて丁寧に示します。
象徴的なエピソードとしては、第二次世界大戦中における原爆投下先の決定過程が挙げられます。京都が標的から外れた背景には、アメリカ陸軍長官ヘンリー・スティムソンがかつて京都を訪れ、その文化的価値に感銘を受けていたという、個人的な経験がありました。
さらに、当初の第二候補だった小倉が投下当日に雲で覆われていたという気象条件が、最終的に長崎への投下という重大な判断へとつながったのです。これは計画でも戦略でもない、まさに「偶然の連鎖」の結果でした。
こうした現象は、歴史上の特異な例に限られるものではありません。私たちのごく日常的な行動の中にも、同様の偶発性が確実に存在しています。たとえば、朝のわずかな遅れ──たった数分のタイミングのずれが、乗る電車を変え、すれ違う人を変え、その日以降の出来事に想像以上の影響を及ぼす可能性があります。日々の何気ない選択が、未来の方向性を大きく左右することは、決して誇張ではないのです。
その一連の変化は、結果的に人生の方向性にすら影響を与えるかもしれません。偶然とは、それほどまでに強力なものなのです。
未来が予測可能であるかのように自信たっぷりに語るのは、ペテン師と愚か者だけだ。
この複雑な関係性を理解するうえで鍵になるのが、「カオス理論」です。カオス理論は、あるシステムの初期条件にわずかな違いがあっただけで、その後の結果が劇的に異なる方向へと変化するという現象を説明する理論です。
いわゆる「バタフライ効果」として知られているように、「ブラジルで蝶が羽ばたけば、テキサスで竜巻が起こるかもしれない」というのは、微細な差異が長期的に見れば極めて大きな変化をもたらすという、直感に反するが本質的な事実を象徴しています。
そしてこの原理は、私たちの日常にも確実に作用しています。たとえば、ある朝いつもと違うルートで通勤したことで、偶然にも将来のパートナーと出会うことがあるかもしれません。あるいは、なんとなく選んだカフェで交わした何気ない会話が、やがて大きな転機のきっかけになるかもしれないのです。
さらには、自分が何気なく発した一言が、予想もしなかったかたちで相手の心に響き、長く記憶に残るフレーズとして、その人の人生に影響を与える──そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。言葉の力は、ときに想像以上に深く、他者の行動や意思決定を動かすのです。
こうした出来事の背景には、「偶然の構造的な力」が存在しています。偶然とは単なる気まぐれではありません。それは、私たちが把握しきれないほど複雑な因果ネットワークの中で、特定の地点に現れる現象です。そしてその現象は、決して孤立して存在しているわけではなく、周囲の無数の要因と連動しながら発生しているのです。
このようなネットワーク構造を前提として世界を見ることができれば、偶然やカオスといった不確実性に対して過剰に不安を抱く必要もなくなります。むしろ、それらを世界の一部として受け入れ、共に歩むという姿勢が、現代をしなやかに生き抜く上での大切な感覚となるのです。
すべてがつながっているという前提に立ったとき、私たちは「偶然」をただの気まぐれではなく、「意味ある構成要素」として捉え直すことができるようになります。
そこには、論理だけでは説明しきれない領域が広がっていますが、それこそが私たちの現実世界をリアルなものにしているとも言えるでしょう。 私たちは往々にして、「重大な決断」によって人生を切り開いていると思いがちですが、実際には、ほんの小さな選択──目を覚ました瞬間に選ぶ行動や、手を伸ばす本の一冊──が、未来の全体像を大きく変えていることがあるのです。
そして、その一見些細な判断の連続が、社会や他者にまで波及し、時には世の中そのものを変えるほどの影響を与える可能性すらあるのです。
私たちのカオス的で絡み合ったあり方は、次のような意味深長で驚くべき事実を明らかにしてくれる。 私たちは何もコントロールしていないが、あらゆることに影響を与えているのです。
こうして浮かび上がってくるのは、私たちが実は「ほとんど何もコントロールできていない」という現実です。未来を完全に見通すことも、すべての結果を意図的に導くこともできません。けれども一方で、私たちは「自分が知らないところで、あらゆることに影響を与えている」という、もう一つの事実にも気づかされます。
一見すると矛盾しているようですが、この「不確実な世界の中でも、私たちの行動が何かを動かしている」という認識こそが、現代を生きるうえで非常に大切な視点なのです。 偶然の力は、単に私たちを翻弄する不条理な存在ではありません。それどころか、予想もしなかった可能性や、新たな道を開いてくれる力でもあります。
すべてが計画どおりに進まないからこそ、そこに人生の豊かさや、意外性の面白さが生まれるのです。 予測できないからこそ意味があり、完璧に管理できないからこそ価値がある──そう考えてみること。それが、不安定で変化の激しいこの時代において、もっともしなやかで賢い生き方なのかもしれません。
その小さな選択が、未来を変える!
すなわち、小さく偶発的で、ただの偶然でさえある変化──偶然の巡り合わせ──は、私たちがたいてい思っているよりもはるかに重要だ。
世界は、ときにほんの些細な偶然によって、その進路を大きく変えます。もしそれが本当なら、私たちがスヌーズボタンを1回押すだけで、未来がわずかに、しかし確実に変わる可能性もあるのです。 自然界にもこの偶発性は明確に現れています。
たとえばカモノハシ──カモのような嘴、ビーバーの尾、カワウソの足を持つ、有毒な卵生哺乳類という進化の異端児なのです。生物学者が「一度きりの進化」と呼ぶほど、他と共通点がなく、偶発的な進化の象徴です。
一方で、全く別の系統から似た形に進化する「収束性」も存在します。ヤドカリやタラバガニなど、系統的には無関係な甲殻類がカニ化する現象はあまりに多く、「カーシニゼーション」という名前までついているほどです。
世界は、偶然と収束のあいだを行き来しながら動いています。 レディング大学の進化生物学者マーク・ペイゲルは、DNA研究から「新種の78%がたった一つの出来事から生まれた」という証拠を発見しました。これは、偶然のインパクトがいかに絶大であるかを示しています。
そして、リチャード・レンスキーとザカリー・ブラウントが主導した大腸菌進化実験では、同じ条件下でも異なる進化が起こる一方、まったく別々の経路を経て似た形に至るケースも観察されました。まさに「偶発的収束性」とも呼べる現象です。
私たちの日常は、予測可能で整然として見えるかもしれません。毎朝ニュースは7時に始まり、通勤時間は決まっていて、社会は収束的に動いているように感じます。しかし現実は、そんな安定の中に潜む「急激な偶発性」によって、突然方向を変えるのです。 そして、そのきっかけは往々にして日常の中にあります。
スヌーズボタンを押した数分のズレ、たまたま選んだ道、偶然の出会い──そうした小さな出来事が、未来を静かに、そして確実に変えていくのです。 秩序はあるように見えて、実はその下に偶然が渦巻いています。私たちはすべてをコントロールできるわけではありませんが、それでも一つひとつの行動が、世界に思いがけない影響を与えることがあるのです。 だからこそ、どの瞬間も大切なのです。
クラースはまた、人間の認知構造にも切り込みます。進化の過程で形成された私たちの脳は、物事を単純な因果関係で理解しようとしがちです。その結果、複雑な出来事にも意味や目的を見出そうとする「目的論的バイアス」が生じます。たとえば、山は人が登るためにあると考える子どものように、私たちも無関係な出来事の間に因果を読み込んでしまうのです。
このようなバイアスを克服するには、教育と認知の鍛錬が必要です。クラースは、あらゆる出来事が意味や意図を持っているわけではなく、時に小さな無作為性や偶然が、世界に予想外の変化をもたらすと指摘します。 重要なのは、偶然が世界を支配しているからといって、人間の影響力が無に帰するわけではないということです。
近頃では、偶発性の気まぐれに遭わずに済む人は、どれほど極端な世捨て人も含めて、誰もいない。これが大群のパラドックスだ。人間社会は秩序立った規則性に向かつ収束性がはるかに高まった(そのおかげで、魅惑的なまでに予測可能に見える)と同時に、偶発性も大幅に高まった(そのせいで、根本的に不確実でカオス的になった)。現代人は、かつて存在しなかったほど秩序立った社会に暮らしているが、私たちの世界は人類史上、他のどんな社会環境よりも、混乱と無秩序に陥りやすい。
複雑系の本質は、非線形性にあります。つまり、変化の大きさとその結果のスケールが必ずしも比例しないということです。ごく小さなきっかけが、やがて制御不能な大変化を引き起こす──そうした予測不能な現象は、実は私たちの周囲に日常的に存在しています。
ナシム・ニコラス・タレブが「ブラック・スワン」として警告したのは、まさにこのタイプの出来事です。ブラック・スワンとは、非常に稀で予測が難しいにもかかわらず、発生すれば社会や歴史に甚大な影響をもたらす事象のこと。
多くの場合、それは一連の小さな出来事が静かに連鎖し、ある臨界点を越えたときに爆発的な結果として現れます。 厄介なのは、この連鎖反応が起こったあとでさえ、私たちはその全容を正確に理解できないことが少なくないという点です。「なぜそうなったのか?」を後から問うても、因果はあまりにも複雑に絡み合っていて、単純な説明では届かない。因果の全体像は、私たちの認知の限界を超えているのです。
クラースはこの現象を「自己組織化臨界性」という概念で説明します。これは、あるシステムが外部の指令なしに自発的に秩序を持ち始める一方で、ちょっとした刺激によっても全体が崩れるような臨界点に常にさらされている状態を指します。
たとえば、雪崩が起きる雪山のように、一見安定しているように見えても、わずかなきっかけで大規模な崩壊が始まる。そんな世界に、私たちは生きているのです。 この視点は、社会構造の変化にも当てはまります。
前近代社会は、局所的には不安定でも、全体としては比較的安定していました。しかし、今日のようなグローバルに接続された世界では逆の構造が生まれています。つまり、個々の場面では秩序が保たれているように見えても、全体はむしろ不安定で、わずかなきっかけで大規模な変化が起きる可能性を常にはらんでいるのです。
偶発性は、ただ驚くべき例外ではありません。それは日常の中に深く根づいており、私たちの人生を書き換え、歴史の流れを変え、新しい形の生命さえ生み出す力を持っています。そして、私たちの脳はその偶発性をしばしば見落とすよう設計されている──因果を単純化し、わかりやすい物語として理解しようとする傾向があるからです。
しかし、世界はそう単純ではありません。無視できるような小さな出来事が、やがてブラック・スワンとなって現れるのです。自己組織化臨界性を持つこの世界では、そうした連鎖がいつどこで起きても不思議ではないのです。 結論は、一見すると厄介なものに思えるかもしれません。
しかし、それは現実の本質を突いています。私たちが暮らす世界は、私たちが信じたいような安定した世界ではなく、むしろ、はるかに不確実で、変化に満ちた世界なのです。
確率と不確実性
サイコロを振った結果は、不確実性ではなくリスクだ。どの目が出るかはわからないが、どの目も出る確率が6分のーであることはわかっている。だから、リスクは手懐けることができる。一方、不確実性は、未来の結果が未知であり、しかもその結果を生む根本的な仕組みも未知で、刻々と変化している可能性さえある状況を指す。何が起こるかわからないし、起こる公算がどれだけあるかも評価のしようがない。皆目見当がつかない。
クラースは、自由意志と決定論、そして確率論の関係にも深く切り込みます。彼は、すべての出来事が過去の状態や物理法則によって決まるという決定論に対して懐疑的な立場を取り、量子力学やカオス理論を引き合いに出して、未来は本質的に不確実だと主張します。
私たちは日常的に、未来を予測するために過去のパターンや統計モデルを頼りにします。けれど、世界そのものが変わってしまうと、そうした確率論的なアプローチが通用しなくなることがあるのです。クラースはこの状態を「ヘラクレイトスの不確実性」と呼びます。これは、過去がもはや未来の手引きとして役に立たない状況を意味します。
なぜなら、出来事の前提条件や因果の構造自体が変わってしまっているからです。 たとえば、1995年の時点で、2020年にイギリス人が一日にスマートフォンをどれだけ使うかを予測できた人はどれだけいたでしょうか。
ベイズ統計でも頻度論でも、高度な数式やスーパーコンピューターを使ったとしても、その予測は的外れになっていたはずです。なぜなら、1995年にはインターネット利用者はわずか130人に1人、スマートフォンは影も形もなかったのです。
私たちが予測を誤る原因のひとつは、「大きな出来事には大きな原因がある」という直感的な仮定に頼りすぎることです。明確な因果を前提とする思考は、複雑な現実に対して適切な説明力を持ちません。
確率論は一見、こうした問題への対処法に見えますが、実際には限界があります。なぜなら、確率を算出するには、まず対象となるリスクをあらかじめ特定しておく必要があるからです。未知の事象、あるいは想定されていない変数については、そもそも確率的な評価が不可能です。
前述の第二次世界大戦末期における原爆投下の決定を考えてみましょう。「アメリカは日本のどこに原子爆弾を投下するか?」という問いに対して、地理、戦略的価値、人口密度といった定量的データを用いた確率的予測は可能です。
しかし、京都が投下対象から除外された背景には、アメリカ陸軍長官ヘンリー・スティムソンの個人的な判断がありました。彼はかつて京都を訪れ、その文化的価値に深い感銘を受けており、その記憶が政策決定に影響を与えたのです。
このような意思決定の核心にあった変数──一個人の経験と感情──は、事前には観測も定量化も困難です。どれほど精緻なモデルを構築したとしても、そうした変数を把握していなければ、予測の精度には限界があるということになります。
間違いなく、確率は既知のリスクを扱ううえでは有効なツールです。しかし、現実の世界には偶発的な出来事や、個人的・文化的な主観的要因が複雑に絡み合っており、それらに対して確率論が機能するとは限りません。むしろ重要なのは、「予測可能性」という前提自体が常に不完全であるという認識を持ち続けることです。
決定理論は、本来、合理的な意思決定を導くために構築された理論体系です。個人や組織が限られた情報とリスクの下で最善の選択を行うために、確率や効用(得られる利益)をもとに選択肢を評価します。環境が安定し、変数が明確に定義されている場合には、有効に機能する理論です。
しかし、私たちが生きているのは、そうした理想的な条件が整った世界ではありません。むしろ、情報は不完全で、変数は予測不能に変化し、因果関係すら曖昧なまま進行するカオス的な現実です。このような環境においては、決定理論が前提とする「合理的な選択」の土台そのものが揺らいでいます。
私たちがこの不確実で複雑な世界に対して過度に整然とした「地図」をあてはめようとしたとき──つまり、すべてを理解し、コントロールできるという前提のもとで行動したとき──状況はかえって危うくなります。傲慢さと単純化された理論が結びつくと、現実はその期待を裏切る形で応答してきます。
だからこそ重要なのは、「克服できない不確実性が常に存在する」という前提を持ち続けることです。予測できないものを前提にするという逆説的な姿勢こそが、カオス的な世界を生き抜くうえでの最も実践的な戦略なのかもしれません。
人生と社会に重大な変化をもたらす、人間の行動の4つの領域
私たちの人生と社会に重大な変化をもたらす、人間の行動の4つの領域を調べることにする。その4つとは、行動をする理由、場所、主体、時だ。
こうした世界の予測不可能性を理解するには、単に過去のデータや数値的な傾向を追うだけでは不十分です。重要なのは、その背後にある構造的な変化、社会や技術が置かれているタイミング、そして人間特有の行動や信念体系がどのように相互に作用しているかを見極めることです。
現実世界では、何が起こるか以上に、どこで起こるか、いつ起こるか、誰によって実行されるか、なぜ、それが選ばれたかが、決定的な意味を持つことがあります。
クラースはこれを9.11テロの事例で示します。あの数分間の出来事は、それ以前の地政学的予測をすべて無効化し、世界の構造を大きく変えてしまいました。つまり、信念や文脈、そしてそのタイミングが、行動に深く影響を与えているのです。
私たちの脳は、断片的な情報を因果的につなげ、物語として再構成するようにできています。この「ナラティブ・バイアス」は、事実を歪め、偶発性やカオスの入り込む余地を狭めてしまいます。合理的だと信じている行動の多くが、実際には物語や信念によって形成されているのです。
このバイアスは、情報の発信者──メッセンジャー──にも影響します。クラースはこれを「カッサンドラ問題」として言及します。どれほど正確な予測をしても、それを伝える人物が信頼されなければ、予言は無視されてしまいます。
つまり、メッセージの内容と同じくらい、誰がそれを語るかが重要なのです。 この認知の偏りは、「スキーマ」や「シグナリング」として知られる心理的メカニズムによって強化されます。人は初対面の相手でも、「起業家」や「インフルエンサー」などのラベルに基づいて、無意識に判断を下しています。言語や文脈の偶発性によって、私たちの理解そのものが変わってしまうのです。
クラースはCOVID-19を例に、時間の影響を強調します。同じ出来事であっても、発生した「タイミング」によって、その意味や社会への影響は大きく異なります。もし1950年に同じウイルスが流行していたとしたらどうでしょうか。当時はリモートワークという概念もなく、インターネットも存在せず、情報通信インフラも未整備だったため、社会の対応や被害の広がり方は現代とはまったく異なるものになっていたはずです。
地理や地質もまた、歴史の偶然を形づくる重要な要素です。クラースは「人間時空偶発性」として、特定の場所と特定の時期に自然環境と人間社会が交差したときに、大きな変化が生まれると述べます。たとえば、サウジアラビアの石油は数百万年にわたって地下に眠っていたものの、内燃機関の発明と結びついた20世紀以降に初めて価値を持つようになりました。
このように、地理的条件が文化や経済を大きく左右するにもかかわらず、現代ではその影響力が軽視されがちです。だが、変化は常に「何かと何かが、どこかで、ある時に、たまたま重なった」結果として起きる。そこには、偶発性と構造の両方が存在します。
そして最終的に、私たちがこの不確実な世界で意味ある行動を取るには、人類が進化の中で培ってきた最大の知的戦略──「協力」──が鍵となります。協力は単なる共同行動ではなく、個人の能力を集合知へと昇華させ、複雑な問題に対処するための重要な基盤です。
私たちの社会は、無数の協力の積み重ねによって築かれています。医療、科学、経済、環境対策など、どの分野を見ても、単独では達成し得ない目標が、集団の相互作用によって初めて可能になるのです。
クラースは、人間の意思決定において「探索」と「活用」のバランスを取ることが極めて重要だと指摘しています。新しい挑戦や未知の選択肢に踏み出す「探索」と、これまでに効果が確認されている方法を繰り返す「活用」。
この2つの戦略は、ビジネスシーンに限らず、日常生活の中にも自然に存在しています。 たとえば、初めてのレストランで未知の料理を選ぶのは探索、慣れ親しんだ店でいつもの定番メニューを注文するのは活用です。探索にはリスクや不確実性がつきものですが、そこから新たな発見や価値ある出会いが生まれることもあります。
一方で、活用は安定性が高く効率的ですが、変化の兆しを見逃すリスクも含んでいます。 著者は、どちらの戦略が優れているかを問うのではなく、状況に応じて柔軟に使い分ける判断力の重要性を強調します。
特に変化のスピードが加速し、将来の予測が難しくなっている現代においては、探索的な姿勢──新しい分野に触れる、異なる視点を取り入れる、他者と協働して学ぶ──といった行動が、より大きな価値を生む可能性があります。
偶然や予測不能性を排除しようとするのではなく、むしろそれらを受け入れ、味方にする思考こそが、現代を生き抜く力になります。私たちは互いに影響を与え合いながら社会を構成しており、一つひとつの小さな選択が、思いがけない未来をつくり出しているのです。
著者が提唱する「アモール・ファティ(運命愛)」の哲学は、現代社会を生きるうえで有益な態度を提供してくれます。すなわち、人生の出来事を「意味づける力」は私たち自身にあり、それこそが偶然を味方につける方法だという発想です。
起こったことを「不運」と片づけず、「そこに何らかの価値があるかもしれない」と捉え直す視点──これは偶然という不可避の要素と共存するための、極めて知的で実践的な態度です。 私たちは未来を正確に計画することはできません。けれども、今この瞬間の選択が、やがて誰かの人生を変えるかもしれない──その前提に立つことで、私たちは「偶然」という不確実な力と共に前を向いて生きていくことができます。
クラースは、偶然の力を味方にし、理解し、受け入れ、活かすための視点を私たちに提供してくれています。そしてその視点は、自分の人生にどのように意味を与えるかを改めて考えるきっかけとなるのです。







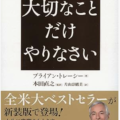
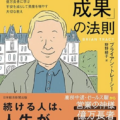







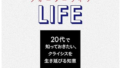

コメント