選ばない仕事選び
浅生鴨
筑摩書房
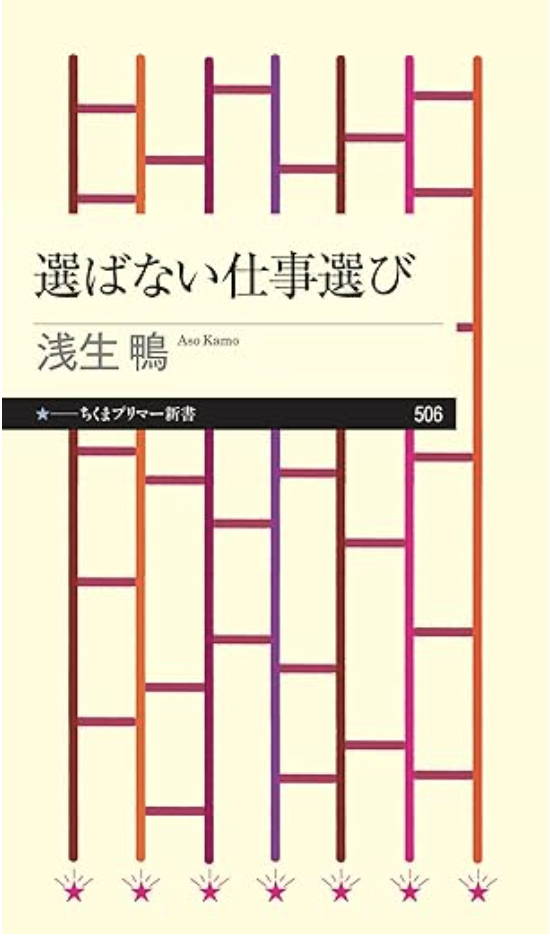
選ばない仕事選び (浅生鴨)の要約
人生は誰かが代わりに生きてくれるものではなく、最終的な決断は常に自分自身に委ねられています。他者の意見は参考にはなりますが、責任を負うのは自分です。行動を通じてしか見えない「自分に合う仕事」や「使命」があり、偶然の出会いや依頼から人生の方向が開けることもあります。浅生鴨氏の『選ばない仕事選び』は、働くとは社会とつながり、世界に小さな変化を生み出す行為だと教えてくれます。
偶然の力が働き方を変える理由
声をかけられるまま、誘われるままにいろいろな職を転々としてみると、どの仕事もだんだん自分に合っているように思えてくるから不思議だ。たぶんもともと僕に合わない仕事は最初から僕のところへはやって来ないのだろう。僕が仕事を選ぶのではなく、どうやら仕事が僕を選んでいるようなのだ。頼まれたり誘われたりってのはそういうことなのだろう。(浅生鴨)
誰かが代わりに生きてくれる人生は存在しません。 だからこそ、最終的な意思決定は、常に自分自身が担うべきものです。 他者の助言に耳を傾けることは、もちろん意味のあることです。
私自身も、本や多くの人との出会いを通じて、異なる視点に触れることで選択肢が広がり、新たな気づきを得てきました。 しかし、どれほど影響力のある人物の言葉であっても、それはあくまで「参考意見」にすぎません。 他人の意見が、私たちの人生に対する責任を代わりに負ってくれることはないのです。
広告会社での勤務を経て独立し、さまざまな業種・業態のプロジェクトに関わる中で、私はひとつの実感を得ました。 それは、「自分に声がかかる仕事の多くは、最終的に自分にとって意味のあるものだった」ということです。 不思議なもので、実際にやってみると「思ったより悪くない」「案外、自分に向いているかもしれない」と思える瞬間が少なくありません。
結局のところ、人生の適職や使命は、頭で考えて見つけるものではなく、行動のなかで立ち上がってくるものです。 誰かの期待ではなく、自分の意思で選び取った経験の積み重ねこそが、自分という人間を形づくっていくのだと思います。
もしかすると、自分にまったく合わない仕事というのは、そもそも最初から自分のもとにはやって来ないのかもしれません。 一見、自分が仕事を選んでいるように見えて、実は仕事のほうが自分を選んでいる──。 そう捉えることも、あながち的外れではないと感じています。
浅生鴨氏の選ばない仕事選びは、こうした視点を理論的かつ柔らかい語り口で提示してくれる一冊です。 著者は作家・広告プランナーであり、出版社「ネコノス」の創業者でもあります。
僕にとって「働く」とは人生の偶然に乗っかることだ。自分からやりたいことなんて特にないから、いつだって偶然に任せるしかない。そうやって人に言われるまま、誘われるまま、頼まれるまま、内容も業種も関係なく適当にいろいろなことをやってきたのだ。
本書の核となるのは、このブログでもたびたび紹介している、クランボルツ博士の「計画的偶発性理論」です。 この理論では、キャリアの多くは偶然の出会いや出来事によって形成されるとされており、「仕事とは出会うものである」という浅生氏のメッセージにも近いと感じています。(クランボルツ博士の関連記事)
この前提に立てば、「正解のキャリア」を早急に見つけようとすることに、さほど意味はありません。 特に社会に出たばかりの若年層にとっては、世の中の仕事を網羅的に理解すること自体が不可能です。私も本当に楽しい仕事、自分らしい仕事に出会えたのは、40代後半になってからでした。
仕事とはつながりを作ること
人生にはたくさんの偶然が転がっている。この道しかないと決めてしまったら、その道から外れたときにどうしていいか分からなくて戸惑うことになる。
私自身も日々、偶然の力によってさまざまなご縁に恵まれています。そこから、新たなビジネスがいくつも生まれてきました。 もちろん、ある程度の計画は立てますが、実際に行動し、偶然を受け入れながら進むことで、結果的に自分らしいワークスタイルが築けるようになってきたと感じています。
著者はこうも語っています。「今の君にとって何よりも大切なのは決めすぎないことだ」。 あまりにきっちりと固まっているものは、小さな衝撃で簡単に壊れてしまいます。 しかし、どこかに柔軟性があれば、予期せぬ出来事が起きてもそれを受け流すことができる。
将来設計もまた、そうした「余白」があるからこそ、持続的なものになるのかもしれません。 この視点に立てば、「最適解」を早期に探し求める必要はなくなります。 とくに若年層にとっては、社会に出たばかりの段階で、世の中の仕事全体を把握すること自体が不可能です。
限られた情報の中で無理に「正解」を選ぶのではなく、偶然の出会いや依頼に身を委ねながら、自分に合う方向性を徐々に見極めていくほうが、はるかに現実的だといえるでしょう。
本書の中で繰り返される「働きたくない。ゴロゴロしていたい」という言葉も印象的です。 一見ネガティブに映るかもしれませんが、これは働くことへの本音を正直に表現したものであり、多くの人が共感できる部分ではないでしょうか。
そして著者は、そのような感情を否定することなく、「それでも大丈夫」と受け止めてくれます。 このスタンスは、読者に努力や根性を求めるのではなく、偶然の中で自分を観察し、少しずつ納得感のある働き方を築いていくプロセスを肯定するものです。
つまり、仕事とは「正解を探す行為」ではなく、「納得を育てていく行為」である──そのように捉えることができます。 キャリア形成において、他者の期待や社会の空気に流されるだけでは、持続的な満足にはつながりません。 むしろ、自分自身の経験や直感、そして偶然の出会いを通じて得られる実感を大切にすること。 それこそが、自分らしい働き方を見つけていくうえでの鍵になるのではないでしょうか。
実は、仕事とは社会とつながるための手段なのだ。世界を動かすこと、世界に何かを付け加えること。それこそが、僕たちが社会や他人とつながるための唯一の方法なのだ。誰かといっしょに何かを作ったり、悩んだり、意見をぶつけ合ったり、解決したりする。その関係の中に、自分の存在が形を持ちはじめる。そして、そんな時間を重ねるうちに、人と人との間に信頼が生まれ、役割が生まれ、それがまた次の行動につながっていく。それが働くことの本質だ。
私たちは、本質的に誰かと関わりながらでないと生きていけない存在です。 働くという行為には、人や社会とつながるという側面があります。 何らかの役割を担い、価値を提供し、誰かの役に立つ。 そのプロセスを通じて、私たちは孤独から解放され、社会の一部として存在する感覚を得られるのです。
つまり、働くこととは、社会と関係性を築き、そこに自分の居場所を見出していく行為でもあります。 世界に対して何かを少しでも付け加えていくこと──それが仕事の本質だと私は考えています。 それは大きな成果でなくても構いません。誰かの一日を少し楽にする、小さな改善を積み重ねる、そんな日々の行動もまた、社会を形づくる立派な「仕事」です。
そしてもし、それを誰かと一緒に行うことができたら──。 そこには協力や対話が生まれ、より深いつながりが育まれていきます。他者に貢献することで感謝されるようになり、そこからお金を頂戴できるようになるのです。
仕事は一人で完結するものではなく、誰かと交わりながら、互いに学び、影響を与え合う営みでもあるのです。 だからこそ、「働くこと」とは単に生きる手段ではなく、 「自分を社会とつなぎ、世界に関与していくための行動」と再定義すると仕事が楽しくなります。 その視点を持つことで、日々の仕事に対する意味づけや向き合い方も、少しずつ変わってくるはずです。仕事に悩んでいる若い世代におすすめの一冊です。




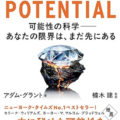

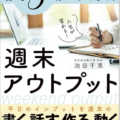



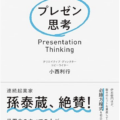







コメント