ストーリーテリングの科学
ウィル・ストー
フィルムアート社
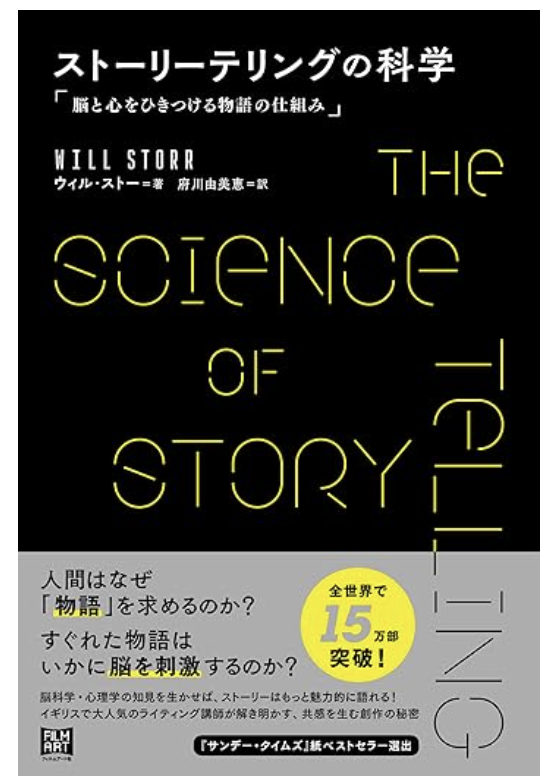
30秒でわかる本書の要点
結論: 優れた物語は「構造(プロット)」の模倣からではなく、脳の認知システムに根ざした「深い人間理解(キャラクターの歪みや信念)」から生まれる。
原因: 人間の脳は事実の羅列ではなく、変化や因果関係のある「物語」として世界を認識する習性があり、型通りの展開よりも「この人物は何者か?」という根源的な問いに強く反応するため。
対策: 「英雄の旅」のようなテンプレートに依存せず、主人公が抱える「不合理な信念(欠点)」や「自分は何者か」という問いを軸に据え、読者の脳が無視できない「変化」と「情報ギャップ」を設計すること。
本書の要約
ウィル・ストーは『ストーリーテリングの科学』で、物語とは娯楽ではなく、人間の脳が世界を理解し生き延びるための認知装置だと述べています。英雄の旅(ヒーローズ・ジャーニー)に代表されるプロット中心主義は物語を再現可能にしましたが、一方で人間の内面を置き去りにしてきました。脳は変化や不確実性、そして「この人物は何者か?」という問いに強く反応します。物語の本質は構造ではなく、信念に揺さぶられ変化を迫られる主人公の人間性にあります。
こんな人におすすめ
1. プロット作りに行き詰まっている創作初心者・中級者 。「英雄の旅」などの既存の物語構造を学んだものの、作品がありきたりになってしまったり、キャラクターに命が宿っていないと感じている人に最適です。構造(プロット)よりも「人間理解」を出発点にすることで、物語を面白くする新たなアプローチが得られます。
2. 人間の心理や行動原理に興味がある人 単なる創作技法としてではなく、「なぜ脳は物語を求めるのか」「なぜ人は不合理な行動をとるのか」という認知科学・心理学的な視点から人間を理解したい人におすすめです。物語を通して人間そのものを深く洞察したい知的好奇心の強い読者に響く内容です。
3. キャラクター造形に深みを出したい書き手 「魅力的なキャラクターが作れない」と悩む人に対し、キャラクターの「欠陥(不合理な信念)」や「神聖な価値観」に焦点を当てることで、共感を呼ぶ人物像を作るヒントが得られます。「この人物は何者か?」という問いを軸に据える重要性が学べます。
4. ビジネスやマーケティングで「ストーリー」を活用したい人 物語が脳の基本的な認知システムであるという前提は、フィクションに限らず、プレゼンテーションやブランディングにおいても強力な武器になります。受け手の脳をどう引きつけ、どう情報をギャップとして提示するかという知見は、ビジネスにおけるストーリーテリングにも応用可能です。
本書を読むメリット
・「脱・テンプレート」の創作術が学べる: 「英雄の旅」などの既存のプロットに頼りすぎて形骸化してしまった物語から脱却し、読者の心を真に動かす「人間主体の物語」を作るための新しいアプローチ(ウィル・ストー流)を獲得できます。
・「脳科学的根拠」に基づいた設計ができる: なぜ人は物語に惹かれるのか、なぜ特定の展開に興奮するのかを「脳の認知システム」から理解することで、感覚任せではなく、意図的かつ効果的に読者の興味を引きつける(変化や情報ギャップを作る)技術が身につきます。
・魅力的なキャラクター造形が可能になる: 主人公の「不合理な信念」や「欠点」に焦点を当てることで、単なる駒ではなく、生きた人間として共感を呼ぶキャラクターを生み出し、物語全体に深みと説得力を与えることができるようになります。
人間の脳はなぜ物語を必要とするのか──ストーリーテリングの科学
われわれを人間たらしめるのは物語である。(ウィル・ストー)
私たちは、日々の出来事をそのまま事実として受け取って生きているわけではありません。人間の脳は、無秩序で偶発的な現実をそのまま処理することが苦手であり、意味づけのために世界を「物語」として再構成します。
因果関係、目的と障害、敵対構造いった枠組みを与えることで、はじめて現実は理解可能なものになります。物語とは娯楽ではなく、脳が世界を把握し、生き延びるために獲得してきた基本的な認知の仕組みです。
この前提に立つと、ストーリーテリングの科学でのウィル・ストーの主張は非常にわかりやすくなります。ストーが言う「物語は脳の仕事だ」とは、物語が表現技法や語りのうまさ以前に、そもそも人間の認知の仕組みそのものだ、という意味です。
人間の脳は、世界をありのままに受け取っているわけではありません。膨大で雑多な現実をそのまま処理することができないため、出来事を大まかに整理し、意味を与え、因果関係のある「物語」として理解しようとします。言い換えれば、脳は現実世界のモデルに一種の魔法をかけ、筋の通ったストーリーへと変換しているのです。
私たちは人生を、バラバラな情報の集積として生きているわけではありません。色や動き、物体や音に満ちた世界を、脳の中で一つの流れとしてまとめ上げ、「いま自分に何が起きているのか」「自分はどこへ向かっているのか」という物語として体験しています。
自分の人生を語れるということは、その前提として、脳が自分の生きている世界全体を一つの像として思い描けている、ということでもあります。
この視点に立つと、ストーリーテリングは単なる書き方や構成の技術ではなくなります。それは、人間がどのように世界を認識し、なぜそのように考え、なぜそのように行動してしまうのかを理解するための手がかりになります。物語を学ぶことは、そのまま人間そのものを学ぶことでもあるのです。
物語論の歴史を振り返ると、ジョゼーフ・キャンベル以降、物語は明確に「プロット中心」で語られるようになってきました。キャンベルが提示した「英雄の旅」は、特定の文化や時代に依存しない普遍的な物語構造として、大きな影響力を持ったのです。
彼は世界各地の神話や伝承、宗教的物語を比較し、主人公が日常の世界を離れ、試練を経て変容し、何かを持ち帰って帰還するという共通の流れを抽出しました。この作業は、物語が恣意的な創作物ではなく、人類に共有された思考の型に基づいていることを示した点で、画期的だったと言えます。
この英雄の旅のフレームは、その後の創作の現場に大きな影響を与えました。たとえばスター・ウォーズ エピソード4をはじめ、映画や小説、ゲームまで、数え切れない物語がこの構造を土台にして設計されるようになります。
物語を「感覚的に味わうもの」から、「理解し、再現できるもの」へと変えた点で、ジョゼーフ・キャンベルの功績はきわめて大きいと言えます。 特に、物語を学びたい人にとっては革命的でした。それまで複雑で捉えどころがなく、才能やセンスの問題だと思われがちだった物語世界に、「ここを出発し、ここで試練があり、ここで変化が起きる」という明確な地図が与えられたからです。
キャンベルの英雄の旅があまりにも強力なテンプレートとして機能した結果、物語は次第に、「いま第何段階か」「次にどのイベントを置くべきか」といった、構造の正しさを優先して語られるようになっていきました。登場人物が何を感じ、何に迷っているのかよりも、通過すべきプロットの節目のほうが前に出てしまう場面が増えていったのです。
本来キャンベルが目指していたのは、人間精神の深層を理解するための比較神話学でした。しかし実際の創作現場では、その思想が次第に「便利な型」として消費されていった側面も否定できません。
その結果、出来事はきれいに整っているのに、なぜか心が動かない物語が増えていきました。この違和感は、物語の重心が人間から構造へと移動してしまったことに由来しています。
魅力的でユニークなプロットは、箇条書きのリストからではなく、登場人物から浮かび上がってくるものだと私は考えている。豊かで真実味があり、物語的なサプライズにあふれる登場人物を創造するのにもっとも良い方法は、登場人物が現実の人生においてどのように動くかを見いだすことだそしてそれは、科学に目を向けるということでもある。
ここで登場するのが、ストーのアプローチです。著者は、従来の物語論とは異なる視点で作品づくりを考察します。無数の物語を並べて型を抽出し、「面白い物語の条件」を定義するのではありません。そもそも、なぜ人間はその型を面白いと感じてしまうのか。その理由を、脳科学と心理学の側から説明しようとします。
人間の脳が、変化や不確実性、社会的な葛藤に強く反応するという性質と、結果的に一致しているだけなのではないか。ストーはこの仮説を、科学的知見を用いて丁寧に検証していきます。
この視点に立つと、物語の中心に戻ってくるのは、「人間」であることは間違いありません。構造はあくまで結果であり、出発点ではありません。主人公がどう感じ、どこで迷い、なぜ誤った選択をしてしまうのか。その理解こそが、物語を本当に生きたものにする。ストーの議論は、構造に寄りすぎた物語論を、もう一度人間の側へと引き戻してくれます。
なぜAIの書く物語は物足りないのか? 脳が求める『情報ギャップ』の正体
この人物は何者なのか?すべての物語が投げかける問いだ。この問いは、まず物語の着火点で浮かび上がってくる。予期せぬ変化が起きたとき、主人公が過剰反応したり、予想外の行動に出たりすると、われわれははっとして急に集中力を高める。
多くの優れた物語は、穏やかな日常からではなく、「何かがおかしい」と感じる瞬間から始まります。理由は単純です。人間の脳は、何も変わらない状態よりも、「予期せぬ変化」が起きたときに強く反応するようにできているからです。
神経科学者のソフィー・スコットが指摘するように、人間の知覚システムは、変化を検知する対象がなければ、ほとんど働きません。環境が安定しているあいだ、脳は比較的静かに状況を眺めています。しかし、想定外の出来事や小さな違和感が生じた瞬間、その変化は一気に神経活動の高まりとして捉えられます。
脳は即座に「これは何だ」「どう対処すべきか」と問い直し、状況を再構築し始めるのです。 物語が読者の注意を一瞬で引きつけるのは、この脳の性質を正確に突いているからです。
突然の変化が起きた瞬間、私たちの脳は自然と物語モードに切り替わり、登場人物の行動や選択を追わずにはいられなくなります。
さらに著者のストーは、人間の好奇心の仕組みにも踏み込みます。心理学者のジョージ・ローウェンスタインによれば、人は「情報が足りない」と気づいた瞬間、自発的にその欠落を埋めようとします。重要かどうかは関係ありません。いわゆる「情報ギャップ」が生まれた瞬間、脳には強い駆動力がかかるのです。
ここで重要なのが、物語における「不完全さ」です。AIが生成する物語は、論理的で整合性が高く、破綻がありません。しかし、人間の脳が本当に引き寄せられるのは、きれいに整った展開ではなく、「なぜこの人物は、こんな不合理な行動を取るのか?」という予測不能なズレです。つまり、キャラクターの歪みや欠点が生む情報ギャップこそが、物語を前に進めます。
ローウェンスタインの情報ギャップ理論が示すように、脳は「知っていること」と「知りたいこと」のあいだに空白が生じた瞬間、それを埋めるために強く動き出します。予定調和なプロットには、この空白が生まれずらいのです。
一方で、主人公が不合理な信念や欠陥を抱えていれば、「この人物は、この状況にどう過剰反応するのか」という問いが自然に立ち上がり、読者の脳はそこに釘付けになります。
情報の欠落そのものが、脳にとっての報酬になるのです。先が見えそうで見えず、期待が裏切られ、登場人物だけが何かを知っているように感じたとき、私たちは物語から離れられなくなります。 物語が進むにつれて、主人公は何度も試されます。挑まれ、選択を迫られ、信念を揺さぶられるたびに、「この人物は何者なのか」という問いが繰り返し浮かび上がります。
この問いが明確に保たれている限り、読者や視聴者は自然と物語に引き込まれます。 逆に、この問いが見えなくなり、出来事だけが前に出てしまうと、物語は軸を失い、受け手は距離を感じてしまいます。
もしストーリーテリングに秘訣があるとすれば、それは「何が起きているか」ではなく、「この出来事によって、この人物が何者として立ち上がろうとしているのか」に焦点を合わせ続けることです。そこにピントが合い続けている限り、物語は人の心を離しません。
はびこる不合理性!これこそ、物語作家としてのわれわれが登場人物の中に探し求めるべきものだ。主人公が変化するには、壊れた状態から始まる必要がある。主人公は第1幕で登場するとき、自分では気づいていないものの、はびこる不合理性という現実の中に埋没していなければならない。
主人公がどこで不合理な行動を取ってしまうのかを理解するためには、その人物が「何を絶対に守ろうとしているのか」に注目するのがいちばんわかりやすい方法です。人が「これだけは譲れない」と思っている価値や信念は、その人がどんな人物なのかを端的に表します。
同時にそれは、判断を誤ったり、自分を追い込んだりする原因にもなります。 その神聖な信念が現実とぶつかったとき、登場人物は冷静ではいられなくなります。頭では間違いだとわかっていても、合理的とは言えない選択をしてしまう。それでも行動せずにはいられない。
その瞬間に、物語のいちばん大切な部分があります。ドラマを生むのは出来事そのものではなく、「何を信じているか」が試されることで、人間の内側にある歪みや弱さが表に出てくるからです。
物語は進むあいだ、ずっと同じ問いを主人公に突きつけ続けます。それは「自分は何者になろうとしているのか」という問いです。読者の側から見れば、「この人物はいったい何者なのか」と言い換えることができます。
著者のストーが指摘するように、これはストーリーテリングにおけるもっとも根本的な問いです。 どれほど派手な事件が起きても、物語が本当に試しているのは能力や運ではありません。その人物が、どの価値を大事にし、どの信念を守ろうとするのかという点です。行動の一つひとつは、その問いに対する途中経過の答えとして積み重なっていきます。
だからこそ、結末が重要になります。どんな終わり方であっても、読者が納得するためには、この問いに対するはっきりした答えが必要です。すべての混乱や葛藤を経たあとで、主人公が結局どんな人間だったのかが見えてこなければ、物語は完結しません。幸せな結末であっても、悲劇であっても、大切なのは結果そのものではなく、人物の輪郭が最後にきちんと定まっているかどうかです。
こうして考えると、物語とは構成の良し悪しではなく、人間を理解するためのプロセスだと言えます。プロットは確かに必要ですが、それは人間性を見える形にするための道具にすぎません。登場人物が生きた人間として立ち上がったとき、プロットは自然に機能し、読者の関心は途切れません。
本書が教えてくれるのは、物語を書くための方法だけではありません。私たちはなぜ他人の人生に引き込まれ、なぜ欠点や歪みを抱えた人間に強く惹かれてしまうのか。その理由を脳と心の両面から著者は明らかにしています。
物語を描くうえで忘れてはいけないのは、どんな場面であっても、主人公は常に「自分は何者になろうとしているのか」という問いにさらされているということです。読者にとっては、それが「この人物はいったい何者なのか」という問いになります。この問いこそが物語の中心であり、物語はその問いを通して、主人公を絶えず試し続けています。作家はここを意識することで、作品のクオリティを高められるのです。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。



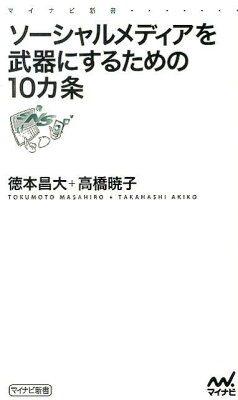













コメント