
日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学
小熊英二
講談社
日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学 (小熊英二)の要約
日本の働き方は「大企業型」、「地元型」、そして「残余型」の3つに分類されます。しかし、非正規労働者を中心とした「残余型」の増加は深刻な社会問題となっています。これらの問題を解決するためには、政治家や官僚に任せるだけではなく、国民全体で課題についてコンセンサスをとる必要があります。
日本社会のしくみとその問題点とは?
①何を学んだかが重要でない学歴重視、②一つの組織での勤続年数の重視、という二つが、「日本社会のしくみ」を構成する原理の重要な要素と考えられる。(小熊英二)
現在、日本社会は停滞の渦中にあります。その原因のひとつとして、慶應大学教授の残余型氏は「労働環境の硬直化・悪化」をあげています。長時間労働などのブラックな働き方が一部の企業では常態化しているにもかかわらず、生産性は低いままで、人材の流動性も他国に比べて少なくなっています。さらに、正社員と非正規労働者の間の賃金格差も拡大しており、これが日本社会のさらなる停滞を招いています。
日本は、高校や大学への進学率が伸びたところまでは、西欧諸国と比べても早かったと言います。しかし、それ以上の高学歴化、つまり大学院レベルの高学歴化は進んでいません。そのため、日本は1980年代までは相対的に高学歴な国でしたが、現在では低学歴な国になりつつあります。
その最大の理由は、日本では「どの大学の入試に通過したか」が重視される一方で、「大学で何を学んだか」が評価されにくいことにあります。専門の学位が評価されるのではなく、入試に通過したという「能力」が重視されるのです。このような採用基準のが、大学院進学や専門性の向上を阻み、日本の競争力を低める結果をもたらしています。
日本の労働者は欧米に比べ長時間労働を強いられていますが、その一方で生産性は他の先進国と比べて低い水準にあります。長時間労働が生産性の向上に直結しないというパラドックスがここに存在しています。これは、労働環境が労働者の効率を最大限に引き出すように設計されていないことを示唆しています。
また、日本の労働市場では人材の流動性が低いことも問題となっています。学歴至上主義やや終身雇用制度や年功序列といった従来の慣習が根強く残っており、これが労働者のキャリアの柔軟性を奪っています。その結果、労働者は一つの企業に長期間留まることが多く、スキルの多様化や専門性の向上が妨げられています。テクノロジーなどのリスクリング教育を行うことが必要な理由もここにあります。
さらに、正社員と非正規労働者の賃金格差が拡大していることも大きな問題です。非正規労働者は低賃金で働かざるを得ない状況にあり、これが社会全体の経済的な不平等を助長しています。非正規労働者の増加は、企業がコスト削減を優先するあまり、労働者の生活の質を犠牲にしている現状を反映しています。
日本社会には、女性や外国人に対する閉鎖性、「地方」や非正規雇用との格差などの問題だけでなく、転職のしにくさ、高度人材獲得の困難、長時間労働のわりに生産性が低いこと、ワークライフバランスの悪さなど、多くの問題が指摘されています。これらの問題を解決するためには、社会全体が協力し合い、根本的な改革に取り組む必要があります。
こうした背景を受け、「働き方改革」がスタートしています。働き方改革は、労働環境の改善を通じて、労働者の生活の質を向上させ、生産性の向上を図ることを目的としています。しかし、日本社会が歴史的に作り上げてきた「慣習(しくみ)」が、私たちを呪縛しています。
日本の労働文化は、長年にわたり、終身雇用や年功序列といったシステムを基盤として発展してきました。これらの慣習は一見すると労働者に安定をもたらすものの、実際には労働市場の柔軟性を奪い、労働者のキャリアパスを制限していると著者は指摘します。本書が執筆された5年前との課題感は、一部のベンチャーやスタートアップを除き、変わっていないような気がします。
ある社会の「しくみ」とは、定着したルールの集合体である。人々の合意によって定着したものは、新たな合意を作らない限り、変更することはむずかしい。
社会に非合理的な「しくみ」があるなら、参加者全員の合意を得て変える必要があります。そのためには、現在の慣習がどのように形成されたのかを理解することが重要です。ルールは元々そこにあったわけではなく、突然現れたものでもないからです。
また、欧米などの他国の良い部分だけを取り入れようとしても改革は成功しません。その社会の慣習は互いに影響し合って成り立っており、一部だけを取り入れても機能しないからです。プラス面とマイナス面を含めた全体の合意が必要です。
著者が本書で対象としているのは、日本社会を規定している「慣習の束」であり、これを本書では「しくみ」と呼んでいます。日本社会には、女性や外国人に対する閉鎖性、「地方」や非正規雇用との格差などの問題だけでなく、転職のしにくさ、高度人材獲得の困難、長時間労働のわりに生産性が低いこと、ワークライフバランスの悪さなど、多くの問題が指摘されています。
これらの問題を解決するためには、社会全体が協力し合い、根本的な改革に取り組む必要があります。
残余型の生き方が増えている理由
所得は低く、地域につながりもなく、高齢になっても持ち家がなく、年金は少ない。いわば、『大企業型』と『地元型』のマイナス面を集めたような類型である。
本書の特徴は、現代日本人の“生き方”を3つに分類している点にあります。その3つとは、「大企業型」「地元型」「残余型」です。これらの分類は、日本社会の多様な生き方を理解する上で非常に有益です。
「大企業型」は、大学を卒業し、大企業や官庁に就職して正社員・終身雇用の人生を歩む人々(およびその家族)を指します。このグループは日本社会の約26%を占め、俗に「勝ち組」とも呼ばれます。安定した収入と社会的地位を持つ一方で、地域に根付くことが難しく、長時間の通勤に悩まされることが多いというデメリットがあります。日本の社会問題はこの大企業型を中心に議論されがちであることに、私たちはもっと留意すべきです。
「地元型」は、地元の中学や高校を卒業し、そのまま地元で働く人々(およびその家族)を指します。職種は農業から自営業、地場産業まで多岐にわたり、大企業型と比べると収入は少ない傾向にありますが、地域のつながりを維持できる利点があります。地元型は日本社会の約36%を占め、地域に根ざした生活を送ることで安定したコミュニティを形成しています。
「残余型」とは、大企業型や地元型のどちらにも属さない人々を指します。このグループの人々は、長期雇用されることなく、また地域に根付くこともできない状態にあります。派遣社員やアルバイト、契約社員などの非正規雇用の形態が多く、安定した職に就くことが難しいのが特徴です。
彼らは生活費を稼ぐために、高齢者になっても働くと言う特徴があります。高齢者の就業率の高さは、地元型の農家、自営業にも言えます。老後に年金だけで生活を送れるのは、昔から大企業型の人が大部分を占めていたのです。
また、残余型の人たちは、地域社会とのつながりも希薄で、孤立した生活環境に置かれることが多くなっています。彼らが直面する最大の課題は、雇用の不安定さです。派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用では、仕事の契約が短期間で終了することが多く、次の仕事を見つけるまでの不安定な期間が生じます。この不安定さは、経済的な不安だけでなく、精神的なストレスも引き起こします。
さらに、地域社会とのつながりが希薄であるため、社会的な支援を受けることが難しく、孤立感が強まります。地域コミュニティに参加する機会が少ないことから、社会的なネットワークが不足し、緊急時に助けを求めることが難しい状況にあります。 社会的支援の欠如 残余型の人々にとって、社会的な支援が欠如していることも大きな問題です。
大企業型の人々には企業による福利厚生や社会保険制度が充実している一方で、残余型の人々はこれらの制度から取り残されがちです。特に、健康保険や年金制度に加入することが難しく、将来的な生活設計が立てにくい現状があります。
総じて日本では、1%の富裕層と99%のそれ以外というよりは、二割から三割の「大企業型」とそれ以外の格差が開いている。とはいえ、「大企業型」といえども、それほど豊かな暮らしができる世帯収入ともいえない。
残余型の人々が増加することは、日本社会全体の不安定化を引き起こします。雇用の不安定さや社会的支援の欠如により、経済的な格差が広がり、貧困層が増加します。これは、社会全体の経済活動にも悪影響を及ぼし、消費の低迷や経済成長の停滞を招くことになります。給与が長年上がらない中、税金や社会保障費や教育費の負担が上がる中で、富裕層を除いた日本人の暮らしは苦しくなっているのが実態です。
また、社会的な孤立感が強まることで、地域コミュニティの結束力が弱まり、社会全体の連帯感が失われていきます。これにより、犯罪やトラブルの増加、地域社会の崩壊などの問題も引き起こされる可能性があります。
日本社会がこの停滞を乗り越えるためには、歴史的な慣習にとらわれず、労働環境の抜本的な改革が必要です。具体的には、労働時間の短縮や柔軟な働き方の推進、人材の流動性を高めるための制度改革が求められます。
大企業型が26%、地元型が36%、残りの38%が残余型と計算され、それぞれが3割前後で均衡していることが格差のもとになっていると考えられます。この均衡が、社会全体における閉塞感や違和感を生み出しているのです。特に、残余型の増加が日本社会の不安定化を引き起こしており、これに対する対策が急務となっています。
日本社会のしくみを変える方法
日本の大企業の社員数はそれほど変化がない一方で、「地元型」から「残余型」へのシフトが進行しており、これに伴うさまざまな問題が顕在化しています。たとえば、持ち家で家族と同居している自営業者にとっては比較的問題が少ない国民年金でも、家賃を払いながら一人で生きる非正規雇用の高齢者は貧困に陥りやすくなっています。
近年、高齢者の就労率が高まっているにもかかわらず、問題が増えてきた理由の一つとして、自営業や農家ではなく非正規雇用で働く高齢者が増加したことが挙げられます。この受け皿が「地元型」と「残余型」という働き方を生み出しました。 日本では「学歴」以外に社会的な能力基準が存在せず、企業の学歴抑制効果と企業秩序の平等化/単線化が進行しました。
アメリカの労働者は、職務がなくなれば一時解雇されることを受け入れ、職員と現場労働者の間に階級的な断絶が存在しています。一方、日本の労働者は、経営の裁量で職務が決まることを受け入れ、他企業との間に企業規模などによる断絶があることを了承したのです。一部の大企業の企業単位の昇給システムだけでは、日本社会の仕組みは変えられません。
著者はここで以下の大胆な仮説を掲げます。日本では、一人の男性の賃金収入だけで十分な生活を営める世帯が全人口の約3分の1を超えたことはありませんでした。残りの人々は、親族から受け継いだ持ち家や地域的なネットワークなど、貨幣に換算されない社会関係資本の助けを得て、一家総出の労働で生きていました。彼らが個々人の所得の少なさを家族関係と社会関係資本で補っていたことが、「一億総中流」の前提だったと指摘します。
過去30年あまりの日本の変化は、「大企業型」の増加が頭打ちになる中で、自営業セクターの衰退と社会関係資本の減少が進んだ結果です。こうした変化の中で、かつての社会契約の「約束」の有効性が疑われるようになりました。社会契約がマイナス面をしのぐだけの利点があるのかが問われるようになってきたのです。
何らかのマイナス面を人々が引き受けることに同意すれば、改革は実現します。だからこそ、あらゆる改革の方向性は、社会の合意によって決めるしかない。 いったん方向性が決まれば、学者はその方向性に沿った政策パッケージを示すことができる。政治家はその政策の実現にむけて努力し、政府はその具体化を行なうことができる。だが方向性そのものは、社会の人々が決めるしかないのだ。
ポジティブな意見とマイナス面をバランスよく受け入れることが、社会の改革を実現するカギとなります。社会全体の意見が一致すれば、改革の方向性が明確になります。その方向性に基づいて学者が適切な政策を提案し、政治家が実現に向けて尽力し、政府が具体化を進められると著者は言います。
しかし、方向性は社会全体が決定しなければなりません。 従って、政治家や官僚に一任するのではなく、国民自身が社会の在り方を再考する必要があります。社会のメンバーが主体的に参加し、意見を交換し合うことで、より良い方向性を見出すことができるでしょう。国民一人一人がこの社会をどうするかの議論に加わり、社会をより良い方向に導くために積極的に行動を起こすべきです。
著者は巻末にスーパーの非正規雇用で働く勤続十年のシングルマザーの賃金についての問いかけを3つ用意しています。この答えを社会全体で考えることが求められています。日本が階層・格差社会から抜け出すための議論が必要だという著者の主張に共感を覚えました。
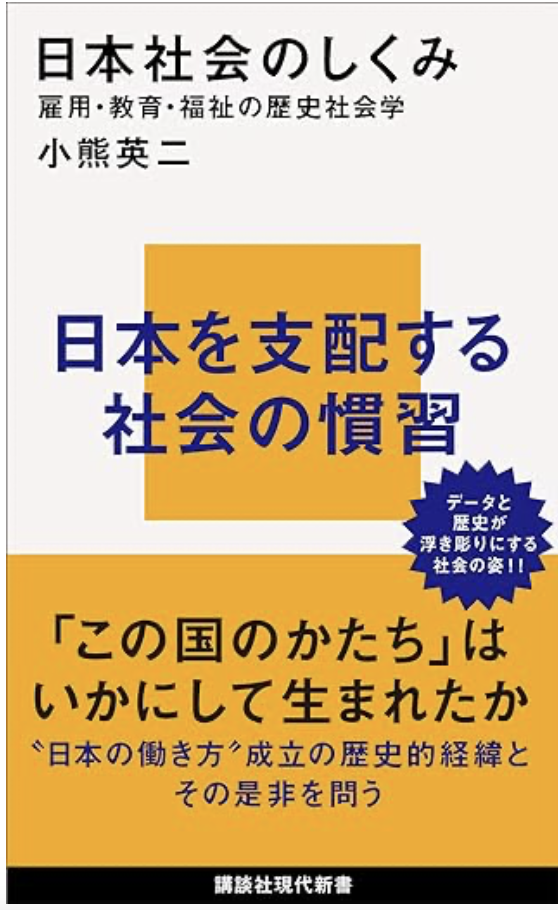
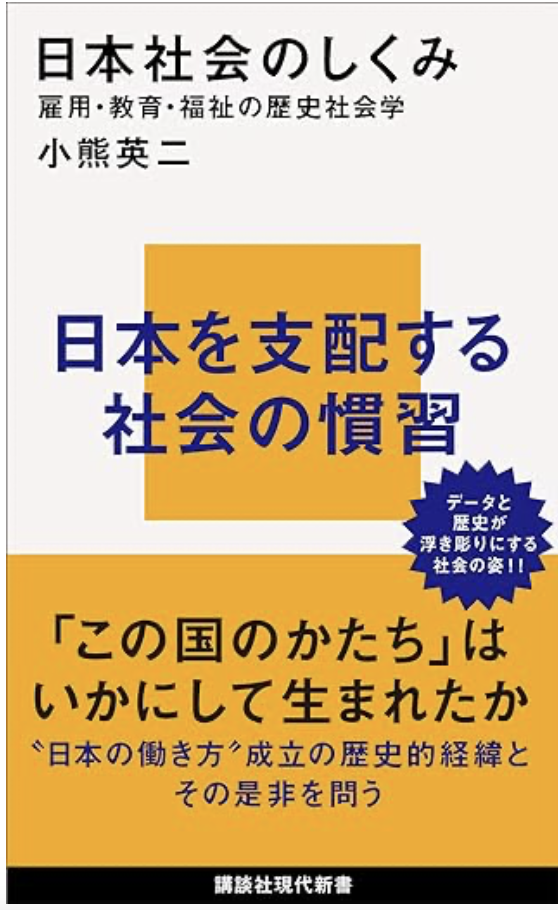
















コメント