 老いが逃げていく10の習慣 自律神経さえ整えばすべてうまくいく
老いが逃げていく10の習慣 自律神経さえ整えばすべてうまくいく
小林弘幸
講談社
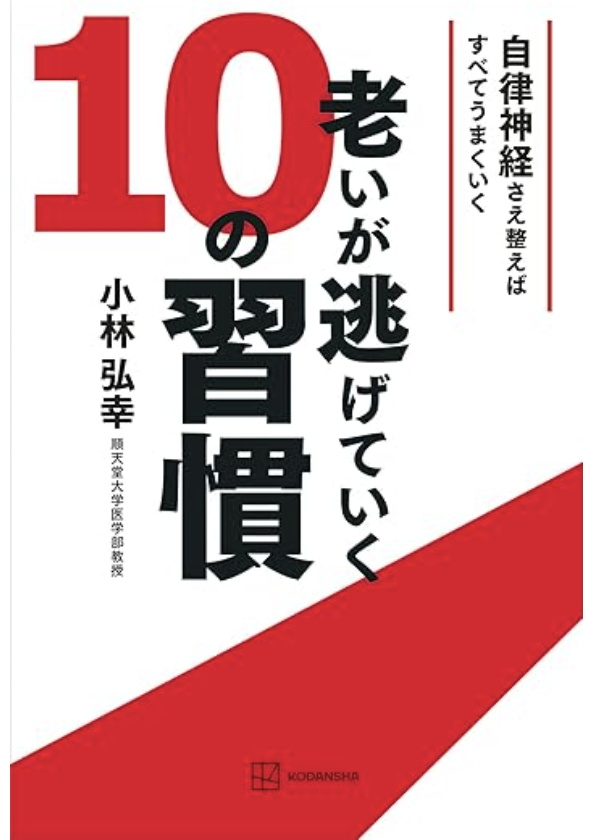
老いが逃げていく10の習慣 (小林弘幸)の要約
自律神経のバランスが整うと、心身ともに若々しさを保つことができます。この若々しさの鍵を握っているのが、私たちの日々の「習慣」なのです。わずか10の習慣を取り入れるだけで未来が大きく変わる可能性があるという事実は、年齢を重ねた多くの方々に新たな希望の光をもたらすはずです。著者が提案する自律神経を整える習慣を積極的に生活に取り入れることで、大きな変化を実感できます。
副交感神経のパワーアップが重要な理由
より大切なのは副交感神経のパワーを上げることです。現代生活はストレスも多く、不規則な生活習慣になりがちで、交感神経が優位になる場面が比較的多いのが現状。ですから、交感神経が大きく落ちることは考えにくいとされています。一方、副交感神経は加齢によって極端に落ちていくので、50歳からのエイジング戦略では副交感神経の働きを高めることに重点を置くべきなのです。(小林弘幸)
自律神経研究の第一人者として名高い小林弘幸氏は、本書で老化を遅らせるための革新的なアプローチを提唱しています。医学的見地から、自律神経の調整が若々しさを保つ鍵であると説く小林氏の理論は、多くの人々の生活習慣を見直すきっかけを与えています。
自律神経の静かな衰え現象について、医学的研究は驚くべき事実を示しています。自律神経の乱れは男性では30代、女性では40代から始まり、50歳を過ぎると機能は野生動物が自然界で生存できないレベルにまで低下するのです。この発見は、現代人の多くが気づかないうちに自律神経の機能低下に直面していることを示しています。
小林氏はいつも「自律神経の主要な機能は全身の血流をコントロールすること」と強調します。自律神経が適切に機能していれば、全身37兆個の細胞に酸素や栄養がしっかりと行き渡り、肌や髪の状態も改善するといいます。
また、消化器官を含む様々な臓器の働きが活性化されることで、疲労回復も促進されます。交感神経と副交感神経のバランスが整うことで、活動と休息のメリハリある生活が可能となり、肉体的にも精神的にも若々しさを保つことができるのです。 「トータルパワー」という概念は自律神経の状態を測る重要な指標だと小林氏は説きます。
これは交感神経と副交感神経を合わせた自律神経全体の活動量を示す総合力であり、体の疲労度を測る目安としても使われます。年齢とともに、このトータルパワーは著しく低下し、50代になると20代の約3分の1にまで減少するといいます。この事実は、加齢とともに疲れやすくなる科学的根拠を示しています。
対策として小林氏が提案するのは、特に年齢による低下が顕著な副交感神経の機能を高めることです。そのためには、自律神経を整える習慣を日常に取り入れることが不可欠となります。
小林氏自身の60代での経験から、50代と60代では肉体的・精神的な衰えの程度が大きく異なることを強調し、遅くとも55歳までに自律神経を整える習慣を身につけることの重要性を説いています。私も60代で体力が落ちてきたので、小林氏のメッセージに共感を覚えました。
この年代で適切な習慣を身につければ、集中力や判断力の衰え、疲れやすさ、免疫力低下、血流低下などに伴う病気の発症を防ぎ、老化のプロセスを遅らせることができるといいます。
より大切なのは副交感神経のパワーを上げることです。小林氏によれば、現代生活はストレスも多く、不規則な生活習慣になりがちで、交感神経が優位になる場面が比較的多いのが現状です。ですから、交感神経が大きく落ちることは考えにくいとされています。
一方、副交感神経は加齢によって極端に落ちていくので、50歳からのエイジング戦略では副交感神経の働きを高めることに重点を置くべきだと小林氏は主張しています。 自律神経を整えるための具体的な方法として、小林氏はまず呼吸法に注目します。呼吸は自律神経の支配下にあり、興奮時には交感神経の働きで呼吸が浅く速くなる一方、リラックス時には副交感神経の優位により呼吸はゆっくり深くなります。
この仕組みを利用し、意識的にゆっくりと深い呼吸を行うことで、副交感神経を活性化できるというのです。肺は再生しない臓器であり、老化で失われた機能は戻りませんが、呼吸の質は自分自身で変えることができます。肺が動きやすい環境を作り、現在の肺機能を最大限に活用する呼吸法の実践が推奨されています。
自律神経のバランスを整えよう!
副交感神経の働きが低下すると「睡眠力」が低下する 。
自律神経のバランスを整えることは、健やかな日々を送るための重要な鍵となっています。交感神経と副交感神経の理想的な1対1の関係を構築することが目標であり、これによってもたらされる効果は健康寿命の延長だけにとどまりません。日々の幸福感や生活の質の向上にも直結しているのです。
自律神経は私たちの意志ではコントロールできない様々な生命活動を支配しており、だからこそそれを整える習慣の重要性は計り知れないものとなっています。 自律神経のバランスが崩れると、特に副交感神経の働きが低下した場合、私たちの心身にはさまざまな悪影響が現れます。
その代表的な症状が「睡眠力」の低下です。副交感神経は身体をリラックスさせる重要な役割を担っており、その機能が低下すると深い眠りに入ることが難しくなり、睡眠の質が著しく低下してしまいます。質の良い睡眠が取れないことで日中の疲労回復が十分に行われず、その結果、慢性的な疲労感やストレスを感じるようになるのです。
自律神経、特に副交感神経の働きを高める方法としては、日常生活の中で意識的に取り入れられる習慣がいくつか存在します。食事の仕方も自律神経に大きな影響を及ぼす一例です。よく噛んで食べることは単に消化を助けるだけではなく、副交感神経を優位にする効果があることが知られています。一口あたり30回程度噛むことによって唾液の分泌量が増え、消化酵素の働きが活性化するとともに、咀嚼の刺激が副交感神経を適度に刺激します。
また、ゆっくりと時間をかけて食事をとることそのものがリラックスタイムとなり、心身の緊張をほぐす効果も期待できるのです。 適度な運動も自律神経のバランスを整えるのに非常に効果的です。運動中は体が活動モードになるため交感神経が優位となりますが、運動後には身体を休めるために副交感神経が自然と活性化します。
このような活動と休息のリズムが自律神経のバランスを整え、心身の健康維持に大きく貢献しています。ここで重要なのは、必ずしも激しい運動である必要はないということです。ウォーキングやストレッチといった、自分のペースで無理なく続けられる運動を習慣として取り入れることが大切なのです。
副交感神経が優位になることで得られる嬉しい効果の一つとして、腸内環境の安定が挙げられます。副交感神経は「休息・消化」の神経とも呼ばれており、消化器官の働きを促進する役割を担っています。
その結果、腸内環境が整い、善玉菌が増えることで、セロトニンといった幸せホルモンの分泌も促されるのです。近年の研究により、腸は「第二の脳」とも表現されるほど心の状態と密接に関連していることが明らかになっており、腸内環境が整うことで気持ちが明るくなり、ポジティブな思考が増えていくという好循環が生まれます。
これらの効果をもたらす自律神経を左右しているのは、私たちの「習慣」にほかなりません。日々の生活の中で何気なく行っている小さな行動の積み重ねが、自律神経のバランスを形作っているのです。
老いないための10の習慣
著者は老いないための10の習慣を明らかにしています。
・老いない習慣01 書き換える
「定年」や「還暦」というと、多くの方は人生の終わりを連想するかもしれません。しかし、これらを人生の新たな出発点として捉え直すことで、私たちの人生観は大きく変わります。 ゴールを見据えて頑張るより、今この瞬間のスタート地点に目を向けるのです。
「ここからはじまる!今からはじまる!」—このように考えるだけで、心が躍り、新しい可能性に胸が膨らみませんか? 著者は、従来の「定年=終わり」「還暦=終わり」というイメージを、「定年=はじまり」「還暦=はじまり」へと書き換えることを提案しています。
特に「還暦」という言葉は、本来とても希望に満ちた意味を持っています。十干十二支が60年で一巡し、生まれた時と同じ干支に戻る—この節目は本来、おめでたい再出発の時なのです。 還暦を迎えるということは、いわば生まれ変わるチャンスです。新しい気持ちで人生のスタートを切るには、これ以上ない絶好のタイミングといえるでしょう。人生経験を積んだ今だからこそ、新たな挑戦がより実りあるものになるのです。私も一昨年還暦を迎えましたが、このマインドセットで人生をエンジョイしています。
・老いない習慣02 片づける
60歳を超えると多くの方が抱える三大不安は、健康面、経済面、そして孤独感です。これらは日常の「片づけ」習慣で軽減できます。
片づけは体を動かす良い機会となり、自然な形での運動になります。この日常的な動きが健康維持に貢献し、結果として医療費の節約にもつながります。 生活空間の整理整頓は、お金の管理にも良い影響を与えます。計画的な行動で無駄な出費を防ぎ、所持品の把握で重複購入も避けられます。
時間を決めて片づけに取り組むことで達成感が生まれ、清潔な空間での充実感は孤独感を和らげます。整った部屋は人を招きたくなるため、自然と交流の機会も増えていきます。 このように、シンプルな「片づけ」が高齢期の三大不安に対して、意外な効果をもたらしてくれます。
・老いない習慣03 鍛える
「鍛える」とは「動く」ことの別の表現です。年齢を重ねるにつれて自然とやる気が低下していきますが、そのモチベーション低下が動く機会を減らします。動かなくなるとさらにモチベーションが下がり、負のスパイラルが始まります。 この悪循環が進むと、あらゆる出来事を後ろ向きに解釈するようになり、さらにモチベーションが低下します。ここまで来ると泥沼状態で、動かなければどんどん深みにはまるばかりです。
だからこそ「動く」ことが重要なのです。最初の一歩として「動くぞ!」という前向きな気持ちを持つことから始めてみましょう。小さな行動から変化は生まれます。
・老いない習慣04 やめる
新しいことを始めることは人生に新たな活力をもたらします。新たなスタートを切れば、人生の新たな章が開きます。しかし、新しいことを始めるには心の余裕が必要です。 この余裕を生み出す第一歩が「やめる」「捨てる」「片づける」という行為です。不要なものや活動を整理できる人は、新しいことに挑戦できる人であり、それはすなわち心も体も若々しさを保つ人なのです。
・老いない習慣05 はじめる
不安から解放される唯一の方法は「動くこと」です。新しいことを始めてわくわくする気持ちに浸れば、不安に心を奪われる余地がなくなります。行動すれば失敗や新たな心配事も生じるかもしれませんが、同時に楽しみも増え、不安への耐性も育ちます。一つの不安にとらわれ続けるより、行動して新しい喜びと不安に出会う方が、はるかに健康的な生き方といえます。
長く温めてきた夢も、行動しないまま時間が過ぎると忘れ去られがちです。そうなる前に「やりたいことリスト」(「わくわくリスト」)を作成しましょう。リスト化することで意識が高まり、関連情報やチャンスに敏感になり、具体的な行動へと進みやすくなります。
・老いない習慣06 時間を決める
「いつかやればいい」という考えは自動的に「今やらなくてもいい」に変わりがちです。そこで最も重要なのは、「今週中にここまで」「今日は何時までにここを」と具体的な時間枠を設定することです。
効率的なアプローチは
・やるべきことを書き出す
・具体的な期限を決める
・順番に実行していく
やるべきことがはっきりしないもやもやした状態は作業効率が最も低く、何をすべきか迷っている間に自律神経も乱れてしまいます。タスクを書き出して整理し、具体的な期限を決めることでモチベーションが大きく向上します。 さらに、設定する時間枠が短ければ短いほど、集中力が高まり、より密度の濃い時間を過ごせます。
・老いない習慣07 記録する
著者は「3行日記」の習慣化を推奨しています。毎日の良かったことを探して記録することで、「良いことを見つける目」も自然と養われるからです。時間が経ってから日記を振り返ると、人生のベストな瞬間が集まった宝物のような記録になります。
この習慣は特に60歳以上の方の自律神経調整に効果的です。40代以降、副交感神経の機能低下により幸せを感じにくくなりがちですが、「3行日記」で「良かったこと」「嬉しかったこと」「楽しかったこと」を意識的に見つける習慣は、心が温かくなる瞬間を増やしてくれます。
私も「感謝日記」を10年前から習慣化していますが、幸福度が確実に向上しているため、記録の効果を実感しています。
・老いない習慣08 定番を持つ
自分が何に惹かれ、何に喜びを感じ、何に「わくわく」するのか—これまで考える余裕なく走り続けてきたなら、今こそ立ち止まって内省するのに適した時かもしれません。集団の流れに身を任せるより、あなただけの個性的なスタイル(定番)を確立する好機です。
・老いない習慣09 音楽を聴く
自律神経の健全維持には食事、運動、睡眠という 3つの基本戦略があります。著者はこれらに一つだけ追加するなら「音楽」だと言います。音楽を聴くだけで緊張緩和、心の安らぎ、睡眠改善、さらには頭痛や便秘の軽減といった実際的な効果が得られることがあるためです。
・老いない習慣10 計画する
わくわくする予定を計画する習慣は、自律神経のバランスを整える効果があります。楽しみにしている予定を作ることで、交感神経は期待感で適度に刺激され、副交感神経は楽しみを想像することでリラックス効果が生まれます。
期待感によって脳内では幸福に関わる神経伝達物質が分泌され、自律神経のバランスが整います。特に高齢になるほど効果的で、交感神経と副交感神経がともに活性化し、全体的な自律神経機能が向上します。 わくわくする予定を持つことは、健康維持につながる素晴らしい習慣です。
著者のアドバイスは身体的な若さだけでなく、精神的な若さの維持にも及んでいます。人生における後悔や失敗を乗り越え、「私の人生も捨てたものではない」と前向きに捉え直す心の持ち方を提案しています。過去の出来事に囚われず未来に目を向けることで、毎日がより楽しく、充実したものになるというメッセージは、多くの人に心に響くはずです。
これらの習慣を「いつからはじめても遅くはない」と小林氏は強調します。見た目も体力も気持ちも若々しさを失ったと感じた瞬間こそが「始めどき」なのだといいます。老化対策をとるかとらないか、つまり習慣を変えるか変えないかで、将来の若々しさに大きな差が生じます。
科学的根拠に基づいた小林氏の習慣の提案は、老いを恐れるのではなく、自律神経という身体の司令塔を整えることで、より健康で充実した人生を送るための道しるべとなります。たった10の習慣で未来を変えられるという可能性は、年齢を重ねた多くの人々に新たな希望を与えてくれるはずです。







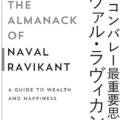



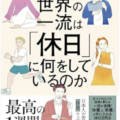



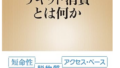

コメント