面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論
山崎亮
光文社
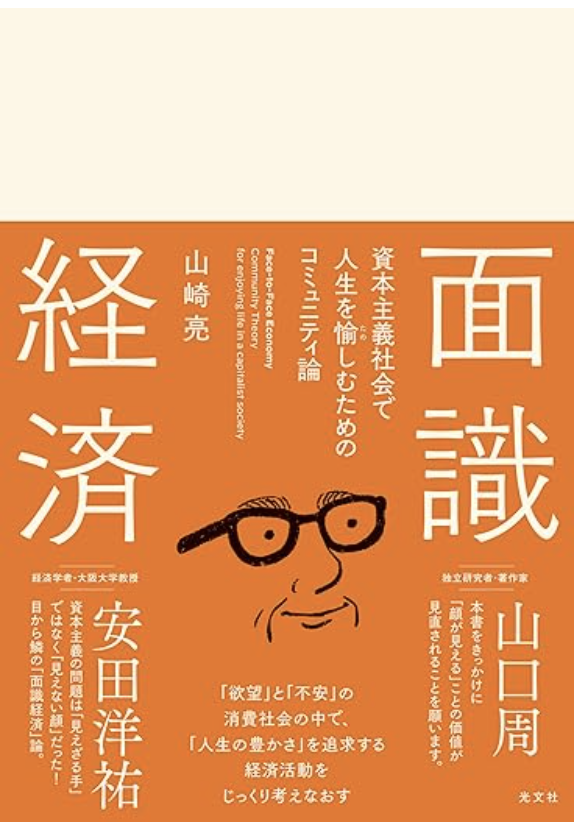
面識経済(山崎亮)の要約
山崎亮氏は、顔の見える関係に基づき、人と人とが支え合う経済活動を「面識経済」と定義し、その可能性を説いています。効率より信頼を重視するこの視点から、地域起業や地元での消費を促し、ジョン・ラスキンの思想を背景に、自分らしく生きるための新たな地域経済のあり方を提示しています。
面識経済が地域を活性化する!
人生こそが財産であることを知り、その財産の力を最大限に発揮させて、お互いの顔が見える規模を維持した経済行為を生み出す人がたくさん暮らす地域。面識経済比率の高い地域。ラスキンに言わせれば、そんな地域こそが「豊かな地域」ということになるのでしょう。(山崎亮)
現代の資本主義社会において、効率や利益の追求によって便利な生活がもたらされた一方で、人と人とのつながりや地域との関係性が希薄になりつつあります。こうした状況に対して、改めて「豊かさとは何か」「地域の活性化とはどうあるべきか」を問い直す動きが広がっています。
studio-L代表であり、東北芸術工科大学教授(コミュニティデザイン学科長)でもある山崎亮氏の面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論は、この問いに対して、コミュニティという視点から新たな経済のあり方と豊かな暮らしの姿を提示しています。
本書の中心にある「面識経済」というコンセプトは、顔の見える関係性の中で営まれる経済活動を指します。これは、単に取引相手を知っているというだけでなく、互いに信頼し合い、応援し合いながら成り立つ経済のあり方です。どこで、誰から、なぜ買うのか?そうした問いを大切にすることで、、貨幣が都市へ流出せず、地域内にとどまります。そこから人と人とのつながりが深まり、地域全体の活性化へとつながっていきます。
山崎氏は、こうした考え方の背景に、経済思想の整理を行っています。アダム・スミス、カール・マルクス、ジョン・メイナード・ケインズの近代以降の主流経済モデルを紹介しながら、それらでは捉えきれないローカルにおける「人間関係に基づいた経済」の可能性を掘り下げています。
その中で、19世紀の思想家ジョン・ラスキンの考え方が重要な位置を占めています。ラスキンは、経済とは他者に良い影響を与え続ける営みであると考え、物質的な豊かさよりも倫理性や共同体の価値を重視しました。山崎氏の面識経済は、このラスキン的な経済観を現代の地域社会において実践する試みとも言えます。
たとえば、地域にある個人商店では、家賃や光熱費、人件費、オーナーの所得など、売上の多くが地域に残ります。仮に売上が330万円で、8割が地域に還元されるとすれば、264万円が地元にとどまる計算です。
これは、全国チェーンの店舗と比較すると、売上が少なくても地域への経済的な貢献度が高いことを示しています。 さらに、こうした個人店が3店舗(カフェ、雑貨屋、ヘアサロンなど)地域にでき、それぞれが地元経済を意識した運営を行っているとすれば、年間売上合計1000万円のうち800万円が地域内で循環します。
同規模の全国チェーンの店舗が地域に残す金額が約200万円であることを考えると、面識経済に基づく店舗の効果は非常に大きいといえます。 この循環は一度きりではありません。地域に残った800万円が再び使われ、その8割、つまり640万円がまた地域に還元されるのです。
このような貨幣の循環が繰り返されることで、地域経済が自立し、持続可能な発展を遂げることが可能になります。 そのため、山崎氏は「自分が使う貨幣の行方」を意識することを提案しています。多くの人がお金を地域で使うことで、その地域や起業家が潤うと言うのです。
1000円を全国チェーンで使えば、その大部分が地域外へ流出してしまいます。一方で、地元の個人店で使えば、その多くが地域にとどまり、次の誰かの活動を支える原資となるのです。
地域の若者起業家を応援しよう!
若者がその地域で起業して、地域貢献型の店をつくったのなら、大人たちは率先してその店に通ってほしい。そうやって応援してほしい。
著者は、地域で起業しようとする若者を支えることの重要性を強調しています。地域外のサービスばかりを利用しながら、「この地域では食べていけない」と悲観的な言葉を投げかけるのではなく、地元で挑戦する若者にこそ応援の手を差し伸べるべきだと語ります。彼らがつくる店や場を地域の人々が日常的に利用することによって、面識経済はより強固なものとなり、地域のつながりと経済の循環が深まっていきます。
このような地域起業が現実的な選択肢となっている背景には、過去の世代によって整備されてきたインフラの存在があります。建物や道路といった物理的基盤に加えて、ウェブサイトやSNSといった情報環境もすでに整っており、かつてのような巨額の初期投資がなくとも、小規模な事業を始めることが可能な時代になっています。
こうした時代の変化が、「面識経済」の広がりを後押ししています。人生こそが最大の財産であり、その財産を活かして他者と関わり合いながら経済活動を営むことができる地域こそ、これからの社会において注目すべき場だといえるでしょう。
ジョン・ラスキンの言葉を借りれば、「他者に良い影響を与え続ける人」が集う地域こそが、真に豊かな地域であると著者は指摘しています。 面識関係、すなわち顔の見える関係性には、目には見えにくいものの、非常に重要な価値が含まれています。
たとえば、相手を思いやること、仕事を認めて褒めること、共に喜び合うこと、応援し合うこと、そして愛情をもって関わることなどです。
こうした行為の積み重ねは、ラスキンが語る「人生という財産が持つ力」にも通じており、人間らしい経済の本質を体現するものだと言えます。 もちろん、私たちの生活すべてを面識経済の中で完結させることは現実的ではありません。
しかし、日々の選択や行動によって、生活の中で面識経済の比率を少しずつ高めていくことは十分に可能です。そのためには、生活者として、また労働者として、それぞれの立場から意識を持つことが大切です。
生活者として意識したい点は3つあると著者は言います。
①地域の経済循環を意識すること。
②必要なものをなるべく顔の見える関係の中から購入すること。
③広告などによって不必要な欲望を刺激されすぎず、本当に必要なものを見極める姿勢を持つことです。
また、労働者としては2つの視点が求められます。第1に、非面識的な労働にかける時間を可能な限り減らし、地域での活動に余暇の時間を振り向けること。
第2に、面識的な仕事を楽しみながら、地域の面識経済に主体的に貢献することです。 こうした意識と行動の積み重ねによって、「地域の活動」と「面識的な仕事」が増え、地域全体としての面識経済比率が高まることが期待されます。
本書は、このような人間らしい経済のあり方を、理論と実践の両面から捉え直しています。顔の見える関係性を大切にし、地域に根ざした経済の可能性を探る内容は、現代の私たちに、経済と暮らしの新しい接点を考えるきっかけを与えてくれます。
そして何より本書は、効率や規模といった従来の経済指標だけでは測れない、生き方の選択肢を示しています。他者とつながり、応援し合いながら働き暮らすという「面識経済」の考え方は、自分らしく生きるための一つの有力な選択肢として、今後さらに注目されていくことでしょう。










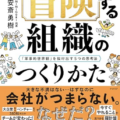




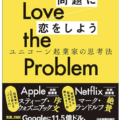
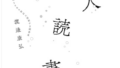

コメント