The Principle of Innovation Engineering イノベーションエンジニアリング原論
乘浜誠司
ビジネス教育出版社
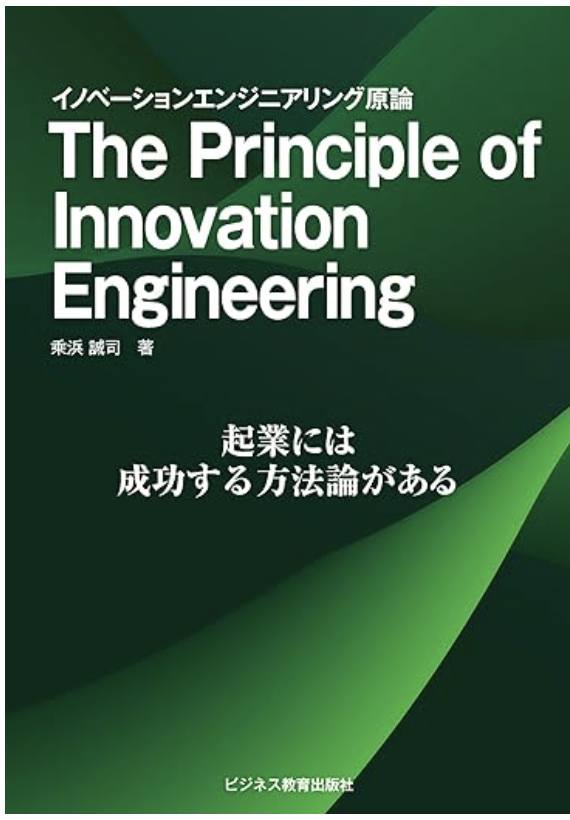
The Principle of Innovation Engineering イノベーションエンジニアリング原論 (乘浜誠司)の要約
『イノベーションエンジニアリング原論』は、アイデアを持続可能なビジネスへと進化させるための体系的プロセスを示した一冊です。論理モデル・プロセスモデル・物理モデルという三層構造を通じて、起業や新規事業開発における成長戦略を構築します。さらに、AIや最新テクノロジーとフレームワークを組み合わせることで、自社に最適化された情報管理基盤「エンサイクロピディア」を構築し、変化に強く柔軟なビジネスを実現できます。
起業を成功させるフレームワークとは?
起業には成功する方法論がある(乘浜誠司)
なぜ起業はこれほど難しいのでしょうか。どれだけ情熱やユニークなアイデアがあっても、それだけでは事業を持続的に成長させることはできません。再現性のある起業の方法論がなければ、意思決定はその場しのぎになり、やがて事業は行き詰まってしまいます。
しっかりと作り込んだつもりの事業計画も、いざ実行に移すと現実と噛み合わず、何から手をつけていいのか分からなくなる。仲間や資金も集まらず、自分の判断が本当に正しいのか、自信を失ってしまう。こうした壁に、多くの起業家が直面しています。
こうした課題に対して、構造的な解決策を提示してくれるのが、乘浜誠司氏によるThe Principle of Innovation Engineering イノベーションエンジニアリング原論です。です。私がフレームワークの授業を担当しているiU 情報経営イノベーション専門職大学において特任教授を務める乘浜氏は、「起業には成功する方法論がある」と指摘します。
この思想は、イノベーションエンジニアリングの中核にあり、これまで運の良さやCEOのカリスマ性といった属人的な要素に依存していた起業観からの脱却を促します。
本書が提案するのは、イノベーションを偶発的な現象ではなく、工学的に再現可能なプロセスとして捉える視点です。論理的なフレームワークに基づけば、誰もがイノベーションを実践可能なスキルとして習得できるという可能性が見えてきます。起業を「感覚」ではなく「構造」でとらえるこのアプローチは、これからの時代において起業家に不可欠な視座を提供してくれます。
成功を科学するという視点から、乘浜氏のフレームワークを用いれば、誰もがイノベーションの実践者になれるという可能性を本書は示してくれます。
本書では、イノベーションの創出プロセスを細部にわたって分解し、具体的な思考法やフレームワークを提示することで、誰もが意識的にイノベーションを起こす可能性にアプローチしています。iUで実践的に起業のフレームワークを展開してきた乘浜氏の主張は、ロジカルかつ現場感覚に富み、最新の理論を踏まえた説得力のある内容でした。
イノベーションエンジニアリングにおいて提示されている「論理モデル」「プロセスモデル」「物理モデル」という3つのフェーズは、単なるビジネスアイデアを、実際の市場で機能する持続可能な事業へと段階的に進化させるための設計思想です。
これらのフェーズは相互に独立したものではなく、継続的なフィードバックを通じて精度を高めながら、実行可能な形に洗練されていきます。
プロセス全体は、「アイデアの創出(論理モデル)→実行可能な計画の策定(プロセスモデル)→実際の運用設計(物理モデル)」という流れで展開され、ビジネスの成功確度を高める実践的な方法論として機能します。
論理モデルでは、事業の基本的なアイデアや方向性、ターゲット市場を明確にし、競争優位性を見極める段階です。
プロセスモデルでは、策定した事業計画を現実の業務プロセスへと落とし込み、マーケティングや販売戦略の具体化を行います。
物理モデルでは、それらを基にシステム実装や資金調達、市場展開へと進め、実際のビジネス運用へと結びつけます。
さらにこの三層モデルには、「構築→設計→RID(仮説検証)→分析→計画」という検証の流れが内包されており、段階的な試行と改善によって精度の高いビジネスモデルが形成されていきます。
中でもRID(Rapid Innovation Development)は、アイデア段階での仮説を短期間で検証し、早期に方向性の是非を判断するための重要なフェーズです。このプロセスでは、ユーザーの反応や市場の初期データに基づいた検証を行い、仮説が現実に適合するかどうかを迅速に見極めることが求められます。
時間やコストのロスを最小限に抑えながら、イノベーションの現実性と有効性を明らかにするため、アジャイル的なアプローチとも親和性が高い点が特徴です。
たとえば、構築フェーズではMVPの開発やプロトタイプの作成を通じて、実行可能性を早期に見極めることができます。設計フェーズでは業務フローやUX設計、技術的選定を行い、RIDフェーズで実際のユーザー反応を検証し、仮説の成否を判断します。
その後の分析フェーズでは、事業の収益性やKPI、競合環境を見定めたうえで、計画フェーズへと進みます。最終的には、スケールアップ戦略や市場展開の方針が明確になり、持続可能なビジネスへとつながっていきます。 このプロセス全体を通じて注目すべきは、データに基づいた意思決定の重視と、段階的にリスクを低減させる構造にあります。感覚や勢いだけに頼るのではなく、検証と計画を繰り返すことで、着実に実行力のある戦略が構築されます。
特に、投資家やステークホルダーへの説得材料としても、このようなフレームワークの存在は大きな強みとなります。ビジネスモデルの仮説検証や実績、さらに今後の事業計画をロジカルかつ実証的に構成し、ピッチ資料として提示することで、投資家の意思決定を促すことが可能になります。
単なるビジョンの提示にとどまらず、それを裏付ける論理とエビデンスを併せ持つことで、資金調達や外部パートナーとの連携においても大きな優位性を発揮します。
私自身も個人投資家として多くのピッチを受けていますが、このような構造化されたアプローチに基づいた提案があれば、投資を積極的に検討したくなるのが正直なところです。
エンサイクロピディア×フレームワーク:変化に強い事業構築の鍵
イノベーションは、単なるアイデアの創出だけではなく、それを実現し、持続的に成長させるための体系的なプロセスを必要とする。この「論理モデル→プロセスモデル→物理モデル」という段階的アプローチを適用することで、起業家や企業は、より確実な成長を遂げることができる。
「論理モデル→プロセスモデル→物理モデル」という段階的アプローチはスタートアップに限らず、大企業の新規事業開発やR&D(研究開発)部門にも広く応用でき、データドリブンな意思決定と高い市場適応力をもたらす点で、持続可能なイノベーションを生み出す強固な基盤となると著者は指摘します。
さらに、情報活用の観点では、「エンサイクロピディア(Encyclopedia)」の概念も極めて重要です。これは、企業や組織が保有する情報資産を一元管理し、効率的かつ整合性の取れたデータ活用を可能にする知識ベースであり、組織内のデータモデルや業務ルール、プロセス、システムの関係性を統合的に記述することで、仕様変更にも柔軟に対応できる仕組みを提供します。
このような知識基盤をイノベーションエンジニアリングの中核に組み込むことで、事業構築のスピードと柔軟性は飛躍的に高まり、変化の激しい環境にもスピーディに対応できる体制が整います。
さらに、AIやNotion、Confluence、Airtable、Miro、SharePointを本書のフレームワークを使って活用するこで、自社のニーズに最適化されたエンサイクロピディア管理環境を構築することが可能になります。これにより、知識とデータの統合的な活用が進み、より洗練された意思決定と持続可能な成長が実現されます。
イノベーションエンジニアリングは、リスクを最小限に抑えつつ、成長を着実に実現するための合理的で柔軟なアプローチです。論理モデル・プロセスモデル・物理モデルという三層構造により、事業の全体像を俯瞰しながら、各フェーズを有機的に連動させることで、精度と実行力を兼ね備えたビジネスモデルを構築できます。
この体系は、市場適応性、スケーラビリティ、財務の健全性、業務効率といった本質的な要素を包括しており、これからの時代に起業家が直面する「ハードシングス」に対しても、解決の糸口を提示してくれるはずです。起業家や大企業の新規事業担当者におすすめの一冊です。
本書は乘浜誠司氏からご恵贈いただきました。





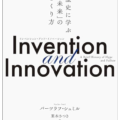

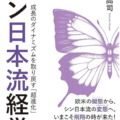










コメント