これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか? と悩んだときに読む採用の新基準
秋山真
アスコム
これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか? と悩んだときに読む採用の新基準(秋山真)の要約
従来の学歴や職歴に重きを置いた採用では、自社に本当に適した人材を見極めることが難しくなっています。価値観や行動様式までが自社と一致する「スタイルマッチ採用」が求められる今、本書ではその実現に向けた3つのステップを提示し、採用のあり方を見直すヒントを与えてくれます。
採用はスタイルマッチの時代へ
現代の成長企業は”合う人”に選ばれるスタイルを持っている。(秋山真)
欲しい人材が集まらない――。ようやく集まっても、すぐに辞めてしまう。 現場からは「もっと即戦力が欲しい」と言われ、経営層からは「人件費に見合う成果を出せ」とプレッシャーがかかる。書類や面接では優秀に見えた人材が、いざ入社してみると職場になじめず、早期離職につながる。こんな課題に頭を抱えている採用担当者や人事責任者は、決して少なくないのではないでしょうか。
少子高齢化による人材不足、価値観の多様化、そしてオンライン選考の一般化により、これまで有効とされてきた「学歴・職歴重視」や「ナビサイト依存型」の採用手法が、もはや機能しづらくなっています。
にもかかわらず、多くの現場では採用業務に忙殺され、「本当に自社に合う人材とは何か」「採用の質をどう高めるか」と立ち止まって考える余裕がないのが実情です。
こうした状況に警鐘を鳴らし、新たな視点を提示しているのが、元博報堂でNo Company代表の秋山真氏によるこれまでと同じ採用手法で大丈夫なのか? と悩んだときに読む採用の新基準です。本書が提案するのは、単なるスキルや経験の一致ではなく、価値観や行動様式といった“スタイルの一致”を基準にした「スタイルマッチ採用」という概念です。
従来の採用が「採って終わり」だったとすれば、スタイルマッチ採用は「入社後の定着と活躍」までを見据えた戦略的アプローチと言えます。これまで主流だった「スペック採用」や「カルチャーマッチ」では、学歴・スキル・企業文化といった外形的な要素に焦点が当てられてきました。
確かに、それらは判断しやすく効率的な軸ではあります。とくに中小企業や専門職採用では、一見有効に機能する場面もあるでしょう。 しかし、スペックとはあくまで過去の情報に過ぎません。
履歴書や職務経歴書では見えない「価値観」「働き方」「意思決定スタイル」こそが、入社後のパフォーマンスや定着に直結するにもかかわらず、これまで十分に考慮されてこなかったのです。
しかし、スペックはあくまで過去の実績や形式的な情報に過ぎません。そこに表れていない「価値観」や「仕事への姿勢」「行動のスタイル」といった要素は、実は入社後の活躍や定着に大きな影響を与えるにもかかわらず、スペック情報からは見えてこないのです。
たとえば、高学歴で有名企業出身の候補者がいたとしても、その人が「曖昧な環境の中でも自ら判断しながら進めていく」ことを求められるカルチャーに適応できるとは限りません。逆に、スペック上は平凡に見える人が、現場で強い自律性や協働力を発揮し、チームに大きく貢献するケースもあります。
さらに、スペックに依存した採用は、しばしば画一的な人材ばかりを集めてしまいがちです。これにより、組織の多様性が失われ、新たな視点や創造性が生まれにくくなるという副作用もあります。 そしてもう一つの課題は、「スペックが似ているからといって、価値観や働き方のスタイルまで一致するとは限らない」という点です。
これは、従来型のカルチャーマッチでも見落とされがちな部分です。 「カルチャーに合う人を採ろう」といった方針は一見もっともらしく聞こえますが、その企業文化自体が抽象的で曖昧な場合、候補者にとって実感を持って判断することは困難です。
企業が「自由な社風」や「スピード感ある環境」といった言葉を使っていても、実際には厳格な承認フローがあったり、逐一の報告が求められる文化だったりすることも少なくありません。 こうした言葉と実態のズレが、入社後の違和感やミスマッチ、さらには早期離職へとつながっていくのです。
だからこそ、いま注目すべきは、単なるスペックや表面的なカルチャーではなく、「行動のスタイル」や「価値観の体現レベルでの一致」を重視する「スタイルマッチ」という視点です。
スタイルマッチを実現するための3つのステップ
スタイルマッチは、多様で選択肢の多い時代に”希望の選び方”を届ける。
スペックだけでは見えない本質的な価値観に目を向けることで、企業に本当にフィットする人材を採用しやすくなります。本書では、そのスタイルマッチを実現するための具体的なプロセスを、3つのステップに整理して解説しています。
ステップ1 自社の「現在地」を正しく把握する
まず必要なのは、自社の採用活動における現状を客観的に見つめ直すことです。マーケティングでよく使われる「3C分析Company(自社)Competitor(競合)Customer(顧客)」の枠組みを応用し、採用における自社の立ち位置を把握します。
この際、経営層、ミドルマネジメント、現場社員といった各層にアンケートやインタビューを行うことで、現場のリアルな声や価値観を浮き彫りにしていきます。
・Business・・・経営者の思い、事業への向き合い方
・Culture・・・社内でよく使われる言葉、人と人との関係性
・Job・・・職種ごとのこだわり、活躍する人の特徴
・Action・・・社員の言動・働き方、個人の裁量や判断軸
競合分析において重要なのは、同業種のビジネス競合を見るだけでなく、採用市場における“採用競合”にも目を向けることです。つまり、自社と同じ人材層をターゲットにしている企業が、どのように候補者にアプローチしているかを把握する必要があります。
採用は「こちらが選ぶ」行為であると同時に、「選ばれる」活動でもある以上、他社と比較されたときに自社がどのように見えているのかを把握することは、極めて戦略的な意味を持ちます。 その際に有効なのが、企業の魅力を構成する4Pの分析です。
Philosophy(目的・方針)、Profession(仕事・成長)、People(人・風土)、Privilege(待遇・給与)から競合分析を行います。企業が何を大切にしているか、どんな仕事と成長環境を提供しているか、どんな人たちがいてどんな文化があるか、そして報酬や福利厚生の水準はどうか。こうした情報を収集・比較することで、単なる条件比較にとどまらない自社の魅力の再定義が可能になります。
さらに見逃せないのが、辞退者からのフィードバックです。選考過程で自社を選ばなかった人たちの声には、自社の打ち出し方や魅力の伝わり方に関するヒントが多く含まれています。なぜ選ばれなかったのか、どこにズレを感じたのか。その理由を丁寧に拾い上げることで、採用コミュニケーションの質を高めることができます。
こうしたインプットとアウトプットを重ねることで、自社にとって相性の良い人材像――つまり、スタイルの合う人の特徴――が見えてきます。スタイルマッチ採用を成功させるうえで、この相性の可視化は欠かせないプロセスです。
ステップ2 自社のスタイルを言語化する
次に、自社の価値観や行動指針を具体的な言葉で表現する作業が求められます。ここで重要なのは、曖昧なスローガンではなく、日々の業務の中に現れている「判断」と「行動」のエピソードから価値観を読み取ることです。
たとえば、「顧客志向」を掲げる企業であれば、どのような場面で、誰が、どんな判断をして行動したのか――そうした具体事例をもとに、自社のスタイルを可視化していきます。言語化が進むことで、企業としての一貫性あるメッセージを発信しやすくなります。
ステップ3 誰に・何を・どう伝えるかを設計する
スタイルを言語化できたら、それを「誰に」「何を」「どう伝えるか」を戦略的に設計するフェーズに入ります。たとえば、Z世代をターゲットにする場合、SNSや動画コンテンツが有効かもしれません。一方で、ミドル層を狙うなら、ウェブサイト上の社員インタビューや現場密着記事が響く可能性もあります。
大切なのは、発信するチャネルを問わず、一貫したスタイルが伝わるように設計することです。メッセージにブレがあると、せっかくの価値観が誤解されるリスクも生まれます。
また、スタイルを社内外に共有するためのすべての情報発信の軸になる取扱説明書=スタイルブックを作成すると良いと言います。
本書では、KDDI、IHIなどの実際の企業事例も紹介されており、それぞれがどのような課題を抱え、どのようにスタイルマッチを実現したかを具体的に知ることができます。
スタイルマッチが広がれば、企業は「合う人」と出会い、個人は「自分らしくいられる場」を選べるようになる。誰もが「何者かでなければならない」という呪縛ではなく、自分のスタイルを認められる社会に近づいていける。 そんな未来を、私たちは本気で目指しています。
スタイルマッチという視点が広がれば、企業は自社に「合う人」と出会えるようになり、個人も「自分らしく働ける場所」を主体的に選べる時代が訪れます。
誰もが無理に「何者か」になろうと背伸びするのではなく、自らのスタイルが認められる――そんな健全な関係性が、組織と個人の間に築かれていくはずです。
採用において「なぜ成果が出ないのか分からない」「定着率が上がらない」と悩んでいる方こそ、一度立ち止まり、これまでの前提を見直すことに意味があります。本書には、そうした思考の転換を支えるヒントと実践知が詰まっています。
“カルチャーマッチ”という曖昧な基準から、“スタイルマッチ”という本質的な共鳴へ。採用の質そのものを問い直すこの変化を、どう読み解き、どう戦略に落とし込むか――。 本書は、これからの採用に真剣に向き合うすべての人にとって、実用的かつ示唆に富んだ一冊です。
本書はアスコムさまからご恵贈いただきました。
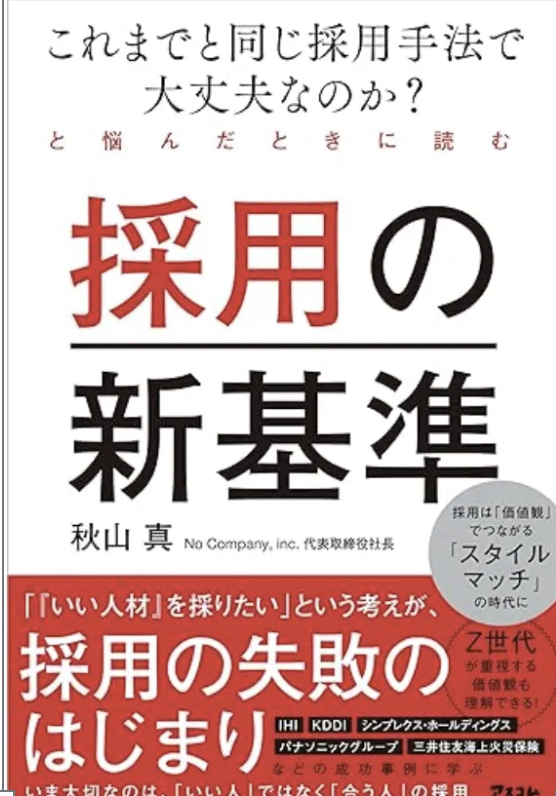















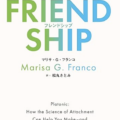

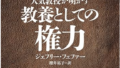
コメント