ウェルビーイングのジレンマ 幸福と経済価値を両立させる「新たなつながり」
デロイト トーマツ グループ
日経BP
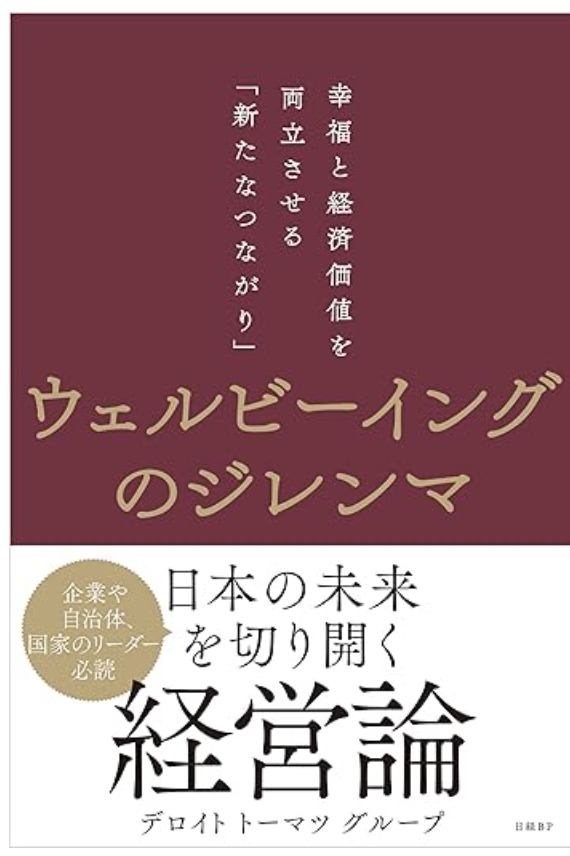
ウェルビーイングのジレンマ 幸福と経済価値を両立させる「新たなつながり」(デロイト トーマツ グループ)の要約
2025年、日本の幸福度は世界55位と低迷し、経済大国でありながら先進国の中で最下位にあります。その背景には、社会的孤独・孤立や将来不安があり、コミュニティーの希薄化が幸福を阻害しています。幸福と経済の両立には、双方向のつながりを重視する「ウェルビーイング経営」が必要であり、個人の成長や貢献を軸に企業・投資家・自治体が連携することが重要です。丸井、日本生命、福井県、FC今治などの事例は、新たなコミュニティー形成の方向性を示し、日本をウェルビーイング先進国へ導く実践的な手がかりとなっています。
ウェルビーイングのジレンマを乗り越える方法
真に豊かなウェルビーイング社会を目指すためには、主観的な幸福度(以下:幸福)と経済的な豊かさ(以下:経済価値)の双方を満たす必要がある。しかし一方で、
その両立を図ることは決して容易な道のりではない。ここに「ウェルビーイングのジレンマ」が存在する。(デロイト トーマツ グループ)
2025年の「世界幸福度報告」において、日本の順位は55位でした。経済規模では世界第4位を誇るにもかかわらず、先進7カ国の中で最下位に位置しているのです。この結果は、日本社会が直面する根深い課題を示しています。
本書はこれを「組織のステークホルダーの幸福と経済価値の両立を図り、持続的成長を実現する経営手法」と定義しています。言い換えれば、幸福と経済価値の双方が重なり合う領域を最大化することで持続的な成長をもたらす方法です。そしてこれは、主観的な幸福と経済価値の両立というジレンマを解消することを目指しています。
ウェルビーイング経営の要諦は、すべてのステークホルダーの幸福を追求する包括的な視点を持つこと、個人の主観的な幸福を真摯に把握して経営に反映させること、そして短期ではなく長期的な関係性を築きながら調和を図ることにあります。幸福の効果は即効的に数値化できるものではなく、時間をかけて積み重なるものです。
例えば、従業員への投資が生産性を高め、やがて企業の成長を導き、最終的に株主の利益にも還元されていきます。このように長期的な視点こそが、ステークホルダー間の調和を実現し、企業価値を持続的に高める原動力となるのです。 そもそも個人の幸福は主観的であり、人によって感じ方や捉え方は異なります。 そのため「これをすれば必ず幸福が実現する」という普遍的な方法論は存在しません。
だからこそ重要になるのが、ステークホルダーとの双方向の関係性です。組織が一方的に幸福を与えるのではなく、対話や協働を通じて人々の幸福度の変化を理解しながら、共に価値を創出していく必要があります。
これからのウェルビーイング社会の実現に向けては、企業、自治体、国などあらゆる組織が、幸福と経済価値の間のジレンマを乗り越えるために、組織からの一方的ではなく、「双方向のつながり」をいかに創出できるかが問われている。
ウェルビーイング経営は単なる理論ではなく、未来の社会の骨格を形づくる具体的な指針です。個人、企業、社会が互いにつながり合い、幸福と経済的豊かさを両立させることで、真に持続可能で創造的な社会が拓かれていきます。その先にあるのは、個が輝き、社会全体が輝く「ウェルビーイング先進国」としての新しい日本の姿なのです。
幸せな会社の特徴とは?
経営層と社員の間で企業理念が共有され、プライベートな話題も含めて社内で人間的な会話ができるのが、幸せな会社の特徴です。
こうした潮流を理解するうえで欠かせないのが、武蔵野大学の前野隆司教授の言葉です。教授は「富や名誉といった目に見える成果がもたらすのは『ドーパミン型の幸せ』で、それは強いけれども一瞬で終わる」と語ります。達成感や成功体験から生じる幸福は確かに力強いものですが、時間とともに消え去ってしまうのです。
対照的に、「共感や感謝がもたらすのはオキシトシンやセロトニンによる幸せで、これは穏やかで長続きします」と教授は指摘します。誰かに感謝されたり、誰かを思いやったりすることで得られる幸福は、一度経験するとやめられないほど持続的で、人の生き方そのものを変えていく力を持っています。
さらに教授は「何かを成し遂げた時に『みんなのおかげだ』と考えることで、ドーパミンとオキシトシン・セロトニンの両方が出る」とも述べています。ここにこそ、人間の幸福を深めるヒントがあります。自分ひとりの成果と捉えるのではなく、仲間や家族、社会の支えがあってこその達成だと認識するとき、人は瞬間的な喜びと持続的な安らぎの両方を得ることができるのです。この「二重の幸福」が、個人をよりしなやかにし、組織や社会全体にも好循環をもたらします。
前野教授は、穏やかで持続的な幸福を得るための最初のステップとして「ボランティアなどの利他的な活動を試みてほしい」と勧めています。無理やりでも行動を起こせばオキシトシンが分泌され、これまで気づかなかった新しい幸福に出会うことができる。幸福とは待つものではなく、行動によって育まれるものだというメッセージです。
この視点を踏まえると、ウェルビーイング経営の本質も見えてきます。組織がステークホルダーに一方的に「幸福」を与えるのではなく、利他的な姿勢を持ちながら双方向の関係性を築き、共感や感謝を循環させていくことが不可欠なのです。個人の幸福は主観的で、普遍的な処方箋は存在しません。だからこそ対話を重ね、互いの価値観を理解しながら協働することが、経済的価値と幸福の両立を可能にする唯一の道なのです。
ウェルビーイングと相関が高い要素を見ていくと、「自分の成長」や「人への貢献」があげられます。コンフォートゾーンでリラックスする時間と、成長や貢献に向けて挑戦する時間。その両者をどうバランスさせるかが幸福の質を左右します。ワークライフバランスという言葉は一般的ですが、重要なのはワークとライフのどちらにおいてもウェルビーイングを追求することです。どちらかが損なわれれば、真の幸福にはつながりません。
日本が目指すべきは、経済的豊かさとともに、共感や感謝に支えられた持続的な幸福を育む社会です。その時々の達成感にとどまらず、利他的な行動や「みんなのおかげだ」という気持ちから生まれる幸福を広げていくことが重要です。それが個人の輝きを引き出し、社会全体をより豊かにし、やがてウェルビーイング先進国としての未来を切り拓いていくのです。
そして前野教授は、幸せな会社の条件として「経営層と社員の間で企業理念が共有され、プライベートな話題も含めて人間的な会話ができること」を挙げています。社員がワクワクする気持ちで働けるように、経営者はウェルビーイングをやり続けるという強い意志を持ち、その姿勢を伝え続けなければなりません。単なる施策にとどまらず、企業文化を変革するほどの覚悟が求められるのです。
結局のところ、ウェルビーイングとは経済的な指標や一過性の成功を超えた、人間らしい豊かさの追求です。感謝と共感の輪を広げ、成長と貢献を両立させ、双方向のつながりを育むこと。その実践が個人を輝かせ、組織を変え、社会全体をウェルビーイングへと導きます。日本が未来に向けて歩むべき道は、まさにそこにあります。
ウェルビーイング経営のフレームワーク
将来有望顧客の潜在ニーズを「顕在化」し、顧客との関係を強化するための「結束化」の取り組みを計画することによって、より「経済化」に向けた道筋が見えてくる。
企業経営に関わるステークホルダーは、顧客や従業員、地域社会、投資家など多様です。だからこそ、自社のパーパス、つまり存在意義や事業の方向性に基づき、誰をステークホルダーとするかをまず定める必要があります。その上で重要になるのが、幸福と経済価値を結びつける三つのプロセスです。
最初の段階は「顕在化」です。これは、各ステークホルダーが潜在的に抱えている幸福の価値観を明らかにし、組織が目指す方向性と重なる部分を可視化する取り組みです。幸福を組織の成長に結びつけるには、相手が本当に求めているものを知らなければなりません。
一方的に理念や戦略を押し付ければ、幸福はただのスローガンに終わってしまいます。だからこそ双方向の対話を通じて理解を深め、共通の目標を見いだすことが欠かせないのです。この合意こそが、経済価値と幸福を両立させるプロセスの出発点になります。
次に訪れるのが「結束化」です。共通の理解や目標を基盤に、組織とステークホルダーが継続的に協力できる関係性を強めていく段階です。大切なのは、自発的に動きたくなる仕組みをつくることです。押し付けられた活動は長続きせず、成果も限定的です。
しかし、自らが共感した目標に沿った行動であれば、人は自然に力を注ぐことができます。企業はこの段階で、制度や仕組みを整え、ステークホルダーが自ら幸福度を高める行動を起こしやすい環境を用意する必要があります。結束が生まれれば、行動の変化や幸福感の高まりが連鎖し、組織と社会の関係は一層強固になります。
そして最後の段階が「経済化」です。双方向の関係性を基盤にして、幸福を経済価値に結びつける仕上げのプロセスです。企業であれば、顧客の幸福度が高まることでファンが増え、口コミや推奨によって新しい顧客が広がっていきます。従業員が幸福を感じていれば創造性や生産性が高まり、利益やブランド力の強化につながります。地域の自治体においても、住民の満足度が高まることで地域活動が活発になり、人が集まり、経済が潤っていきます。
幸福を経済的成果へと転換することは、企業にとっても自治体や国家にとっても欠かせない視点です。 重要なのは、この3つのステップを独立したものとしてではなく、段階的に連動させ、長期的な視点で継続していくことです。
「顕在化」で共通の理解を形成し、「結束化」で協力を深め、その関係を「経済化」によって成果へと昇華させていく。この循環が回り始めれば、幸福と経済は相反するものではなく、互いを高め合う関係として社会の持続的な成長を支えていきます。
ウェルビーイング社会の実現は、理念やスローガンではなく、こうした逆算思考に基づく実践の積み重ねによって拓かれるのです。
新たなつがなりが重要な理由
これからの日本社会で、多様な形で人と人との「双方向のつながり」を強くする新たなコミュニティーを創出することは、孤独や孤立、将来的な不安といった課題を解消するために必要不可欠な取り組みである。こうした多様な形で生まれる新たなコミュニティーは、ウェルビーイング先進国を実現する上での”土台”になる。
日本は経済的な豊かさを誇りながらも、幸福度が低い国だとしばしば指摘されます。その背景には、二つの深刻な社会問題が横たわっています。第一は、社会的孤独・孤立です。内閣府が2023年に実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」によれば、日本人の約半数が孤独を感じていると答えています。
OECDの「Better Life Index」では「必要なときに頼れる人がいる」と答えた人の割合が41カ国中32位と低く、日本の孤立傾向は国際的にも際立っています。さらに千葉大学の中込敦士特任准教授らの研究によると、社会的孤立は幸福度を下げるだけでなく、死亡リスクを1.9倍、認知症リスクを1.66倍、介護リスクを1.5倍に高めることが明らかになっています。孤独は心の問題にとどまらず、健康や生存そのものを脅かす深刻な課題なのです。
第二の問題は、所得や仕事に起因する将来不安です。雇用の安定性や年金制度、社会保障への不信感が広がり、経済的な不安が人々の幸福を揺るがしています。老後に身寄りがなく、十分な年金もない状況を想像すれば、「自分は何を頼りに生きていけばよいのか」という不安が押し寄せます。
コミュニティーの希薄化が進み、「頼れる人がいない」という現実が、この不安をさらに強めているのです。 単身世帯の増加や都市化による地域の結びつきの弱体化は、従来のコミュニティーの機能を失わせています。その結果、人は「居場所」を失い、孤独や孤立、経済的不安に直面するリスクを高めています。
本来、地域や職場、家族といったコミュニティーは、人が安心感や人間関係を得るための土台でした。しかし現代社会では、それらが十分に機能せず、個人が自力で人間関係を築かなければならなくなっています。こうして社会構造の変容そのものが、日本人の幸福を阻む要因になっているのです。 では、どうすればよいのでしょうか。鍵は「新たなコミュニティー」の創出にあると著者たちは指摘します。
ここで言う新たなコミュニティーとは、既存の家族や職場といった枠組みを現代に合わせてアップデートすることに加え、生活のあらゆる領域に応じて多層的にコミュニティーを築くことを意味します。
買い物や食事、学びや趣味、スポーツや娯楽、さらにはオンラインの世界にまで広がる多様なつながりを通じて、人々は双方向の関係を取り戻すことができます。その結果、孤独や孤立、将来不安といった課題が解消され、ウェルビーイング社会を実現する土台が築かれていくのです。
丸井やノボ ノルディスクといった企業の実践が注目される一方で、日本生命のような投資家がウェルビーイングを軸に投資を行う姿勢や、福井県に見られる地域コミュニティーの取り組みなど、企業・投資家・自治体それぞれのケーススタディが充実している点も評価できます。こうした多角的な視点の重なりが、ウェルビーイングを経済と社会に定着させる推進力になるからです。
私は特に、FC今治が掲げる「共助のコミュニティー」という考え方に強く共感を覚えました。人々が互いに支え合い、幸福を共有する姿勢は、これからの日本が必要とする新しい社会像を映し出しています。経済的な豊かさの上に、人と人とのつながりを再生し、共感と感謝が循環する仕組みを築くこと。それこそが、孤独や不安を超えて、日本をウェルビーイング先進国へと導く確かな道筋なのです。
経済的な豊かさだけでは幸福は成り立たず、孤独や不安を和らげる人と人との双方向のつながりが不可欠であることを本書は明らかにしています。多様なコミュニティーを再構築し、その上で制度や社会の仕組みを刷新していくことが、日本をウェルビーイング先進国へと導く大きな一歩になるのです。





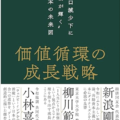


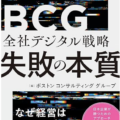


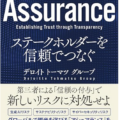

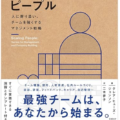




コメント