古典に学ぶ現代世界
滝田洋一
日経BP
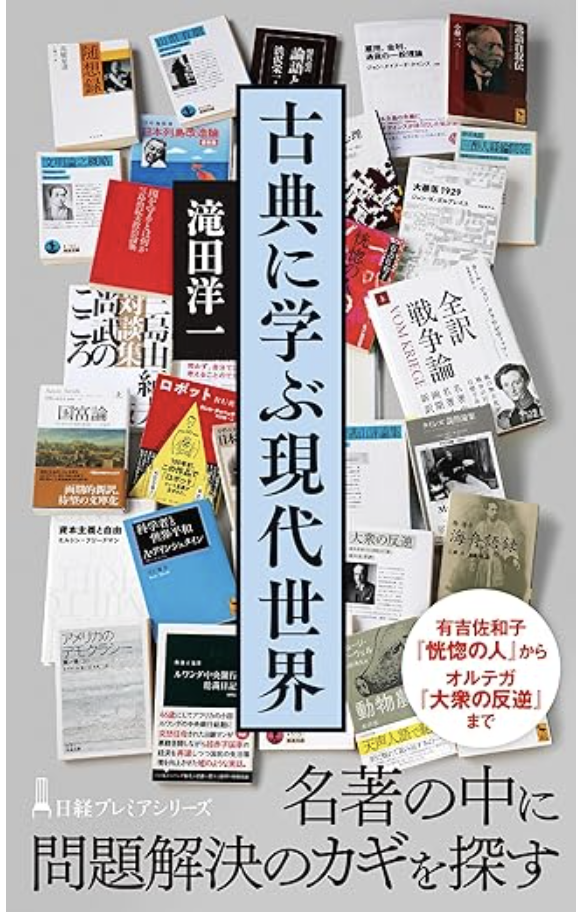
古典に学ぶ現代世界 (滝田洋一)の要約
本書は、過去の名著を現代の視点で読み直し、古典がいまを読み解くヒントとなることを示しています。政治、経済、社会、文化など6つの視点から多様な書籍を紹介し、特に『ケインズ 説得論集』や『国富論』『戦略論』などを通じて、現代の課題との接点を浮かび上がらせます。古典に挑む価値を再認識させてくれる一冊です。
私たちが古典を読むべき理由
読んだつもりの古典。積ん読の名著。中身をすっかり忘れた既読書──。混迷を深める今こそ、そんな書物をひもとく機会である。(滝田洋一)
現代に生きる私たちにとって、古典を読むことは敷居が高いと感じられがちです。新刊本のほうが現代の課題に即していて、すぐに役立つように思えるでしょう。インターネットで最新情報があふれ、数秒ごとにアップデートされる世界に暮らしていると、何十年、あるいは何百年も前に書かれた本に価値があるのか疑問を抱くのも無理はありません。
私自身、これまでに何冊も古典に挑戦しては、途中で投げ出してしまった経験があります。読もうと思って買ったのに積ん読になったままの本、数ページで挫折した本、最後まで読み切ったのに内容をすっかり忘れてしまった本──振り返れば、思い当たるものばかりです。古典は読みたい気持ちがあっても、なかなか腰が重く、読者にとって「難しい存在」として立ちはだかります。
そんな先入観をくつがえし、古典の価値をいまに引き寄せてくれるのが、古典に学ぶ現代世界です。 著者は、日本経済新聞社の客員編集委員・滝田洋一氏。経済ジャーナリストとしての豊富な知見と、古典を現代の視点で読み直す鋭い洞察をもとに、日経BOOKプラスでの人気連載を大幅に加筆・再構成しています。
滝田氏は古典を「昔の難しい本」として扱うのではなく、現代の経済や国際情勢、社会の問題と重ね合わせて読み解きます。古典は、ただの歴史的な記録ではなく、私たちが今日を生き抜くためのヒントを与えてくれるコンパスなのです。
取り上げられているのは、ジョージ・オーウェルの動物農場から、J・K・ガルブレイスの大暴落1929に至るまで、政治・経済・社会・文化を横断する34冊の名著。どれも単なる「過去の書物」ではなく、現代の文脈と交差する示唆に満ちた書籍ばかりです。
① 描かれていた未来
オーウェルの『動物農場』やカレル・チャペックのロボット小説、有吉佐和子の恍惚の人といった作品には、未来社会を先取りするような視点が描かれています。
② 戦争とポピュリズム
クラウゼヴィッツの戦争論では、防御側の優位性や、外国からの支援を得るための条件が示されています。「国家としての健全さ」が支援の前提であるという視点は、日本の安全保障にも直結します。
一方で、トクヴィル、ル・ボン、オルテガ、カール・ポパーといった思想家たちは、大衆迎合主義(ポピュリズム)の危うさと、民主主義の構造的な脆弱性を鋭く捉えています。彼らの議論は、現代のメディア環境や政治的分断を理解するための重要な補助線となります。
③ 日本社会への眼差し
福沢諭吉による啓蒙思想、中根千枝の社会階層論、ルース・ベネディクトの菊と刀、イザベラ・バードの旅行記、岡潔や寺田寅彦の随筆などが取り上げられています。日本人の思考様式や社会構造に対して、内側と外側の視点から多角的な考察がなされています。
④ 政治家が挑んだ課題
勝海舟、山県有朋、高橋是清、石橋湛山、田中角栄といった歴史的な政治家たちは、それぞれの時代における危機の局面で、困難な選択を迫られてきました。彼らの判断や思想には、現代のリーダーシップ論にも通じる多くの教訓があります。 特に、田中角栄と周恩来、キッシンジャーによる日中・米中の交渉は、戦略と信義が交錯する外交のリアルを映し出しており、歴史の複雑な奥行きを感じさせます。
⑤ ビジネスを切り拓く
カーネギー、渋沢栄一、小林一三、服部正也(ルワンダ中央銀行総裁)などのビジネスパーソンの足跡を通じて、経済活動の現場で求められる価値観や行動様式が浮かび上がります。変化の時代においても、彼らの姿勢には普遍性があり、現代のビジネスにも応用できる洞察が詰まっています。
⑥ 経済学の巨人の教え
アダム・スミス、ケインズ、シュンペーター、フリードマン、ガルブレイスといった経済学の巨人たちの思想がわかりやすく紹介されています。著者は理論だけでなく、その背景にある時代や哲学、社会観にも目を向けており、経済を「人間の営み」として読み解く視点が得られます。
中でも、ケインズ 説得論集を通じて、滝田氏がケインズの思想を現代的に再評価している点はとても印象的です。ケインズの柔軟な思考と論理的な説得力は、いまもなお色褪せることなく、現代経済に通じる視座を提供してくれます。
たとえばケインズは、「インフレよりもデフレの方が深刻である」と明言しました。この指摘は、長期にわたるデフレを経験し、ようやく緩やかなインフレの局面に入った私たちの実感と重なります。物価が適度に上昇し、経済がようやく動き始める――そのこと自体が健全な兆候であるという視点は、まさに現代の空気感に通じるものです。
未来を読むために古典をひらく
ユダヤ人は偉大な民族ですが、国をつくると狂信的でありすぎるのかもしれません。現在イスラエルが中東でやっていることを見ると、気が気ではありません。 (高坂正堯)
国際情勢の変化を読み解くうえで、高坂正堯の史観はいまも示唆に富んでいます。外交官・国際政治学者として政策の現場に関与しながら、リアリズムと知性を併せ持つ語り口を貫いた彼の視点は、現代の情勢に対しても鮮度を失っていません。
国家とは本質的に抑制の効かない構造を孕んだ存在である。高坂がかつて警鐘を鳴らしたその構造的暴走は、イスラエルによるガザ侵攻を見れば明らかです。安全保障と正義の名のもとに、国家は容易に自制を手放します。イスラエルという国家が抱える過剰性は、まさに高坂が指摘した「国家を持ったユダヤ人の狂信性」という命題の実例として、現実に立ち上がってきています。
同様に、ロシアによるウクライナ侵攻もまた、国家の力が暴走する構図の典型です。情報操作とプロパガンダによって正当性を演出し、侵略が「秩序の回復」にすり替えられていく。その手法は、ジョージ・オーウェルの『動物農場』に描かれたスターリン体制と見事に重なります。だからこそ、オーウェルの古典は長い時間を経てもなお、現実を読み解く鋭利なツールとして機能し続けているのです。
2022年以降、米中ロの三極構造が改めて意識される中で、「新たな冷戦」という言葉が再浮上しました。人口学者エマニュエル・トッドは、「第三次世界大戦はすでに始まっている」と警告しています。この緊張感の中で、「冷戦」という言葉自体の起源に注目するのも一つの知的態度です。チャーチルではなく、実はオーウェルが最初にこの言葉を使ったという事実は、彼の洞察力の深さを示しています。(エマニュエル・トッドの関連記事)
オーウェルの1984年に描かれた世界──ユーラシア、オセアニア、イースタシアの三大国家による分割支配=フィクションとして読まれてきたその構図が、いまや現実になりつつあります。
ロシアの勢力拡大は、まるでオーウェルの描いた「ユーラシア」を想起させます。米英豪による安全保障枠組み「オーカス」は、オセアニア的な体制を思わせ、そして中国の覇権的影響力が東アジアを覆う様は、イースタシアの現実的な再現とすら言えるでしょう。フィクションの中に描かれた構図が、いま目の前で再演されつつあるのです。
その中で、ドイツのメルケル政権が果たした役割は歴史的に重いものでした。理念として脱原発・脱炭素政策を優先した結果、ロシアのエネルギーに依存を深めることとなり、抑止力を自ら手放してしまったのです。エネルギーによる従属関係が、安全保障の脆弱性を生む――その典型的な事例といえるでしょう。
また2017年、習近平主席がトランプ大統領に語った「太平洋には米中が共存できる空間がある」という発言も看過できません。これはまさに『1984年』のストーリーを想起させます。太平洋を東西に分割するという発想は、もはや小説の中だけの空想ではなく、現実の戦略的構想として浮かび上がっているのです。
さらに戦争の形も変質しています。かつては物理的な領土争奪が主でしたが、いまや戦争は情報空間で展開され、認識や世論を奪い合う新たな様相を呈しています。国家同士の競合は、領土・資源だけでなく、人々の「思考」や「情報環境」をも舞台として広がっているのです。
中国人民解放軍が戦略として採用している「三戦」──輿論戦・心理戦・法律戦──は、相手国の判断力や意志決定を外部から操作しようとする試みです。日本の政治家や官僚組織がこの戦略に対して鈍感であることが、日本の将来的なリスクを高めています。中国からの帰化が増えることも三戦の一環だと捉え、私たちはもっと危機感を持つべきだと思います。
加藤秀治郎・東洋大学名誉教授による新訳『全訳戦争論』も、いま再び読むべき一冊です。クラウゼヴィッツは「防御側こそが他国の支援を得やすい」と述べていますが、その支援の前提となるのは、国家としての健全さと自助努力です。国際支援とは、単なる善意ではなく、戦略的合理性に基づいて行われるのです。
一方で、日本国内にも静かなる危機が進行しています。高齢化と核家族化がもたらした介護の問題は、家庭と職場の両方に深刻な負荷を与えています。その中で導入された介護保険制度は、社会によるケアの分担という発想を実装した画期的な制度でした。現在、約606万人が制度を利用していますが、その財政的持続性には大きな課題が残されています。
有吉佐和子の『悦惚の人』は、介護というテーマにいち早く切り込んだ先駆的な小説です。認知症を患った父が発症から1年で亡くなるという物語上の設定は、実際の介護現場のリアリティから見れば、むしろ軽度であるとも言えます。
もしこの介護が3年、5年と続いていたら──そのとき家庭はどうなっていたのか。滝田氏は、有吉があえてその「先」を描かなかったことに注目し、それは読者に想像を委ねるための意図的な省略だったと指摘します。物語の余白が、現実の重さを逆照射しているのです。
介護保険制度は、高齢化という構造的課題に対して、「介護の社会化」という明確な回答を提示しました。家庭内で抱え込んでいたケアの負担を、制度の枠組みで分担しようという試みは画期的です。ただし、その代償として、膨大な財政負担が国家と国民にのしかかり続けています。
「必要性」と「持続可能性」の間で揺れる構造的ジレンマは、制度設計の限界を如実に物語っています。 『悦惚の人』は今、さらに重要な作品として読み直されるべきです。医療、福祉、行政、そして政治──いずれの分野もこのテーマから逃れられません。そして最終的には、私たち一人ひとりが「自分の問題」として向き合わなければならない課題なのです。
一方、視線を経済へと移せば、アダム・スミスの国富論(山岡洋一訳)が再びその存在感を放ちます。「社会のために事業を行っている人が、実際に社会の役に立った例は聞いたことがない」。この辛辣な一文には、公益を掲げる制度や規制が、しばしば創造性や競争を抑圧するという、鋭い批判精神が込められています。
制度が理念に寄りすぎれば、現実の柔軟性を失い、イノベーションの芽を摘む結果になりかねません。過剰な統制が市場の活力を奪い、形式的な正義が機能不全を生む。スミスが示したのは、自由な競争の中でこそ、社会の力学が最も健全に働くという原理です。それは今なお、経済の本質を突く原則として有効です。
本書で紹介されている書籍の多くは、読もうと思いながら手をつけられていない本、途中で挫折した本、内容を忘れてしまった既読書、あるいは新訳であらためて読み直したくなるような古典ばかりです。 滝田氏のレコメンドを通じて、古典には時代を超えて今を照らす力があることを、あらためて実感しました。
今回、その流れで、「ケインズ 説得論集」新訳の「国富論」「戦略論」の3冊を購入しました。積ん読の山がこれ以上高くならない保証はありませんが、それでもなお、古典に挑む価値はあると確信しています。
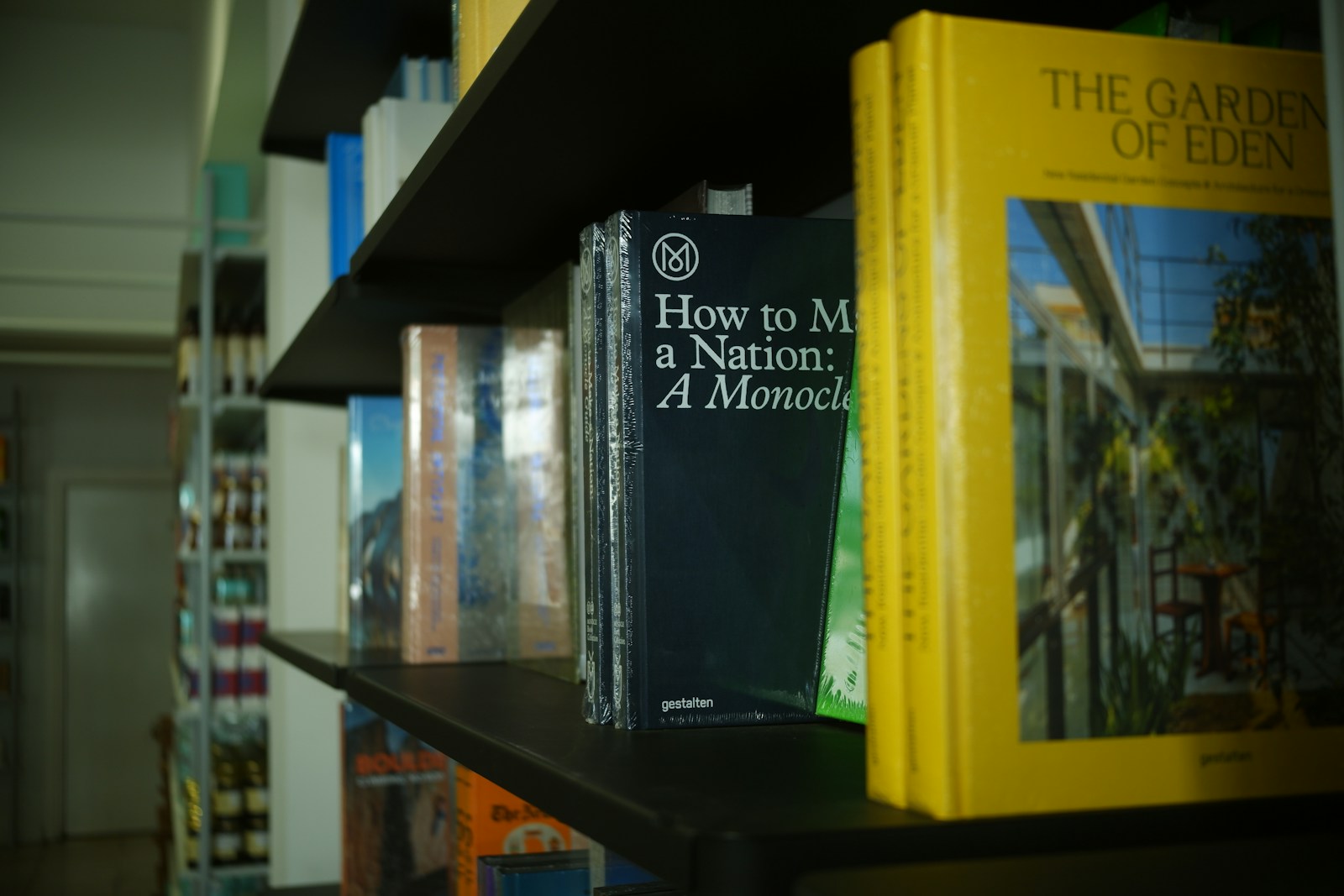




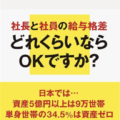



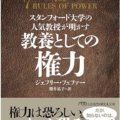




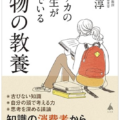
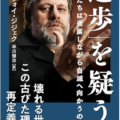


コメント