精神科医が教える 良質読書
名越康文
かんき出版
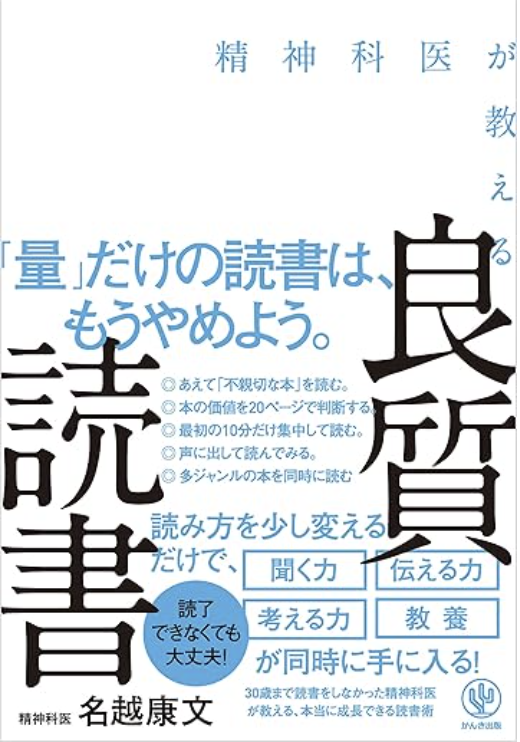
精神科医が教える 良質読書(名越康文)の要約
名越康文氏は、親切でわかりやすい本ばかり読んでいても思考力は鍛えられず、「限界を超える読書」こそが本当の知的成長を促すと述べています。わからない部分に立ち止まり、問いを抱えながら本と対話することで、理解が深まり、自分の内面も変化していきます。そうした読書の積み重ねが、人生の困難を乗り越える力となり、世界の見え方さえ変えてくれるのです。
限界を超える読書
少しでも「限界を超えた」という感覚が得られれば、それは今後の人生を生きてゆく力になっていきます。そうした経験を積み重ねていくことで、人生で出くわすきつい場面を乗り切るための力が得られるのです。(名越康文)
本が売れない時代になり、難解な本が減り、わかりやすい本が増えています。しかし、そこに問題があると精神科医の名越康文氏は指摘します。 たとえば、自分にとって楽な筋トレを続けても筋肉がつかないのと同じように、「親切な本」をいくら読んでも、思考力や知性といった“頭の筋肉”は鍛えられません。
精神科医が教える 良質読書は、読書が苦手な人や、読書をしても自己成長につながっていないと感じる人に向けた一冊です。30歳まで本を読まなかった著者自身が、試行錯誤を経て身につけた読書術を紹介しており、「量」よりも「質」を重視する姿勢を打ち出しています。
本当に自分を成長させてくれるのは、「不親切な本」です。つまり、読み手にやさしく語りかけてはくれない本です。読者自身が繰り返し立ち止まり、自問しながら読み進めなければならない本こそが、知的な対話を促し、深い学びへと導いてくれます。
名越氏は、自分を成長させてくれる本を、1日数ページずつじっくり遅読することを推奨しています。遅読とは、ただ読むスピードが遅いという意味ではありません。内容を咀嚼し、自分の中に落とし込むプロセスを大切にする「対話型の読書」です。読み手が本と向き合い、問い返し、考えながら進むことで、知性が鍛えられていきます。
私はまず目次や「はじめに」「あとがき」に目を通し、本全体の地図を描きます。速読によって要点をすくい上げ、その一冊が投資に値するかどうかを瞬時に判断するのです。ここでは徹底して効率を重視します。 そして、真に自分を成長させてくれると感じた本に出会ったとき、読み方を一転させます。
今度は「遅読」へ切り替え、ページを行きつ戻りつしながら著者と対話し、言葉をじっくり咀嚼していく。このプロセスこそが、知識を血肉化する営みです。
本書では、読書から得られる学びを深めるための工夫が数多く紹介されています。中でも、現在の自分には難しいと感じる「限界を超える本」を、対話を重ねるように少しずつ読むことこそが、最も深い成長につながると強調されます。
著者は、多読や速読が“良い読書”とされがちな風潮に対し、それは誤解だと断じます。人生を豊かにするには「良質な読書」が不可欠であり、本書はそのための具体的な方法を示しているのです。 著者が読書を続ける理由は2つあります。
1つは、テレビのコメンテーターや講演活動など、アウトプットが求められる場面に備えるためです。もう1つは、読書とは「自分に会うため」にするものだと考えているからです。ここでいう「自分に会う」とは、精神科医として長年抱いてきた「人間とは何か」を問う営みそのものです。
「人間はどこまで成長できるのか」「どこまでを理解し、表現できるのか」「社会をどう変えていけるのか」といった問いに向き合うには、難解な本に挑む必要があります。しかも、それは一気に読破するような類のものではなく、丁寧に行間を読み取り、対話を繰り返すように読み進めるべき本なのです。 そのような“限界を超える本”は、読むのが本当に苦しいものです。
私も、翻訳本の専門書や哲学書は、1日数ページ、あるいは数行しか進めないこともあります。それでも読み続けるのは、そこに自己成長につながる効用があると考えるからです。
著者の名越氏も、限界を超える本だけが自分を成長させてくれると述べていますが、こういう本と対峙することが、読書の醍醐味なのです。 「限界を超える経験」は、生きる力になります。読書を通じてその感覚を得るには、本と対話するように向き合いながら、少しずつページをめくっていくことが必要です。そうした時間が、自分にとって本当に大切な問いと出会う機会を生み出します。
また、「限界を超える読書」には、意外な副産物があるといいます。読書を通じて心が落ち着き、人の話を丁寧に聞けるようになるのです。私たちは、他人の話の7割を聞き逃し、3割を誤解しているとさえ言われます。難しい本に粘り強く向き合う経験は、そのまま「他者の話を理解しようとする姿勢」に転化されていきます。これはまさに、本との対話が人との対話にも影響を与えることを示しています。
本書では、著者が実践しているさまざまな読書法も紹介されています。読む・考える・書く(ツイート)を組み合わせた「三角読み」、お経のように繰り返し読む「お経読み」、複数の本を往復しながら読む「振り子読み」、合わなければ飛ばす「斜め読み」、「どうせこうだろう」と決めつける「上から目線読み」、1時間で6冊を交互に読む方法、「10分だけ集中読書」、異分野の本を関連づける「他ジャンルリンク読み」、好きな俳優の声を想像して読む「音読」、音声を聞きながら黙読する方法など、多彩なテクニックが紹介されています。
私自身も日々このブログを書く中で、名越氏が紹介している「三角読み」「他ジャンルリンク読み」「斜め読み」といった手法を取り入れています。特に、さまざまなテーマを扱う記事を構成するには、幅広い情報をインプットしながら思考を深める必要があります。
そのためには、一気に全体像を掴む速読と、本と対話を重ねるような遅読のバランスが欠かせません。速読によって大まかな流れをつかみ、遅読によって本質を探る。この掛け合わせが、文章の質を高め、より深い洞察を引き出す読書につながると実感しています。
量子的読書が成長を加速させる!
難しい本を読むことで、多少なりともその感覚が味わえる瞬間がある。感覚を先取りしておくと、実際の壁の乗り越えにも好影響があります。
難解な本に取り組むと、最初はまったく歯が立たず、わずか数ページで挫折しそうになることがあります。私も古典や哲学書を読む際、意味がつかめず、行きつ戻りつしながら、著者との対話を繰り返します。
しかし、この「わからなさ」こそが、読書の本質であり、知的成長の入り口であると私は考えています。理解できない文章に出会うとき、私たちは無意識のうちに、自分の中に問いを抱えるようになります。
「なぜこの表現なのか」「著者の視点はどこにあるのか」といった疑問が、読書体験を深めてくれます。その問いがあるからこそ、何度もページをめくり直すことになるのです。
最初は霧の中を進むようで不安でも、読み返すうちに、ある瞬間に輪郭が立ち上がるような感覚に出会うことがあります。点と点が線につながり、知識や概念が自分の中で一つのまとまりとして形を成していくのです。この「つながった」と感じる瞬間には、独特の高揚感があります。
昨日まで理解できなかった概念が、今日は少しだけ言語化できるようになる。その小さな変化の積み重ねが、やがて知識を情報の集積から「思考の道具」へと変えていきます。
私自身、この感覚に何度も助けられてきました。読書を続けていて本当に良かったと感じるのは、スムーズに理解できたときではなく、苦労の末にようやく突破口が見えた瞬間です。
名越氏も、理解できないことを無理に解決しようとせず、わからないまま問いを抱えながらページをめくる。そのような読書の姿勢が、やがて大きな知的飛躍をもたらすと述べています。
本との対話を重ねるなかで、自分の中の前提が揺さぶられ、思考の深度が自然と増していく。そうした変化こそが、読書の醍醐味なのだと思います。
言葉にできない違和感を抱えながら、試行錯誤を繰り返し、やがて「ああ、そういうことか」と腑に落ちる。難しい本に向き合うという行為は、こうした内的プロセスを凝縮して体験させてくれるものです。
だからこそ、歯が立たないと感じる本ほど、私たちを鍛えてくれます。読みづらさやわかりにくさに直面する場面こそ、知的成長の種が潜んでいるのです。
さらに、異なるジャンルの本を並行して読むことで、思考はより柔軟に、創造的になります。たとえば、ロジカルな理論書を読みながら雑誌を眺めたり、小説と哲学書、ビジネス書と歴史書を行き来したりすることで、頭の中に新しい組み合わせが自然と生まれてくることがあります。
それは意図的というより、むしろ自然発生的な「思考の化学反応」に近いものです。 このような読み方は、決して非効率ではありません。むしろ、私たちの脳の構造にかなった方法だと言えます。
私たちの脳は、目の前に広がる情報を個々の点としてではなく、全体の「場」として把握しようとします。森の中で食べられる植物を直感的に見分けるように、複雑な情報の中から意味を抽出する能力が備わっていると、著者は述べています。
こうした量子的な読書によって、ひとつの論理が浮かび上がり、それが別の視点や知識と結びつくことで、全く新しいアイデアや理解が生まれていくのです。 読書は、ただ知識を得るための行為ではありません。自分の内面が静かに動き出し、同じ世界が少し違って見えるようになる。そうした読書体験こそが、私たちの人生に確かな変化をもたらしてくれるのです。





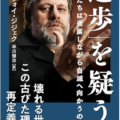












コメント