ハーバード・ビジネス・レビューが贈る リーダーを支える365の言葉
ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
ダイヤモンド社
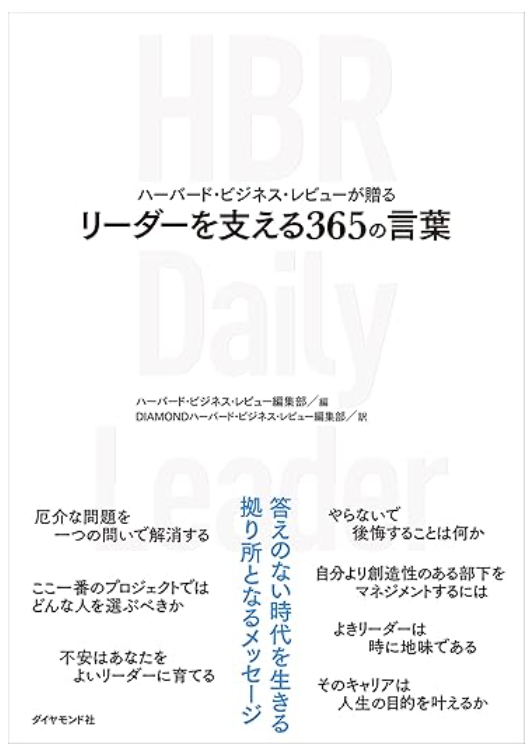
ハーバード・ビジネス・レビューが贈る リーダーを支える365の言葉の要約
AIが職場に浸透する中、リーダーの役割も変わってきています。コミュニケーションが希薄化する中で、信頼や共感をどう築くかが鍵になっています。『リーダーを支える365の言葉』は、クリステンセンやヘファーナンらの知恵を日々学べる一冊。リーダーが問いを持ち、謙虚に学び、変化に柔軟に対応するための伴走者として、AI時代の人間らしいリーダーシップを導いてくれます。
365の言葉で思考と行動を変えよう!
「私たちは何のためにここにいるのか」。リーダーならば、この問いに答えられなければならない。責任範囲や戦略は変化し、昇進する人もいれば解雇される人もいる。そうした中でも、変動の多い時期にはなおさら、自分が何を、何のために目指しているのかという確たる信念が必要だ。現状維持では不十分だ。(マーガレット・ヘファーナン)
AIなどのテクノロジーがオフィスの中で存在感を増す今、リーダーの働き方は、これまでの延長線上にはありません。 チャットやタスク管理ツールが意思疎通の中心となり、リアルな会話よりも通知が先に届く。業務は効率化されても、チームの温度は少しずつ下がっていく――そんな分断を感じているリーダーは少なくないはずです。
テクノロジーが進化するほど、信頼や共感といった目に見えない資本の維持が難しくなっています。成果や生産性はダッシュボードで数値化できても、人の感情やモチベーションは可視化できません。 どれだけデータを読み解き、AIツールを駆使しても、人の心までは動かせない──このジレンマに、今、多くのリーダーが直面しています。
そんな悩みを抱えるリーダーにお薦めしたい一冊が、ハーバード・ビジネス・レビューが贈る リーダーを支える365の言葉です。世界中のリーダーに読まれてきた『Harvard Business Review(HBR)』の膨大なアーカイブから、クレイトン・M・クリステンセン、ジョン・コッター、ダニエル・ゴールマン、そして起業家・CEOとしても知られるマーガレット・ヘファーナンなどの知の巨人たちの知見が凝縮されています。
各ページには、厳選された1つのメッセージとその出典記事が明記されており、読者は気づきを得たその瞬間に、より深い知見へアクセスできるよう設計されています。 つまりこの本は、単なる名言集ではなく、“知の入り口”を365個備えたリーダーシップのためのプラットフォームなのです。
毎日1ページを開くだけで、経営戦略・コーチング・心理学・イノベーション理論など、多角的な視点が自然と自分の思考に組み込まれていきます。短い言葉から始まり、そこに込められた洞察を咀嚼し、日々の判断や意思決定に活かす。その積み重ねこそが、思考の精度を高め、やがて優れたリーダーへと成長する道を築いてくれるのです。
リーダーという役割には、必ず孤独がつきまといます。多くの人は、相談できない重圧や、誰にも共有できない迷いを抱えながら、それでも組織の方向を決めなければなりません。 本書の365のメッセージは、そうしたリーダーの孤独を理解し、寄り添いながら、次の一手を考えるための思考のパートナーとして機能します。
最初に紹介したいのが、起業家であり、複数の企業の経営者のマーガレット・ヘファーナンの「リーダーは不確実性を恐れず、問いを持ち続ける勇気を持て」という考え方です。彼女は、完璧な情報も正確な予測も存在しない現実のなかでこそ、リーダーは自らのパーパスを軸に意思決定を行うべきだと説きます。
AIやデータが「正しさ」を示してくれる時代において、リーダーが発揮すべき力とは、「確信なき中で選び取る勇気」なのです。 変化が激しい時代には、論理よりも「意味」が組織を動かします。
数字やKPIでは人は動かない。動かすのは、「なぜそれをやるのか」という物語です。リーダーが明確な目的意識を持ち、その背景にある価値や信念を語ることで、チームは指示ではなく共鳴によって動き出す。目的が共有されると、行動に一貫性が生まれ、メンバーも自走できるようになります。
パーパスとは、単なるスローガンではなく、存在理由であり、意思決定の源泉です。 リーダーがこの軸を持たずして、チームを導くことはできません。むしろ、リーダーこそが最も深く問い続ける存在でなければならないのです。
なぜ自分たちはこの仕事をするのか、何を社会にもたらしたいのか――その問いがある限り、組織は生きた知性として進化し続けます。
さらに、ハーバード・ビジネス・スクール名誉教授のロバート・S・キャプランもこう指摘します。 「リーダーがビジョンを示さなければ、部下はついてこない」。 方向性を語らずに成果を求めても、組織は迷走するだけです。だからこそ、リーダーは自らの言葉でなぜやるのかを明確に示す義務があるのです。
AIやSNSがあらゆる組織の意思決定を変えつつある今、リーダーに求められているのは「正解を出す力」ではなく、「人を動かす力」です。アルゴリズムが合理性を担う時代だからこそ、リーダーの本質はますます人間らしさに回帰しています。信頼、共感、そして目的意識──それらをどう言語化し、どう行動に転換できるかが問われているのです。
AI時代のリーダーシップは、これまでと根本的に異なるのだろうか。(中略)もちろん、そんなことはない。だが、重要な違いが2つある。第1に、リーダーが持つハードスキルの重要性は、スマートマシンによって今後も低下し続け、ソフトスキルはいままで以上に重要になる。第2に、誠実さやEl(感情的知性)のような、時代を問わない個人的資質の重要性は変わらない。ただし、Al時代の指導者は、他者の貢献を謙虚に受け入れ、行く手に次々と発生する課題に対応し、その先のゴールについて揺るぎないビジョンを持ち、世の中の変化に敏感であり続けることが求められる。(トマス・チャモロ=プレミュジック マイケル・ウェィド ジェニファー・ジョーダン)
CQ(好奇心指数)やEQ(感情知能指数)の重要性を説くトマス・チャモロ=プレミュジックらは、AI時代に必要なリーダーの本質的能力を明確に示しています。彼らが強調するのは、知識の多寡やスキルの量ではなく、未知を探求する好奇心と、人を理解する感性です。
AIが情報を処理する存在だとすれば、人間は意味を創り出す存在である――この視点が、AI時代のリーダーシップを定義します。
AIが最適解を瞬時に導き出す時代に、リーダーの価値は「正解を出すこと」から「問いを立てること」へとシフトしています。もはや情報の量やスピードではAIに勝てない。だからこそ、人間のリーダーにしかできないのは、『なぜそれをやるのか」「その選択にどんな意味があるのか」を問い続けることなのです。
問いは方向を決め、意味は行動を生む。AIが最適化するのは「過去」からの延長線ですが、リーダーが創るのは「未来」そのものです。 AI時代におけるリーダーのコンピテンシーとは、もはや専門知識やスキルセットの総量ではありません。
むしろ、曖昧さを受け入れ、複数の可能性を同時に扱いながら、自分の判断を下せる思考の柔軟さにあります。状況を読む直感力、異なる意見を持つ他者への共感力、矛盾の中から本質を見抜くクリティカルシンキング、部下の意見を尊重できる謙虚な姿勢――これらはどれも、AIには模倣できない人間固有の能力です。
優れたリーダーは、問いを通じてチームの視野を広げ、意味を与えることで行動を促します。AIが示す「正解」ではなく、自らが生み出す「納得解」を共有できるリーダーこそ、これからの組織に必要とされる存在です。
謙虚に学ぶ姿勢が重要な理由
若い時には、親や教師、上司など、自分より賢い相手から学びを得る。けれどもリーダーになる頃には、自分がその場で一番賢い人の一人になっている可能性が高い。それはそれで気分がいいかもしれないが、キャリアの初期の頃のように、自分より賢い人からしか学ぶものはないと思っていると、成長はそこで止まる。成長し続けるためには、他者、特に自分とは異なる考えや経歴の持ち主に意見を求め、耳を傾けよう。すべての人から謙虚に学ぼうとする姿勢があれば、学ぶ機会は無限に広がる。(クレイトン・M・クリステンセン)
特に印象的なのは、名だたるリーダーたちの言葉が、どれも「内省」と「学び」に貫かれている点です。私が尊敬するクレイトン・M・クリステンセンは、「謙虚に学び続けることこそ、真のリーダーの条件だ」と述べています。
立場や経験を重ねるほど、人は無意識のうちに学びを止めがちになります。しかし、変化の速い時代において、過去の成功体験ほど危険な足かせはありません。成長を止めないためには、常に新しい知の源に身を置くことが求められます。
若い世代からの視点、異なる業界のプロフェッショナルとの交流、そして書籍からの学び。これらはすべて、自分の思考を更新し続けるために欠かせぬものです。自分とは異なる意見に耳を傾け、対話を重ねることこそ、リーダーが持つべき最大の知的謙虚さだといえます。その姿勢がやがてチーム全体の心理的安全性を育み、組織に「学び続ける文化」を根づかせるのです。
コーン・フェリーの調査によると、リーダーとして長年使ってきた行動のレパートリーや考え方に依存している人は、伸び悩みや業績不振に陥りやすく、出世コースから外れがちだといいます。エグゼクティブコーチ・ビジネス書著者のモニク・バルコアはここで「ラーニング・アジリティ(Learning Agility)」の重要性を指摘します。それは、変化に素早く対応し、学び続ける力のことです。
特に印象的なのは、彼女がその方法として「フィードバックへの防衛反応をやめる」ことを挙げている点です。成功を重ねてきた人ほど、批判に耳を貸さず、問題を一過性のものと捉えがちです。けれども、成長を続けるリーダーは、耳の痛い言葉ほど真剣に受け止めます。
反論せず、まずは傾聴する。そして、自分の考えを一度リセットして受け入れる。その中にこそ、真の変化の芽があるのです。 私自身、長年経営者や起業家と関わる中で痛感しているのは、「学び続ける人ほど若々しい」ということです。肩書きや年齢ではなく、柔らかく、吸収しようとする姿勢が人を魅力的にします。だからこそ、日々の読書や対話、そして他者からのフィードバックを、自分を磨く最高の贈り物として受け取ることが大切なのです。
ビジネスコーチのエリカ・アンダーセンは、「一流のリーダーは決して学ぶことをやめない」と語っています。リーダーが過去の成功体験に安住した瞬間から、時代とのズレが始まります。彼女が説く学びとは、単に知識を増やすことではなく、「現実を新しい視点で捉え直す力」を鍛えることです。 そのために必要なのが、観察力・傾聴力・仮説力という3つのスキルになります。
クライアントやチームの課題を正確に掴み、新しい価値を提案できる人こそ、信頼されるリーダーといえるでしょう。ビジネスは常に「問題」と「価値提案」のループで回っています。だからこそ、リーダー自身が学び続け、相手の文脈を理解し、自分の発想をアップデートし続けることが、組織を進化させる原動力となるのです。
アンダーセンはさらに、「新しい知識を素早く、継続的に学ぶ力こそ、時代が変わっても価値が失われないスキルだ」と言います。その原動力は、飽くなき好奇心。わからないことがあれば、「なぜ?」「どうして?」「どのように?」と問いを投げかけましょう。その小さな問いが、未来を拓く学びの第一歩になるのです。
また、潔く負けることも重要だという姿勢を、ぜひ起業家に学んでもらえたらと思います。経営思想家・作家のティム・リーバーレヒトはピボットをする勇気を説きます。
あなたはリーダーとして、勝つことだけを考えている。とはいえ、常に成功する人などいないわけで、潔く負けることも学ばなければならない。それには、戦う土俵を変えるという手がある。あるプロジェクトや取り組みがうまくいかない時は、一歩引いて、他の方向性はないか検討する。試したことの中で、うまくいったことは何か。そのスキル、イノベーション、アイデアを他の方法で活かせないか。進めてきたことがちょうど役に立ちそうな別の問題はないか。失敗を創造や発想の終わりにしてはいけない。(ティム・リーバーレヒト)
あるプロジェクトがうまくいかないとき、POCの答えが見えない時など、多くの人は「努力が足りない」と考えて前へ進もうとします。しかし、リーダーに必要なのは、「引く勇気」です。一歩退き、構造を俯瞰し、土俵そのものを変える。この視点の転換が、敗北を「終わり」ではなく「始まり」に変えます。
ピボットとは、失敗を否定することではなく、そこに含まれた学びや資産を別のコンテキストに置き換える行為です。うまくいかなかった戦略の中にも、必ず「使える要素」は残っています。それを抽出し、別の課題や市場、チームに応用する。そうすることで、過去の挫折が新しい可能性を開いてくれます。
AI時代において、変化への対応力は単なるスキルではなく、知的レジリエンスそのものです。リーダーは、「正しい計画」を遂行する人ではなく、「環境に応じて意味を再定義できる人」でなければなりません。
ピボットとは、単なる方向転換ではなく、目的を保ちながら手段を柔軟に変化させる力――つまり、時代の変化を恐れず、自らの信念をアップデートし続けるチャレンジなのです。
何度でも使いたい質問「待って、どういうこと?」
よい質問は、自分自身と部下双方の好奇心や創造性を呼び覚まし、熟考を促す。たとえば、「待って、どういうこと?」は有用な質問である。誰か(特にあなた)が結論を急ぎ、情報不足のまま性急な判断を下すのを防ぐ効果がある。(ジェームズ・E.ライアン)
リーダーの本質は、「答えを知ること」ではなく「問いを立て続けること」にあります。ハーバード大学教育大学院のジェームズ・E・ライアンは、腑に落ちない時や、解決策があまりに簡単に思える時こそ、「待って、どういうこと?」と尋ねる勇気を持てと語ります。
この一言は、部下の思い込みを解き、思考の質を高めるブレーキとして機能します。優れたリーダーほど、理解を深めるために時間を使い、判断を急がないのです。
「待って、どういうこと?」という問いには、急がずに本質を掘り下げようとする知的な謙虚さが宿っています。これは単なる質問ではなく、信頼を育む対話の始まりでもあります。私自身、経営者との対話の中でこの「待つ勇気」の大切さを痛感してきました。わかったつもりで動かず、一度立ち止まり問い直す。その一瞬にこそ、思考の深まりと新しい発見が生まれるのです。
また、ハーバード大学教育大学院(HGSE)の元学長ジェームズ・E・ライアンは、「〜だけでもしませんか?」という質問が、相手との間に自然な合意を生み出し、対話や状況の突破口を開く力を持っていると指摘しています。この一言には、相手の創造性を引き出し、無理なく前向きな変化へと導く効果があります。
さらにライアンは、「本当に大事なことは何か?」と問いかけることで、自分自身や部下の好奇心を呼び覚まし、熟考と創造性を促すことができると説いています。
優れたリーダーは、刺激的な質問をして人を鼓舞する。これまで会社がやってきたことの枠を超えて、広く考えさせようとする。自分が答えをすべて持っているわけではないことを認め、その答えを見つけるために協力を求める。(ジョン・ヘーゲル3世)
コンサルタントのジョン・ヘーゲル3世は、リーダーの役割を「答えること」ではなく「問いで人を動かすこと」だと説きます。刺激的な質問は人を鼓舞し、想像力を解き放ちます。
たとえば、「どうすれば顧客対応時間を10%短縮できるか」ではなく、「まだ満たされていない顧客ニーズは何か」と問いかけます。前者は効率化の問い、後者は未来をつくる問いです。リーダーがこのような大局的な質問を投げかけることで、組織の思考が広がり、成長への意欲が芽生えます。 質問には、相手を支配する力ではなく、共に考える力があります。
リーダーが「わからないことを一緒に考えよう」と示す姿勢は、チームに学びの文化を育みます。問いを共有し、答えを共に探す――その過程こそが組織を進化させる原動力です。 私がこれまで出会ってきたリーダーの多くも、例外なく「問い」を大切にしていました。
「どうすれば良くなるか?」ではなく、「何がまだ見えていないのか?」と問うことが、会議を議論の場から創造の場へと変えていくのです。
AIが「正解」を瞬時に提示する時代において、リーダーの真価は「問いで未来を描く力」にあります。ヘーゲルが言うように、刺激的な問いは人と組織の潜在能力を引き出し、未知への探求を促します。リーダーとは、正解を持つ人ではなく、問いを持ち続け、迷いながらも前進する人です。
本書は、変化と不確実性の時代を生きるリーダーにとって、自らを日々アップデートし続けるためのお薦めの一冊です。迷いや不安を感じたときこそページを開き、ハーバードの知の巨人たちをコーチやメンターとして活用できます。
彼らの一言ひとことが、思考の軸を整え、意思決定の精度を高めてくれます。状況が変わり続ける今こそ、学びを止めず、自らを更新し続けることが大切です。その姿勢こそが、時代に選ばれるリーダーの条件なのです。
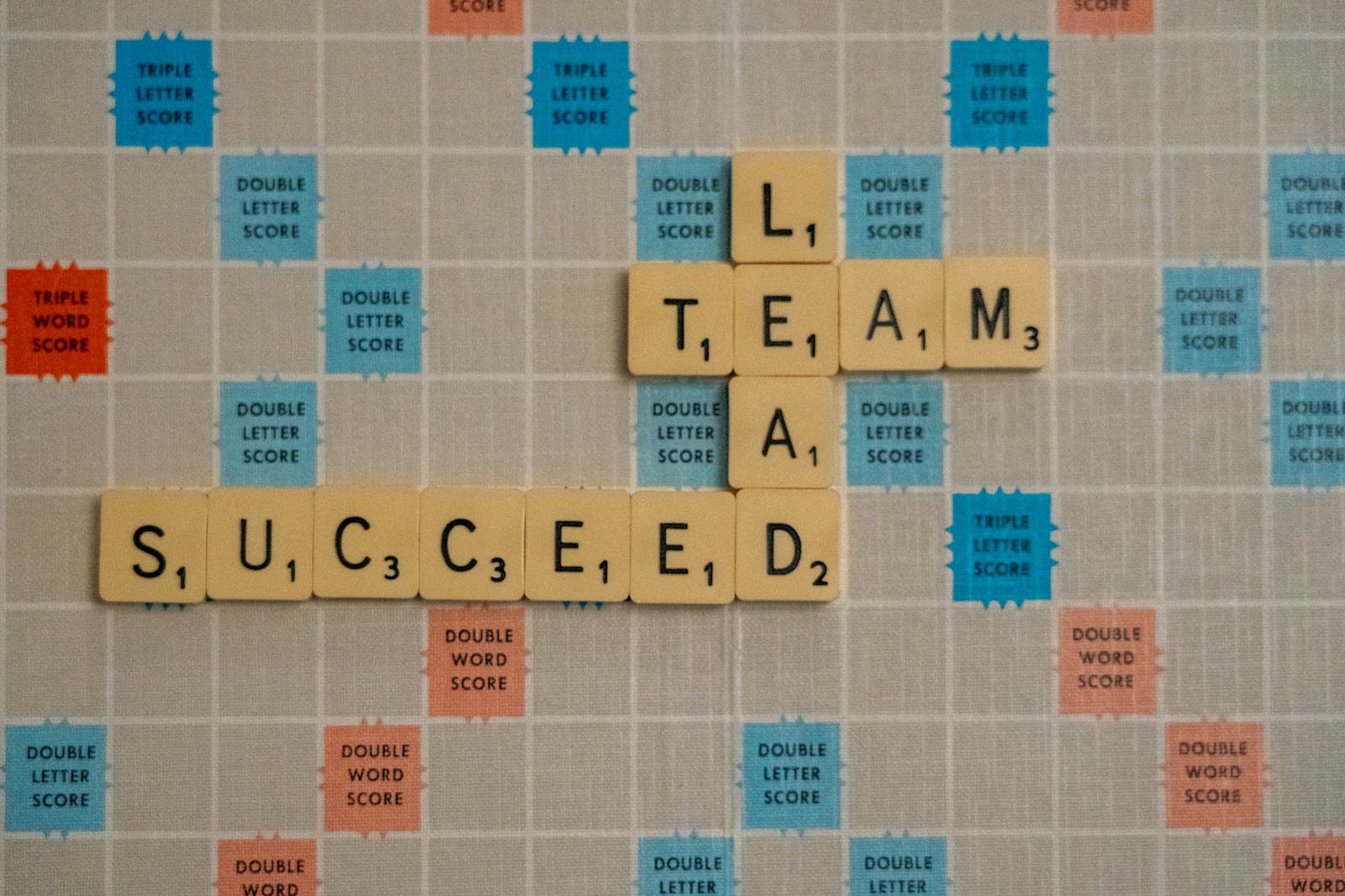






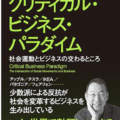




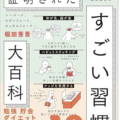





コメント