「答えを急がない」ほうがうまくいく あいまいな世界でよりよい判断をするための社会心理学
三浦麻子
日経BP
「答えを急がない」ほうがうまくいく (三浦麻子)の要約
ネガティブ・ケイパビリティ(あいまいさへの耐性)は創造の源です。即答志向の現代では、不確実性を受容し思考を深めることが大切です。対面・オンライン環境の違いや、即断型・熟考型思考の適切な切替えが重要です。個人の内面と外部環境の両方からこの能力を育む取り組みが、真の創造力を引き出します。答えを焦らず、熟考する姿勢を取り入れましょう。
認知資源の浪費がバイアスを生み、正しい答えを得られなくする?
答えを急いでしまう罠から逃れられない。(三浦麻子)
私たちは、日々の生活や仕事の中で、早く結論を出そうとする傾向があります。しかし、大阪大学大学院人間科学研究科の教授であり、社会心理学者である三浦麻子氏の著書は、そのような衝動に警鐘を鳴らし、より良い判断をするための方法を提示しています。
現代社会はますます複雑化し、不確実性が高まっています。そのため、即断即決が必ずしも最良の選択とは限りません。むしろ、あいまいな状況を受け入れ、一旦立ち止まることで、多角的な視点から問題を理解し、より適切な判断を下せる可能性が高まります。
では、答えがまだ見つかっていないあいまいな状態に、私たちはどうやって耐えればよいのでしょうか?著者はこの問いに対して、社会心理学という学問が役に立つことがあるのではないか、と思ったことが、本書を執筆するきっかけとなったと言います。
本書では、社会心理学の知識や考え方が、どのように日常の意思決定に応用できるかが具体的に解説されています。 「認知資源」とは、私たちが思考や判断を行う際に消費する限られた精神的エネルギーのことを指します。これはゲームのように数値で測れるものではなく、もともとの量や減り方も人によって異なります。
しかし、使いすぎると枯渇して能力が低下することや、意識していなくても本能的に、なるべく枯渇しないように無意識に節約することは、すべての人に共通する傾向です。この傾向が、私たちの判断に数々のバイアスをかける要因となるのです。
私たちの脳は、限られた認知資源を効率よく使おうとするため、無意識のうちに情報を取捨選択し、迅速に意思決定を行おうとします。その結果として、私たちは日常的に認知バイアスの影響を受けています。
例えば、確証バイアスは、自分の信じている情報を優先的に受け入れ、それに反する情報を軽視する傾向を生み出します。また、利用可能性ヒューリスティックは、記憶に残りやすい情報を重視するため、実際の確率よりも頻繁に発生すると錯覚することにつながります。
このようなバイアスがかかると、判断の精度が低下し、誤った決定を下してしまう可能性が高まります。例えば、私たちはニュースやSNSで目にした印象的な出来事を実際よりも重要だと考えがちであり、それが意思決定に影響を及ぼすことがあります。また、情報過多の現代においては、認知資源の節約が一層求められるため、短絡的な判断をしやすくなります。
こうしたバイアスを克服するためには、まず自分自身の思考の癖を理解し、意識的に多様な情報を取り入れることが大切です。また、時間をかけて熟考し、異なる視点を持つ人々と対話することで、偏った判断を避けることができます。
他者とのコミュニケーションにおいても、社会心理学の知識は有益です。相手の立場や感情を理解し、共感を意識した対話を心がけることで、より良好な人間関係を築き、建設的な合意形成が可能になります。認知バイアスの影響を最小限に抑え、冷静かつ客観的な判断をするために、私たちは自身の認知資源を適切に管理し、慎重に意思決定を行うことが求められます。
あいまいさに耐えられる人がうまくいく7つの理由
あいまいさは悪いことばかりではないと感じるはずだ。あいまいで不確実な状況は、不安のもとになるだけでなく、未知の新しい可能性を拓くきっかけにもなる。そういうふうに、これまでとは少し違う新しい世界の見え方を提供できることは、心理学の面白さのひとつだと思っている。
現代社会において、あいまいさへの耐性は重要なスキルとなっています。確実性が低く、変化の激しい時代だからこそ、あいまいさと上手に付き合える人が成功への道を切り開いていけるのです。以下に、あいまいさに耐えられる人がうまくいく7つの理由を著者は明らかにしています。
①状況から受ける影響を考慮できる 物事を白黒はっきりさせたがる人は、状況の複雑さを見落としがちです。一方、あいまいさに耐えられる人は、様々な要因が絡み合う状況を丁寧に読み解くことができます。例えば、業務上の判断を下す際も、市場環境や組織の状況、関係者の立場など、多角的な視点から検討を重ねることができます。
②リスクや利益を正しく見積もれる
あいまいな状況下でも冷静に判断できる人は、リスクと利益のバランスを適切に評価できます。完璧な答えを求めすぎず、限られた情報の中で最適な選択をする能力に長けています。これは投資判断やキャリア選択など、人生の重要な場面で大きな強みとなります。
③人間関係がうまくいく
人間関係には常にあいまいな要素が含まれています。相手の真意を100%理解することは難しく、また状況によって人の態度や行動は変化します。あいまいさに耐えられる人は、このような不確実性を受け入れた上で、柔軟なコミュニケーションを取ることができます。
④感情をふまえて判断できる
論理だけでなく感情の要素も大切にできることは、あいまいさに強い人の特徴です。数字やデータでは測れない感情的な価値も考慮に入れ、バランスの取れた判断を下すことができます。これは特にリーダーシップを発揮する場面で重要となります。
⑤ネット社会とうまく付き合える
情報があふれるネット社会では、真偽の判断が難しい情報に常にさらされています。あいまいさに耐性のある人は、情報を適切にフィルタリングし、必要な情報を選び取る能力に優れています。また、SNSでの人間関係特有の曖昧さにも上手に対応できます。
⑥創造的な思考ができる
イノベーションは、既存の枠組みを超えて新しい可能性を探る過程で生まれます。あいまいさを受け入れられる人は、確立された答えのない領域に踏み込むことを恐れません。そのため、創造的な解決策を見出すことができます。
⑦偏見に気づき、抗える
固定観念や偏見は、物事を単純化して理解したい心理から生まれます。あいまいさに耐えられる人は、自分の中にある偏見に気づき、それを乗り越えようとする姿勢を持っています。多様性を受け入れ、より豊かな視点で世界を見ることができます。
このように、あいまいさへの耐性は、現代社会を生き抜くための重要な能力といえます。ただし、これは生まれ持った才能ではなく、意識的な努力によって徐々に身につけていけるスキルです。日々の生活の中で、あいまいさと向き合い、受け入れる練習を重ねることで、誰でも少しずつ強くなっていけるのです。
創造力にあいまいさが必要な理由
新しいものやアイディアを作り出すためには、これまでとは違うやり方が必要になる。作り方から考えなくてはならないし、できあがったものを評価する基準も存在しない。手っ取り早くインターネットで検索したり、生成AIに問いを投げたり、誰かに聞いたりして、手軽な答えを見つけて早々と納得してしまえば、あいまいな状態から抜け出すことができるが、そうやって出てきた答えは、たいてい創造的なものではない。
現代社会では、即座に答えを得られることが当たり前となっています。インターネットで検索すれば、どんな疑問にも瞬時に答えが見つかります。生成AIに問いかければ、整理された回答が返ってきます。この手軽さは、私たちの思考や行動に大きな影響を与えています。
しかし、真に創造的な営みには、このような即効性のある解決策は通用しません。創造のプロセスは、本質的にあいまいさと向き合う旅路です。霧の中を進むように、確かな道筋も最終的なゴールも見えない中で、一歩一歩を慎重に進んでいく必要があります。
ネガティブ・ケイパビリティとは、詩人キーツが提唱した「あいまいさや不確実性に耐える能力」を指し、著者はこれが創造力の鍵だと指摘しています。時には立ち止まり、時には引き返し、また新しい方向を模索する。その過程で直面する困難や失敗も、何が原因なのかを特定することが難しいものです。
方法が間違っていたのか、目指すべきゴールの設定が適切でなかったのか、あるいはそもそもの課題認識に誤りがあったのか。これらの問いに対する明確な答えは、なかなか見つかりません。
このような不確実性に満ちた状況で前進するには、あいまいさに耐える力が不可欠です。その力がなければ、創造的な取り組みは途中で挫折してしまうでしょう。
さらに深刻なのは、未知の領域に足を踏み入れることそのものを躊躇してしまう可能性です。確実な成功が約束されていない冒険に、第一歩を踏み出せなくなってしまうのです。
この文脈で興味深いのが、コミュニケーション環境の違いが創造性に及ぼす影響です。対面でのミーティングとZoomなどを使用したオンラインミーティングでは、創造力の発揮に明確な差が生じることが明らかになっています。その主な要因は、共有される空間の広さの違いにあります。
対面の場合、参加者は同じ物理的空間を共有し、周囲の環境全体を自然に認識することができます。一方、オンラインの場合、共有空間はスクリーンという限られた範囲に制限されます。
研究によれば、オンラインでの作業中、参加者はパートナーの映像を直接見ることに多くの時間を費やしていることが分かっています。画面という狭い範囲に継続的に注意を向け続けることは、認知資源を大きく消費します。これがオンライン会議特有の疲労感につながり、結果として創造的思考に割ける余力が減少してしまうのです。 このような状況を克服するためには、私たちの思考の二重性を理解し、活用することが重要です。
ダニエル・カーネマンは、人間の思考には2つのモードがあると提唱しました。速やかな判断を下す「ファスト思考」と、じっくりと熟考する「スロー思考」です。彼の研究によれば、ファスト思考は日常的な意思決定に役立つものの、バイアスの影響を受けやすい傾向があります。一方、スロー思考は深い分析や創造的な発想に必要不可欠なものです。
著者の三浦氏は、この2つの思考モードを「せっかちモード」と「じっくりモード」と言い換えています。せっかちモードは直感的で迅速な判断を可能にしますが、思考の抜け漏れや誤解が生じやすくなります。対して、じっくりモードは時間をかけた深い思考を促し、より的確で柔軟な判断を可能にするのです。
日常生活において、この二つの思考モードを意識的に使い分け、状況に応じて適切に切り替えていく術を身につけることで、創造的な潜在能力をより効果的に引き出すことができるでしょう。
創造性とあいまいさは、切り離すことのできない関係にあります。即座の解決や確実な答えを求める現代の傾向に流されることなく、あいまいさと向き合い、そこから新しい価値を生み出していく姿勢が、これからの時代にますます重要になっていくことでしょう。創造的な営みを進めるためには、不確実性に耐え、試行錯誤を繰り返すことが求められます。それができるかどうかが、未来の可能性を大きく左右するのです。
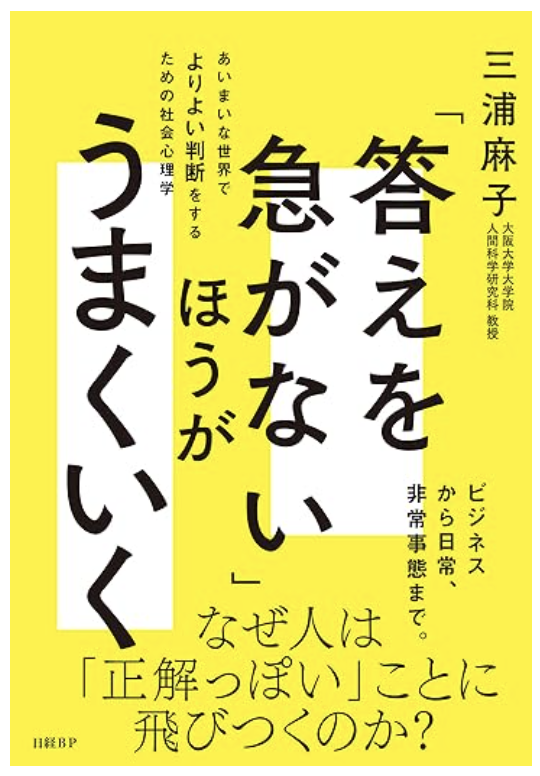


















コメント