
愛される書店をつくるために僕が2000日間考え続けてきたこと キャラクターは会社を変えられるか?
ハヤシユタカ
クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
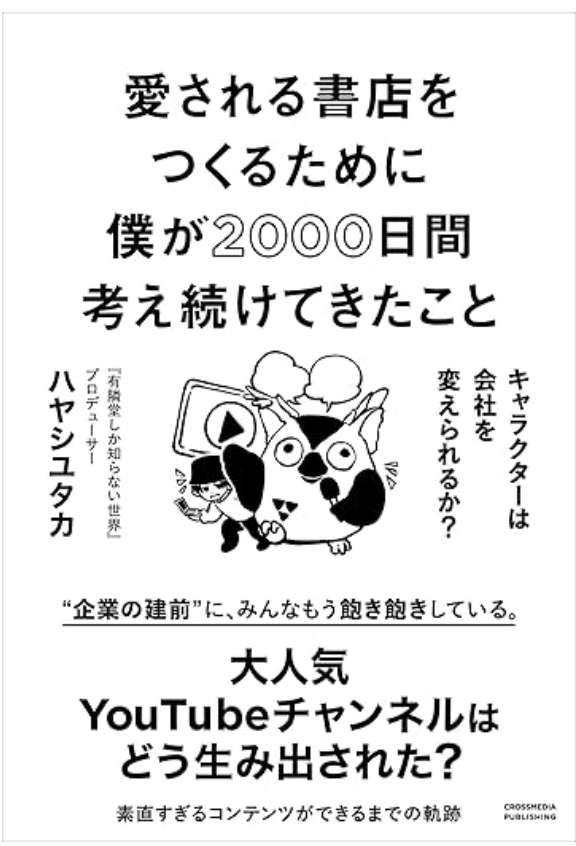
愛される書店をつくるために僕が2000日間考え続けてきたこと キャラクターは会社を変えられるか?(ハヤシユタカ)の要約
有隣堂が運営するYouTubeチャンネル『有隣堂しか知らない世界』は、広告を使わず自然流入のみで37万人以上の登録者を獲得しています。ブッコローというキャラクターの本音発言と緻密な編集が視聴者の共感を集め、メディア掲載も100件超。企画・編集の自由を守る企業の「覚悟」と、外部クリエイターへの信頼が成功の鍵となっています。企業YouTubeに悩む人にとって示唆に富んだ事例です。
YouTubeで成功した「有隣堂しか知らない世界」とは?
そんなブッコローだが、出演する動画はどれも10万回以上再生され、イベントでは大勢の人が押し寄せるほど、たくさんの人に愛されている。なんと言われようと、有隣堂という企業の看板を立派に背負っているのだ。 (ハヤシユタカ)
企業がYouTubeに参入しても成果が出ない。そうした悩みを抱えている方は少なくありません。せっかく社内リソースを投入し、撮影や編集に多大な時間と労力をかけているにもかかわらず、再生回数は数百回止まり。コメントや「いいね」などの反応も乏しく、チャンネル登録者数も一向に伸びない。まるで誰にも見られていないかのような空虚さが残ります。
そして次第に、「やはり企業がYouTubeで成功するのは難しいのでは」と諦めの気持ちが生まれてしまうのです。 そんな絶望的な状況から脱却し、企業チャンネルとして異例の成功を遂げたのが、神奈川県の老舗書店「有隣堂」の公式YouTubeチャンネル有隣堂しか知らない世界です。
この成功の背景には、失敗を恐れず試行錯誤を重ねた姿勢、そして一人のクリエイターの存在がありました。 有隣堂のYouTube事業は、副社長(現社長)松信健太郎氏の発案でスタートしました。初期には「書店員つんどくの本棚」というアニメーション形式の動画を制作しましたが、結果は芳しくありませんでした。ナレーションの棒読み感や、既存YouTuberとの差別化不足が原因となり、再生回数は伸びず、6本の動画で打ち切りとなりました。
しかし、ここから巻き返しが始まります。大体的に発表したYouTubeは打ちきれず、社内の熱意ある人物が主導し、コストを抑えつつ試行錯誤を続ける中、ついにプロフェッショナルの手を借りることになります。それが、映像ディレクターのハヤシユタカ氏です。
ハヤシ氏は、TV番組を中心に映像制作を多数手がけてきた人物で、緻密な編集と独特のユーモア感覚に定評があります。彼が『有隣堂しか知らない世界』の制作を手がけることにより、チャンネルの方向性は劇的に変わりました。
ブッコローという自由奔放なキャラクターをMCとした動画シリーズがスタートすることで、徐々に認知が高まっていきます。2020年6月に誕生したこのキャラクターは、鮮やかな色合いとミミズクをモチーフにした独特なビジュアルで、強烈な第一印象を与えます。
しかし真価はその中身にあります。忖度なしの発言で、企業の枠を飛び越えるようなコメントを次々と発信。「アマゾンの方が安いのでは?」「冷蔵庫の下から出てきたたくあん」「アプリでよくないっすか?」といった発言が、かえってリアリティと信頼感を生み、ファンの心を掴んでいったのです。
今回、そのYouTubeとキャラクターについて書かれた愛される書店をつくるために僕が2000日間考え続けてきたこと キャラクターは会社を変えられるか?を偶然手に取り読み進めていくうちに、実際に動画を視聴してみました。そこで目にしたのは、キャラクターの自由奔放な発言と、ハヤシ氏による秀逸な構成力が織り成す、まさに「企業チャンネルの概念を覆す」コンテンツでした。構成、編集、トークの間合い、そのすべてに目を奪われ、気づけば次々と動画を再生していました。
開設から2年半で登録者数は20万人を突破し、現在では37万人を超える規模にまで成長しています。視聴者は動画に強い親しみと期待を持ち、1本1本を楽しみに待つようになりました。コメント数、シェア数、いいねの数も右肩上がりに増加し、YouTubeデータ解析会社・株式会社エビリーの分析によると、推計エンゲージメントはトヨタや松井証券といった大手企業チャンネルの3倍以上に達しています。
2023年には「誠品生活日本橋」を舞台にした24時間生配信にも挑戦。最大同時接続数8000人、のべ視聴者数28万人という驚異的な数字を記録し、実店舗への来店者は4000人、売上は850万円を突破。広告換算では8000万円以上の効果があったとされています。このイベントの成功も、映像演出とリアルタイム感を徹底的に追求したハヤシ氏の企画力と編集力があってこそ成し得たものでした。
視聴者を優先するためには企業の覚悟が問われる!
魅力的なキャラクターを作れるかどうかの答えは、企業に覚悟があるかどうかだと思う。
『有隣堂しか知らない世界』では「広告を回さない」方針を貫いています。すべてオーガニック流入による視聴であり、だからこそ視聴者の熱量が極めて高く、コメント欄も応援や共感の声であふれています。
また、動画の信頼性を守るため、出演者からの事前チェック依頼には一切応じていません。ブッコローの反応が作為的になることを防ぐためです。 チャンネルは「有隣堂のファンをつくること」を目的に運営されており、更新頻度は週1本に限定されています。
SNSでは「#ブッコローイラスト」などのタグを通じてファンによる創作が活発に行われ、コンテンツの広がりを支えています。「視聴回数」よりも「接触時間」に価値を置く姿勢が、他の企業チャンネルと一線を画す最大の要因といえます。
さらに現在では、著名人や大手企業からの出演希望も相次いでいます。たとえば、文具業界を代表するコクヨ、三菱鉛筆、ゼブラの社長3名が出演し、知育玩具を使って対決するというユニークな企画を展開しました。ビジネスの話をするのではなく、本気で遊ぶ姿を見せることで、「企業らしくない企業チャンネル」としての魅力を発信しています。
特筆すべきは、このYouTubeチャンネルが広報活動としても大きな成果を上げている点です。これまでに掲載されたメディアは100を超え、ウェブメディアや専門誌、経済誌、新聞、テレビ、ラジオに至るまで多岐にわたります。自社発信の動画がメディアにも波及し、第三者の視点で語られることにより、より高い信頼とブランド認知を獲得しています。
『有隣堂しか知らない世界』には明確な運営ポリシーがあります。
①人権侵害をしない
②反社会的な行為をしない
③誰かを傷つけない
④品性を著しく欠かない
この4つを守る限り、外部クリエイターに大きな裁量が与えられています。 さらに、5年間にわたり経営陣からの企画指示や修正依頼が一切なかったという点も見逃せません。完全にクリエイターを信頼し、任せる文化が根づいていることが、成果を生む下地となっているのです。
企業の公式キャラクターが本音で語り、外部の制作スタッフが自由に編集する。そのような運営体制を実現するには、企業側に強い「覚悟」が必要です。
企業がYouTubeを活用するうえで大切なのは、単なる動画制作ではなく、信頼される存在としての「一貫した姿勢」を保つことです。そのためには、クリエイターやキャラクターを信じて任せる度量、批判を恐れず発信を続ける姿勢が求められます。
「社内で決裁を通すための無難な動画」ではなく、「本当に視聴者に届く動画」を作るには、組織として何を優先すべきか。今、企業がYouTubeというメディアに取り組むならば、その問いと向き合う「覚悟」が問われていますが、その答えが本書に書かれています。

















コメント