なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門
松村真宏
幻冬舎
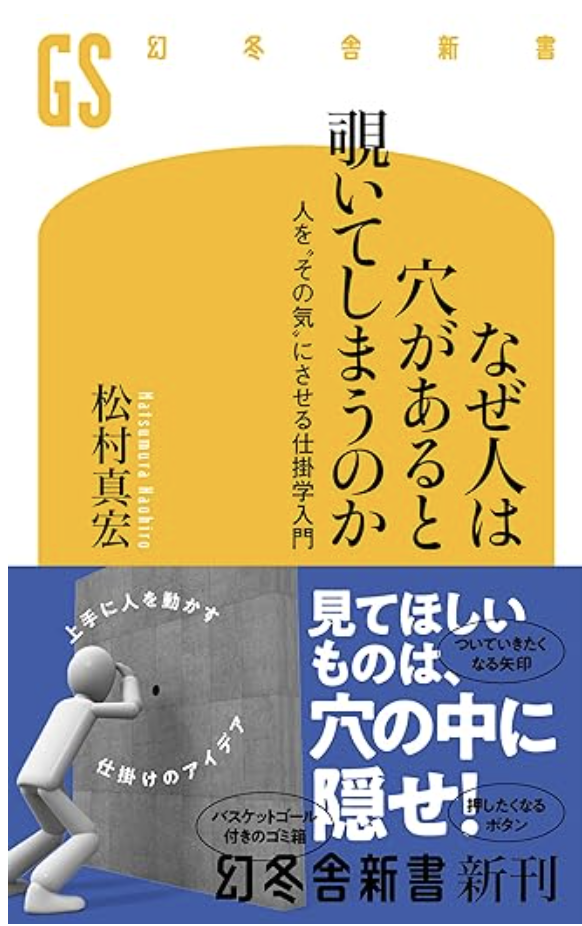
なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門 (松村真宏)の要約
仕掛学は、人の好奇心や感情に働きかけ、自発的な行動を促す設計思想です。命令や強制ではなく、「やってみたい」と思わせる仕組みが、人を自然に動かします。教育や地域づくりにも応用可能で、ユーモアや遊び心が行動の持続力を生み出します。社会にこの考え方が浸透すれば、日常に創造的な仕掛けが増え、暮らしは静かに、しかし確実に心地よい方向へと変化していくでしょう。
人の行動を楽しく変える「仕掛け学」とは何か?
「仕掛け」とは、人の行動を促したり、行動を変化させたりするために考案されたしくみのこと。こうしたしくみを体系的に捉え、学問として発展させたものが「仕掛学」です。(松村真宏)
なぜ人は、穴があると覗いてしまうのか──。この何気ない行動の裏には、人間の本能とも言える「好奇心」や「遊び心」が潜んでいます。
松村真宏氏のなぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門は、そんな私たちの心の動きを丁寧に読み解き、「行動を変える仕組み」を科学的に設計する方法を紹介してくれる一冊です。
ナッジ理論が広く知られるようになった今、日本でも「人を動かす設計」はもはや珍しいものではありません。ただ、その多くは合理性や効率性をベースにしたものが中心ですが、より感情や直感に訴えかけるような仕組みを作ることで、人々の行動が変わり、より良い社会を実現できるはずです。
そうした中で、本書が提示する「仕掛学」は、ユーモアと創造性を軸に、人間の内側から行動を引き出すアプローチとして際立っています。
有名な事例として紹介されるのが、オランダ・スキポール空港の小便器に描かれた「ハエ」のマークです。利用者は無意識のうちにそのハエを狙い、結果として飛び散りが80%も減少したといいます。日本でも同様の発想は応用されており、阪神電鉄の駅では「焚き火」のシールが小便器に貼られています。つい火を消したくなる心理を活用したこの試みは、誰かに注意されることなく、自然と行動を変えさせる点で極めて効果的です。
さらに、大学のキャンパスに設置されたバスケットゴール付きのゴミ箱の事例では、ゲーム感覚でゴミを捨てるという体験が、利用者の行動に明らかな変化をもたらしました。通常のゴミ箱よりも多くの人がゴール付きの方を使い、失敗しても再挑戦する姿が見られたといいます。
ただの行動を楽しみに変える──この発想は、強制や罰則とは対極にあるものであり、「仕掛け」の本質をよく示しています。
著者の松村氏は、大阪大学大学院経済学研究科の教授であり、仕掛学という学問の提唱者でもあります。そのキャリアは工学に始まり、経済学、さらにはデザイン思考へと広がりを見せており、行動の変容を生み出す構造的なアプローチに説得力を持たせています。
ナッジと仕掛けは、いずれも人の行動に影響を与える設計手法ですが、そのアプローチには本質的な違いがあります。最も大きな違いは、ナッジが無意識の認知バイアスを利用して行動を“選ばせる”のに対し、仕掛けは「やりたい」と思わせることで自発的な行動を引き出すという点です。
ナッジは、行動経済学の知見に基づいた設計です。人は常に合理的に判断しているわけではなく、しばしば「現状維持バイアス」や「選択回避バイアス」といった無意識の偏りによって、選択の方向が決まってしまうことがあります。
その性質を利用し、たとえば臓器提供の同意を「オプトアウト(あえて拒否しない限り同意)」に設定しておくことで、実際には多くの人が参加する仕組みができます。これは、選択の自由を形式上は確保しながらも、実質的には人の意思決定を操作しているとも言えます。
一方で仕掛けは、人の好奇心や遊び心に働きかけ、「やってみたい」と思わせることで行動を促します。たとえば、バスケットゴールが取り付けられたゴミ箱や、鍵盤の音が鳴る階段、マジックハンドを使ったポケットティッシュ配りなど、日常とは少し異なる非日常的な体験が、人々に自然な関心を呼び起こします。
これらは、行動に必須なものではないにもかかわらず、「面白そうだからやってみる」という気持ちにさせる点が特徴です。 また、仕掛けはすべての人に一律の行動を求めるものではありません。あくまで選択肢を広げることを目的としており、その中から「自分もやってみよう」と感じた人が行動する設計になっています。この点で、仕掛けは強制ではなく、あくまで自発性を重視したアプローチです。
社会課題の性質によっては、ナッジと仕掛けを使い分けることが有効です。たとえば、医療や防災のように迅速かつ広範な対応が求められる分野では、ナッジのような仕組みが即効性を発揮します。一方で、日常的な習慣づくりや地域参加、公共空間の改善といった分野では、仕掛けのような「行動のきっかけ」を丁寧に設計するアプローチが適しています。
つまり、ナッジと仕掛けは対立する概念ではなく、人の行動特性を理解した上で、文脈に応じて選択されるべ補完的な手段なのです。行動の選択をコントロールするのではなく、選びたくなる環境を整えること。仕掛けが目指すのは、そのようなやさしく創造的な社会のデザインです。
本書を通じて明らかになるのは、人間の行動は決してロジックだけでは語れないという事実であり、だからこそ、遊び心や驚きを持ったデザインの力が、社会の中でより重要になってくるという未来への示唆でもあります。
仕掛けのためのFAD要件+ユーモア
「仕掛け」が満たすべき要件に、「公平性(Fairness)」、「誘引性(Attractiveness)、「目的の二重性(Duality of Purpose)」の3つを掲げています。
仕掛けが単なるアイデアや装飾にとどまらず、実社会の中で継続的に機能するためには、それを裏づける理論的な骨格が求められます。その指針として著者が提示するのが、「FAD要件」です。
これは、効果的な仕掛けに共通する3つの要素──Fairness(公平性)、Attractiveness(誘引性)、Duality of Purpose(目的の二重性)──によって構成されており、仕掛けの社会実装における実効性を支える枠組みとなっています。
まずFairness(公平性)は、仕掛けが特定の個人や属性のみに恩恵をもたらすのではなく、関わるすべての人にとって受け入れ可能であり、なおかつ利益や便益が平等に行き渡る構造になっていることを指します。仕掛けを導入することで誰かが一方的に得をしたり、別の誰かが損をするような設計では、継続的な運用は難しくなります。公平性の担保は、仕掛けが社会的に受け入れられるための最低条件と言えるでしょう。
次にAttractiveness(誘引性)は、人の注意を引き、思わず参加したくなるような魅力の有無に関わります。仕掛けの多くは「やらされている」感を排除し、「やってみたい」と思わせる設計になっていることが重要です。視覚的な面白さに加え、ちょっとした違和感や遊び心、あるいは共感を呼び起こすストーリーが、行動の引き金になります。
そしてDuality of Purpose(目的二重性)は、表向きの目的と裏に隠れた本来の目的が巧妙に重なっている設計を意味します。たとえば、バスケットゴール付きのゴミ箱は「遊びたい」という気持ちをきっかけに「ゴミを捨てる」という目的を自然に達成させます。行動を促す本当の意図を前面に出さず、別の動機によって結果的に目的を果たす──この二重構造が、強制ではなく自発性を引き出す鍵となります。
FAD要件を満たす仕掛けは、単に人を動かすだけでなく、その行動が社会に対してもプラスに働くよう設計されています。つまり、個人の関心と社会的な目的が矛盾せず共存できる状態を生み出すのです。
仕掛けを効果的にするためには、「公共性(F)」「誘引性(A)」「目的の二重性(D)」の3つが重要です。さらにここに「ユーモア(H)」を加えることで、人の心を動かす力が大きく高まります。仕掛けは正しさだけでなく、ちょっとした面白さや遊び心があることで、人に「やってみたい」と思わせることができます。
その関係性を数式で表すと、 仕掛けスコア = F ×(A + D + H) となります。つまり、公共性が土台となり、その上に「魅力」「仕組みの面白さ」「ユーモア」が積み重なることで、仕掛けの効果が決まります。 ユーモアは単なるおまけではなく、行動を軽やかに、自然に引き出すための重要な要素なのです。
優れた仕掛けを考えるための6つのコツ
「やりたい」という気持ちを肯定しながらWinーWinの関係を生み出す仕掛けの発想をみんなが身につければ、社会はもっと暮らしやすくなるはずです。
松村氏は、優れた仕掛けを考えるための6つのコツを挙げます。
・正論で考えない ・・・小さな仕掛けをつくって効果を検証し、正論より有効であることを証明
・3秒で勝負を決める・・・関心を失わせないために3秒で引きつける
・誰もが知るもので仕掛ける・・・過去の素材を応用する
・ユーモアで心をほぐす・・・人に興味を持ってもらうためには、ユーモアが欠かせない
・利己的かつ利他的で、喜びを生む・・・仕掛けた方と仕掛けられた双方がWinーWinの関係を築く
・「新規性×親近性」で心をつかむ・・・新規性と親近性を同時に満たすための新たな文脈を考える
仕掛けを成立させる6つの原則に共通しているキーワードは、「人の興味を引くこと」です。人は命令されて動くよりも、自ら「やってみたい」と感じたときにこそ、大きく動きます。そこにあるのは、強制ではなく誘導。論理ではなく感情。このバランスの転換こそが、仕掛学の核にある思考です。 人間は、合理的な判断をする存在である前に、感情に反応する生き物です。
「禁止」や「義務」で行動を促そうとしても、そこには抵抗や無関心が生まれやすくなります。しかし、思わず笑ってしまうような仕掛けや、つい触れてみたくなるような工夫があれば、人は自らの意思で行動を選びます。そこには、行動を変えるための「快のデザイン」が働いているのです。
たとえば、階段をピアノの鍵盤に見立て、踏むと音が鳴るようにするだけで、多くの人がエスカレーターではなく階段を使うようになります。合理性ではなく、好奇心に訴える設計が、人の足を自然と動かしているのです。
そうしたユーモアの感情は一時的なものではなく、行動の継続性を生み出す持続力へと変わります。 この発想は、教育やビジネス、地域づくりなど、さまざまな分野に応用が可能です。学びを「やらされること」から「やりたくなること」に変えることで、世の中が少しだけよくできるです。
好奇心が行動の起点になる社会では、強制や管理に頼らずとも、人々は自発的に動き始めます。本書にはそうした設計のヒントとなる事例が数多く紹介されており、読者は実社会で応用可能な「行動変容のヒント」を得ることができます。
著者が指摘するように、仕掛けという考え方が社会に広がれば、日常のあらゆる場面に創造的な仕組みが組み込まれていくはずです。それは大がかりな制度変更や設備投資を必要とするものではありません。
むしろ、人の行動原理に寄り添った、小さく、シンプルで、再現性のある工夫がベースとなります。 そしてその積み重ねこそが、公共空間や生活環境に自然なユーモアや遊び心をもたらし、人を無理なく動かす設計として社会に定着していくのです。その結果、私たちの暮らしは劇的ではないにせよ、確実に、そして心地よく変化していくことになるでしょう。






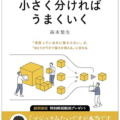

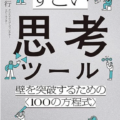




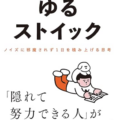
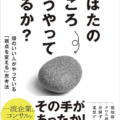
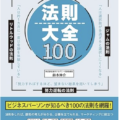


コメント