人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」
石山恒貴
光文社
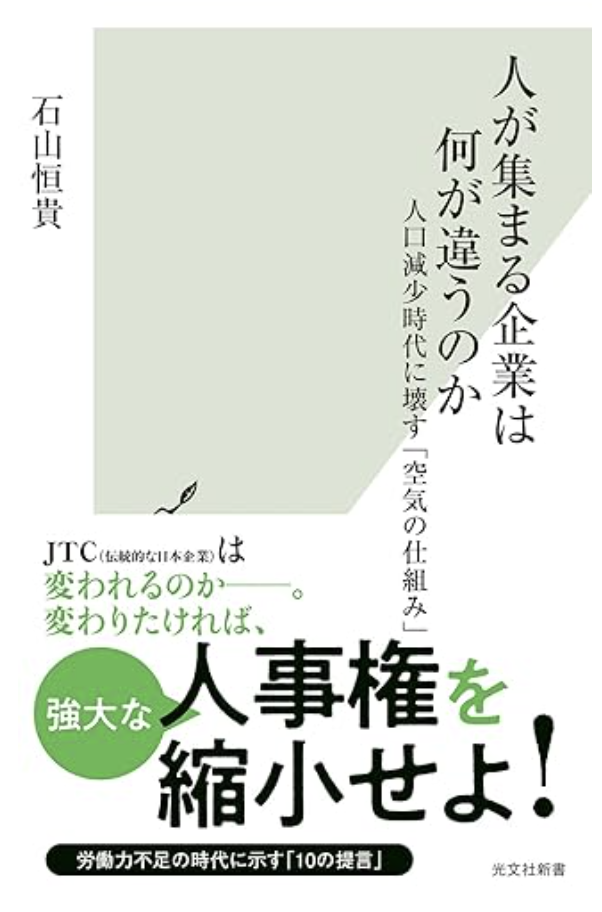
人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」 (石山恒貴)の要約
人口減少と人手不足が進む中、「人が集まる企業」の条件を理論と実践の両面から解き明かす本書は、企業文化に根づく「三位一体の地位規範信仰」を問題視し、変革の鍵として10の具体的提言を提示しています。サイボウズやカゴメなどの成功事例も交え、企業が人材戦略をどう再設計すべきかを示す、経営者必読の一冊です。
三位一体の地位規範信仰の問題点とは何か?
三位一体の地位規範信仰に基づく日本企業の仕組みは日本的雇用の本質に影響を与えている。だからこそ、日本的雇用の本質も変わっていないのである。 (石山恒貴)
人が足りない、採れない、定着せずにすぐに辞めていく——。 この現実に、今、多くの企業が真正面から向き合わざるを得なくなっています。 人的資本経営を実践すると言いながら、本音では人材は代えが効くと考えている経営者がいまだに多いように感じます。
かつては「人さえいればなんとかなる」という感覚が、経営や人事部の根底にありました。実際、そうした時代が確かにあったのです。高度経済成長の波に乗り、人が組織に忠誠を尽くし、終身雇用と年功序列で人生を預けられる——そんな時代背景がそれを可能にしていました。
しかし今、私たちは全く異なるフェーズに突入しています。人口減少という構造的問題はすでに「未来のリスク」ではなく、「現在のリアル」として、私たちの目の前に立ちはだかっています。
あらゆる業界で人手不足が慢性化し、人材獲得はますます難しくなっています。しかも、やっと採用できても、数年で辞めていく。そんな現象が珍しくなくなった今、旧来の人事制度や組織運営ではもはや限界が来ているのです。
それでも、一方でなぜか人が集まり、辞めない企業が存在しています。この事実は希望であり、同時に問いかけでもあります。しかもそれは、いわゆる意識の高いスタートアップや自由なカルチャーを持つ外資系に限らず、国内の伝統的な企業の中にも見られるということに注目すべきです。
この差は何なのか? 何が、その企業に人を引き寄せているのか? その答えを探す中で出会ったのが、本書人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」です。
この本は、単なる制度改革や働き方改革のHow-toではありません。法政大学教授の石山恒貴氏は、日本的雇用慣行が抱える根深い構造問題にメスを入れ、「なぜ変わらないのか」「どうすれば変えられるのか」という問いに真正面から向き合います。
そして、その答えを理論と実践の両面から、極めて明快に、そして現実的に提示しているのです。 石山氏が核心的なキーワードとして掲げるのが、「三位一体の地位規範信仰」です。これは、今の日本企業を根底から支えてきた一方で、多様性や柔軟性といった現代的価値観の浸透を阻んでいる“見えない呪縛”とも言える存在です。
しかも、この信仰はもはや誰かが明確に「信じている」というレベルの話ではありません。石山氏は言います——三位一体の地位規範信仰は、もはや“空気”になっているのだと。 空気のように当たり前にそこにある。 空気のように見えないから、自分がその影響を受けていることにすら気づかない。 だからこそ、成果主義を取り入れても、ジョブ型に舵を切っても、人的資本経営を打ち出しても、根っこの空気が変わっていなければ、実質的には何も変わらないのです。
こうして、日本企業は“外装”だけをアップデートし、実質的な組織文化や人材マネジメントの構造は、古いまま温存され続けている。これこそが、日本企業が「変われない」理由の核心だと、石山氏は喝破します。
この「三位一体の地位規範信仰」は、以下の3つの構成要素から成り立っています。 ひとつ目は「無限定性」。これは正社員総合職に代表されるように、職務や勤務地が限定されず、企業側が人事において大きな裁量を持つ仕組みのことです。配置転換も転勤も、社員の意思とは関係なく行われる前提に立った制度であり、働き方の柔軟性とは相反する性質を持っています。
ふたつ目は「標準労働者モデル」。年功序列、フルタイム勤務、男性中心のキャリア形成など、かつての典型的な社員像に基づいた制度設計です。現代のライフスタイルや働き方の多様性とは明らかに乖離しており、多様な人材を受け入れるためのハードルになっています。
3つ目の要素が「マッチョイズム」です。 これは、長時間労働を厭わず、厳しい環境に身を置くことを美徳とする価値観のことです。がんばってなんぼ、弱音は甘え、犠牲こそが尊い。こうした空気が、日本企業の中に根深く染みついてきました。これは特定のブラック企業に限った話ではなく、戦後の経済成長を支えてきた当たり前の延長線にあるものです。
石山氏は、マッチョイズムを「行き過ぎた仕事至上主義」と定義しています。「弱みを見せるな」「強くあれ」「仕事がすべて」「競争に勝て」といった4つの規範が、その背景にあります。これは無限定正社員や年功序列の標準労働者モデルとも深く結びつき、日本特有の地位規範として根を張ってきました。
この信仰の中で働く人々は、私生活を犠牲にして過剰な責任を担うことが前提となります。家庭内では、そのしわ寄せを誰か——多くはパートナー——が引き受ける構造が暗黙のうちに成立してきました。人口ボーナス期には、こうした役割分担が現実的だったため、社会全体としても三位一体の構造が成立していたのです。
しかし今は違います。人生100年時代となり、定年後の生き方に注目が集まる中で、三位一体の働き方だけでは人生の全期間をカバーできないという認識が広がり始めました。この変化が、「もっと自分らしく生きたい」という価値観の高まりにつながっています。
そうした背景の中で注目されているのが「サステナブルキャリア」です。これは、仕事だけにとどまらず、家庭や地域、余暇なども含めた人生全体を有機的に捉え、持続可能なキャリアを築いていくという考え方です。
サステナブルキャリアは、時間軸の「縦」、生活空間の「横」の両面にまたがる概念であり、自らの意味を追い求め、多様な経験を通じて成長していくことを重視します。
石山氏は、その成果として以下の3点を挙げています。 1つ目は、心身の健康。 2つ目は、主観的な幸福感。 3つ目は、現職で成果を出し、将来の可能性を拓いていく力。 これらのバランスが取れてこそ、持続可能なキャリアは成立すると言います。
しかし、こうしたキャリア観が広がるうえで大きな障壁となっているのが、依然として企業文化に残る「三位一体の地位規範信仰」です。 たとえば、リクルートワークス研究所が指摘する日本的雇用の問題には、次の4点があります。
① 一度枠から外れると戻るのが難しい
② 男女間の賃金格差
③ 学びと仕事のつながりの希薄さ
④ 個人のキャリア自律性の欠如
これらはいずれも、企業への依存が強すぎることと無関係ではありません。「企業がなんとかしてくれる」という意識が、自発的な学びやキャリア設計を妨げているのです。 結果として、“枠の外”に出た人の多くがキャリアを停滞させ、非正規にとどまる状況が続いています。これは、個人にも社会にも持続可能とは言えません。
そもそも、無限定性・標準労働者モデル・マッチョイズムという4つの要素は、高度経済成長期には合理的で効果的なシステムでした。人口は右肩上がり、終身雇用も年功も前提として成り立っていたからです。
企業と個人は、いわば運命共同体でした。 しかし現代はどうでしょうか。外部環境は激変し、働き方も価値観も多様化しています。それにも関わらず、企業内部の制度や文化は、いまだに昭和の空気を引きずったまま。制度と文化が相互に補強しあい、変化を拒んでいる。その結果、企業は変わるどころか、時代の変化に取り残され、じわじわと衰退していっているのです。
組織に変革をもたらす10の提言
本書として提示するグランドデザインの骨子は、無限定/限定中立社会の実現である。
本書の魅力は、理論だけでなく、実際に組織で取り組むべきアクションが明確に提示されている点にあります。著者が示す10の提言は、決して理想論ではありません。いずれも、現場での実行を前提とした現実的な内容であり、組織の意思決定次第で確実に着手できるものばかりです。
【組織に変革をもたらす10の提言】
[提言1]グランドデザインの明確化
[提言2][企業に対して]本人同意原則の導入――企業が自ら強大な人事権を放棄する
[提言3][企業に対して]無限定/限定の処遇中立化
[提言4][企業に対して]ライフキャリア最優先企業の実現
[提言5][企業に対して]企業のあり方の再定義と日本企業的パターナリズムの放棄
[提言6][企業に対して]ICTを活用して「社員の平等」の強みを活かす
[提言7][企業に対して]入口改革――構成する人材の多様化とオンボーディングの強化
[提言8][企業に対して]出口改革――定年の見直し、オフボーディングの強化
[提言9][労働組合に対して]無限定/限定の中立化と多様な働き手の包摂
[提言10][国・社会に対して]グランドデザイン(無限定/限定中立社会)の実現
これらの提言の中心にあるのが、「グランドデザインの明確化」です。 ここでいうグランドデザインとは、企業や社会が目指すべき人材活用の全体像を描くことにほかなりません。
その核となるのが、「無限定と限定の中立化」「多様な働き手における働きがい(ディーセント・ワーク)の確保」、そして「個人のライフキャリアの尊重」といった上位目標です。これらを明確にしたうえで、具体的には雇用の維持・拡大や制度設計へと落とし込んでいくことが求められます。
特に重要なのは、「三位一体の地位の有無による処遇格差をなくすこと」です。現在の日本社会では、正社員という地位が、無限定性・年功序列・マッチョイズムという文化的背景と結びつき、まるで“身分”のように固定化されてしまっています。
そこから外れると、待遇も、機会も、評価も大きく下がってしまう——そんな状況が常態化しているのです。 この固定化を打破し、正社員・非正規・フリーランスといった雇用形態を柔軟に行き来できる状態をつくることが大切です。
それにより、すべての働き手においてディーセント・ワークの機会が保障される社会を目指せます。これこそが、石山氏が語る「無限定/限定中立社会」の姿であり、グランドデザインにおける最優先のゴールなのです。
ただし、こうしたグランドデザインを掲げただけでは、理想のままで終わってしまうリスクもあります。そこで鍵を握るのが、「本人同意原則の導入」です。企業が持つ強大な人事権を一方的に行使するのではなく、社員との間で人事異動に関する合意形成を行う——。この姿勢の転換が、企業と個人との関係性を根本から変えていきます。
企業と社員がお互いに意向を擦り合わせるという行為そのものが、これまで日本企業に深く根づいていたパターナリズムの縮小につながるのです。
また、「無限定と限定の処遇の中立化」も大きな柱です。いわゆる無限定プレミアムを見直し、雇用形態の違いによる処遇格差を最小限に抑えることで、無限定・限定・非正規の区分を柔軟に行き来できるようにする。これは、社員のキャリア選択肢を広げるうえで、極めて重要な取り組みです。
企業文化の根本に変化をもたらすという点では、「ライフキャリア最優先企業」の実現も注目すべき視点です。ライフイベントが尊重されることで、社員同士が自然に支え合う空気が生まれます。信頼、互酬性、ネットワークといったソーシャルキャピタルの3要素が、組織の内側から醸成されていくのです。これは、制度ではなく「文化」として根づかせていくべきものです。
さらに、これからの企業に求められるのは、「社員以外」との共生です。副業者、フリーランス、アルムナイ(退職者)といった多様な関係者とオープンに交流する姿勢が、結果的に健全な企業文化を育てていきます。組織の“外”を排除せず、共に価値をつくる姿勢が、新たな競争力にもつながっていくはずです。
そのためには、ICTの積極活用も不可欠です。単なる業務効率化ではなく、働き手一人ひとりの選択肢を増やすためのインフラとして、テクノロジーを使いこなすことが求められます。
一方で、人材の“入口”と“出口”に関する設計も見直さなければなりません。採用時には、年齢・性別・キャリアの背景に関係なく多様な人材を受け入れられるようにし、同時に「オンボーディング」のプロセスを丁寧に整備する必要があります。新たに仲間になる人が、スムーズに組織文化へ適応できるよう、オリエンテーション、フォローアップ、メンタリングといった支援が重要になります。
そして「出口」においても、改革は急務です。定年の見直しや退職後のキャリア支援を含めた「オフボーディング」の充実こそが、企業にとっての真価を問われる領域です。アルムナイと良好な関係を保ち続けることは、単なる“離職者対応”ではなく、未来への資産形成とも言えます。退職した人すら大切にできない組織が、多様な働き手を受け入れられるはずがないのです。
こうした提言の数々に共通しているのは、「キャリアの選択における納得感」の重視です。従来のように命じられた仕事を淡々とこなすのではなく、自分の意思でキャリアを選び、企業がそのストーリーに伴走していく。それが、これからの時代に必要な企業のあり方です。そして最後に、本書が私たちに突きつけてくる問いは明確です。
それは「人材戦略とは、企業の存在意義そのものである」というメッセージです。福利厚生や制度の見直しという表層の話ではなく、組織が社会の中で何を目指し、どう人と関わっていくのか——経営そのものに直結する本質的な問いが、ここにあるのです。
だからこそ、この本は人事部門だけでなく、経営者こそ読むべき一冊です。人が集まる企業は、偶然ではなく、意志をもってつくられているのです。
本書では、サイボウズ、カゴメ、ギャップ・ジャパンなど、すでに人材戦略を経営の中心に据え、成果を上げている企業の事例も紹介されています。単なる理念に終わらせず、組織変革を実行に移してきた企業たちのリアルな姿は、きっと多くの経営者にとって大きなヒントになるはずです。





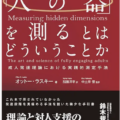


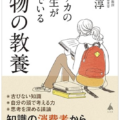




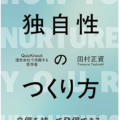


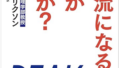

コメント