私たちは意外に近いうちに老いなくなる
吉森保
日経BP
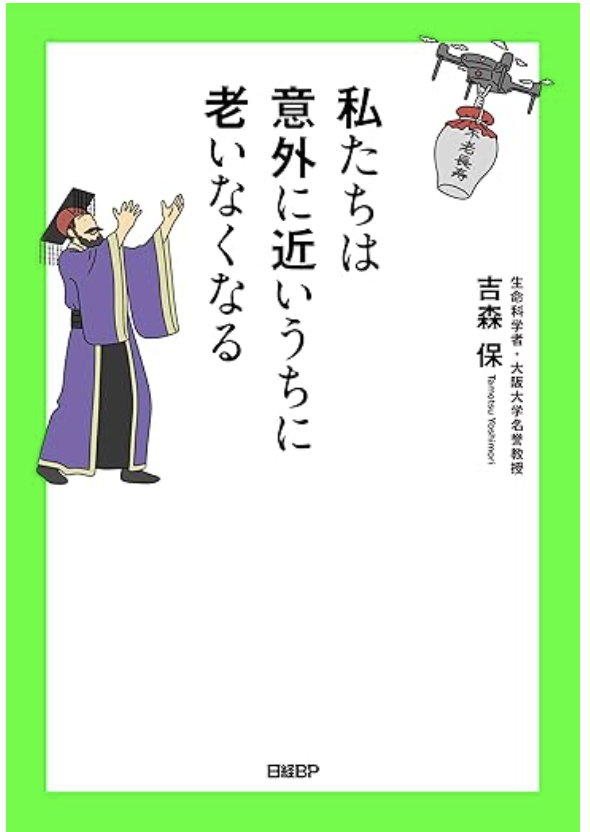
私たちは意外に近いうちに老いなくなる (吉森保)の要約
老化はもはや避けられない運命ではなく、科学の進歩によってそのメカニズムが解明されつつあります。大阪大学の吉森保教授による著書では、オートファジーをはじめとする最新の研究成果をわかりやすく紹介し、老化を遅らせる鍵は特別な方法ではなく、日々の習慣にあることを教えてくれます。健康長寿を目指す現代人に希望と行動のヒントを与えてくれる一冊です。
人類の夢である「不老長寿」は実現するのか?
21世紀に入り、生命科学研究の最前線では「老い」に対する考え方は大きく変わっています。老化は私たちがあたりまえに受けとめていた「避けられない運命」ではなく、回避できるものかもしれないのです。人類の長年の夢だった不老長寿が夢物語ではなくなりつつあるのです。(吉森保)
日本はすでに長寿社会に入り、100年を生きることが珍しくなくなりました。それでも「不老長寿」という言葉を聞くと、どこか夢物語のように感じる人が多いはずです。ただ、ここ数年で進化してきた生命科学やバイオテクノロジーは、その距離を確実に縮めています。
大阪大学の吉森保教授による私たちは意外に近いうちに老いなくなるは、老化研究の最前線をわかりやすく紹介する一冊として注目されています。 吉森教授は、大阪大学大学院生命機能研究科および医学系研究科で教授を務め、2017年には大阪大学栄誉教授に就任した人物です。
1996年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏のもとでオートファジー研究に従事し、この分野のパイオニアとして広く知られています。
本書では、ノーベル賞級の活躍を見せる研究者たちに吉森教授が直接取材を行い、最先端の研究内容をわかりやすく解説しています。 細胞の老化、免疫、皮膚、NMNなど、10のテーマが取り上げられており、老化メカニズムの全体像を多角的に知ることができる構成となっています。
21世紀に入り、老化に対する捉え方は大きく変化しています。かつて避けられない宿命と考えられていた老化は、実は回避できる可能性があるのではないかという見方が強まってきました。人類が長年夢見てきた「老いない体」は、すでに空想の域を出て、現実に近づきつつあるのです。
「不老不死のクラゲ」として知られるタリトプシス・ドーニーは、成熟した個体が若い段階へと戻るという驚くべき能力を持っています。細胞の再プログラミングによってライフサイクルをリセットするこのクラゲは、理論上、無限に生きることが可能だとされています。
また、ヒドラは自己再生能力により老化しない生物とされ、ホッキョククジラはがんをはじめとする老化関連疾患にかかりにくく、200年以上の寿命を持つことでも知られています。
こうした事例から、老化は避けられない現象ではなく、特定のメカニズムによって制御されている可能性があるという仮説が導かれています。もし、その仕組みが解明できれば、老化を遅らせたり、部分的に逆転させたりすることも理論的には可能となるかもしれません。
老化の要因として注目されているのが「慢性炎症」です。これは、免疫の働きが追いつかなくなった結果、体内にくすぶるような炎症が続く状態を指します。長寿の人々は、こうした炎症のレベルが低く抑えられていることが多いという研究結果もあります。
吉森教授が注目するオートファジーは、細胞内の不要物を掃除するだけでなく、損傷を受けた細胞小器官の修復も担っており、老化防止に重要な役割を果たしています。この働きを妨げるのが「ルビコン」というたんぱく質です。加齢とともにルビコンが増えることで、オートファジーの活性が抑制され、老化が進行すると考えられています。
一方で、このルビコンの働きを抑える可能性があるのが「MondoA」という因子です。MondoAはオートファジーを維持し、細胞の老化を遅らせる働きを持っているとされますが、こちらも加齢とともに減少する傾向があります。特に腎臓などの臓器では、MondoAの減少と病気の進行に明確な関連があることが示されています。 オートファジーを活性化させる食品成分にも注目が集まっています。
たとえば、納豆や味噌、しょうゆ、キノコ類、チーズに含まれる「スペルミジン」、ザクロの「ウロリチン」、赤ワインの「レスベラトロール」などがその一例です。これらは伝統的な和食や発酵食品にも多く含まれており、日本人の食生活がオートファジーを活性化するのに適している可能性があることも興味深い点です。
最近では、徳島県の伝統的なお茶「阿波番茶」にも、オートファジーを活性化させる作用があることが報告され、注目を集めています。阿波番茶は伝統的な発酵茶で、昔ながらの製法を守り続けてきた飲み物です。その中の濃縮エキスが老化の抑制を超えて、実際の若返り効果があると著者は指摘します。
オートファジーを高めるのは、当たり前の習慣
バランスのよい食事、適度な運動、よく寝る、食べすぎや過剰な摂食はしない。「あたりまえのことばかりだな」と思われた人も多いかもしれませんが、日常生活でオートファジーを高める特別な方法は実はありません。
細胞の老化を防ぐには、特別な方法があるわけではありません。実は、昔から「体にいい」と言われてきた生活習慣こそが、細胞の若さを保つカギだったのです。たとえば、たばこを吸わないことや、お酒をほどほどにすること、暴飲暴食を避け、紫外線を浴びすぎないように気をつけること。適度に体を動かし、しっかり眠ることも大切です。
バランスの取れた食事、過不足のない運動、質の良い睡眠といった、いわば当たり前のことの積み重ねが、オートファジーを活性化し、細胞の老化を抑えてくれるのです。
つい、何か特別な方法や新しい成分に目が向きがちですが、研究が示しているのは、最新科学の結論が「昔ながらの健康習慣は正しかった」という事実であるということ。日常生活の中でオートファジーを劇的に高める特効薬のようなものは存在しません。
でも、だからこそ、毎日の積み重ねが何よりも大切なのです。 老化は、体全体に起こるものだと思われがちですが、実際には細胞レベルでも進行しています。細胞が新しく生まれ変わる力が弱まると、体そのものの若さも失われていきます。
そして、SASP(老化関連分泌因子)という物質が、細胞老化の重要なカギを握っていることがわかってきました。さらに興味深いのは、老化細胞にはがん細胞の発生を防ぐという側面もあり、単純にすべてが悪者ではないということです。
加齢による免疫の衰えも見過ごせません。特に40代以降になると、免疫機能の要である胸腺が萎縮し、免疫バランスが崩れやすくなることで、慢性的な炎症や自己免疫疾患のリスクが高まります。私たちの体は、「自分」と「異物」を見分けるシステムが少しずつ鈍くなっていくのです。
肌の老化も例外ではありません。しわやたるみ、しみなどの変化は、単なる年齢のせいではなく、紫外線のダメージが大きな要因となっています。日光から肌を守ろうと分泌される酵素が、逆に皮膚を老化させてしまうこともあるのです。免疫細胞の力が弱まると、肌の防御力も落ち、しみができやすくなっていきます。
老化を研究する上で、注目されているのがハダカデバネズミという動物です。彼らは老化細胞を自ら除去する仕組みを持ち、年齢を重ねても死亡率がほとんど上昇しない「老化耐性」を持っています。人間に換算すれば、数百年生きるほどの驚異的な寿命を持っており、環境を整えることの重要性を私たちに教えてくれます。
また、NMNという成分が注目されており、これは「サーチュイン」と呼ばれる酵素を活性化することで、老化を遅らせ、寿命を延ばす可能性があると期待されています。この酵素は、視床下部という脳の中枢が老化のスイッチを握っていることとも深く関係しています。
100歳を超えても元気に生きている人たちの研究も進んでいます。彼らには病気を引き起こす遺伝子が少ないという共通点がある一方で、たとえ遺伝的に不利だとしても、生活習慣次第でそのリスクを補うことができると、研究者たちは語っています。
中でも、110歳を超える“スーパーセンチナリアン”と呼ばれる人たちに関する興味深い調査結果があります。慶應義塾大学の百寿総合研究センターの調査によれば、彼らの多くは100歳を迎えた時点でも、自力で食事をとり、着替えをし、身の回りのことをこなす自立した生活を送っていたことがわかっています。
つまり、自立していた人ほど、その後さらに長く健康に生きられる可能性が高いのです。そして、この「自立」という言葉の背景にある医学的な重要ポイントは、「認知機能がしっかりと保たれていること」だと言えるでしょう。認知機能の維持こそが、超高齢社会において真の健康長寿を実現するための土台なのです。
百寿者は、一般的に病気の発症につながるとされる遺伝的な要因をあまり持ち合わせていないことも分かっています。実際に、遺伝子レベルで見ると、アルツハイマー病や糖尿病、心筋梗塞などの疾患にかかりにくい体質であることが明らかになっているのです。
近年、構造生物学の進化によって、体を構成するたんぱく質を人工的にデザインすることが可能になってきました。これにより、より精密な薬の開発が進み、難病に対する新しい治療法の扉が開かれようとしています。
また、老化研究においては魚類が非常に優れたモデルとされており、あらゆる生物に共通する「長寿のカギ」が存在するのではないかという可能性も出てきています。
さらに、なぜ女性の方が男性よりも長生きするのかという疑問に対しても、精子と卵子の役割の違いが寿命に影響しているという新しい視点が浮かび上がってきました。
動物は眠らなければ死にます。そして、人間は睡眠が不足すると老化が加速します。老化は病気になりやすくなることですから、結果的に死ぬ確率は上がります。
眠は、老化に影響を与える最大の生活要因のひとつです。 慢性的な睡眠不足はホルモンバランスを乱し、細胞の修復を妨げ、炎症を引き起こすことで、老化を一気に進行させてしまいます。必要な睡眠時間には個人差がありますが、自分にとって最適な睡眠量を把握し、それを毎日確保することこそが、老化を遅らせるための日常的な投資と言えるでしょう。
私自身、浅い睡眠に悩まされていますが、ドクターのアドバイスに従い、できるだけ横になる時間を確保し、睡眠の質を高めるよう意識しています。
また、睡眠の質を語るうえで欠かせないのが「レム睡眠」です。 レム睡眠は「夢を見る浅い眠り」と説明されることが多いですが、実際には記憶の整理や感情の調整、脳の可塑性(かそせい)の向上に深く関わっており、メンタルと身体の回復を支える重要な睡眠です。
ノンレム睡眠が身体の修復を担い、レム睡眠が脳のコンディションを整える――この二つがそろってこそ、真の意味での「若さ」を保つことができるのです。
本書が魅力的なのは、老化を不可逆の衰えではなく、科学的に介入可能なプロセスとして捉え直している点です。細胞、代謝、ホルモン、免疫、そして睡眠という生活要因まで、老化を多角的に読み解きながら、未来の健康に向けて今日から変えられる行動を提示してくれます。
「老い=衰え」という固定観念は、すでに古い常識になりつつあります。むしろ今は、どう歳を重ねればより健やかで魅力的でいられるかという視点が必要であり、本書はその答えを科学と希望の両面から示してくれています。




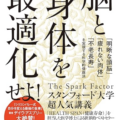
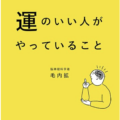
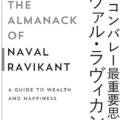
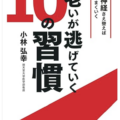

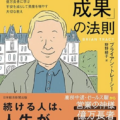

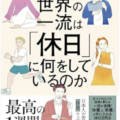
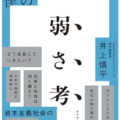
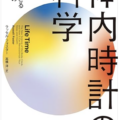

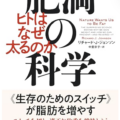


コメント