人がモノを買うしくみを言語化する ”知ったかマーケター”からの脱却
富永朋信
日経BP

30秒でわかる本書の要点
結論: 本書は、曖昧になりがちな購買心理を「心の機序(メカニズム)」として徹底的に言語化し、それを組織文化へと実装する具体的な道筋を提示することで、マーケティングに真の成功をもたらします。
原因:多くの現場で成果が出ないのは、マーケターが効率的な「近道」を求めるあまり、表面的なフレームワークに情報を当てはめるだけの教条的な仕事に終始し、人間の心の動きという本質から目を逸らしているからです。
対策: 「知ったか」の状態を脱するために、人がモノを買う瞬間に働く心理プロセスを根本から理解し、自分自身の言葉で言語化します。さらに、その一貫性をMVV(理念)と結びつけ、Routinizer(ルーティナイザー)によって組織に浸透させることで、持続的なブランド価値を構築します。
本書の要約
マーケティングの「知ったか」を脱するため、人がモノを買う瞬間に働く「心の機序」を根本から理解し、自らの言葉で徹底的に言語化します。ターゲットを属性ではなく「利用意図」の解像度で捉え直し、変化に強い多面体としてのブランドを設計。さらに理念をRoutinizerで組織の習慣へ実装し、社員をブランドの体現者に変えることで、マーケティングに劇的な成功をもたらす一冊です。
おすすめの人
・フレームワークを使っているが、いまいち成果や手応えを感じられていないマーケター
・組織のMVV(理念)が形骸化しており、現場の行動に繋がっていない経営者
・マネージャー デジタルやSNSなど手法論に偏った知識を、本質的な「人間理解」で統合したい人
・自分の企画や戦略に、周囲を「ぐうの音も出ないほど納得させる」根拠を持たせたい人
読書が得られるメリット
・言語化能力の向上: 「なんとなく」で進めていた施策に、明確な論理的裏付けを持てるようになる。
・戦略の精度向上: 顧客の「負」や「利用意図」を突く、空振りの少ないアプローチが可能になる。
・組織の実装力: 優れた戦略を「絵に描いた餅」にせず、社員が自ら動く仕組みへと変換できる。
・思考のOS強化: 流行のテクニックに惑わされない、時代を問わないマーケティングの普遍的な土台が身に付く。
知ったかマーケターからの脱却のために必要なこと
フレームワークの本質は何か、それがなぜ機能するのか、といったレベルで腹落ちしている必要がある。いわば「ぐうの音も出ない」くらいにマーケティングを理解している必要があるのだ。(富永朋信)
広告会社出身という背景もあり、私はこれまで多くのマーケティング関連の書籍を読み、そしてこのブログでもたびたび紹介してきました。マーケティングという言葉は、誰もが口にする一方で、その定義や領域は著者や立場によってまちまちです。最近ではSNSやデジタルマーケティングに特化した本が数多く出版され、実務者にとって参考になる情報も豊富になりました。
しかし、それらの情報の多くは技術的・戦術的なノウハウに偏っており、「人がモノを買うとはどういうことか」という本質にまで踏み込んでいるものは意外と少ないと感じています。 マーケティングとは、単なる手法やテクニックの集積ではなく、「仕組みづくり」です。すなわち、人が自発的に動き、商品やサービスを手に取るように導く“装置”を設計する営みであるべきです。
そうした視点から読んで非常に腹落ちしたのが、富永朋信氏による人がモノを買うしくみを言語化する ”知ったかマーケター”からの脱却という一冊です。 富永氏は、マスマーケティングからデジタルマーケティング、ブランディング戦略に至るまで幅広い領域で経験を重ねた、実務家としての知見と感性を兼ね備えたマーケターです。
本書では、マーケティングに携わる多くの人が陥りがちな“知ったかぶり”の状態を痛快に指摘しながら、購買行動の裏にある人間の心理を丁寧にひもといています。 私も本書を読むことで、言語化の解像度が確実に上がりました。
マーケティングとは、人に働きかけ、その人の心を動かす営みです。したがって、人の心の仕組みを理解しなければ、その本質には辿り着けません。ところが、多くの現場ではフレームワークに当てはめる作法ばかりが重視され、人の心にまで遡った思考やアプローチがなされていないのが実情です。
こうした傾向はマーケターに限らず、人間誰しもが持つ「近道を探したい」という欲求から生じるものであり、容易には打破できません。 本書が提案する視点は、従来の形式的なマーケティングの常識に対して明確なアンチテーゼとなっています。まず、「人は欲しいから買うのではない」という認識です。
人は現状に対する不満や不便、不安といった“負”の状態を解消するために行動する。この「マイナスを埋める」という構造を理解することで、訴求の精度が劇的に高まるとしています。
人がモノを買う理由は、「なじみがあるから」「良いから」「好きだから」の3種類がある。
人がモノを買う理由は、「なじみがあるから」「良いから」「好きだから」の3つに収斂すると著者は指摘します。 「なじみ」をつくるためには、単に接点を増やすだけでなく、繰り返しの中で想起される存在となることが重要です。
最初は広告や店頭で見かけることで助成想起に入り、その後、日常会話や関連体験の中で自然と浮かび上がる非助成想起へと昇華させていく必要があります。なじみは信頼や安心感につながり、購買のハードルを下げる重要な資産となるのです。
一方で「良いから買う」については、競合との比較の中で、どのようにして自社の商品やサービスが優れているかを示すことが問われます。そのためには、POP(Point of Parity=競合と同等の点)とPOD(Point of Difference=競合と異なる強み)を明確にし、ユーザーにとっての選択理由を作るポジショニングが欠かせません。
競合は直感的に設定してはならず、ブランドの利用理由を基にユースケースを洗い出し、それぞれにおける適切なポジショニングを定め、戦略と照らし合わせながら優先順位を明確にしていく必要があります。
「好きだから買う」という行動は、論理ではなく感情に根ざしています。ブランドに対する親しみや愛着といった情緒的なつながりが、購買の最終的な意思決定を後押しするのです。この感情的な結びつきを生み出すためには、ブランドの世界観やストーリー、ビジュアル、語感、接客体験など、すべてのタッチポイントにおいて一貫性のある「らしさ」を築き上げることが欠かせません。
ターゲットを「意図」の解像度で捉え直す:変化に強い多面体としてのブランド設計
ターゲティングとは、製品開発・コミュニケーションなどの対象を絞るため、自ブランドの商品・サービスを欲しいと感じている、またはそうなる可能性がある、コミュニケーション可能な人を定義することである。
ターゲティングとは、製品開発やコミュニケーション戦略の対象を明確にするために、自社の商品やサービスを「欲しいと感じている人」、あるいは「将来的にそうなる可能性がある人」で、かつ情報をきちんと届けられる人々を定義することです。
本書では、ターゲティングを三つの層で考えるアプローチを提案しています。第一に「コンセプチュアルターゲット」は、ブランドや製品の理想像を体現する理想的なユーザーです。
第二に「コミュニケーションターゲット」は、実際にそのブランドのメッセージに共鳴しやすい現実のユーザー層です。
第三に「プロモーションターゲット」は、キャンペーンや広告を通じて一時的に関心を持ち、購買に至る可能性のある広範なお客層を指します。
この三層構造に基づいて施策を設計することで、ブランドは柔軟かつ効果的なアプローチを実現できます。
「人」の解像度ではなく、それよりも一段詳細なレベルである、その心にある「意図」を単位とした解像度でターゲティングをすべきである。
さらに本書では、ターゲティングを「人」ではなく「意図」、すなわちその人が持つ目的や動機に着目すべきだと説いています。人が商品を求める背景には、「もっと効率的に作業したい」「自分を癒やしたい」「時間を節約したい」といった具体的な利用目的があります。
このように意図を単位として捉えることで、特定の人物像に縛られることなく、より本質的かつ普遍的なマーケティング戦略を構築することができます。
また、市場環境やトレンドが変化しても、利用目的ごとに構造的に整理しておけば、柔軟にリポジショニングすることができ、スピーディーな対応も可能になります。だからこそ、ターゲティングは「人よりも意図」で考えるべきなのです。
消費者の心の中で蓄積されたブランド理解・企業や製品にかかる印象の総和がブランドなのだ。ブランド価値規定はマーケターの机やパソコンの中に、ブランドは消費者の心の中にあるのだ。
「好きだから買う」という行動は、論理ではなく感情に根ざしています。ブランドに対する親しみや愛着といった情緒的なつながりが、購買の最終的な意思決定を後押しするのです。この感情的な結びつきを生み出すためには、ブランドの世界観やストーリー、ビジュアル、語感、接客体験など、すべてのタッチポイントにおいて一貫性のある「らしさ」を築き上げることが欠かせません。
消費者の心の中で蓄積されたブランド理解や、企業や製品に対する印象の総体こそがブランドであり、ブランド価値はマーケターの机上ではなく、あくまで消費者の記憶と感情の中に形成されていくものです。ブランドが「好きだから買う」という消費者の状態をつくるには、ブランドコンセプト、情緒的便益、パーソナリティなどを通じて、ブランドと消費者の関係性を明確に描く必要があります。
たとえば、「このブランドを使うと温かい気分になる」「自分がスマートに見える」「前向きな気持ちになれる」といった情緒的な価値がしっかりと伝わることが求められます。
そのためには、ブランドの存在を消費者に継続的に伝え続けると同時に、ブランド独自の世界観を構築し、体感させる工夫が不可欠です。特に画像や動画はその世界観の形成において大きな力を発揮します。なぜなら、画像は現実の一場面として受け取られやすく、その中にブランドの情緒的便益やパーソナリティを想起させる小道具や演出を盛り込むことで、ブランドの持つ空気感やストーリーが視覚的に強く伝わるからです。
実際のブランドには複数の利用目的が存在し、それぞれのユースケースをひとつの「面」として捉えると、ブランドは多面体のような構造を持っています。施策を打つたびに、ある特定の面が大きくなり、次第にその多面体は成長していきます。そして、そのすべての面を支える土台には、ブランドのパーソナリティやシンボルといった共通の基盤が存在しているのです。
ブランディングという手法は、人が情報を認識・判断する仕組みに基づいた、極めて人間的なアプローチです。人は参照点を設定したうえで、それと比較して物事の良し悪しを判断します。これがポジショニングが重要である理由です。
同じように、人は抽象的な概念として物事を捉えるため、ブランドもまた「概念の集合」として消費者の中に形成されていきます。だからこそ、ブランディングはマーケティングにおいて欠かせない営みなのです。
また、インサイトの本質は、単にユーザーが自覚していない「潜在ニーズ」を見つけることにとどまりません。それは顕在的か潜在的かを問わず、その人が商品を手にする瞬間の引き金となる「心の機序(メカニズム)」を解き明かすことにあります。
私たちは往々にして、観察から得た気づきを「似たような事象との共通性」という枠組みで整理してしまいがちですが、真に求められるのは、その行動の背後に潜む「根源的な利用理由」を突き止める視点です。 この視点を血肉化するためには、単なる知識の習得ではなく、実践を通じた思考の訓練が欠かせません。
具体的には、対象を徹底的に観察し、そこから導き出した仮説を現実の反応にぶつけて反証するというサイクルを愚直に繰り返すことが重要です。この「観察・仮説・反証」のプロセスを積み重ねることで、表面的な現象に惑わされることなく、人間の行動を突き動かす心理的メカニズム、すなわち真のインサイトへと辿り着く力が養われます。
社員をブランドの体現者に変える:MVVを「自分事」化するRoutinizer
コミュニケーションの目的は、より振れ幅が大きい認知変容や態度変容。
コミュニケーションが果たすべき真の目的は、単なる情報伝達ではなく、受け手の認知や態度における大きな振れ幅を伴う「変容」を引き起こすことにあります。
この目的を達成し、競争の激しい市場で勝ち抜くためには、ターゲットとの接触頻度を高めることが有効ですが、それには多大なコストを要するという現実があります。この予算の壁を乗り越え、限られた接触機会の中で頻度を補完するのが「インパクト」の役割です。
ここでのインパクトとは、意外性による「びっくり」と、論理的帰結による「納得」が高度に融合した状態を指します。
効果的なメッセージを構築するには、SNSのタイムラインや屋外広告(OOH)など、媒体ごとに異なるユーザーの接触態度や許容時間を精緻に分析し、そこから逆算して「びっくり」と「納得」のバランスを設計しなければなりません。メディアの特性を理解した上で、顧客を「認知」「理解」「納得」そして「行動」へと導くことが求められます。
顧客に向けた一貫性のあるメッセージ設計と、組織をあるべき姿へと方向づけるミッション・ビジョン・バリューは、表裏一体の存在です。組織全体が同じ方向を向き、一人ひとりの社員がその理念に基づいた意思決定を行うことで、市場において劇的な認知変容や態度変容を実現することが可能となるのです。
こうした一連の対外的なコミュニケーション活動は、組織の内実を映し出す鏡でもあります。組織としての施策や意思決定が理念と乖離しないための「物差し」がミッションとビジョンであり、個々の社員の行動を組織の文化に同調させる「転轍機(ポイント)」がバリューとして機能します。
ミッション・ビジョン・バリューがしっかり定まっている組織において、それらの決め事とうまくかみ合った形でブランド価値規定の要素も定められていると、Routinizerの力を使うことで、社員をビークル・メディア(情報やコンテンツを届けるための媒体や手段)としたブランドビルディングが機能し始める。
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)がどれだけ立派に掲げられていても、それが実際の組織運営やマーケティング活動に落とし込まれていなければ、単なるスローガンに終わってしまいます。理念が額面通りの存在にとどまり、現場の意思決定や行動に反映されない状態では、ブランドが持つ本来の力を発揮することは難しいのです。 だからこそカギを握るのが、「Routinizer(ルーティナイザー)」という考え方です。
これは、MVVやパーパスを掲げて終わりにせず、社員一人ひとりの判断や日常行動にまで自然に落とし込むための装置です。ブランドの理念を単なる“言葉”で終わらせず、組織の“無意識の習慣”として根づかせることで、社員は「浸透を待つ対象」から、ブランドを自ら動かす「体現者」へと進化します。 大切なのは、理念が頭で共有されることではなく、それが日々の選択において無理なく行動に表れることです。
MVVが浸透することで、社員自身がブランドの真のファンとなり、顧客とのあらゆる接点において一貫したブランド価値を届ける「ビークル(媒体)」となります。この「Routinizer」というエンジンによって社内と社外が強固に繋がったとき、マーケティング活動には揺るぎない一貫性が生まれ、顧客からの深い信頼と共感へと結実していくのです。
著者は、「フレームワークや法則の類は、最大公約数的な補助線に過ぎない」と指摘しています。完璧を目指すのではなく、まずは一定の精度で企画を立て、小さく始めてすばやく試す。そして得られたフィードバックをもとに、柔軟に改善を重ねていく。このアジャイルな思考と行動のサイクルこそが、変化の激しい現代のマーケティング環境において、実際に成果を生み出す現実的なアプローチであると説いています。
この姿勢には、大学でフレームワークを教える私の立場としても深く共感しています。教科書に載っている理論や図解を形式的に覚えることよりも、状況に応じてどう応用するか、目の前の課題に対してどう機能させるかが問われる時代です。マーケティングにおける知識は「使ってこそ価値がある」ものなのです。
本書は、テクニックを紹介するだけのハウツー本ではありません。理論と実践のあいだにある“考え方の土台”を鍛えるための一冊です。
目の前の課題にどう向き合い、どう解決へ導くかという視点を持てるようになります。現場で即座に判断を求められるマーケターはもちろん、日々の選択が組織の方向性を左右する経営者にとっても、そしてこれからマーケティングを学ぶ学生にとっても、本書は迷わず進むための信頼できる羅針盤となってくれるはずです。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。



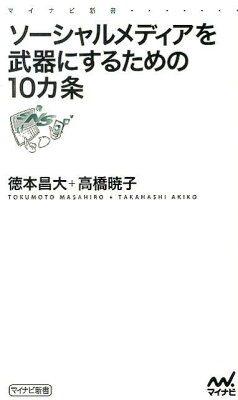













コメント