国民の違和感は9割正しい
堤未果
PHP研究所
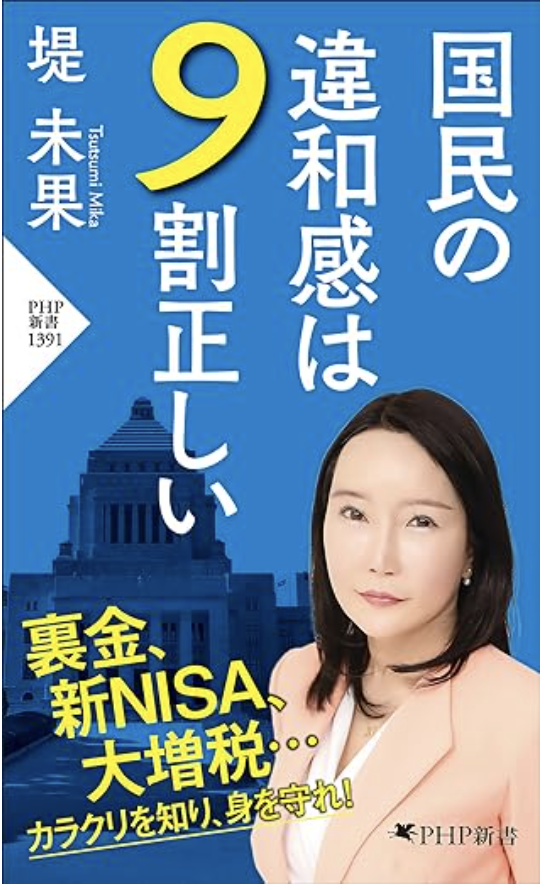
国民の違和感は9割正しい (堤未果)の要約
本書は社会の不条理や矛盾に対する違和感を大切にし、それを解決に向けた行動へとつなげるための指南書です。読者は、日常生活の中で感じる違和感を放置すると為政者に騙されてしまいます。私たちは違和感をむしろ積極的に考察し、行動に移すことで、社会の改善に貢献できるのです。
今の政府を信じられない理由
脱税している人が納税を呼びかけ、法律を守らない人が憲法改正を訴え、戦争に行かない人が戦争の準備をせっせと進める今の日本を、おかしいなあと感じている人は、決して少なくないのです。(堤未果)
最近、メディアの報道がドジャーズの大谷選手や芸能人に偏っていることが、経営者の集まりで話題になります。このような報道の陰で、重要法案が次々と可決され、私たちの生活は厳しさを増しています。これは、政治家やメディア、SNS企業と政府の間で情報が操作され、異なる意見が封じられている現状を反映しています。
メディアの偏向報道がもたらす影響は深刻です。国民の関心が芸能ニュースやスポーツに集中している間に、重要な政策や法案が可決されているのです。これにより、国民は自らの生活に直接影響を与える問題についての情報を見逃してしまう危険があります。
本来、債務償還費の15兆円を使うべき防衛予算増額ですが、財務省のメディアコントロールにより、以下の施策に置き換えられました。
・歳出改革
児童手当など、さまざまな分野での支出をカットし、浮いたお金を防衛費へ回す。
・決算剰余金: 予算の余りを防衛費に充てる。
例として、コロナ禍の雇用対策のために確保された予算の余りを防衛費に回す。
・国有財産の売却
NTT株という外資に投資させてはいけない政府が保有する資産を売却し、その収益を防衛費に充てる。
政府が細かくチェックされたくない法案ほど、成立プロセスを荒く、スピーディに進める傾向があります。2021年のコロナ禍で拙速に成立した「デジタル改革関連法案」を例に取ると、審議時間は30時間以下で、63本の法案がまとめて一回で採決されました。このような手法は、後ろめたさや問題のある内容を隠すためと考えられます。 法案成立後、個人情報保護の緩和など、多くの問題点が明らかになりました。
テクノロジーの進化により、見えない形で情報が統制されやすい社会が形成されています。デジタル世界では、物事を「正しいか、間違っているか」、「正義か悪か」、「ゼロか100か」の二元論で捉えがちです。このような視点に陥ると、思い込みやステレオタイプが強化され、自分の生きる現実に第三の視点が入ってこなくなります。
二元論に支配された社会では、正しくないものを許せなくなる一方で、間違えることを恐れるようになり、本当の自分がわからなくなる危険性があります。SNSではこの二元論が主流になり、お互いがディスり合っていますが、正しい情報を取りながら、客観的に考えることで問題点が見えてきます。
情報操作が続く中で、国民が沈黙し続けることは全体主義の進行を許すことになります。異なる意見が封じられ、情報が一方的に操作される社会では、個々の自由や権利が侵害されるリスクが高まります。このような状況を防ぐためには、国民が冷静に現状を問い、違和感を無視せずに行動することが重要です。
事故や事件、スキャンダル報道が過剰に行われるときこそ、政府の動向を確認することが必要です。国民の関心を逸らすような問題法案が隠されている可能性が高いからです。例えば、大規模な自然災害や著名人のスキャンダルが報じられる際に、背後でどのような政策決定が行われているかを注意深く見守るべきです。
違和感を感じたら、思考し、行動しよう!
国民が主権を取り戻し、未来を守るためには、情報に盲目的に従うのではなく、自ら考え行動することが必要です。以下のような具体的なアクションが求められます。
・多様な情報源の確認
一つのメディアだけに頼らず、複数の情報源からニュースを得ることで、バランスの取れた視点を持つことができます。
・批判的思考の養成
報道内容を鵜呑みにせず、自分で調べ、考え、疑問を持つことが重要です。報道の背後にある意図や背景を考慮する習慣を持ちましょう。
・政治への関心
日常生活に直接影響を与える法案や政策について、自ら情報を収集し、理解を深める努力が必要です。政治家の動向や政府の政策決定過程を注視することで、重要な決定がどのように行われているかを把握できます。
〈違和感〉を覚えたら、まだ大丈夫、と安心して下さい。感じる力が働いていることは、思考停止した受け身の消費者でなく、血の通った身体と健やかな心がある、人間である証拠です。〈民は愚かで弱い〉というのは、私たちがそれを受け入れ、自信を失い、無力になることで、得をする誰かからの刷り込みにすぎません。
「〈民は愚かで弱い〉という言葉は、他者からの偏見や制限を受け入れ、自信を失うことで、無力になることを意味します。しかし、私たちはそれを受け入れる必要はありません。違和感を感じたときに、自分の考えをしっかり持ち、行動に移すことで、自信を取り戻し、未来を切り開いていくことができます。
日常の中でふと抱く違和感を行動に変えることで、本来の力を取り戻し社会を変え始めた、ごく普通の人々のように、私たちが、今この瞬間に意識を向け、自分の頭で考え、次の現実を決める力を手放さないかぎり、未来はいくらでも創り出してゆけると著者は指摘します。
大谷翔平選手や芸能人のニュースが過剰に報道されていたら、政府が国民に知られたくない重要法案を審議している可能性があります。そのような状況下では、国民は情報を精査し、行動を起こすことが重要です。大谷選手のニュースに過度に注目することで、重要な社会問題や政治情勢が見過ごされるおそれがあります。
大正デモクラシーは、急速に軍国主義の波に飲み込まれました。その時代においても、人々は違和感を感じながらも、それを放置してしまった結果、戦前の状況に至ったと言えます。現代も同様に、違和感を感じたときには、それを無視せずに行動を起こすことが必要です。
大谷選手や芸能人のニュースに過度に注目することは、社会の健全な発展にとってプラスになるとは限りません。重要な政治情勢や社会問題にも目を向け、情報を適切に精査し、自らの立場から行動を起こすことが、民主主義社会を守り、進化させるために必要なことであると言えます。
違和感を大切にし、それを行動に変えることで、自信を取り戻し、未来を切り開く力を持っています。歴史の中で、普通の人々が違和感を行動に変えることで社会を変えてきたように、私たちも同じように未来を創り出していけるのです。違和感を覚えたときこそ、自分の感覚を信じて行動し、社会にポジティブな変化をもたらす力を発揮しましょう。
本書は社会の不条理や矛盾に対する違和感を大切にし、それを解決に向けた行動へとつなげるための指南書です。私たちは日常生活の中で感じる違和感を放置せず、むしろそれを積極的に考察し、行動に移すことで、社会の改善に貢献できるのです。
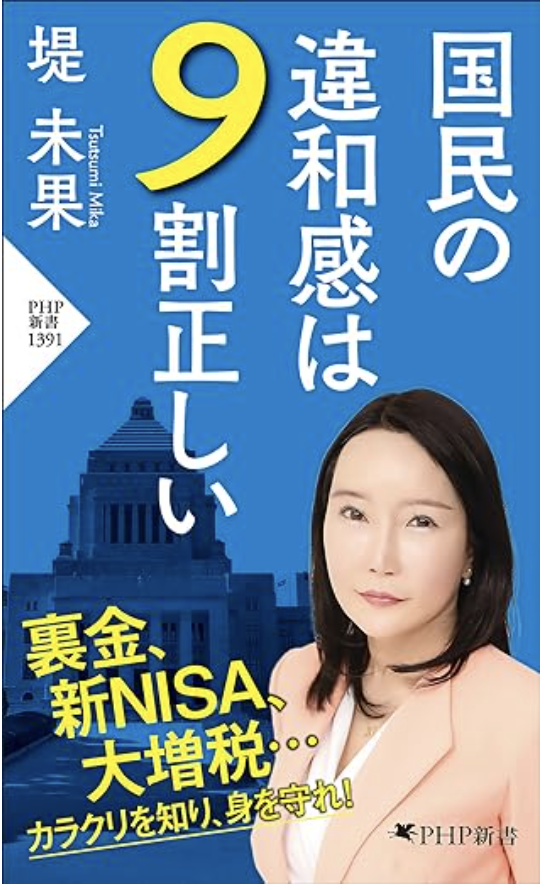









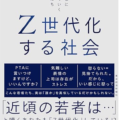







コメント