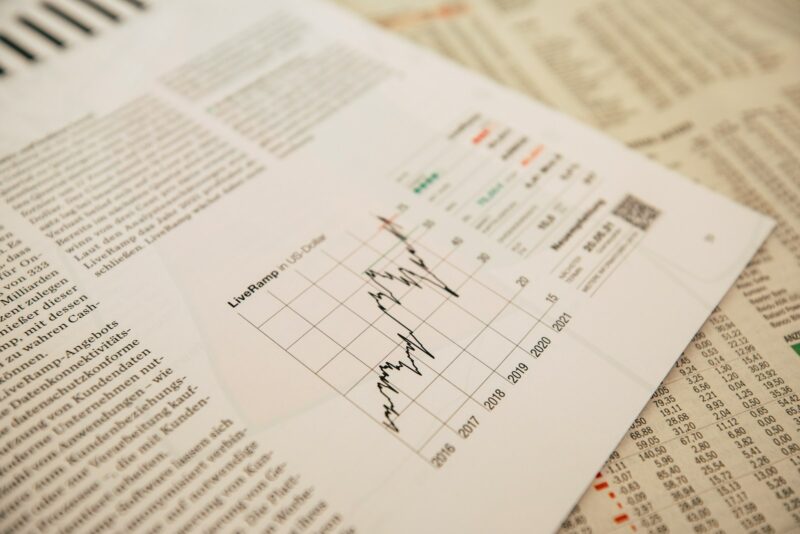
資本主義の宿命 経済学は格差とどう向き合ってきたか
橘木俊詔
講談社
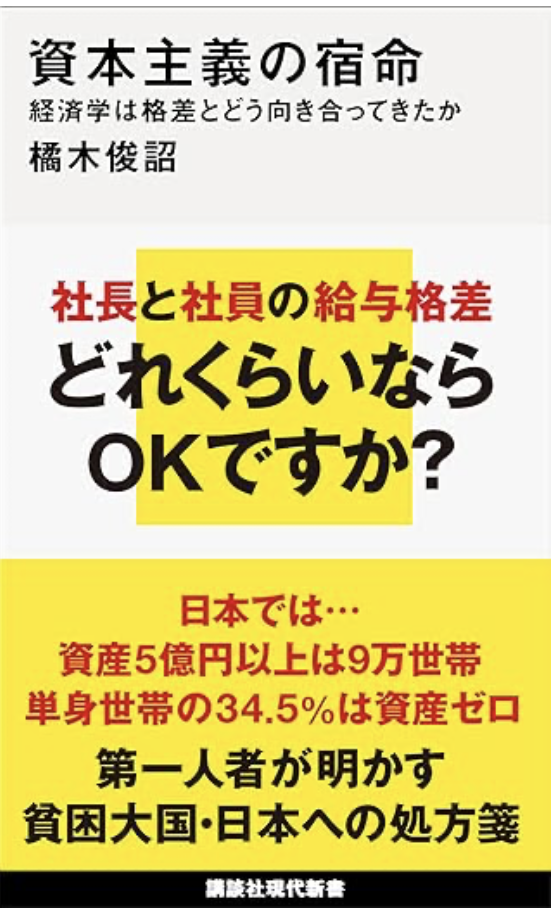
資本主義の宿命 経済学は格差とどう向き合ってきたか (橘木俊詔) の要約
資本主義社会における格差問題は、重要かつ複雑な課題であり、経済学はその解決に向けて常に進化し続ける必要があります。著者の提案を通じて、日本は持続可能で公平な社会を築くことができるでしょう。経済効率性と平等性のバランスを取りながら、国民全体の生活水準を向上させることが、今こそ求められています。
経済学者は格差をどう見てきたか?
格差問題は優れて社会・経済的な問題である。具体的には、格差を是正すると経済成長(あるいは経済効率性)を阻害する可能性があるとされる。これは経済成長(効率性)と公平性(平等性)がトレードオフの関係にあるとみなされているからである。(橘木俊詔)
経済学者の橘木俊詔氏は、格差という現代社会において避けて通れないテーマの「格差」に焦点を当てています。特に近年の日本では、相対的貧困率が15%を超え、資産5億円以上の世帯が9万も存在するという現実があります。このような状況下で、経済学はどのようにして格差を分析し、是正策を提案してきたのでしょうか?
著者は、アダム・スミス、マルクス、ケインズ、そしてピケティまでの経済学者たちがどのように資本主義の問題に取り組んできたかを参考にしながら、資本主義の欠点を修正するためのアイデアを提示します。
アダム・スミス
アダム・スミスは自由経済の信者として知られていますが、不正な取引行為を排する道徳哲学者としての一面もあります。スミスは市場の自律性を重視し、市場の「見えざる手」による調整メカニズムを説きましたが、自由経済の結果として発生する格差についてはあまり触れていません。これは、その時代背景において、格差の問題がまだ熟していなかったためとも考えられます。
カール・マルクス
カール・マルクスの経済学は、労働者の搾取を否定し、労働者間の平等と弱者の救済を主張する思想です。マルクスは、資本主義がもたらす格差を厳しく批判し、その是正を目指す行動を奨励しました。マルクス主義は、平等な社会を目指すために具体的な行動を起こすことを提唱しています。
ジョン・メイナード・ケインズ
ジョン・メイナード・ケインズは、労働組合や独占・寡占企業の存在が賃金や物価の下落を妨げることに注目しました。彼は、有効需要の理論を提唱し、経済の総供給量と総需要のバランスが重要であると説きました。ケインズは、総需要が不足すると失業が発生するため、政府の介入によって有効需要を増加させる政策を提案しました。
・所得税の減税
家計の可処分所得を増やし、消費を促進する。
・政府支出の増加
公共事業への投資を通じて需要を創出する。
・金利の低下
企業の設備投資を促進し、経済活動を活性化する。 ケインズの理論は、政府の積極的な経済政策を通じて非自発的失業を防ぐことを目指しており、現代のマクロ経済学の基盤となっています。
トマ・ピケティ
現代の経済学者トマ・ピケティは、格差が拡大傾向にあることを指摘し、富裕層と貧困層の間の格差是正を提唱しています。彼の著書21世紀の資本は、歴史的なデータ分析に基づき、資本収益率が経済成長率を上回ることが格差拡大の主因であると論じました。
累進課税制度は、所得が高いほど高い税率を適用することで、富の再分配を促進します。ピケティも提唱するように、累進課税の強化は富裕層からの資産収集を通じて、格差を縮小する有力な手段です。 最低賃金の引き上げ 最低賃金の引き上げは、低所得者層の収入を増加させ、貧困の緩和に寄与します。
適切な最低賃金の設定は、労働市場の健全化と格差是正に重要な役割を果たします。 社会福祉制度の充実 社会福祉制度の充実は、教育、医療、住宅などの基本的な生活支援を提供することで、格差を縮小する重要な手段です。特に教育への投資は、長期的な経済成長と格差是正に寄与します。
貧困や格差、富裕層の問題は、資本主義が拡大する中で避けられない問題です。資本主義が成長するにつれて、貧困はより深刻な問題となり、富裕層はますます豊かになり、格差は拡大していきます。
CEOの高い所得は企業の経営実績に大きく影響するため、経済効率を保持するためには、社長に高い所得税率を課すことは避けるべきだという意見があります。これにより、社長の課税後所得が高くなることを容認することになります。
この観点から、経済効率性と平等性(課税後所得の平等を目指す考え方)の対立が生じます。所得格差が大きいほど経済効率性は高まり、格差が小さいほど平等性が高まるという命題が導かれます。これを「経済効率性と公平性のトレードオフ」と呼びます。
著者は高所得者は少しぐらい所得税を上げても 彼らは働くことをやめないため、この政策は効果的だと指摘します。
また、ほぼどの国でも、高い教育を受けた人は高い所得を得ます。例えば、大卒者は高所得者となる傾向があります。 その国で誰でも平等に教育を受けられ、誰でも大学教育を受けられるなら、たとえ所得格差が存在しても容認される可能性が高いです。逆に、教育が親の所得水準に左右されるなら、所得格差の解消には教育という機会の格差から検討する必要があります。
日本は格差社会であるという事実
日本の貧困率は先進国のなかでもトップ級に属するほど高い国ということになる。
日本では機会の格差が存在しており、教育、就労、昇進においても男女、年齢、人種などの差別が見られます。日本のジニ係数は他の先進国と比較しても高く、所得格差が大きいことが確認されています。これは日本が戦後、格差が拡大してきたこと、そしてG7諸国の中で最も相対的貧困率が高いことに関連しています。
日本銀行の2022年の統計によると、金融資産を全く保有しない家計は二人以上の世帯で23.1%、単身世帯で34.5%に上ります。これらの数字は、収入が途絶えた際に生活苦に直面する可能性がある貧困予備軍の多さを示しており、日本の貧困率は先進国の中でも特に高い水準にあります。日本を格差社会の国として理解することは、先進国の中でも顕著な貧困率の高さによって象徴されます。
先進国を大きく区分すると、ヨーロッパは福祉国家として知られています。北欧諸国は高福祉国家、中欧諸国は中福祉国家、南欧諸国は低福祉国家に分類され、フランスは中福祉国家に位置づけられます。一方で、日本とアメリカは非福祉国家の典型とされています。
ピケティは、資本主義国における所得格差が大きくなっていることを明らかにしました。特に、高所得者の所得がますます高くなり、資本収益率が高いことから、彼らの資本所得も増加しています。これにより、高資本保有者と高所得者はますます富を蓄積し、有利な立場を築いています。
世界の資本主義を4つの地域に区分すると、次のようになります。
・英米両国:アメリカとイギリス
・カナダとオーストラリア
・大陸ヨーロッパ諸国
・日本
この中で、もっとも富裕化が進んだのはアメリカとイギリス、次いでカナダとオーストラリア、その次が日本と大陸ヨーロッパ諸国となります。ただし、大陸ヨーロッパと日本においても、格差社会の進行が見られました。これらの国々でも資本主義の宿命から逃れることはできず、格差は拡大していますが、その程度はアングロ・サクソン諸国ほど深刻ではありません。
ピケティの研究によると、日本の貧困率は先進国の中でも非常に高く、格差社会の特徴を顕著に示しています。貧困者と超高所得者の双方の視点から見ても、日本は格差社会に位置しており、これが日本の現状を反映しています。
日本においても格差の問題は無視できない状況にあり、今後の犯罪率の増加が懸念されています。また、格差社会では家庭ごとの支出にも大きな差が生じます。特に教育費に関しては、家庭の所得格差が教育達成に大きな影響を与えています。
高所得者の子どもは高い教育を受ける一方、低所得者の子どもは教育機会が限られるため、社会移動が困難になります。これは、親の教育や職業、所得がそのまま子どもに引き継がれる閉鎖的な社会を意味します。
さらに、格差社会では、社会の分断が進行し、多くの人がそれを認識しています。豊かな人と貧しい人、上流階級と下流階級、高級住宅地と庶民の住宅地などが分断されることで、相互の交流が減少し、相手に対する憎悪が高まる可能性があります。こうした分断は、社会の連帯感を弱め、意思疎通が難しくなるため、社会の進歩が停滞し、政治の不安定さを増長させるリスクがあります。
発展途上国では、貧困層が軍部と結託してクーデターを起こし、軍人独裁が圧政を行う例も見られます。アジアのミャンマーや南米、アフリカのいくつかの国々がその例です。先進国ではクーデターまでは至らないものの、政治の不安定さが顕著になることがあります。
アメリカでは、民主党と共和党の対立が高所得者と低所得者の対立を反映しており、連邦議会議事堂の襲撃事件のような政治事件を引き起こしています。 このように、格差社会がもたらす影響は多岐にわたり、犯罪率の増加や社会の分断、政治の不安定さなどが挙げられます。これらの問題に対処するためには、貧富の格差を縮小し、教育機会の均等化を図ることが重要です。
日本型福祉国家の推進のために必要なこと
日本が福祉国家へと転換することで、格差問題を大きく改善することが可能です。高福祉国家である北欧諸国の例を参考に、福祉制度の充実を図ります。
日本が福祉政策を進めるにあたり、以下の3つの候補が考えられます。
①アメリカ流の自立主義の徹底
自分の力で生活を成り立たせる方法。しかし、日本人はアメリカ人のような強い自立の精神を持っていないため、この方法は困難と判断されます。
②企業福祉の復活
かつての大企業が提供していた福利厚生制度の復活を目指すもの。しかし、現代の経済環境では持続可能性に疑問があります。
③ヨーロッパ流の福祉国家
年金、医療、介護、失業、生活苦などを政府が保障することで、生活の安心感を提供し、貧困を防ぐもの。日本に最適な方法として挙げられます。
日本が福祉国家になるべき理由は以下の通りです。
・生活の安心感
政府が年金、医療、介護、失業、生活苦などを保障することで、国民は生活における安心感を得ることができます。
・貧困者の減少
福祉国家になることで、貧困者の数を減らすことができ、格差是正につながります。
しかし、福祉国家にはいくつかのデメリットもあります。
・経済への影響
国民に多額の税金と社会保険料の拠出を求めるため、経済効率性が低下する可能性があります。
・政府の非効率性
政府の仕事が非効率になると、年金や医療などのサービスが低品質になる恐れがあります。
日本が福祉国家になるための具体策 以下に、著者が提案する具体的な格差是正策を紹介します。
①同一価値労働・同一賃金の徹底
正規労働者と非正規労働者の賃金差をなくし、同じ仕事をしているならば時間あたり賃金を同一にすること。
②最低賃金額のアップ
最低賃金額を引き上げることで、働きながらも貧困に苦しむ人々を減少させる。
③所得税率の累進度の強化
高額所得者への所得税率を高くし、その財源を貧困者の所得支援や社会保障制度の充実に用いる。
④消費税における軽減税制の強化
食料品や生活必需品に対する消費税率をさらに軽減し、低所得者の負担を減らす。
⑤企業内の賃金格差是正
管理職と平社員、特に社長と平社員の収入差を縮小することで、企業内の収入格差を是正。
⑥失業者の数を減らす政策
職業訓練や再就職支援を強化し、失業者の数を減らす。
⑦高齢者の雇用数を高める
定年延長や年金受給と並行した働き方を推進し、高齢者の雇用を増やす。
⑧政治と官僚の信頼回復
日本が福祉国家になるためには、政治家と官僚の信頼回復が不可欠です。特に現在の自民党政治は特権化しており、多くの国民からの信頼を失っています。税金や社会負担費は北欧並みに高まっているにも関わらず、福祉の質が見劣りする状況が続いています。この背景には、企業への厚遇や税金の中抜きが原因となっています。
資本主義社会における格差問題は、重要かつ複雑な課題であり、経済学はその解決に向けて常に進化し続ける必要があります。アダム・スミスからトマ・ピケティに至るまで、経済学者たちは様々なアプローチで格差問題に取り組んできました。
これらの議論や提言を総合し、持続可能な社会の実現に向けて、格差是正に取り組むことが不可欠です。経済学の役割は、単なる理論の構築にとどまらず、実践的な政策提案を通じて社会の変革を促進することにあります。著者の提言を実行することで、格差問題は解消するはずですが、まずは政治家と官僚の信頼回復が求められています。
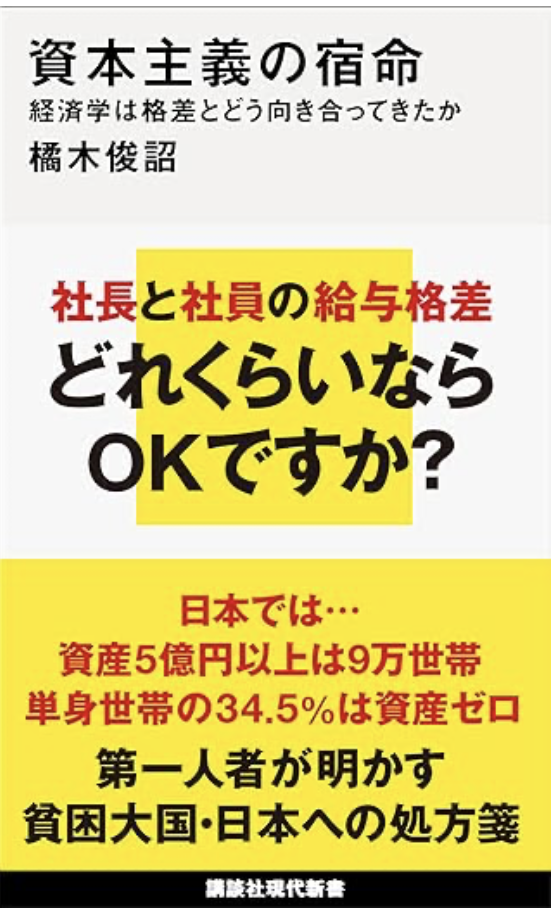



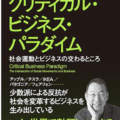
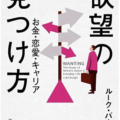
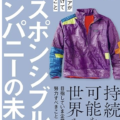



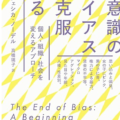





コメント