あいては人か 話が通じないときワニかもしれません
レーナ・スコーグホルム
サンマーク出版
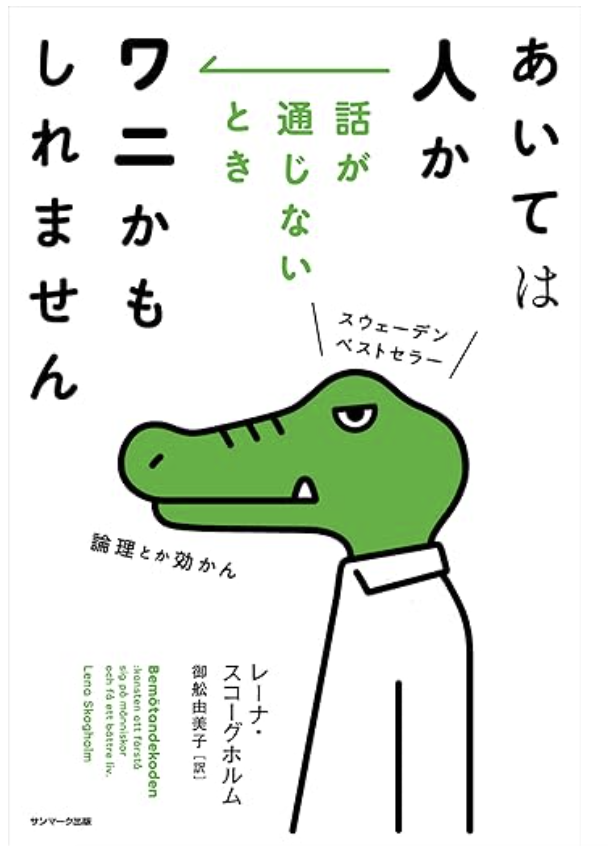
あいては人か 話が通じないときワニかもしれませんの要約
脳には「ヒト脳」「サル脳」「ワニ脳」の三層構造があります。ヒト脳は理性的な判断を、サル脳は感情を、ワニ脳は生存本能を司ります。ストレスが強まるとヒト脳から順に機能が低下し、最終的にワニ脳だけが働きます。効果的なコミュニケーションには、ストレスケアで脳全体を活用し、状況に応じて適切な対応をすることが重要です。
ワニ脳、サル脳、ヒト脳の三層構造を理解する!
自分という人間は、他者との交流のなかで創造され、命を吹き込まれるのだ。(レーナ・スコーグホルム)
私たちの日常生活において、コミュニケーションの行き詰まりは避けられない現実です。会話が通じない、理解し合えないと感じる場面に遭遇するたび、多くの人は相手を非難したり、自分の伝え方を責めたりしてしまいます。しかし、行動科学者のレーナ・スコーグホルムは、これらのコミュニケーションの問題の根源が、実は私たちの脳の構造にあると指摘しています。
著者の説によれば、人間の脳には「爬虫類脳(ワニ脳)」「哺乳類脳(サル脳)」「新皮質(ヒト脳)」という三層構造があると言います。ワニ脳が活性化すると、人は「闘争(フライト)・逃走ファイト・凍結(フリーズ)」という本能的な反応に支配されやすくなるのです。
円滑なコミュニケーションを実現するには、ワニ脳の暴走を抑え、三層の脳をバランスよく機能させることが求められます。 人間関係において最も重要な要素の一つである「信用」は、相手の視点に立つことから生まれます。相手を理解しようとする姿勢なしに、真の信頼関係を築くことはできません。このことは、脳科学の知見からも裏付けられています。
相手の立場に立つためには、まず三層構造を理解し、相手の脳がどの状態にあるかを見極めることが重要です。この見極めができれば、相手に適した言葉を選ぶことができます。
例えば、強いストレスを感じている相手は「ワニ脳」が優位になり、闘争・逃走・フリーズの反応を示すことがあります。このような状態の相手には、まずワニ脳が理解しやすい単純で明確な言葉で語りかけ、安全な場所にいることを伝えます。
次に「サル脳」に働きかけ、感情を受け止め、共感を示すことが大切です。サル脳は常に共感と理解を求めているため、「お気持ちよくわかります」「そうですね、確かにそうですね」といった共感の言葉や笑顔、傾聴が効果的です。このステップで焦らず、相手のペースに合わせることが重要です。
相手が落ち着いてきたら、徐々に「ヒト脳」に働きかけ、理性的な対話を進めることができます。ただし、その過程で相手が再び感情的になり、サル脳に戻ることがあります。このような場合は、すぐにサル脳レベルでの共感的なコミュニケーションに戻る必要があります。
相手の状態の変化を敏感に察知し、柔軟に対応することが、信頼関係を築く鍵となります。 信頼関係の構築には時間がかかりますが、相手の脳の状態を見極め、それに応じたコミュニケーションを心がけることで、信頼は着実に育まれます。
これは、ビジネスの場面でも同様です。顧客との関係、同僚との協働、部下の育成など、あらゆる場面で、相手の状態を理解し、適切なコミュニケーション方法を選択することが、信頼関係構築の基盤となるのです。
著者は、このような状態を防ぐためには、自己認識と感情コントロールが重要だと説いています。 では、実践的な対処法はどうすればよいのでしょうか?
まず大切なのは、自分が「ワニ化」している状態に気づくことです。ワニ化とは、感情の高ぶりや呼吸の乱れ、不快な記憶の想起などによって、本来の冷静な思考ができなくなる状態を指します。この兆候は人によって異なるため、自分なりのサインを知っておくことが重要です。
自分がワニ化していることに気づいたら、落ち着くための対策をとりましょう。たとえば、深呼吸をする、瞑想を取り入れる、一時的にその場を離れるなど、自分に合った方法を実践するのがおすすめです。こうした対処法を習慣化すれば、感情のコントロールがしやすくなります。
また、問題に直面して「絶対に解決できない」と思ったとしても、ひと晩しっかり眠ることで、意外と解決策が見えてくることがあります。十分な休息をとることで脳がリフレッシュされ、本来の冷静な思考を取り戻せるからです。
特に、マインドフルネスを実践すると、感情を安定させる効果が期待できます。深い呼吸を意識しながら今この瞬間に集中することで、ネガティブな感情に流されにくくなるでしょう。
一方で、相手がワニ化している場合は、感情的に反論せず、共感的な態度で接することが大切です。「お気持ちお察しします」といった言葉をかけると、相手の興奮を鎮め、冷静な対話へとつなげやすくなります。 このとき重要なのは、相手の感情を否定せず、まずは受け止めることです。相手が落ち着いてから、問題の解決に向けた建設的な対話を始めると、より良い結果につながると著者は指摘します。
ミラーニューロンの働きを理解することで、相手との関係を変えられる!
常に伝染を引き起こすミラーニューロンをとおして、自分のすべてを相手にさらけ出そう。長所も短所も含めて、だ。そうすれば、相手もまた長所と短所のある人間として、自然体でいられる。
著者はミラーニューロンの働きに注目し、私たちの態度や感情が他者に伝染することを指摘しています。望ましい対話を実現するには、まず自分自身が安定した心の状態を保つことが重要です。
ミラーニューロンの特性を理解することで、自分の態度が相手に与える影響を意識し、より良い対話が可能になります。 コミュニケーションでは、言葉の選び方が大切です。相手を否定したり批判したりすると、「ワニ化」を誘発する可能性があります。代わりに、相手の良い点を認め、建設的な提案をすることで、より良い対話が生まれます。
相手も自分も「ワニ化」する可能性があると理解し、互いを思いやる姿勢を持つことが、良いコミュニケーションの基盤となります。そのためには、継続的な実践と振り返りが必要です。自分がどのような状況で「ワニ化」しやすいのか、どのような対処法が有効かを知ることで、より効果的な対話が可能になります。 また、相手の反応を観察し、自分の言動が相手に与える影響を意識することも重要です。
ミラーニューロンを通じて自分をさらけ出すことで、相手も自然体でいられ、互いの理解が深まります。私たちは生身の人間であり、人生には良い時も悪い時もあります。頭ではなく心に語りかけることで、伝えたいことがしっかり伝わります。
いまの社会では論理のほうが優先されがちだが、じつは脳で重要な役割を演じているのは感情のほうだ。そのため、左右の脳をバランスよく使うには、論理的な話をする前に相手の言葉に耳を傾け、それを肯定することが大切だ。
左脳の論理的な言語と、右脳の感情豊かな言語をバランスよく使うことも大切です。現代社会では論理が優先されがちですが、感情も重要な役割を果たします。論理的な話をする前に相手の言葉に耳を傾け、肯定することが効果的です。
良い会話をするには、安定した心の状態を保ち、相手の話に耳を傾け、解決志向で建設的な提案を行うことが大切です。要点を明確にし、会話の終わりには良い感情が残るよう配慮することが求められます。
相手の不平や批判は前向きなフィードバックとして捉え、成長の機会とする姿勢が重要です。 私たちは誰もが影響力を持ち、期待は伝染します。相手の脳の構造に合わせて波長を調整すれば、信頼関係が生まれます。
また、自分自身を思いやることが大切だと著者は指摘します。内なる批評家を手放し、ありのままの自分を受け入れることで、心の安定が生まれます。「今この瞬間を意識する」ことで気持ちが穏やかになり、日常のストレスから解放されます。マインドフルネスを続けることで、心身の健康が向上します。
内なるストレスを解消するには、自分がリラックスできることを行い、短い休憩を取り、自己対話で励ますことが有効です。マインドフルネスで心身を整え、メンタルトレーニングで精神的な強さを養うことも大切です。 自分の気分が周囲に与える影響を意識し、まずは自分自身を大切にしましょう。決して諦めず、前向きな姿勢を持つことが、良い人間関係につながります。
本書の教えは、ビジネスだけでなく、家庭や友人関係にも応用できます。著者が提唱する「脳の三層構造」の理解と、それに基づくコミュニケーションを実践することで、豊かな人間関係を築けるようになります。











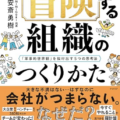






コメント