決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣
堀田秀吾
新潮社
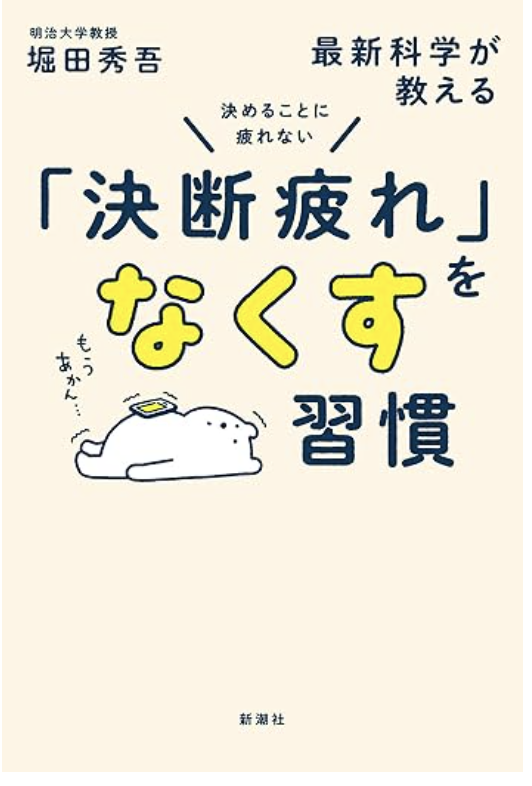
「決断疲れ」をなくす習慣(堀田秀吾)の要約
明治大学教授・堀田秀吾氏の『決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣』は、情報過多によって生じる決断疲れを、最新の科学的知見をもとに解消する方法を紹介しています。選択肢を絞る、習慣化する、尊敬する人を真似るといった実践が有効です。「完璧な決断なんて存在しない」と考え、行動を継続することが何より大切です。「自分で決めた」という意識が、人生を切り拓く力になるのです。
決断疲れとはなにか?
「自分で決めたのだ」という気持ちが、あなたの決断をより良いものへ変えてくれるのです。(堀田秀吾)
明治大学教授の堀田秀吾氏の決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣は、日常の意思決定に伴う「決断疲れ」を、最新の科学的知見に基づいて解消するための実用的な方法を提示する一冊です。 (堀田秀吾氏の関連記事)
本書では、「決断に時間をかけすぎるとかえって良い選択ができなくなる」「意識的に休憩を取ることで判断力を維持できる」といった科学的な知見が数多く紹介されています。こうした内容を通じて、日常の中でより良い選択をするための具体的なヒントが得られます。
たとえば、イギリス・ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアンおよびカリフォルニア大学サンディエゴ校のジョン・ラブゼッタの研究によると、人は1日に約3万5000回の決断を行っているとされています。 この中には、「いつもの通勤経路を選ぶ」「歯磨きの際に口を何回濯ぐか」といった、無意識に下される決断も数多く含まれています。
実際、こうした「習慣化された決断;は、全決断の約95%を占めているとも言われています。 逆に言えば、残りの約5%、すなわち約1750回は、意識的な決断であるということになります。仮に1日7時間の睡眠をとり、17時間起きているとすれば、1時間あたり約103回も私たちは意識的な選択を行っている計算になります。
このような背景のもと、コロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガーは、自身の研究において、「人は1日に70回ほど、意識的な決断をしている」と述べています。この決断を正しくしたり、その結果をポジティブに評価することが重要だと著者の堀田氏は指摘します。
「決断疲れ」とは、意思決定を担う脳の領域が過剰に働く、あるいは正常に機能しなくなることで引き起こされる現象です。 BBCニュースによると、現代人が1日に接する情報量は、中世後期の平均的な人が約1万2775日かけて得ていた情報量に匹敵するそうです。
日本でも、「現代人が1日に接する情報は、江戸時代の1年分、平安時代の一生分に相当する」と言われています。 当然のことながら、情報の量が増えれば、脳が処理すべき内容も増え、認知資源への負荷も高まります。
服従実験で有名な社会心理学者のスタンレー・ミルグラムは、過剰負荷環境における人の行動特徴を次の4つにまとめています。
①短時間処理
必要最低限の情報しか他者と共有しない(例:道を聞かれても簡潔に答える)
②情報の排除
重要でない情報を無視する(例:すれ違う人に無関心)
③責任回避
問題が起きても自分で対処しない(例:「上司が気づくだろう」と考える)
④他者の利用
自ら動かず、他人に任せる(例:レストランで注文を他人に任せる)
このように私たちは、膨大な情報の中から必要で都合の良いものだけを選び取り、それ以外を排除することで、無意識のうちに心身の消耗を抑えようとしています。この脳の働きを理解することは、より良い意思決定をするための第一歩となります。
また、マルチタスクを行うと、脳のリソースが分散され、注意力や判断力が低下してしまいます。たとえば、電話に集中しているときには「聞く」「話す」「理解する」といった作業にリソースが使われています。その状態で資料を作成しようとすれば、「文章を構成する」などの追加負荷がかかり、効率が落ちてしまうのです。
スタンフォード大学のアンソニー・ワグナーらの研究では、マルチタスクに慣れている学生を対象に、注意力や作業記憶に関する課題を実施し、シングルタスクとの比較が行われました。その結果、マルチタスク時には「注意の集中」や「不要な情報の排除」といった認知コントロールに関わる脳の活動が低下することが確認されました。
さらに、同じくスタンフォード大学のエヤル・オフィールは、「マルチタスク中の脳は、実際には2つのことを同時に行っているのではなく、超高速でタスクを切り替えているだけ」と指摘しています。つまり、脳は一方の作業を一時的に中断し、情報を整理したうえで、別の作業に移行しているのです。 このような切り替えは、結果的に時間を要し、脳への負担も大きくなります。
もちろん、マルチタスクが得意な人もいますが、苦手な人が無理をすると判断の質が著しく低下し、「決断疲れ」を引き起こしやすくなります。効率を求めるあまり、脳に過剰な負荷をかけるのは避けるべきでしょう。
人生をよくする決断の力
自分が選んだ決断を楽しんでください。小さな益を見つけてください。きっとその決断が、あなたの明日をより良いものにしてくれるはずです。
著者は、「決断疲れ」を軽減し、より良い選択をするための方法を紹介しています。今日はその中らいくつか取り上げてみます。
まず有効なのは、あえて短時間で決断するという方法です。選択に長時間をかければかけるほど、私たちの判断力は消耗していきます。「迷う時間」そのものが脳のリソースを奪うからです。たとえば、「昼食を何にするか」など日常的な選択については30秒以内に決めるというルールを設けると良いと言います。こうした小さな工夫でも、意思力の節約には効果的です。
次に、選択肢をあらかじめ絞っておくことも有効です。たとえば、「平日の服装は3パターンに固定する」「朝食は決まった2種類から選ぶ」といったシンプルな仕組みが、日々の判断負担を軽減してくれます。選ぶたびにゼロから考える必要がなくなり、より大事な決断にエネルギーを回せるようになります。スティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグはこのメソッドを取り入れ、服選びで自分を消耗させないようにしています。
日々の決断には、大きく分けて「重要なもの」「あまり重要でないもの」「その中間」の3段階があります。この分類を意識しておくだけでも、意思決定の優先順位を明確にすることができます。たとえば、仕事の方針やキャリア選択といった重大な決断には時間をかける一方で、「どのルートで帰宅するか」といった軽微な選択には即断で済ませる。
このように、判断へのリソース配分を戦略的にコントロールするのです。 また、決断の際のルールをあらかじめ決めておくことも有効です。たとえば、「直感がYesなら進む」「迷ったら挑戦する側を選ぶ」といった“自分なりの原則”を設けることで、判断が速くなり、後悔も少なくなります。ポリシーに従った選択には納得感が伴いやすく、結果的に自信を持てるようになるのです。
心理学では「イフゼンプランニング(If-Then Planning)」という概念があります。これは、「もし○○になったら××する」という行動計画をあらかじめ設定しておく方法です。たとえば、「会議が終わったらすぐにToDoを3つ書き出す」「雨が降ったらジムで運動する」といった具合に行動を明確化することで、実行の確率が高まり、判断に迷う時間も減らせます。
私は朝起きるとすぐに日記とブログを書くことにしていますが、この習慣によって、ビジネスがうまくいくようになりました。
さらに、尊敬する人を“真似る”ことも有効な手法です。ペンシルバニア大学のケイティ・メーアの研究では、運動習慣に関する調査において、「尊敬する人の行動を模倣したグループ」が、最も高い成果を出したと報告されています。
著者の堀田氏は、アメリカの大学院時代に、目標としていた先輩のスケジュールを完全にコピーしたそうです。朝食の時間から図書館の利用時間までを同じにし、判断に迷ったときには「先輩ならどうするか?」を基準に行動したと言います。その結果、学業への集中力が飛躍的に高まり、最年少で博士号を取得することができたのです。
人は、大きな目標に向かっていきなり進もうとすると、途中で徒労感に襲われ、なかなか行動に移せないことがあります。そんなときに効果的なのが、「ブログを3行だけ書く」「週に3回散歩をする」といった、小さく達成しやすい目標を設定することです。このように行動を細かく分ける手法は「サラミスライス法」と呼ばれ、本当に効果があります。
スタンフォード大学の心理学者、アルバート・バンデューラは、人間の行動が「他者の観察」や「社会的影響」を通じて学ばれるという社会的学習理論を提唱し、現代の心理学に大きな影響を与えました。 彼が特に注目を集めたのは、「自己効力感」という概念です。
これは、「自分にはできる」という感覚や信念のことを指し、目標達成や行動の継続に深く関係しています。バンデューラは、「小さな成功体験の積み重ねが自己効力感を高め、それが新たな挑戦へのモチベーションになる」と指摘しています。
たとえば、「今日は10分だけやってみよう」と自分に声をかけ、小さな一歩を踏み出すこと。それだけでも、思っている以上に大きな効果があります。「できた」という実感が心に残り、次の行動へのモチベーションを自然と高めてくれるのです。
このアプローチは、習慣化の基本であり、先延ばし癖のある方にも非常に効果的な実践法です。最初から完璧を目指すのではなく、小さな行動に集中することで、無理なく継続できるようになります。 実際、私がこのブログを書き始めた頃も、「今日は数行だけでも書こう」と自分に言い聞かせながら始めました。決してハードルを上げず、気軽に取り組むことを優先していたのです。その小さな達成感が少しずつ積み重なり、今では自然と毎日文章を書くことが習慣となりました。
重要なのは、最初の一歩を「軽く」することです。気負わずに始められる設計にすることで、継続への心理的な抵抗が減ります。そして、その一歩が自己効力感を生み、日々の行動に好循環を生み出してくれます。 継続が苦手だと感じている方こそ、「小さな一歩」の力を試してみてください。わずか10分からでも、確かな変化が始まります。
ストックホルム大学のペール・ローゼンタールとオーレ・カールブリングの研究では、先延ばしを防ぐための3つの行動要素が明らかにされています。
1つ目は、「すぐに得られる報酬を用意すること」です。たとえば、「課題が終わったらお気に入りの動画を1本見る」といったように、小さなご褒美を設定することが有効です。
2つ目は、「他の選択肢を減らすこと」。スマートフォンの通知をオフにしたり、作業環境をシンプルにしたりすることで、注意の分散を防げます。
3つ目は、「失敗への不安を軽減すること」です。完璧を目指しすぎず、「まずはやってみる」と自分に許可を出すことで、行動のハードルがぐっと下がります。 大切なのは、「昨日よりほんの少し前に進めた」と実感することです。たとえ完璧ではなくても、自分の意志で一歩を踏み出せたという事実が、次の決断の質を高めてくれるのです。
「完壁な決断なんて存在しないし、できない」と気づいたときから、少しずつ心が軽くなっていきました。人生には、すぐには正解がわからないことがたくさんあります。だからこそ、私たちができるのは、そのときの自分にとってベストだと思える選択をし、それを受け入れていくこと。そして、その選択がたとえ完壁でなかったとしても、それを糧に次のステップに進む力に変えていくことです。
学説やフレームワークといった方法論は、正しい決断を導くうえで確かに力強いサポートになります。優れた理論や手順を活用すれば、物事の全体像を捉えやすくなり、迷いがちな選択肢の中から、自分にとって最善の道を見出しやすくなるからです。
たとえば、「メリット・デメリットを比較する」「緊急度と重要度で判断する」「あるべき姿からバックキャスティングして選ぶ」などの手法は、決断の精度を高めてくれます。ビジネスや自己成長の場面では、こうした思考が成果に直結することも少なくありません。
しかし、どれだけ優れた方法論を身につけていても、最終的に選択を下すのは“自分自身”です。そしてその決断の質は、心の状態や価値観によって大きく左右されます。だからこそ、正しい決断には「考え方」だけでなく、「心のあり方」——つまりマインドセットが欠かせないのです。
迷いや不安があってもかまいません。大切なのは、自分の中に「何を信じて進むのか」という軸を持つことです。完璧を求めすぎず、そのときの自分が最善だと思える選択を、自分の意志で選び取っていく。そうした姿勢が、確かな決断力につながっていきます。 日々の小さな決断の中で、マインドセットは鍛えられていきます。
また、自分で決めたという感覚は、行動へのモチベーションや継続力にもつながります。自ら選んだ道だからこそ、その先にある成果に対しても納得感を持ちやすくなり、たとえ困難に直面しても、「自分の意思でここに立っている」という感覚が、強い心の支えになります。
正しい決断というのは、誰かに与えられるものではありません。「これが正解だよ」と提示されるものではなく、自分自身が「これを選びたい」と信じて、覚悟を持って選び取るものです。 そして本当に大切なのは、その選んだ道を、あとから「これでよかった」と思えるように、自分の手で正解に育てていくことです。
最初から完璧な選択ができる人なんて、どこにもいません。 迷うことがあっても大丈夫です。気持ちが揺れることも、人として自然なことです。そんな中でも、最後には自分の気持ちにしっかりと向き合い、「これが自分の選択だ」と納得できるようになることが大切です。 そうして、自分の意志で選び、自分の足で進んでいく。その積み重ねが、やがて人生そのものを、自分の力で切り拓く力へと変わっていきます。
堀田氏の著書らしく、本書も例にもれず、豊富な学説や理論、実際のケーススタディがバランスよく紹介されており、非常に学びの多い一冊でした。特に印象的だったのは、このブログでもたびたび取り上げてきた著者の言葉や思考が随所に登場していたことです。過去のブログ記事を振り返りながら読み進めることで、本書をより楽しめました。









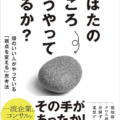

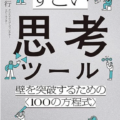
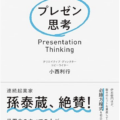
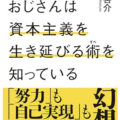
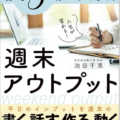



コメント