クリエイティブ・エシックスの時代
橋口幸生
宣伝会議
クリエイティブ・エシックスの時代(橋口幸生)の要約
電通の橋口幸生氏の『クリエイティブ・エシックスの時代』は、現代の広告・マーケティングに求められる倫理と創造性の融合を提唱しています。倫理を制約ではなく戦略資源と捉え、DEIの実践やグローバル事例を通じてその有効性を示します。NetflixやDoorDashなどの成功例に学びながら、日本の旧来型広告の構造課題にも鋭く切り込む一冊です。
クリエイティブ・エシックスが求められる理由
どんなに高いスキルを持っていてもクリエイティブ・エシックスが無かったら、今の時代に成功することは決してできないでしょう。それどころか、スタートラインに立つことすら難しいと思います。(橋口幸生)
昭和の広告会社でキャリアをスタートさせた私にとって、令和のマーケティング環境はまさに当時とは別世界になっています。かつては、明確なヒエラルキーの中で「何が正しいか」よりも「誰が言ったか」が重視され、上司やクライアントの期待に応えることが最優先とされていました。当時のクリエイティブは、ある種の職人的感性と経験の蓄積によって形づくられるものだったという印象があります。
しかし今、その「常識」は音を立てて崩れています。 多様性、平等性、透明性、持続可能性といった新しい倫理観が、マーケティングの土台そのものを塗り替えています。
現在では、感覚や経験に頼っただけのクリエイティブは通用しなくなっています。データと倫理、創造性と社会性をどう統合させるかが問われる時代に突入しています。そんな中で私が直面したのは、自分自身の思考様式のアップデートの必要性でした。
これは、私に限った話ではありません。かつての常識に依存してきた多くのマーケターやクリエイターが、同じような壁にぶつかっているのではないでしょうか。 変化を受け入れるには、まずそれを「直視」する必要があります。過去の価値観を否定するのではなく、再評価しながら、次の世代の基準に自分を接続し直す。そのプロセスこそが、今を生きるクリエイターに求められている態度だと感じています。
そうした気づきの中で出会ったのが、橋口幸生氏のクリエイティブ・エシックスの時代です。本書は、現代のビジネスパーソンが直面する倫理的課題とその実践事例を豊富に紹介し、倫理を単なる制約ではなく、戦略的資源として捉える新たな視座を提供しています。グローバル市場での競争優位を築くための道筋が、倫理というキーワードから見えてくるのです。
本書が提唱する「クリエイティブ・エシックス」は、従来の「炎上を避けるためのコンプライアンス」といった守りの姿勢では不十分であると指摘し、企業活動の中核に倫理的視点を組み込むという積極的なアプローチです。CSRやサステナビリティの枠を超えて、創造性そのものと倫理を融合させる概念として提示されています。倫理と創造性は相反するものではなく、むしろ相互に補完し合う関係にあると述べられています。
著者の橋口氏は、国内外で多数の広告賞を受賞する電通所属のクリエイティブ・ディレクター/コピーライターであり、DEIのコンシャルティング・チーム「BORDERLESS CREATIVE」の主催者の1人としても知られる存在です。
その実績に裏打ちされた本書の事例研究には、欧米のグローバルブランドを中心に、倫理と創造性がどのように共存し、成果を生んでいるのかが具体的に示されています。 本書の最大の特徴は、抽象的な理論に留まらず、企業活動や広告キャンペーンの成功例・失敗例を分析することで、読者の理解を深めようとしている点にあります。
多様な文化的背景を持つステークホルダーとどう関係を築き、どのように普遍的な倫理基準を現場に適用していくか?本書では、こうした現実的な課題にも踏み込んでおり、理想論に終始しない、地に足のついた洞察が随所に見られます。
その背景にあるキーワードのひとつが、DEIです。Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包摂性)の頭文字を取ったこの言葉は、近年グローバル企業を中心に急速に浸透しています。女性の社会進出やセクシュアル・ハラスメントの防止、採用・評価における無意識の差別をなくす取り組みなど、私たちの身近な場面でもDEIの考え方が実践され始めています。
DEIの意味するところを、単なる形式や表明にとどまらず、行動のレベルにまで落とし込んだ言葉があります。DEIの専門コンサルティング会社Bold Cultureのルビナ・マリクは、「DEIとは、ダンスパーティに誘うだけでなく、一緒に踊ろうと声をかけること」と表現しています。ただ席を用意するだけではなく、その人が安心して参加し、輝ける環境を整えること。それがDEIの本質だと言うのです。
DEIが注目される背景には、「世界を今より良い場所にする」という倫理的な目的があります。しかし、それだけではありません。多様性のある組織の方が、実際に高い創造性を発揮できるという実利的なメリットが、数多くの研究や事例から明らかになってきています。
異なる視点や経験を持つ人々がチームにいることで、新しい発想が生まれやすくなり、結果として競争力の源泉にもなっていくのです。 つまり、DEIの推進は「善いことをする」ためだけではなく、「強い組織をつくる」ための戦略だと捉えるべきです。そして、この視点こそが、クリエイティブ・エシックスの実装において欠かせないものになっています。
日本の広告の炎上理由は多様性の欠如?
日本の広告の炎上の多くは、企画・制作チームが男性中心で多様性に欠けていることが原因だと私は考えています。コピーライターやCMプランナーの能力は、先輩/後輩の上下関係の中でトレーニングされます。これは専門性を高めるのに有効な方法ですが、専門外への視野は狭くなりがちです。
特に、意思決定層において男性が大半を占めている現状は見過ごせません。これは単なる人員構成の問題にとどまらず、感覚や価値観の偏りを生み出しやすい構造的な課題です。私自身、昭和の広告会社で育った人間として、当時の制作現場がどれほど「同質性」に依存していたかを痛感しています。
実際、コピーライターやCMプランナーのスキルは、厳しい上下関係の中で磨かれます。OJTを通じた実地訓練は、確かに専門性の深化には有効でした。しかし、こうした縦型の人材育成では、異なる視点や異文化的な感性に触れる機会が極端に乏しい。
結果として、クライアントや生活者に対して独りよがり提案をしてしまいがちになるのです。 「男性視点のクリエイティブで勝負する」ことが、かつては許されていました。あるいは、賞を取ることが正義とされた時代もありました。
しかし今、そのロジックは通用しなくなっています。価値観の多様化、ジェンダー意識の変容、社会的公正への関心の高まり——広告を受け取る側のOSが変わったのに、作る側のOSが昭和のままであれば、炎上は必然です。
このような状況に対し、Netflixはグローバル企業として極めて高い次元で対応しています。同社が重要視しているのが「多様性(ダイバーシティ)」です。
ただし、それはスローガンや理念にとどまらず、実際の作品制作や組織運営にまで深く反映されています。公式サイトでも、「多様性と包括性が私たちの革新性と創造性を引き出す」と明言しており、異なる背景を持つ人々の視点を活かすことが、質の高いエンターテイメントにつながるという姿勢を明確にしています。
とはいえ、単に「多様性を大切にしています」と表明するだけでは不十分です。実際、多くの企業が理念としては掲げていても、現場レベルでは十分に実践できていないという課題も少なくありません。その点でNetflixは、言葉にとどまらず、取り組みの実態をデータで開示している点が特徴的です。
たとえば、同社の2023年の報告によると、2018〜2021年に制作されたNetflixオリジナル作品のうち、55%で女性が主演または助演を担当し、47%で有色人種の俳優が主要キャストに起用されています。
また、女性監督の割合も業界平均の12.7%に対し、Netflixでは26.9%。女性クリエイターの割合も、2018年の26.9%から2021年には38.1%へと増加しました。 さらに、シリーズ作品では、2021年に制作されたタイトルの54.7%で、有色人種の女性が主演または助演として登場しています。こうした数値は、多様性の推進が単なる方針ではなく、制作プロセス全体に浸透していることを示しています。
Netflixのこの取り組みは、クリエイティブ・エシックスの実践例としても非常に示唆に富んでいます。単なる倫理的配慮ではなく、視聴者との新しい接点を生み出す戦略として多様性を活用し、結果として、批評的評価と商業的成功の両面で成果を挙げているのです。
多様性は、もはや配慮すべきことではなく、競争力の源泉なのです。Netflixのアクションは、それを明確に証明しています。
クリエイティブ・エシックスの成功事例 Self Love Bouquet
「女性も男性も生きやすい世界をつくるための表現をうみだそう」と考えるのがクリエイティブ・エシックスです。そして、世界的にヒットした映画やドラマ、熱狂的に支持されるブランド、急成長している企業など、近年のビジネスの成功事例を見てみると、ほぼ例外なくクリエイティブ・エシックスの下でつくられています。
こうした変化のなかで、クリエイティブ・エシックスという考え方は、単なる防衛的な倫理対応ではなく、積極的に社会と共鳴しようとする創造的な試みとして注目を集めています。「誰もが生きやすい社会をつくるための表現とは何か?」という問いを出発点とする姿勢は、今や世界のスタンダードになりつつあります。
世界的にヒットしている映画やドラマ、熱狂的に支持されているブランド、急成長するスタートアップ企業の多くは、こうした倫理的視点をビジネス戦略の中核に組み込んでいます。
それはイメージ向上を目的とした表層的な「配慮」ではなく、企業と社会の持続的な関係構築を見据えた構造的な意思決定です。 コンプライアンスが「守りの姿勢」だとすれば、クリエイティブ・エシックスは「攻めの構想力」です。
リスクを避けるだけでなく、社会と共鳴する価値観を表現に組み込み、今まで届かなかった共感や支持を獲得する。この転換のためには、まず自らの中にあるアンコンシャス・バイアスに気づき、それを問い直す感性が求められます。
クリエイティブ・エシックスは、無意識の偏見によって狭められていた表現の可能性を、もう一度広げ直す思考の技術でもあります。倫理的視点を備えることは、炎上を防ぐだけでなく、より多様で共感的な表現を生み出すための土壌になるのです。
多様性を尊重することは、クリエイター自身の視野を広げ、結果としてマーケティングの可能性を拡張します。 その実践が実際のビジネス成果にどう結びつくのか。
その好例として注目すべきなのが、DoorDashの「Self Love Bouquet」キャンペーンです。 このキャンペーンは、バレンタインデーを「恋人のためのイベント」とする固定観念を覆し、「自分自身を愛する日」と再定義することで、大きな注目を集めました。
12本のバラの中に1本だけローズ型のセックス・トイが紛れているという設計は、女性のセクシュアリティをポジティブに捉え直す試みであり、巧みに設計されたメッセージ性を持っています。
このアプローチは、社会的なタブーへの挑戦であると同時に、DoorDashが持つ顧客理解の深さを示すものでもあります。アメリカでは成人女性の4人に1人がバレンタインを一人で過ごしており、同社の利用者の52%が女性というデータを踏まえ、パーソナルで共感性の高いキャンペーンが設計されました。
結果、キャンペーンは1700万ドルの売上を記録し、生花店への注文は前年比2倍の600万ドルを超える成果をあげました。この成功は、「倫理」と「収益」が矛盾しないどころか、むしろ両立することを証明しています。
クリエイティブ・エシックスの視点が、従来の広告文脈では見逃されてきた感情やニーズを掘り起こし、マーケティングの新たな地平を切り拓いたのです。
『クリエイティブ・エシックスの時代』は、こうした潮流を単なる現象としてではなく、構造変化として捉え直すための羅針盤です。表現と倫理、経済合理性と社会的共感——それらを対立させるのではなく、共にデザインする力が今まさに問われています。
時代の価値観が大きく転換しつつある今、自分自身の思考と表現の軸をどれだけ柔軟にアップデートできるか。それが、これからの時代におけるクリエイティブの競争力であり、社会的責任でもあるのです。
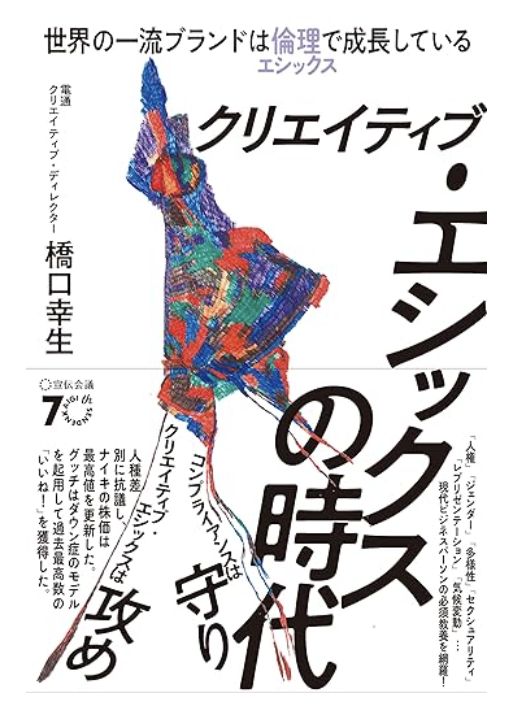




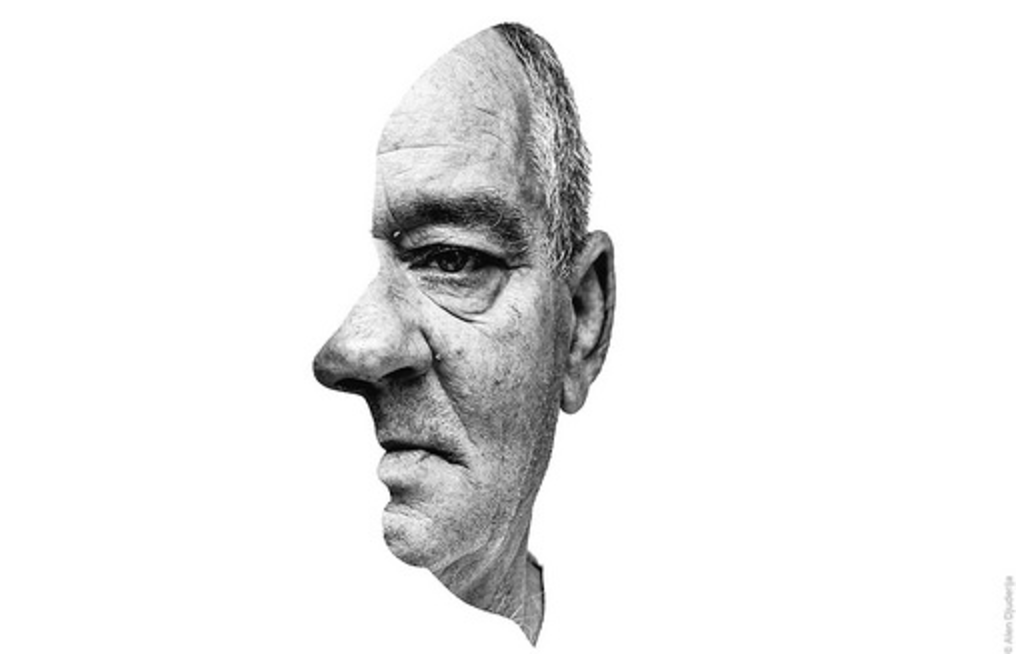
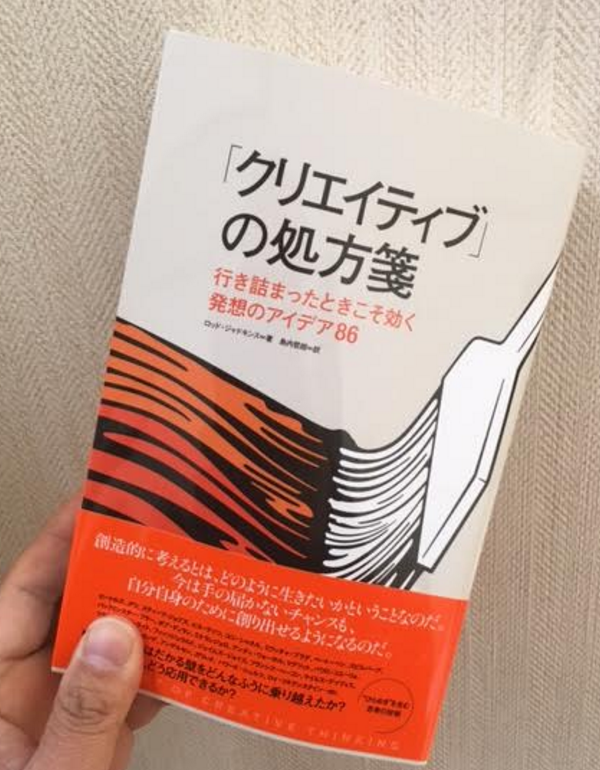





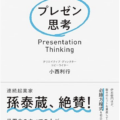



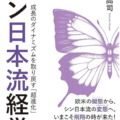


コメント