本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策
加谷珪一
幻冬舎
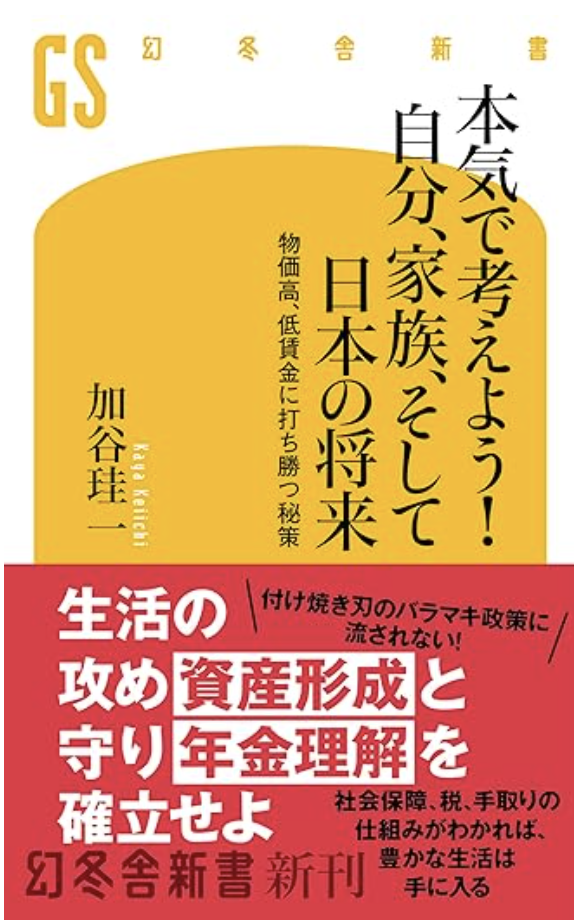
本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策 (加谷珪一)の要約
現代資本主義の行き詰まりと日本の経済困窮により、不安と疲弊が広がる中、加谷珪一氏の著書は、物価高・低賃金の背景を分析し、資産形成や制度理解を通じて主体的に生きる力を説いています。企業と労働者の在り方、税制の改善も提案し、現実を直視し行動する重要性を示しています。
物価高とインフレが日本にもたらすこと
面倒な判断を少しずつ回避していった結果、私たちの暮らしは坂道を転げ落ちるように悪くなっています。(加谷珪一)
現代資本主義の仕組みが行き詰まりを見せ始める中で、日本では経済的な困窮がその傾向に拍車をかけています。将来に対する不透明感が増し、不安やストレスが社会全体にじわじわと広がり、それが日常生活のさまざまな場面で心理的な疲弊として現れています。
私たちはいま、社会の土台が静かに揺らぎ、個人の感情にも確実に影を落としている状況にあります。 こうした空気を肌で感じ取っている人は少なくないでしょう。物価が上がる一方で賃金はほとんど変わらず、努力が生活の安定に結びつかないという感覚が、焦りや苛立ちを生んでいます。将来に明るい展望を持てず、「何を信じ、どう行動すればいいのか」が見えづらくなっているのです。
そんな中で、加谷珪一氏の本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策は、複雑化する社会において個人や家族がどう現実と向き合えばよいのかを明快に示してくれます。(加谷珪一氏の関連記事)
本書では、物価高と賃金停滞という「二重苦」の背景をデータに基づいて分析し、日本経済が抱える構造的な問題を冷静に掘り下げています。 さらに、ただ悲観的な見通しを述べるのではなく、資産形成という「攻め」の姿勢と、年金制度などの理解という「守り」の姿勢を両輪として提案し、不確実な時代における実践的な選択肢を読者に提示しています。
年金、税、賃金の仕組みを正しく理解することが、他人任せにしない生き方へとつながり、手取りを増やすための具体的なヒントになるという点も、本書の大きな特徴です。
今後、世界の人口は増加を続ける見通しである一方、食料やエネルギーなど供給面の制約が強まり、日本では日銀の金融緩和が長期化することで円安傾向が続く可能性も否定できません。これらを総合的に見れば、物価の上昇圧力は今後も続くと考えざるを得ないでしょう。
こうした背景を無視することなく、現実的な前提として認識することが求められます。 その結果として、社会の中間層が徐々に減りつつあり、高価格で高品質な商品か、極端に安く品質が劣る商品しか選択肢がなくなるという、二極化した市場構造が進行しています。
このような変化は、これまで当たり前に手に入っていた「ほどよい価格で、ほどほどの品質」の商品を市場から消し去る可能性すらあります。 いま、社会全体の中で感じられる停滞感や苛立ちは、こうした変化を無意識のうちに多くの人が察知していることの表れかもしれません。だからこそ、今の日本社会に必要なのは、「知らずに流されること」から脱し、確かな知識と自分の判断で動く力を持つことなのです。
競争力が低下した企業の経営陣と労働者のどちらを守るべきか?
ダメになった企業は即座に経営陣に退陣してもらい、新しい経営者を招聰すると同時に、労働者が路頭に迷わないよう、政府は公費を投入して失業した労働者の生活と再就職を徹底的に支援すべきです。今までの日本はこれとは正反対の政策ばかり繰り返してきたことで、企業の競争力が低下し、 結果的に労働者の賃金は下がる一方となっています。
企業に対しては、経営陣の責任を明確化し、経営が行き詰まった際には早急に刷新を図ると同時に、労働者の生活と再就職を政府が公費でしっかりと支えることが求められます。
これまでのように企業を過度に保護する政策を続けた結果、転職市場が育たず、労働者が企業に縛られ続けるという状況が生まれてきました。一方、ドイツなどの欧州諸国では、企業の解雇が比較的容易であるにもかかわらず、労働者が不安に陥ることはありません。
その背景には、再就職支援の制度が充実しており、労働者が次のステージへと移行しやすい社会構造があります。こうした制度設計の違いが、働く人々の心理的な安心感を生み出しているのです。
資本主義の基本は、企業が労働者に正当な報酬を支払い、労働環境を整えることで、生産性と利益の向上を図るという循環にあります。企業を甘やかす政策は、決して経済成長にも、賃上げにもつながらないのです。特に法人税に関しては、これまで何度も減税が実施され、現在では国際的にもかなり低い水準となっています。
しかし、その結果得られた利益の多くが内部留保として積み上げられ、設備投資に回されていない現実を見ると、法人減税が経済成長に寄与しているとは言いがたい状況です。 法人税は単なる財源確保の手段ではなく、企業の行動を誘導するツールとしても機能するべきです。
たとえば、設備投資や賃上げに消極的な企業には相応の税負担を求めるといった仕組みにすることで、企業活動を社会的に望ましい方向へと導くことが可能となります。
私たちは、もはや「いいとこ取り」が通用しない時代に生きています。国としての勢いが衰え始めている今だからこそ、現実を直視し、地に足のついた生き方が求められているのです。
すべてを成功者のように立ち回る必要はありませんが、その一部を学び取り、自分の生活に落とし込んでいくことで、十分な成果を得ることは可能です。
最後に、著者が紹介する「お金に振り回されないための7つの法則」を紹介し、この記事を締めくくります。
①他人が嫌がることはしない
②友達は限定する
③スケジュール調整の際には、まず自分の都合を伝える
④積極的に「ありがとう」と声をかける
⑤基本的にどんぶり勘定で構わない
⑥情報は出し惜しみしない
⑦必要なモノにお金を出し、欲しいモノには出さない
本書は、社会保障や税、賃金の仕組みを理解し、主体的に行動することで、不確実な時代を生き抜くための道筋を示してくれる一冊と言えます。私たちは現実から目を背けるのではなく、制度を知り、自分なりの判断軸を持つことが、これからの時代における生活の安定や成長につながるのです。








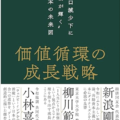






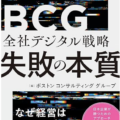
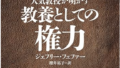

コメント