ラーメンと瞑想
宇野常寛
集英社
ラーメンと瞑想 (宇野常寛)の要約
宇野常寛氏の『ラーメンと瞑想』は、編集者T氏との6年間の「水曜日の朝活」を描いたエッセイ集です。ジョギング、瞑想、昼食を通じ、ラーメンを「獣の世界」、瞑想を「神の世界」と位置づけ、人間を相対化する営みを提示します。立ち食いそばやタヌキとの遭遇は、半径五百メートルの世界を見直す契機となり、情報過多の時代に「今ここ」に集中する重要性を教えてくれます。
「ラーメンと瞑想」──宇野常寛が語る、食と精神を往復する時間
僕が思う存分、食べたいものを食べたいだけ食べるのは一日のうち昼食の一回だけだということだ。そしてそうなると人間はこう考えるのだ。一日一回の、この「食べる」という行為の与える快楽を、可能な限り最大化したい、と。 (宇野常寛)
私は2007年に断酒をして以来、食との向き合い方が大きく変わりました。当時、ダイエットを兼ねて食事をほぼ晩御飯だけに絞り、以来その習慣を続けています。仕事柄、会食の機会は少なくありません。ステーキ屋やイタリアン、鮨屋に出向くことも多いのですが、酒を口にしないために、必然的に目の前の食事そのものに集中することになります。
以前は鮨や肉を前にしても、酒を飲むことを優先していました。しかし今では、周囲の人が酒を嗜む間に、全力で目の前にある料理に集中するようになったのです。酔いに頼らず、ただ料理と向き合う時間は、自分にとって特別な意味を持つようになりました。
私と同じように「食べる」という行為に強い意識を向けているのが、編集者であり評論家の宇野常寛氏です。宇野氏は一日一度の昼食に全力を注ぎ、その体験を軸に思索を深めています。ラーメンと瞑想は、まさに食と精神の往復を描いたエッセイ集です。
本書は宇野氏が6年間にわたり続けてきた「水曜日の朝活」を素材にし、長年の友人である編集者T氏との対話を通じて構成されています。 二人は早朝にジョギングを行い、その後瞑想に取り組み、そして昼食を共にする。その一連の流れが繰り返し描かれていきます。
食事の内容はラーメンだけに限られません。おしゃれなカフェ、とんかつ、立ち食いそば、回転寿司などを巡りながら、著者とT氏の二人は新しい体験に挑戦していきます。食事を挟んで交わされるのは、三島由紀夫や福田和夫、さらには自然をめぐる哲学的な対話です。趣味も性格も異なる40代後半の二人の男性が、食と瞑想を媒介に互いの思索を深めていく様子が記録されています。
対話の相手であるT氏は、編集歴二十年以上のベテランであると同時に、私生活では武道の修行や古典の翻訳を日々の鍛錬とする求道者でもあります。その存在が、宇野氏との往復運動をいっそう豊かなものにしています。
たとえば立ち食いそば屋は、ただ純粋にそばに集中できる場であり、会話や出会いを排除することで、事物そのものと向き合う純度の高い時間を生み出します。その孤独な集中は、瞑想の境地と確かに響き合っています。
また、コロナ禍の最中に著者は自宅近くでタヌキを目撃します。都会の住宅街に現れたその姿は、偶然の出来事として片づけられるものではありませんでした。その瞬間に著者は、まずは自分の家の周囲、半径五百メートルの世界に敏感でなければならないと考えるようになります。
足元のリアルを見落とす人間が、どれほど遠くへ旅をしても、そこで受け取れるのは記号化された「観光」の断片にすぎず、本質的な体験を持ち帰ることはできないのです。 情報が氾濫する現代において、私たちはしばしば身近なものに鈍感になっています。
スマートフォンを開けば世界中のニュースが流れ込んできますが、その一方で、自宅の周りに咲く花や、夕暮れに響く鳥の声には目も耳も向けなくなっています。著者がタヌキを見たときに感じたのは、まさに現代人が失いかけている「リアルへの感受性」でした。
結局のところ、大切なのは「今ここ」に集中することです。日常の中で自分の足で歩き、五感を研ぎ澄まし、小さな驚きや発見を積み重ねることこそが、人間にとっての本質的な営みなのです。
そして、こうした感覚はAIには決して持ち得ません。AIは膨大な情報を処理することはできても、タヌキと出会った驚きや、蕎麦をすする一瞬の香りに心を揺さぶられることはできません。人間だけが、自分の身体を通じて世界を感じ取り、そこから意味を紡ぎ出すことができるのです。
食べる瞑想によって変える人生
獣の世界に物語はなく
神の世界に幻想はなく
獣と神の世界には、過去も未来も演劇性もなく
宇野氏は、ラーメンを「獣の世界」、瞑想を「神の世界」と呼びます。獣の世界に身を置くとき、人は頭を空にし、欲望の赴くままに食を全身全霊で味わいます。その瞬間、ビジネスやお金、人間関係といった現実から解放され、社会的な仮面を脱ぎ捨てた存在へと変わるのです。
対照的に瞑想は、呼吸を整え、精神を研ぎ澄まし、静かに神へと近づく行為です。 一見すると相反するこの二つは、宇野氏とT氏にとって対立するものではありません。むしろ往復することで互いを補完し、人間をより自由にする営みとして機能しています。
彼らが導き出した核心は「食べることそのものが瞑想である」という発想です。ラーメンの湯気、そばの香り、寿揚げたてのとんかつ。これらに全身の感覚を委ねると、人は一瞬にして目の前の食事に没入します。この没入こそが「食べる瞑想」です。
本来、食事は欲望を刺激しやすく、惰性や過剰な消費へと流されがちですが、意識の向け方ひとつで修行の場へと変わります。咀嚼のリズムや食材の質感、味の移ろいに注意を向けることで、人は「今ここ」に立ち返り、自分自身と正面から向き合えるのです。
二人の食事スタイルもまた象徴的です。食べている間はほとんど会話をせず、黙々と箸を進めます。その姿はまさに二人同時の「食べる瞑想」にほかなりません。言葉がなくても、同じ時間と空間を共有しながら事物に没入することで、通常の対話では生まれない結びつきが育まれます。社会的な関係性を超えて、ただ存在を共にする――そこに彼らの実践の深みがあります。
食と瞑想を往還する習慣は、人間の存在を相対化し、現代を生き抜くための知恵として機能しています。ラーメンと瞑想――獣の世界と神の世界――を行き来することで、私たちは一時的に「人間」という枠組みから離脱することができます。著者にとってこの時間は、心身を整え、社会と距離をとりながら自分を見つめ直すための、かけがえのない実践となっているのです。
さらに宇野氏は、ラーメンの特異性を強調します。どれほど親しい相手と一緒でも、着丼の瞬間に人は他者から切り離され、ラーメンへと全身全霊を注ぎ込むことになります。ラーメンは人を孤独へ導き、食べる行為を純化させる装置のように作用するのです。一方、瞑想は「何者でもない」存在としての自分に立ち返る時間です。両者は異なる営みに見えながら、宇野氏とT氏の対話を通じて接続され、新しい瞑想のかたちを生み出しています。
今回、『ラーメンと瞑想』に触れ、宇野氏とT氏の記録を読みながら、食べる体験の広がりと深さをあらためて理解できました。食を単なる習慣や欲望の充足ではなく、瞑想と同じ強度をもつ営みとして捉える視点は、社会に縛られがちな私たちにとって、自分を解放し自由に立ち返るための大切な回路になると感じています。
人間が心から食を楽しめる時間には限りがあります。あと何年、一食一食を大切にできるかは誰にもわかりません。だからこそ、目の前の料理に全身で集中することが、日常を豊かにし、自分を取り戻すための確かな行為になるのだと思います。
2人が三浦半島を散策する場面は、前作「庭の話」を思い起こさせてくれました。食と瞑想を往復する実践が都市の喧騒を離れ、自然の中へと拡張していく様子を追うことで、本書が前作と地続きにつながっている感覚を得ることができました。
そして読み終えたときには、高田馬場にはほとんど足を運ばない私でさえ、とんかつの「とん太」に行ってみたいと思いました。同時に、無性にラーメンを食べたくなっていたのです。著者の食レポの力に圧倒され、彼の文章が食欲を直接刺激することを改めて実感しました。
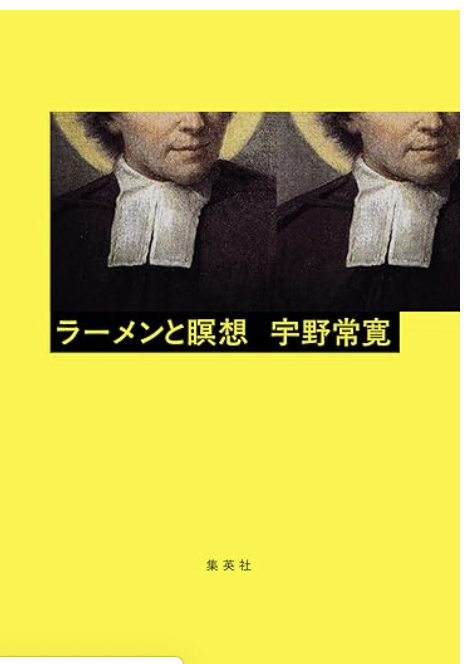





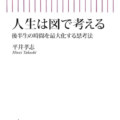



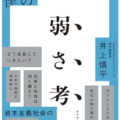





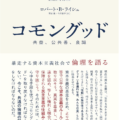


コメント