生きる言葉
俵万智
新潮社
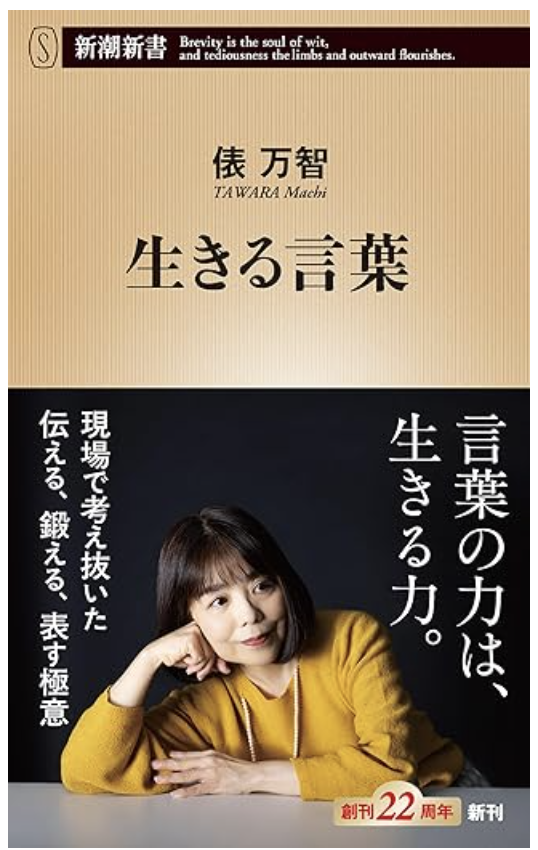
生きる言葉(俵万智)の要約
俵万智は本書で、恋愛や子育て、SNS、そしてAIといった日常に身近なテーマを切り口に、「言葉の力」を鮮やかに浮かび上がらせています。言葉を丁寧に磨くことで、誤解やすれ違いは減り、やりとりが驚くほどスムーズになります。人間関係の負担が軽くなれば、自分らしさを大切にしながら、変化の激しい時代をしなやかに生き抜くことができる。
言葉の力と危うさ──SNS時代に求められるコミュ力
「個人の言葉の背景を理解してもらえる環境」ではないところで、多くのコミュニケーションをしていかねばならないのが現代社会だ。家族や友人、恋人同士などはこの限りではないけれど、行動範囲がグンと広がり、ネットでのやり取りが日常になっている今、背景抜きの言葉をつかいこなす力は、非常に重要だ。それは、生きる力と言ってもいい。(俵万智)
言葉は光にも影にもなり、私たちの関係を形づけていきます。適切に使えば人を支え、誤れば人を深く傷つけます。とくにSNSでは、相手の背景を知らないままやり取りすることが当たり前になり、たった一言が非常識と受け取られて炎上に発展することもあります。
しかも、冷静に場を収めようとする人よりも、さらに火を大きくしようとする人が群がってしまいます。これは現代社会を映し出す象徴的な光景です。
違うルールで高速道路を走る車のように、前提が食い違えば衝突は避けられません。顔の見える関係の先に、顔の見えない関係が追加されたことで、言葉は力であると同時にリスクにもなったのです。Xなどでは言葉の暴力が際立ち、見知らぬ相手を傷つけることが常態化しています。この現実を直視しない限り、私たちは言葉の持つ危うさを克服できません。
俵万智氏の生きる言葉は、この現実に真正面から切り込みます。歌人であり母でもある著者は、子育てや日常の体験を通じて、言葉が人を結びつける力と、拒まれることで無力になる限界を描きます。子どもの率直な質問に答える場面や、SNSでの予期せぬ行き違い、野田秀樹の演劇の解釈、ラップと短歌の共通性、さらに『源氏物語』における和歌のやり取りから現代のAIまでを見渡しながら、言葉が持つ力強さと危うさを具体的に描き出しています。
「つかうほど増えてゆくもの かけるほど子が育つもの 答えは言葉」という一首には、日常の中で言葉がいかに人を育み、広がっていくかが端的に表されています。
当時高校生だった息子の影響で、著者はラップに関心を抱くようになります。リズムに合わせて言葉を操る感覚は、幼い頃から楽しんできた言葉遊びの自然な延長線上にありました。この「言葉遊び」があるからこそ、他者とのやり取りを面白がる姿勢が育ち、結果として自然にコミュニケーション力が磨かれていくのです。
遊びの中で積み重ねられた経験が、やがて社会で必要とされる表現力や対話力につながっていくことを示しています。
演劇と短歌の対比も鮮烈です。演劇は人と人との間に生まれるダイアローグによって物語が進み、登場人物の感情や関係性を少しずつ積み重ね、ひとつの主題を立ち上げていきます。
いっぽう短歌はモノローグであり、心の奥にあるたったひとつの思いを伝えるために、余分を削ぎ落としていく作業です。積み上げと削ぎ落としという異なるプロセスは、言葉の多様性を示すと同時に、人間の感情や経験がどのように形を変え、表現へと結実するのかを教えてくれます。自分がいま、積み重ねるスタイルを選ぶべきなのか、それとも削ぎ落とすスタイルを選ぶべきなのかを意識することで、相手との関係をより良くできる可能性が見えてきます。
本書には、絵本の読み聞かせを通じて子どもが成長する姿も描かれています。紹介されている絵本の一言一言が、私自身の子育ての記憶を鮮明に呼び起こしました。20年前、私は2人の子どもに同じ絵本を繰り返し読み聞かせました。正直、同じ本を何度もせがまれることに疲れることもありましたが、根気強く続けたことで2人は大人になった今も自然に本を読む習慣を持っています。あの時の小さな苦労は、確かな成果へとつながったのです。絵本を通じて親子がともに成長していく姿は、本書を通じて改めて印象に残りました。
遊びなんだから、いくらでも間違えていいと書いたが、これが仕事となると間違えられない。若者たち、社会に出るにあたって、いきなり「コミュ力」を求められて気の毒だなと思う。学校にいるあいだは、勉強さえしていれば大人は機嫌がよかったのに。「コミュ力」なんて教科は、なかった。もちろんそれは机の上の勉強や教科書を読んで身につくようなものではない。
著者はさらに「遊びであれば、いくら間違えても構わない」と述べています。しかし社会に出れば、間違いは仕事上の責任問題となり、許されなくなります。若者たちは突然「コミュ力」という新しい力を求められますが、それは学校教育の中で体系的に教えられてきたものではありませんでした。
学生時代は勉強していれば大人に認められたのに、社会に出た途端、知識だけでは通用せず「伝える力」「受け止める力」が必須になる。この断層への指摘は、教育と現実社会のギャップを鮮やかに突くものであり、多くの共感を呼びます。
私自身、大学で学生と接する際には常に「コミュ力」を意識しています。知識を一方的に伝えるのではなく、対話のなかで学生の思考を引き出し、互いに学び合える場をつくることを大切にしているのです。授業をインタラクティブに進めることで、学生が自分の言葉で考えを表現し、他者とのつながりを体感する瞬間に立ち会えます。その瞬間こそ教育者としての大きな喜びであり、教育の本質が息づく場面だと感じます。
知識の習得を超えて、社会に不可欠なコミュニケーションの基盤を少しずつ育んでいく。そのプロセスを目の当たりにするとき、教育の意味は「知を伝えること」だけでなく、「人と人を結ぶ力を育てること」にこそあるのだと実感します。
プロフェショナルの条件とは?
むっちゃ夢中とことん得意どこまでも努力できればプロフェッショナル。
俵万智の短歌「むっちゃ夢中 とことん得意 どこまでも 努力できれば プロフェッショナル」は、起業の成功条件を端的に言い表しています。
「むっちゃ夢中」であることは、起業家にとって原動力です。損得勘定や外部からの評価に左右されず、心から没頭できるテーマを持つことが、長期戦を生き抜くための燃料になります。情熱は一時的に高まることはあっても、持続させるには「夢中でいられる対象」を選ぶことが欠かせません。
「とことん得意」であることは、競争優位の源泉です。誰よりも強みを発揮できる分野を持ち、それを徹底的に磨くことで、市場の中で独自のポジションを確立できます。起業において「広く浅く」よりも「狭く深く」が武器になる局面は多く、その集中こそがブランド力を高めるのです。
「どこまでも努力できる」ことは、再現性のある成長を生み出します。起業は予測不能の連続であり、ハードシングスに直面することが常態です。そのなかで諦めずに試行錯誤を続ける力が、成功を引き寄せます。努力を積み重ねられるのは、夢中であり、得意だからこそ。3つが相互に作用することで、プロフェッショナルとしての姿が立ち上がってくるのです。
この短歌は、プロフェッショナルであることを「肩書き」や「実績」ではなく、「夢中」「得意」「努力」という3つの軸で定義しています。起業家にとっては、この3つをいかに掛け合わせるかが、事業を持続的に成長させるカギになります。夢中であり、得意であり、そして努力を惜しまない。
この3つを一首に収めてしまう著者のセンスには脱帽せざるを得ません。短い形式の中でエッセンスを凝縮する力が、まさに言葉のプロフェッショナルの証なのです。
なかでも「言葉が拒まれるとき」という章は非常に示唆的です。Xにおいて、いわゆるクソリプがなぜ発生するのかを俵氏は分析しています。前提や常識の食い違いから言葉の衝突が生まれ、互いの意図がすれ違う構造を理解することで、私たちはネット時代をより冷静に生きられるようになります。
この構造を知り、その背後にある本質を見抜く力を養うことが、炎上や摩擦を回避する知恵につながるのです。 言葉は共感を生み出す一方で、受け入れられなければ無力となり、関係を壊してしまいます。言葉の効力と無力を同時に抱える現実は、人間関係の複雑さを端的に示しています。
俵氏は、この時代をしなやかに生き抜くためには「日本語の足腰を鍛える」ことが欠かせないと説きます。言葉の基礎体力を磨くことこそが、誤解や衝突を防ぎ、ネットでも現実でも豊かな関係を築くための唯一の道だからです。
言葉がなければ、世界をうまく理解することはできません。 私たちは言葉を使って、考えを整理し、気持ちを伝え、人とつながっています。 だからこそ、言葉は生きていくために欠かせない、大切な力なのです。
短歌を詠むことは、言葉を通じて自分の人生を見つめ直し、内面と静かに向き合う行為なのかもしれません。 それこそが、「言葉の力」が果たす本質的な役割だと感じました。 私自身も、読書やブログを通して過去の経験を言語化し、もう一度自分自身を捉え直す時間を持っています。 表現のかたちは違っても、「言葉で自己と向き合う」という営みは、思考を深め、人生に静かな豊かさをもたらしてくれるように思います。
そして、私たちは日々、言葉にしくじりながら生きています。人生とは言葉の失敗の繰り返しです。言葉の裏に隠れた背景を想像できるかによって、人との関係も変わります。
人と話すとき、SNSに何かを書きこむとき。何を言うかと同じくらい、何を言わないかを考える。誰に向けての言葉なのかを意識する。発してしまう前に、一呼吸おいて確認したい。言葉が簡単に届けられる時代だから、なおさらである。
本書は、恋愛や子育て、SNS、AIといった身近なテーマを通じて、「言葉が持つ本当の力」に気づかせてくれます。 言葉の力を磨けば、誤解は減り、コミュニケーションもスムーズになります。 人間関係がラクになれば、自分らしさを大切にしながら、変化の時代をしなやかに生きていけるのです。 人生を前向きに整えるヒントが、きっとここに見つかります。
ここで紹介できたのは、ほんの一部にすぎません。 著者の言葉には、まだまだ心に残る気づきがたくさん詰まっています。 ぜひ本書を手に取り、そのひと言ひと言を、自分の人生に照らし合わせながら味わってみてください。







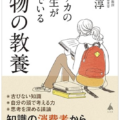
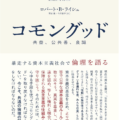
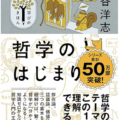
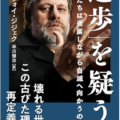






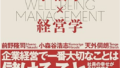
コメント