STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣
ニック・トレントン
ダイヤモンド社
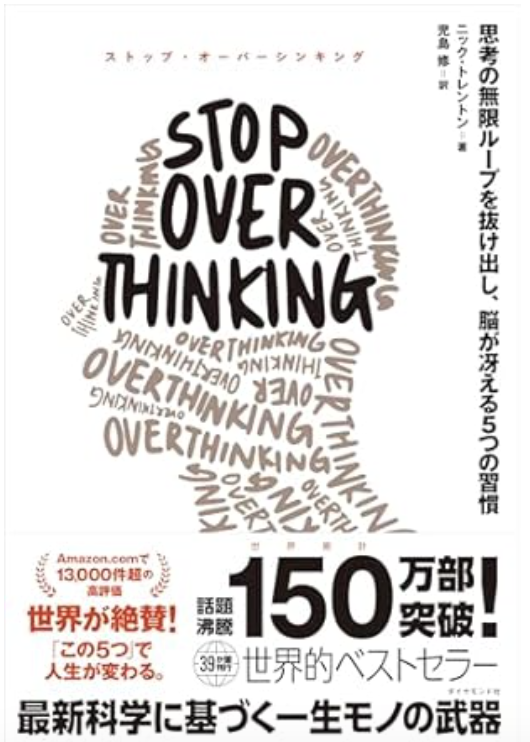
STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣(ニック・トレントン)の要約
現代人が陥りがちな「考えすぎ」の悪循環に対し、著述家のニック・トレントンは行動心理学の知見をもとに、思考と行動を整える5つの習慣を提示します。ストレスと時間の管理、心身のリセット、思考の見直し、態度の転換を通じて、不安に振り回されず「今」を生きる力を養う、実践的かつ再現性の高い一冊です。
考えすぎないための5つの習慣
現代社会には緊張感が張り詰め、刺激物や情報であふれている。そのため考えすぎてしまうと、脳のキャパに過度の負担がかかる。思考が制御不能に陥り、さらに考えすぎてしまうのだ。(ニック・トレントン)
私たちが生きる現代社会には、常に緊張感が漂っています。日常は情報と刺激に満ちあふれ、気づかぬうちに心も体も過負荷状態になっています。こうした環境において、私たちは往々にして「考えすぎる」という習慣に陥りがちです。
心理学者マット・キリングワースとダニエル・ギルバートが2010年に発表した論文「A wandering mind is an unhappy mind(さまよう心は不幸な心である)」では、脳は実際に起きたことだけでなく、まだ起きていないことについても頻繁に思いを巡らせていることが明らかにされています。特に、現実ではない事柄に時間を割けば割くほど、幸福感が損なわれやすくなるという指摘には私も深く共感しました。
また、「ニューロサイエンス・バイオビヘイビアラル・レビュー」に掲載されたビヨイドらの研究によれば、不安や抑うつを抱える人々は、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)が過活動である傾向が強いとされています。DMNとは、意識的な思考や外界とのやり取りがない時に働く脳のネットワークで、自己への内省や未来のシミュレーションを担っていますが、過剰に働くとネガティブな思考に支配されやすくなるのです。
私たちは、仕事、お金、家庭、人間関係、そして老いといった不安材料を常に抱えて生活しています。こうした不安には、ある程度の遺伝的な要素が関係していますが、実際にどれほど不安を感じるかは、日々の体験や環境に大きく左右されるのが現実です。
アメリカの著述家のニック・トレントンのSTOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣は、この「考えすぎ」という現代人特有の課題に対して、行動心理学の視点から具体的な解決策を提示してくれる一冊です。(ニック・トレントンの関連記事)
本書の核心は、過去の後悔と未来への不安に心がとらわれることで、私たちが「今、ここ」にある幸福を見失ってしまうという心のメカニズムを明らかにしている点にあります。
トレントンは、「遺伝的要因+ストレスの原因となる出来事=考えすぎ」というシンプルな方程式を用いて、思考過多の構造をわかりやすく解き明かします。 従来は精神疾患の原因として、脳内の化学物質のアンバランスが重視されてきましたが、近年ではストレスフルな環境や出来事こそが不安や抑うつを引き起こす主因であるという認識が広まりつつあります。
では、どうすれば考えすぎから抜け出せるのでしょうか。トレントンは「手放すこと」の重要性を説きます。過剰な思考はコントロールの幻想であり、むしろ自分を縛る鎖に変わってしまう。
だからこそ、自分を解放するには、「今ここ」に意識を向けるマインドセットが不可欠だというのです。 本書では、実践的かつ科学的根拠のある「5つの習慣」を通じて、考えすぎのループから抜け出すための方法を紹介しています。
1.ストレスを管理する(第1の習慣)
2.時間を管理する(第2の習慣)
3.心と体を瞬時に落ち着かせる(第3の習慣)
4.思考や行動を変える(第4の習慣)
5.「態度」を変える(第5の習慣)
不安を減らすためには、思考と態度を変えること
私たちが考えすぎに襲われるとき、行動自体を恐れているか、行動できないと感じているか、行動できることと行動すべきことを分けられないことが多い。 行動すると心が落ち着き、憶測やストレスフルな反すうから抜け出しやすい。
1つ目の習慣は「ストレスを管理する」ことです。ストレスは避けられないものである以上、それをどう受け止め、処理するかが鍵になります。ここでは、ストレスマネジメントの「4A 回避(Avoid)・変更(Alter)・受容(Accept)・適応(Adapt)」やジャーナリング、このブログでもお馴染みの感謝日記などが推奨されています。
ここで注目したいのは、近年、心理学や脳科学の分野で再評価されている「感謝」の力です。感謝とは、今あるものや状況に目を向け、それを肯定的に受け入れ、楽しむ心の姿勢です。これは、過去や未来に対する不安にとらわれがちな思考とは、まさに正反対のベクトルを持っています。
2016年にウォンらが行った研究では、「感謝の気持ちを文章にして書く」ことが、精神的な幸福感を高めることに寄与するという結果が示されています。つまり、ストレスに圧倒されそうなときこそ、自分の中にある「うまくいっていること」に光を当てることが、心の回復力を高める鍵になるのです。
冷静な人は、困難な状況にあっても、自らの力と再起力を信じて行動を選びます。ストレスのただ中で感謝を思い出すこと──これは決して現実逃避ではなく、自分を立て直すための“戦略的視点”なのです。
私自身も感謝日記を10年以上継続しており、不安を感じたときにそれを和らげる力があることを日々実感しています。どんなに小さなことでも「ありがたい」と感じる視点を持つことで、気持ちが前向きに切り替わる瞬間が確かにあるのです。
2つ目の習慣は「時間を管理する」です。時間の使い方が曖昧になると、不安が増大します。私たちはつい、目の前のタスクに追われるまま一日を終えてしまいがちですが、これは「本当に大切なこと」に意識を向ける余裕を奪ってしまいます。
トレントンは、ToDoリストの活用、価値観に基づいた優先順位の設定、目標の細分化、そしてアイゼンハワー・マトリクスやSMARTの法則といった具体的な手法を通じて、思考の焦点を明確にすることを勧めています。
アイゼンハワー・マトリクスは、タスクを「緊急性」と「重要性」の2軸で分類するフレームワークで、「緊急かつ重要」「緊急ではないが重要」「緊急だが重要ではない」「緊急でも重要でもない」の4つの領域に分けて優先順位を判断します。これにより、本質的に意味のある行動に時間を割く意識が養われ、行動の質が格段に上がります。
また、SMARTの法則とは、目標設定において押さえるべき5つの要素──具体的(Specific)・測定可能(Measurable)・達成可能(Attainable)・関連性(Relevant)・期限付き(Time-bound)──を指します。この原則に沿って目標を設定することで、漠然とした不安に対して「何を・いつまでに・どのように」取り組めば良いかが可視化され、行動へのハードルが下がっていきます。
時間管理は単に効率を高めるためのスキルではありません。自分の人生を主体的に選び取るための土台であり、不安やストレスを軽減する強力な武器なのです。
3つ目の習慣は、「心と体を瞬時に落ち着かせる」ことです。呼吸法やマインドフルネスなど、短時間で実践できるリラクゼーション法を取り入れることで、不安に飲み込まれそうなときも冷静さを取り戻すことができます。
心理学者エイドリアン・ウェルズは、「心配そのものを心配する=メタ心配」が不安障害を悪化させると指摘しています。その悪循環を断ち切るには、「今は心配しないだけ」と自分に言い聞かせ、心配を一時的に先送りする方法が有効です。シンプルですが、思考の暴走を防ぐ効果があります。
4つ目は、「思考や行動のパターンを変える」こと。認知行動療法のテクニックを活用し、現実そのものではなく、現実の捉え方を変えることが求められます。本書では、「認知の歪みの特定」や「セルフスクリプト(自己対話の書き換え)」が紹介されており、ネガティブな思考から抜け出す具体的なプロセスが提示されています。
まず、自分の中にある否定的な思考パターンや自動反応に気づくこと。そのうえで、思考の前提にある「本当にそうなのか?」という問いを投げかけ、根拠を確かめていきます。このプロセスは、自分自身の思考や行動を客観視するために欠かせないステップです。
こうした思考の修正ワークによって、思考を整理し、感情の渦から距離を取ることが可能になります。結果として、現実に対する解釈が変わり、不安や怒りといった感情にも振り回されにくくなるのです。
思考にラベルを貼り、古い記憶を擬人化したり、「外在化」したりして、自分がしていることが問題解決なのか、ただの反すうなのかを自問する習慣を身につけよう。
そして5つ目の習慣は、「態度を変える」ことです。自分自身や他者に対して抱く態度、そして物事への捉え方を変えることで、私たちはより柔軟に、穏やかに現実を受け入れられるようになります。
①コントロールできないことではなく、「コントロールできること」に集中する
②できないことではなく、「できること」に集中する
③持っていないことではなく、「持っているもの」に集中する
④過去や未来ではなく、「現在に集中する」
⑤欲しいものではなく、「必要なものに集中する」
本書の優れている点は、「考えすぎは良くない」という表面的な提言にとどまらず、著者の行動心理学の知見から明快に解説し、それらを日常の行動へと落とし込んでいるところにあります。「今を生きる」とは何かという本質的な問いに対して、思考と行動の両面からアプローチする実践的なヒントが随所に盛り込まれています。
不安や思考過多に振り回されないためには、何よりもまず「自分の思考の扱い方を変える」ことが求められます。本書では、それを今すぐ実践できるかたちで提示しており、外部の環境がどうであれ、内面の反応を整えることで現実の捉え方を変えていく方法が明示されています。
再現性の高い具体的な手法が詰まった一冊として、思考に疲れた現代人にとって実用的なナビゲーションとなるはずです。




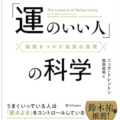


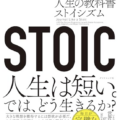
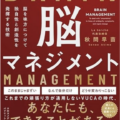
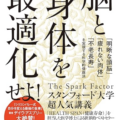

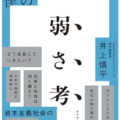
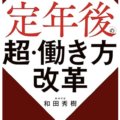

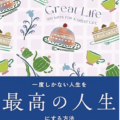
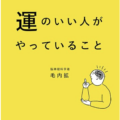


コメント