自分をよろこばせる習慣
田中克成
すばる舎
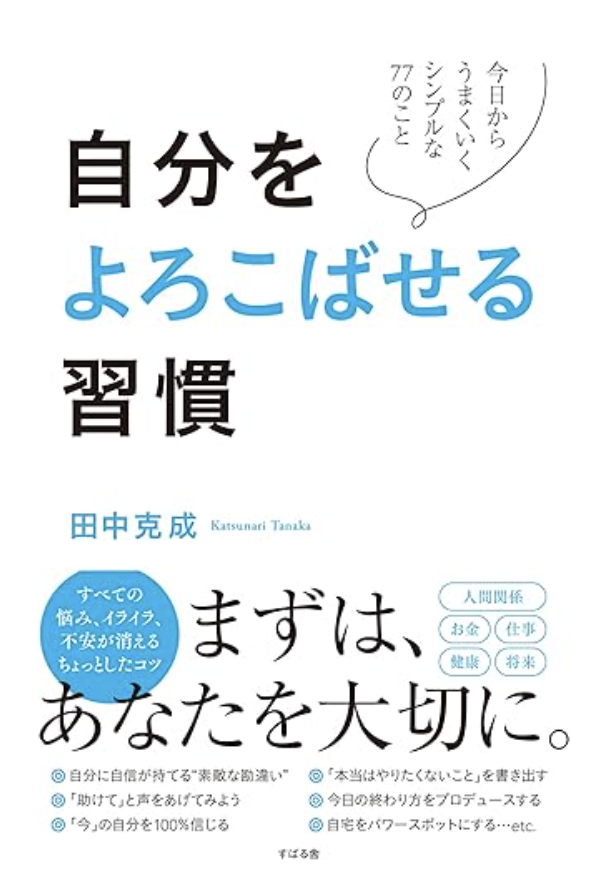
自分をよろこばせる習慣 (田中克成)の要約
田中克成の『自分をよろこばせる習慣』は、「幸せは他人から与えられるものではなく、自分の内側から生まれる悦びにある」と説く一冊です。小さな悦びを意識的に増やすことで、心の安定と幸福を育てていくことを提案します。著者は「嫌いな自分でいる時間を減らし、好きな自分でいられる時間を増やす」ことを行動の軸とし、父の「ビビったらGOだぞ」という言葉を胸に、自分で人生を動かす勇気を勧めます。
喜びではなく、「悦び」が重要な理由
人は、自分の「悦び」を探すだけで、幸せな人生を手に入れられます。(田中克成)
私たちはどうしたら幸せになれるのでしょうか? 田中克成氏の自分をよろこばせる習慣は、その問いに対して非常にシンプルで力強いメッセージを伝えてくれます。
本書が提案するのは、他人に喜ばされるのではなく、自分自身が内側から「悦び」を感じる時間を日常に増やすことです。外的な刺激ではなく、内発的な満足こそが、揺るぎない幸せを生むという考え方です。
「悦」という漢字はあまり使われることがありませんが、この言葉には深い意味があります。もともとは、神様に祈りを捧げたときに、邪気が払われて心がすっきりと晴れるような感情を表しているそうです。「ご満悦」「悦に入る」といった表現にもその名残があり、自己の内側から自然に湧いてくる感情を指します。
たとえば、誰かに贈り物を選んでいるときのワクワク感、好きなアーティストのライブ前の高揚感。こうした「自己完結型の幸福」が、まさに悦びと呼ばれるものです。
重要なのは、「継続が難しい習慣」や「長い努力」ではありません。日常の中に小さな悦びを見つけ、その時間を意識的に増やすこと。そして、自分でコントロールできる感情や行動にフォーカスすることです。
本書では、「嫌いな自分でいる時間を減らし、好きな自分でいられる時間を増やす」というシンプルな行動指針が、繰り返し強調されています。 本書では、月に一度のプチ旅行や、誰かのために本を読むことなど、日常に取り入れやすい習慣も紹介されています。
私自身も日々、仕事の中で「悦ぶ」という感覚を意識しています。出張が多い生活ですが、その前後には旅先のパワースポットに立ち寄ったり、美味しい食事を楽しんだりすることで、内側からの満足感を大切にしています。こうして自分の悦びに素直でいることが、結果的に仕事にも良い影響を与えてくれるのです。
この書評ブログも、自分自身の成長のためであると同時に、私がコンサルティングをしている経営者たちの課題解決のヒントを見つけるために書き続けています。彼らのグロースを支援することが私の仕事であり、本を通じて得た知見を彼らに伝え、喜ばれ、感謝されるという循環が、私自身の悦びとなってこのブログの継続にもつながっています。
読書については、相手の悩みを想定して本を選び、必要な情報を拾い読みし、要点を届けるという「わらしべ商人の読書術」が紹介されています。これにより、読書は単なるインプットではなく、悦びの循環を生む実践的な行動に変わるのです。
また、自分を悦ばせることができる人は、他人の悦びも大切にできる人だと本書では語られています。恋愛でもビジネスでも、成功する人の多くは、相手の悦びを想像し、それを提供できる人たちなのです。
自分のコントロールできることだけに集中する!
ビビったらGOだぞ。
また、本書の土台には、著者の父親の実体験が大きく影響しています。かつてプロ野球選手になるチャンスを何度も得ながらも、決断を先延ばしにし続けた結果、最後にはその道を断たれてしまったという経験です。後に振り返り、「プロに行って結果を出せなかったら……」という不安に打ち勝てず、挑戦を諦めたことを深く後悔したそうです。
そんな父の思いを受け、田中氏は「ビビったらGOだぞ。後悔だけはするなよ」という言葉を胸に生きてきました。 そこから生まれたのが、「プロ精神八ヶ条」です。
一条:自分の進む道を決め、具体的な夢、目標を持て。
二条:夢、目標に向かって毎日やるべきことを決めろ。
三条:今日やるべきことを今日やれ。そして、何が何でも継続しろ。
四条:毎日の努力は誰よりも集中して短時間で終えろ。
五条:補欠思考、目標の妨げになる環境を自らの意思で断て。
六条:常に上のステージでプレーしていると思え。
七条:体調管理を徹底しろ。
八条:全ての人や起こる事に感謝を忘れるな。
これらの言葉には、人生の主導権を他人に渡さず、自分で自分を動かしていくという覚悟が込められています。行動の決断に迷ったとき、「ビビったらGO」と心の中で呟いてみるだけで、勇気が湧いてきます。
あなたの人生は、あなた自身のものです。他人や環境に期待していても、幸せは偶然にしか訪れません。「運が良かった」「運が悪かった」「助けてもらえた」「助けてもらえなかった」といった〈たまたま〉に振り回される人生では、この先も不安を抱えながら過ごすことになります。
だからこそ大切なのは、コントロールできることをコントロールすること。そして、コントロールできないことを無理に変えようとしないこと。たったそれだけのことで、人生の安定感は大きく変わります。もう一度、声を大にして言いたいのは、「コントロールできることに集中し、できないことは手放す」という、当たり前のようで難しいこの原則こそが、幸せへの近道なのです。
私たちは、とかく自分ではどうにもできない周囲の出来事に一喜一憂しがちです。期待し、すがり、失望して、いつの間にか自分の人生のハンドルを手放してしまいます。そうならないためにも、大切なのは「習慣を続けること」ではなく、「自分の悦びを探し続けること」なのだと、本書は繰り返し語っています。
私も毎朝、神棚に向かって手を合わせています。未来を祝う「予祝のビジョン日記」と「感謝日記」を書くことも、すっかり日課となりました。この習慣によって、心が整い、気持ちよく一日をスタートできるようになったのです。
多くの成功者たちもまた、運動や瞑想など、自分自身が悦べる「悦る習慣」から一日を始めているといいます。大事なのは、その習慣がひとりでも悦べるものであること。誰かに認められなくても、自分の心が満たされる時間を持つことが、充実した人生をつくる基盤になるのです。
『自分をよろこばせる習慣』は、自分を悦ばせることが、結果として周囲を悦ばせ、幸せな循環を生み出すという普遍的な原理を教えてくれます。私たち一人ひとりが、自分の「悦び」にもっと素直になれたとき、人生はもっと自由に、もっと楽しく、そしてもっと深く味わえるものになるのかもしれません。





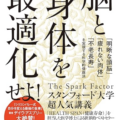
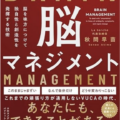


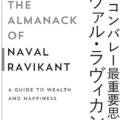
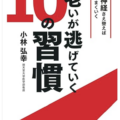
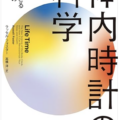




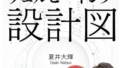
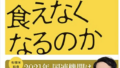
コメント