満足できない脳: 私たちが「もっと」を求める本当の理由
マイケル・イースター
東洋経済新報社
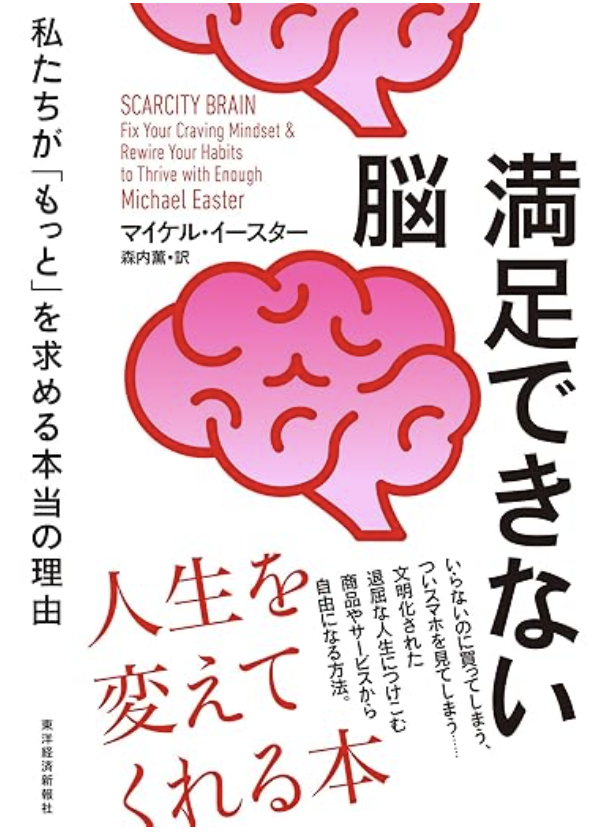
満足できない脳: 私たちが「もっと」を求める本当の理由 (マイケル・イースター)の要約
マイケル・イースターの『満足できない脳』は、「もっと欲しい」と感じる脳のクセを綿密な取材から解き明かす一冊です。現代社会は欠乏ループに満ちており、私たちは無意識に行動を操られています。過食やモノの過剰所有もその一例で、脳は刺激に反応し続ける仕組みにハマっているのです。自分の行動を可視化し、「足りている」と思える選択を重ねることで、満足と幸福の感覚を取り戻すことができます。
脳が満足できない!欠乏ループとは何か?
ギャンブルや過食、過剰な買い物や過剰な視聴、暴飲など、私たちが矢継ぎ早に繰り返してしまう行動は、「欠乏ループ」によって引き起こされている。このループは3つの部分でできている。機会→予測不可能な報酬→迅速な再現性(マイケル・イースター)
私たちは今、これまで人類が渇望してきたものを、過去に例を見ないほど容易に手に入れる時代を生きています。食料、物資、情報、娯楽、社会的つながり──すべてがスマートフォン一つで完結する世界です。クリックひとつで翌日には商品が届き、必要な知識もSNSや検索エンジンで即座に得られる。ある意味で、現代は“究極の充足”が可能になった時代とも言えます。
それにもかかわらず、どこか満たされない。便利になればなるほど、なぜか心が落ち着かない。気づけば私たちは、スマホを開いてはSNSを確認し、動画を流し見し、ネットショップを徘徊している──理由もなく、反射的に。そして、その背後には一つの共通した感覚があります。「まだ足りない」という思いです。
マイケル・イースターは、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家であり、健康、行動科学、進化心理学をテーマにした著作で知られています。
その彼が書いた満足できない脳: 私たちが「もっと」を求める本当の理由(Scarcity Brain)は、まさにこの「飽くなき欲望」の正体に鋭く切り込む一冊です。本書が提示するのは、私たちの脳が進化の過程で形成した欠乏志向が、現代のテクノロジーと結びついたとき、どのような影響を及ぼすのかという問題です。
食料も情報も余るほどにある時代に、なぜ脳は常に「不足」を探し続けてしまうのか──その疑問に対する、科学的かつ実践的な答えが本書には詰まっています。 イースターが繰り返し説くのが「スカシティ・ループ(欠乏ループ)」という概念です。
これは、「即時性」「予測不能性」「反復性」の3要素が組み合わさることで、人間の脳が極めて反応しやすくなり、同じ行動を無意識に繰り返してしまうというものです。スロットマシン、SNSの通知、タイムセール、動画の自動再生──これらはすべて、私たちの注意と時間を“無限ループ”に引き込む設計になっています。
たとえば、SNSで「いいね」やコメントが届くかどうかは予測不能であり、しかもすぐ確認でき、何度でも繰り返すことができます。この構造こそが、脳の報酬系を過剰に刺激し、結果として依存的な行動パターンを生み出すのです。短期的な快楽を得る一方で、満足感は持続せず、むしろ“もっと欲しい”という渇望だけが強化されていきます。
こうしたメカニズムは、ECアプリや広告にも応用されています。中国のECアプリテムはその象徴的存在です。Amazonの利便性、TikTokのアルゴリズム的魅力、スロットマシンの偶発性──これらを組み合わせたような体験設計が特徴で、ユーザーは選んでいるつもりで、実際にはAIに導かれるまま無限のオファーとディールを提示され続けます。
『ニューヨーク・マガジン』は、テムを「AI店員との会話の中で追い詰められていくアプリ」と表現しました。AIは特別オファー、限定セール、期間限定のプレゼントといったプロモーションを次々に提示し、ユーザーの判断を鈍らせていきます。このような設計は、ユーザーのニーズではなく、脳の反応を基軸に構築されたものです。
さらに、こうした欠乏ループは広告の世界にも浸透しています。『アドウィーク』誌では、ギャンブル的要素を取り入れた広告が売上に直結していると報告されています。たとえば「ルーレット形式」で割引額が決まる仕掛けなど、ユーザーの期待と偶発性を利用した演出が有効とされています。
このように、現代のテクノロジーやマーケティングの多くは、「選択の自由」のように見える枠組みの中で、実際には脳の快楽回路に対して設計された“選ばされる体験”を提供しています。そして、それに気づかないまま私たちは、時間、注意、エネルギー、そして本来の判断力を少しずつ手放してしまっているのです。
依存症も欠乏ループが原因?
より多くを求める渇きがすぐに癒されない場合、自分には何が欠けているのかという疑念が私たちの心を苛む。
依存症とは、たとえ悪い結果が見えていても、それでもなお報酬を求めて同じ行動を繰り返してしまう状態のことを指します。この定義をベースに考えると、初期の人類もまた、ある意味で依存症的な行動をとっていたのではないかと著者は指摘します。
命の危険を冒しながら狩猟を行い、未知の土地を切り開き、飢えや寒さと戦ってきた。その背景には、「より多くを得ようとする脳の性質」があったのです。
私たちの脳は、報酬にとても敏感で、とくにその「予測できなさ」に強く反応します。ウォータールー大学の研究によると、薬物による予測不能な報酬が人の判断を鈍らせ、ときには死すらも恐れないような行動を引き起こすことがあるといいます。
このメカニズムは、ギャンブル、酒やドラッグのような依存症だけでなく、食べ物や買い物、SNSや情報の過剰摂取にもまったく同じように当てはまります。 私たちは「今日はたくさん食べよう」と意図しているわけではないのに、つい大量の食品を手に取り、食べてしまう。これは意志の弱さではなく、私たちの脳が仕掛けられた刺激に反応している結果なのです。
甘さ、脂肪、パリパリとした食感、洗練されたパッケージ──それらはすべて、脳の快楽回路を刺激するように設計されています。かつては「食べられるときに食べておく」ことが生存のために重要でしたが、現代ではその本能が「足るを知る力」を超えてしまい、体や心に余分な負荷をかけています。
私自身、著者のマイケル・イースターと同じく、アルコール依存症からの回復を経験しています。その過程で学んだのは、「何かを足す」ことで解決しようとするのではなく、「静けさと向き合う」ことの大切さでした。読書やアウトプット、自然の中を歩くこと、瞑想、信頼できる人との会話──そうした時間の中で、自分自身を少しずつ取り戻すことができたのです。
依存とは、もともとは役に立っていた行動が、ある時点から自分を支配するループへと変化してしまうものだと、身をもって実感しました。 そして、この構造はモノへの執着にもあらわれます。
テキサス大学の人類学者たちは、人間が物質的な財を集めるように進化してきた理由を3つ挙げています。ひとつ目は、生存のためです。かつては道具や衣類、保存食などを持っていれば、安全に暮らし、他者との交換にも役立ちました。
2つ目は、モノが社会的なステータスを示す手段であるという点です。どのようなモノを持っているかで、周囲の評価や認知が変わり、自分の立場を示すことができました。
そして3つ目は、所属感です。ブランドのロゴやスタイルを共有することで、自分と似た価値観を持つ仲間とのつながりを感じることができます。
この「ブランドの部族主義」とも言われる現象は、ホールフーズやパタゴニア、グープなどを見ればよくわかります。その商品を手に入れることは、単なる消費ではなく、ライフスタイルや社会的な姿勢、そして仲間意識の表明でもあるのです。 しかし、こうした欲求が行きすぎると、私たちは自分の手にしたものに満足できなくなっていきます。
UCLAの研究者は、人間には「所有の限界を調節する機能」が備わっていないと指摘しています。食べ物には満腹感がありますが、モノや情報にはそれがありません。どれだけ手に入れても「もう十分」と感じられないのです。だからこそ、次々と新しいモノを求め、古いモノを手放せなくなってしまう。 その結果、創造性や集中力が落ち、思考のクリアさが失われていきます。本質的な問題解決力までもが蝕まれてしまうのです。
だからこそ、私たちは「足す」よりも「引く」という選択肢を持たなければなりません。目の前の問題を何かで埋めようとするのではなく、「本当にそれは必要か?」と立ち止まって問い直すことが大切です。
イースターが提案する「モノではなく装備」という視点は、その問いかけに大きなヒントをくれます。モノは欲望や感情を満たすための道具である一方、装備とは目的を達成するための手段です。この違いを理解し、「それは何のために必要なのか?」と自問するだけで、私たちの消費はもっと健やかで意味のあるものになります。
クリックする前に、買い物カゴに入れる前に、そっと一呼吸置いてみる。その瞬間が、欠乏ループから自由になるための第一歩になるのだと思います。
引き算思考で欠乏ループから脱却する!
現代においては、未知の世界に足を踏み入れることで、私たちを欠乏ループから押し出してくれる第二、第三の力を頼みにでき、結果的に欠乏ループから抜け出すことが可能になる。
インターネットの登場は、私たちの脳に3つの大きな変化をもたらしました。
①集中力の低下
SNS、通知、動画の波にさらされ、私たちは平均19秒ごとにタスクを切り替えていると言われています。
②記憶の外部化
情報をすぐに検索できる便利さの裏で、知識が断片化し、理解の深度が浅くなるリスクが指摘されています。
③社会的交流の変質
ネット上でのコミュニケーションが人間関係の質を変え、若年層の社会不安の増加に拍車をかけています。
こうした現代的課題に対し、イースターは「未知に身を置くこと」の意義を説いています。自然の中での活動や、新しい場所への探検は、予測不能な報酬をポジティブな文脈に再構築する手段です。アルゴリズムに導かれる快楽ではなく、自らの感性で得る発見は、深い満足とつながりをもたらします。 欠乏ループの構造を理解すれば、それを応用することも可能になります。
ビジネスパーソンにとっても、これは職場だけでなくプライベートにおける習慣設計にも活かせます。たとえば、運動や読書、趣味への取り組みにおいて、定期的なルーティンだけでなく、予測できない小さなご褒美や気づきの瞬間を組み込むことで、行動を継続しやすくなります。
報酬があることそのものではなく、それがいつ、どのように現れるかという“偶発性”が、私たちのやる気や集中力を高めてくれるのです。プライベートの充実こそが、仕事のパフォーマンスにもつながっていくことを忘れてはなりません。
結局のところ、私たちが求めているのは「刺激」ではなく「意味」なのです。真の幸福とは、行き先の見えない道を歩むプロセスの中にあります。容易に手に入る報酬の繰り返しではなく、困難に立ち向かい、自分を知り、他者とつながりながら、少しずつ進んでいくこと。
それこそが、現代を生きる私たちが見失いかけていた本質なのではないでしょうか。 しかし、立ち止まること、気づくこと、手放すことは、決して後退ではなく、むしろ未来に向けた選択なのだと気づいたのです。どれだけ多くを手に入れるかではなく、「これでいい」と思える瞬間をいかに育てていくか。
何を加えるかではなく、何を引き算できるかという思考こそが、今の私たちに必要な転換点です。テクノロジーと欲望が結託するこの時代において、私たちに求められているのは、“選ばされる”のではなく、“自ら選ぶ”という意識です。その一歩を踏み出すことで、私たちはようやく本来の自由を取り戻すことができるのかもしれません。





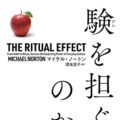






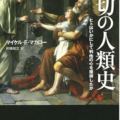





コメント