ひと月百冊読み、三百枚書く私の方法
福田和也
PHP研究所
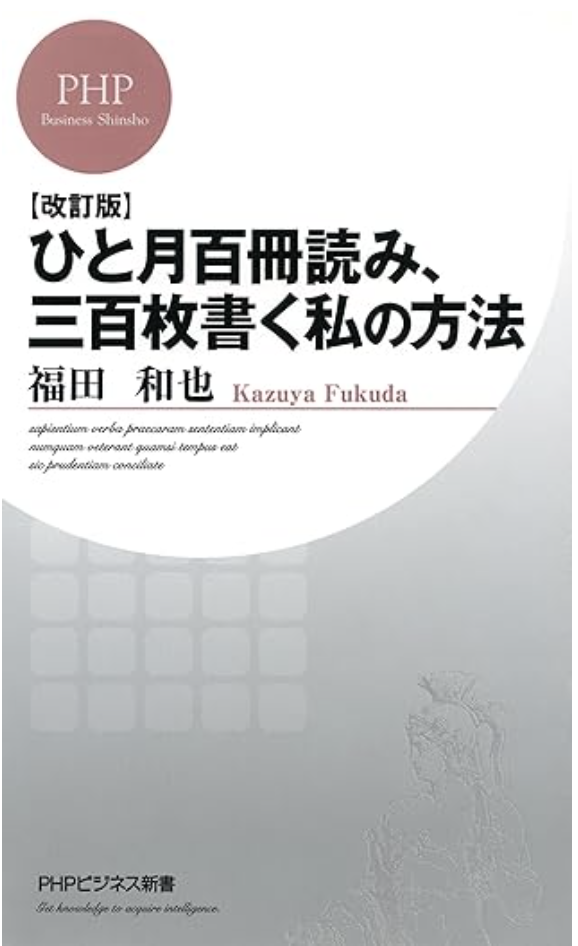
ひと月百冊読み、三百枚書く私の方法 (福田和也)の要約
福田和也氏は、読書と執筆を人生を動かすエンジンと捉えています。重要なのは「選び方」と「向き合い方」であり、目的を持った読書が発想と仕事を生み出すのです。抜書きは書き手の思考を追体験し、理解を深める有効な手段です。さらに、文章上達の鍵は模倣から分解、そして自分の言葉に置き換えることです。読む・コピー・分解・書くというサイクルを続けることで、確かな成長と読者に届く力を育てていくのです。
読書というインプットと書くというアウトプットには新たな発見がある!
何故なら、読むこと、書くことには、必ず発見があるからです。そしてその発見こそが、新しい仕事の原動力になるからです。(福田和也)
私は毎朝、この書評ブログを更新しています。そのなかでよくいただくのが、「本を読む時間がない」「読んでも結果につながらない」といった相談です。忙しさに追われて積ん読が増えていく人や、読後に何も残らないと感じてしまう人の悩みは尽きません。そうした声を耳にするたびに、読書の魅力や可能性をどのように伝えるかを、自分なりに工夫してきました。
先日、福田和也氏の言葉に触れたことで、本書を再読することにしました。ひと月百冊読み、三百枚書く私の方法を読むと、読書と執筆を単なる習慣や趣味の延長ではなく、仕事や人生を動かすエンジンとして捉えている著者の姿勢に圧倒されます。福田氏は「読むこと、書くことには必ず発見がある」と断言します。その発見こそが、新しい仕事の原動力になり、発想や視点を拡張していくのです。
本書の最大の魅力は、読書量や執筆量の多さそのものではなく、その「選び方」と「向き合い方」にあります。効率的に読むための最重要ポイントは「本の選択」にあると著者は言います。
たとえ読む時間を短縮できても、価値のない本に費やせばそれは完全な浪費になる。逆に、多少時間がかかっても、自分にとって有益な本であれば、その時間は確実に自分を豊かにする。読む目的を明確にし、その目的を果たすための選書に手を抜いてはいけない。この原則は、情報があふれる現代においてこそ際立ちます。
著者ほど大量の書籍を読んでいるわけではありませんが、私も読書というインプットと書くというアウトプットから新たな仕事をいただくことがあります。
日々の読書によって自分をアップデートし、時代の変化に追いつけるようになっています。仕事でわからないことがあれば、すぐに本を手に取り、自分なりの解決策を見つける。そしてその内容をアウトプットすることで頭が整理され、知識が確実に身についていくのです。この循環こそが、日常と仕事の質を高める土台になっています。
読む本を厳選することは、自分の時間を厳選することでもあります。そして、その時間で得た発見を文章に落とし込むことで、思考はさらに深まり、次のインプットを呼び込みます。インプットとアウトプットが相互に刺激し合うこの流れは、単なる努力ではなく、知的生産のための戦略です。
文章が分からない、ということは、すなわち、書き手が何を考えているか分からない、ということになりますね。逆にいえば、何を考えているかが分かれば、文章も分かるはずです。では、どうすれば、書き手の考えが分かるのか。抜書きは、書き手の考えを理解する上で、とても役に立ちます。
さらに福田氏は、文章を理解するためには書き手の考えを理解することが不可欠だと説きます。だとすれば、文章が分からないということは、書き手が何を考えているか分からないということ。逆にいえば、何を考えているかが分かれば、その文章も理解できるはずです。その手がかりとして有効なのが「抜書き」です。
気になった部分や印象に残った言葉を抜き出すことで、書き手の思考の輪郭が見え、自分の理解も深まっていきます。翻訳本の場合には原書にもあたり、それを抜書きすることが良いと著者は述べていますが、私も若い頃にレイモンド・チャンドラーの文体に憧れ、抜書きをしていたことを思い出しました。その体験を振り返るうちに、あらためて抜書きに挑戦したいという気持ちが湧いてきました。
福田和也氏が語る「難しい本」との向き合い方は、読書術の中でも非常に実践的で示唆に富んでいます。私たちが「難しい」と感じるのは、要するに理解できず、頭に入らず、字面を追っても文脈が入ってこない、情景も浮かばず、書き手の意図が伝わってこない状態です。その原因は大きく3つに分けられます。
第1に、議論の前提が分からない場合です。これは著者がある程度の予備知識を読者に求めているにもかかわらず、それを自分が持っていないケースです。こうしたときは、難しい本に正面から挑む前に、できるだけ平易な資料や解説を参照するのが近道になります。私も、難解な翻訳書を読む際には、英語で書かれた書評を先に読んで理解してから、読み直すようにしています。
第2に、言葉や概念が分からない場合です。このケースでは、出てきた言葉をそのままにせず、まず抜き出して調べていくことが欠かせません。面倒に思えても、この積み重ねによって語彙や知識が増え、やがて難解な本も読めるようになります。
第3に、論理の筋道が分からない場合です。これはさらに2つに分けられます。ひとつは、論理自体は正しくても文章が分かりにくい、あるいは非論理的な書きぶりで理解が阻まれている場合です。こうしたときには、文章を分解して部分ごとに構造を確認すると、全体の筋道が見えてきます。
もうひとつは、そもそも論理そのものが混濁している場合です。ここでは理解しようと力むのではなく、感覚やインスピレーションで読み流してしまう柔軟さが求められます。 それでも分からないときは、潔く放り投げることも大切です。
私自身も、読むべき本が大量にあるからこそ、翻訳が合わない、ロジックがかみ合わないと感じた瞬間に読むのをやめるようにしています。難しい本を読みこなすことは挑戦であり、飛躍の契機にもなりますが、無理にしがみつく必要はありません。 本の「難しさ」の正体を見極め、自分にとって乗り越えるべき壁か、あるいは一旦距離を置くべきものかを判断する。その取捨選択の積み重ねこそが、知的生産における真の読書力だといえるのです。
文章上達のために必要なこと
書くための認識については、大別して2種類があります。第1は、書く文章の構造についての認識。 第2は、自分が、何を書くという事についての認識です。
文章を書くうえで重要なのは2つの認識だと福田氏は述べています。ひとつは文章構造そのものへの理解であり、もうひとつは自分が何を書くのかという主題への自覚です。
福田氏はまず、好きな作家のコピーから始めると良いとすすめます。語彙やリズム、論理展開をなぞることこそが成長の第一歩であり、好きな作家の文章をなぞることは、良い文章を書くための扉を開く行為なのです。
音楽家が好きな曲をコピーして腕を磨くように、模倣は創造へ至る王道です。大切なのは、ただ書き写して終わらせるのではなく、その先にある分解のプロセスを踏むことです。段落をひとつのブロックとして捉え、全体の進行を観察することで、どの時点から語り始め、どの順番で展開しているのかが見えてきます。
典型的な流れは「前提」から始まり「問題提起」「条件の検討」「展開」「答え」へとつながっていきますが、必ずしもその型に従う必要はありません。ある文章は問題提起から始まり、ある文章はいきなり答えから入ります。中には答えや展開を省略するものすらあり、型を知ることによって、型を超える自由さに気づくことができるのです。
全体の流れをつかんだら、次に段落の中の進行を観察します。ひとつの段落が全体の中で「前提」や「展開」を担っていたとしても、その内部の文章は独自の有機的なつながりを持っています。最初に要点を提示してから補足を重ねる書き手もいれば、情報を少しずつ小出しにして読者を引き込み、緊張感を作り出す書き手もいます。
大切なのは、全体の進行と段落内の進行との関係を意識することです。この視点を持つことで、文章はただ並んだ言葉ではなく、生きた思考の流れとして立ち上がってきます。
コピーを続けることで、自分らしい文章の構造を作り、伝えたい目的を読者にわかりやすく届ける力が確実に育ちます。コピーは単なる模倣ではなく、優れた文章の思考の型を自分の中に取り込む作業だからです。
好きな作家や尊敬する書き手の文章を写すと、語彙の選び方やリズムの作り方、論理の運び方が自然と身体に染み込んでいきます。読むだけでは気づけない細部の工夫も、実際に手を動かして写すことで理解できるのです。繰り返すうちに「なぜこの表現なのか」「なぜこの構成なのか」といった分析の目が育ち、著者の思考法を追体験することができます。
そして重要なのは、コピーをそのままにせず、必ず自分の言葉に置き換えてみることです。模倣と分解を通じて得た型に、自分自身の経験や感情を流し込むことで、初めて自分らしい文章へと進化していくのです。
さらに福田氏は、10年近く前に書かれた改訂版で年代別の時間の使い方のコツを紹介しています。「20代は人生のモチーフを決める時期」「30代は選んだ領域で修業を積む時期」「40代は独自の視点を磨く時期」「50代は臆せず新分野に挑戦する時期」と位置付けていました。
福田氏は昨年(2024年)、若くして亡くなりました。もし60代半ばを迎えてなお筆を執っていたなら、さらに深く成熟した視点で読書と執筆について語っていたに違いありません。その未来を想像するたびに、もう新たな言葉に出会えないことが残念で仕方ありません。
本書から私たちが学べるのはシンプルな事実です。好きな文章を分解し、型を身につけ、やがて自分の型へと進化させる。この地道な往復運動を習慣化することこそ、知的生産の最短距離なのです。
大切なのは、このサイクルを止めないこと。選んで、読んで、分解して、書く。これを継続する限り、私たちは必ず前進できます。その歩みはやがて、読者に届く価値へと変わっていくのです。














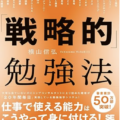
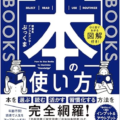


コメント