過疎ビジネス
横山勲
集英社
過疎ビジネス (横山勲)の要約
横山勲著『過疎ビジネス』は、地方自治体の財政難や人材不足につけ込む制度悪用の実態を描きます。国見町の救急車リース事業では、企業版ふるさと納税がDMMグループに還流し、委託先ワンテーブル社が利益を得る構図が浮上しました。制度の匿名性や競争性欠如が透明性を損ない、自治体は責任を外部に委ね住民不在に陥っています。コンサルが栄え、国が滅ぶことを避けるためには、制度の悪用を辞めさせる必要があります。
コンサル栄え、国滅ぶ「過疎ビジネス」の実態とは?
人口減少で活力を失った小さな自治体に地方創生の夢を熱弁して近づき、施策のアウトソーシングを巧みに持ちかけて公金を吸い上げる。大きな自治体は避け、手なずけやすい小さな自治体を狙い打ちにする。(横山勲)
少子高齢化と人口減少に直面する地方自治体では、人的リソースや財政の限界が行政運営に深刻な影響を与えています。そうした隙間を縫うように、外部のコンサルタントや企業が制度の盲点を突いて利益を得る「過疎ビジネス」が各地で進行しています。
その実態を明らかにしたのが、河北新報の記者の横山勲氏の著書過疎ビジネスです。 本書では、地方自治体の構造的な弱点に付け込み、公金を利権化する外部コンサルタントの悪質な手口が告発されています。
河北新報による国見町の報道は、町長を含む3人の特別職の給与引き上げに対する内部からの疑問の声が発端でした。そこから、財政難の自治体がなぜ高額な救急車を多数導入できたのかという新たな疑問が浮上しました。
横山氏は、自治体が人材不足や財政難を理由に外部に依存する一方で、コンサルタントや企業が制度を利用して利益を得る構図が常態化していると指摘します。本書が明らかにするのは、住民の目が届かない中で進む行政の私物化と、その背景にある「限界役場」の実態です。
福島県国見町で発覚した寄付金還流事件をきっかけに、著者は現場取材を重ね、同様の構造が全国に広がっていることを明らかにしました。こうした事例が続けば、「コンサルが栄え、国が滅ぶ」という深刻な状況が現実のものとなりかねません。
本来、地域の未来を形づくる政策は、住民の声に根ざすべきです。ところが現実には、企業やコンサルタントに施策を丸投げし、その結果への責任すら負わない自治体が増えています。 問題が起きても、自らの関与を曖昧にし、住民の意見が置き去りにされたまま物事が進んでいく。こうした姿勢が、地域からの信頼を確実に損ねているのです。 もちろん、すべての官民連携が問題というわけではありません。意義ある協力も数多く存在します。
しかし、補助金や交付金の獲得が目的化し、民意を軽視する施策が繰り返されるようでは、それはもはや「自治」とは言えません。 制度の活用にばかり目を奪われ、公共性や倫理が置き去りにされている――。著者は、こうした地方行政と企業・外部コンサルタントとの関係に、深刻なモラルハザードが生じている実態を明らかにしています。
企業版ふるさと納税は、地方創生の財源不足に悩む自治体向けに国が創設した制度だ。寄付額の最大9割が法人税などから税額控除される。自治体に寄付をした企業のグループ会社が、その寄付金を使った事業を受注すれば、利益を囲い込める。何ともよく考えられた事業スキームだった。
福島県国見町は、企業版ふるさと納税で集めた約4億3,200万円を使い、高規格救急車12台を購入しました。ただし、救急車は町内では使用されず、他の自治体や消防組合に貸し出すビジネスに活用されています。 事業を委託されたのは防災系ベンチャーのワンテーブル社で、プロポーザルには同社1社のみが応募していました。
また、救急車の製造はDMMグループの子会社が担当しており、寄付金がグループ内で循環する構図となっていました。 企業版ふるさと納税は寄付額の最大90%が税控除され、匿名での寄付も可能です。そのため、寄付した企業と契約先企業の関係性が外部からは見えづらく、制度の透明性が損なわれています。
収益を得ているのはワンテーブル社であり、国見町には経済的なリターンがありません。導入の目的は「研究開発」や「ネームバリューの向上」と説明されていますが、町内での活用はなく、住民への直接的な利益は見えにくい状況です。
さらに、救急車は市場価格よりも高く、仕様条件も特定企業に有利な内容だったとされます。入札前に町と企業側で事前のすり合わせがあったことも判明し、形式上のプロポーザルでありながら競争性に欠けていた実態が浮かび上がっています。
この国見町の事例は、税制優遇を利用しながら企業が寄付を通じて利益を得る、制度の盲点を突いた典型例です。自治体の主体性が弱まり、公共の利益が後回しにされている現実が問われています。
限界役場から脱却するために必要なこと
入手した計10時間分の録音データには、地方の自治体を見下し、行政の支配を目論むかのような暴言が記録されていた。そこで明らかとなったのは、小さな自治体を狙い打ちにして公金を吸い上げる「過疎ビジネス」の実態だった。
いま、地方自治体は深刻な人材不足と財政難に直面し、自ら政策を立てて実行する力を急速に失いつつあります。その結果、外部の専門家に頼らざるを得ない状況が各地で広がっています。総務省が進める「地域力創造アドバイザー」や「地域おこし協力隊」も、その流れの一環です。
本来、こうした制度は地域に専門知をもたらすためのものでした。しかし現場では、コンサルタントが行政内部に深く入り込み、実質的な意思決定まで担ってしまう例が少なくありません。住民の声よりも補助金や制度ありきで物事が動き、最終的には自らの企業や関係先に利益が落ちる仕組みをつくってしまう――。そんな構造が各地で生まれています。
福島県国見町の事例もまさにその象徴です。事業の初期段階からコンサルタントが関わり、結果として利益が特定の企業に集中する構図となりました。
取材で入手した録音データには、「財政力指数0.5以下(の自治体)って、人もいない、ぶっちゃけバカです」「本当に(議会を)制圧できる」「我々のほうで仕様書を変えることができる」といった信じがたいコンサルタントの発言が記録されていました。地方自治を軽視し、地方をただの市場として扱うビジネス視点が露骨に表れています。
官民連携とは本来、行政と民間が対等な立場で協力し、地域の課題を共に解決していくものです。ところが今は、行政が主導権を手放し、支援者であるはずのコンサルタントが実権を握るという、いびつな関係が各地に広がっています。
その結果、住民の声は聞かれず、地域には的外れな事業ばかりが残ってしまうのです。 政策は、住民とともに考え、つくりあげるものです。しかし現実は、「地方創生」の名のもとに東京や大阪のコンサル会社に巨額の資金が流れ、地方に残るのは名ばかりの事業と、説明のつかない成果ばかりです。
制度も複雑化し、市民には仕組みが見えにくくなっています。説明責任は形だけ、チェック機能も不十分。透明性を欠いたままでは、たとえ悪意がなくても信頼を失うのは時間の問題です。
もちろん、外部の力を借りること自体が悪いわけではありません。問題は、そこにルールと監視があるかどうかです。制度の中身ではなく、それをどう使い、誰のために動かすのか――公共性を支える構造こそが本質なのです。 今こそ問われるべきなのは、「この地域を本当に動かしているのは誰なのか?」という根本的な問いです。
もしその答えが住民自身の中にないのだとしたら、それはもう自治とは呼べません。 過疎地をビジネスの場として利用し、責任を取らずに去っていく企業と、それを黙認してしまう行政。このままでは、地方は都市の利益のために疲弊し、補助金頼みの「限界役場」へと転落していきます。
地域の未来を、企業任せにしてはいけません。公金を食い物にされ、説明も責任も放棄するような自治体の姿を、これ以上、見過ごすわけにはいかないのです。
私は、できるなら国見町議会に変わってほしかった。「お任せ民主主義」と決別し、「もう雑魚とは呼ばせない」という気概を見せてほしかった。議会が白分たちの力で問題を解決できなければ、国見町は今後も自治体を食い物にしようとする企業に手を替え品を替えて狙われ続けるだろう。
地方行政は責任の所在が見えない「お任せ民主主義」から脱却しなければなりません。行政や制度を他人事とせず、住民一人ひとりが関心を持ち、自分の声を上げていくことが求められています。行政を本気で変えたければ、まず市民が変わること。その意識の変化こそが、企業やコンサルタントを儲けさせる「過疎ビジネス」を終わらせる第一歩になるのです。
本書には、著者による丁寧な取材と粘り強い報道の積み重ねが描かれています。その姿勢に共感した取材協力者が次々と名乗りを上げ、隠されていた事実が少しずつ明らかになっていきます。読者は、まるで著者と一緒に真実を掘り起こしているような臨場感を味わうことができます。そして、かつて見下され、バカにされてきた住民や議会が、本気で地域を変えようと立ち上がる姿にも、胸を打たれます。
東洋経済オンラインや日経電子版が後追いで報じた内容がSNSを通じて広がったことを受け、国見町では百条委員会が設置されました。これにより、DMMによる匿名寄付の実態が初めて公の場で明らかとなります。かつてコンサルタンと雑魚と侮られた議員たちも、真相解明に向けて追及の手を緩めることはありませんでした。
やがて事態は内閣府にも波及し、国見町には「報告徴収」という行政処分が下されます。そして次の選挙では町長が落選し、町議会も大きく刷新されることになりました。
権力にひるむことなく、裁判のリスクも恐れず、地域のために真実を追い続ける河北新報の姿勢には、心から感動しました。大手メディアではなかなか伝えきれない地方の現実を、地元メディアだからこそ丁寧にすくい上げる。その底力を強く感じました。
「どんな取材でも、私は必ず現場に立ち会いたい。自分の目と耳で得た情報にしか出せない空気感がある」――。著者がそう語る言葉には、真のジャーナリズム精神が息づいています。 この一連の報道は高く評価され、著者は「第29回新聞労連ジャーナリズム大賞」を受賞しました。
現場に足を運び、自らの五感で真実を捉えるという基本を貫く姿勢に、私たちは改めて学ぶ必要があります。 こうした信念を持つジャーナリストこそ、これからの日本にますます求められていく存在だと強く感じます。今こそ、地域とメディアと市民が、それぞれの立場から声を上げ、未来を変えていくときです。
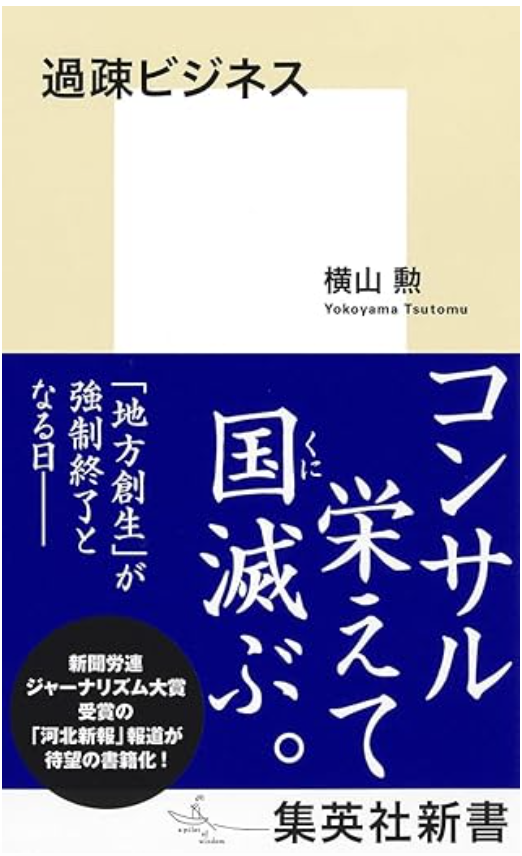















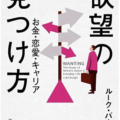


コメント