商人の戦国時代
川戸貴史
筑摩書房
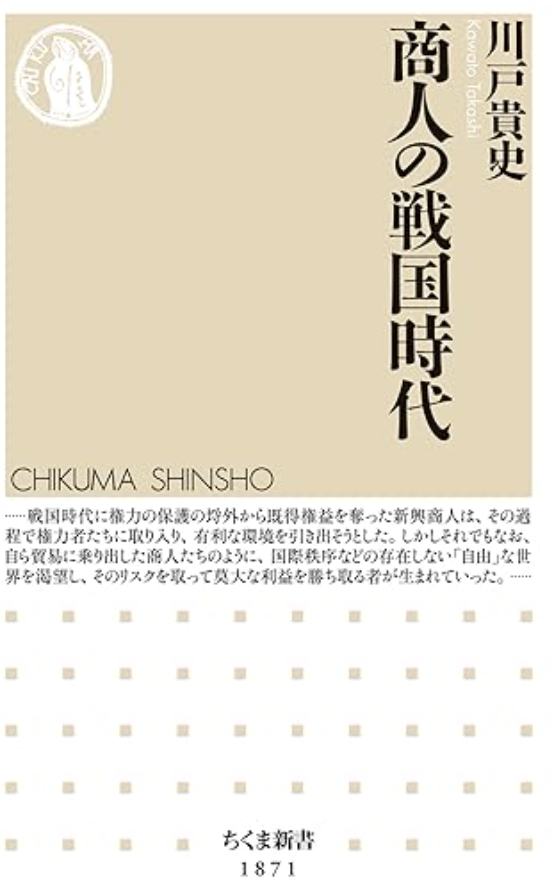
商人の戦国時代 (川戸貴史)の要約
『商人の戦国時代』は、戦国時代を武将中心の歴史から転換し、経済・流通・外交の視点で再構成する意欲的な書です。戦乱の陰で活躍した商人たちの実像を描き、制度の揺らぎや国際的なつながり、商業の自由と再編の動きを通して、戦国社会の多面性と現代的意義を鮮やかに浮かび上がらせています。
戦国時代に台頭する商人という存在
戦国時代にあっても、社会を構成し成り立たせていたのは一握りの権力者ではなく、名も無き大多数の庶民であった。(川戸貴史)
戦国時代というと、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった英雄たちの歴史小説や大河ドラマを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本書商人の戦国時代は、そうした武士を中心に描く従来の歴史観をロジカルに覆します。
川戸貴史氏が注目するのは、合戦の裏側で、新たな経済秩序を築き上げた商人たちの姿です。戦国武将と互いに利益をもたらす関係を築きながら、この時代をしたたかに生き抜いた彼ら商人の実像に、本書は光をあてています。
著者の川戸氏は、日本中世史や貨幣経済史を専門とする歴史学者であり、その豊富な知見をもとに、従来の戦国像に新たな視点を加えています。戦乱を支え、あるいは巧みに活用しながら、日本各地で新たな経済秩序を築いた商人たちの実像を描き出すことで、戦国という時代を改めて捉え直そうとする意欲的な試みです。
本書を読み進めていくと、戦国時代を支えていたもう一つの秩序、すなわち商人の存在が浮かび上がってきます。中でも注目すべきは、戦国以前から続いていた「道路や市場の利権化」という中世特有の構造です。道路、川、港、市場といったインフラは、単なる流通経路ではなく、それぞれを支配する地域の権力者にとって極めて重要な経済資源でした。
このような利権をめぐる構造の中で形成されたのが、「座」と呼ばれる商人組織です。一般には独占販売権を持つ商人集団と理解されがちですが、実際の座はより多様で柔軟な存在でした。
たとえば、「駕輿丁座(かよちょうざ)」のように共通する身分階層の出自を持ちつつ、複数の商品を扱う複合的な集団もあれば、近江国の「保内商人」のように、同じ村落に住むという地縁を基盤とした商人共同体も存在していました。
座は確かに、権力者から調達権や販売権などの特権を得ていましたが、単なる独占販売組織というよりは、生産、物流、販売といった多様な経済活動の特定領域において特化した役割を果たす制度的な枠組みだったと、著者は指摘します。
やがて、こうした既存の構造が揺らぎ始めます。中央の権威が衰退し、大名や地域勢力が自立を強める中で、特権的な商人たちに代わって新興の商人たちが各地に台頭していきました。列島各地を自在に往来し、既存の秩序を打ち破る彼らのような商人に対して、もはや幕府や寺社といった諸権力は、十分な規制を及ぼせなくなっていきます。
こうした利権構造が揺らぎ始める中、戦国時代の畿内では幕府内部の混乱により、徐々に政治秩序が不安定化していきます。幕府の有力な実力者であった細川氏の被官で、阿波国を本拠としていた三好氏が次第に台頭していくのもこの時期です。
三好氏の勢力拡大の背景には、軍事力だけではなく、大坂湾の物流ネットワークを掌握したことが大きく関わっていました。当時の港湾都市には、商人たちの経済活動を支える宗教基盤として法華宗寺院が数多く存在しており、戦国期の商人には法華宗の信者が多く含まれていました。
三好氏はこの点に着目し、大坂湾の主要港である兵庫、尼崎、堺などに所在する法華宗寺院を積極的に保護します。その結果、寺院の檀那であった商人たちの強い支持を獲得することに成功しました。宗教的庇護を通じた経済ネットワークへの浸透は、三好氏の戦略の中核でもあったのです。
さらに、淀川の河川流通にも三好氏の影響力は広がっていきました。これまで幕府や寺社といった従来の権力者が掌握していた河川利権に割って入るかたちで、三好政権は徐々にその支配を拡大していきます。このように、政治秩序の動揺に乗じて新たな経済権力を築いた三好氏は、商人との結びつきを通じて畿内における実効支配を強めていったのです。
大山崎の神人は中世を通じて室町幕府から権益を安堵され、大荏胡麻油の流通や販売を担っていました。しかし、戦国期に入ると次第にその影響力を失い、代々の将軍が形式上はその権益を保障していたものの、実効力は京都周辺の限られた地域にとどまるようになっていきます。
永禄2年(1568)に織田信長が上洛した際には、大山崎神人の権益を「棄破」、すなわち破棄したとする記録も残されています(この点には異論もあると言います)。その後、天正2年(1583)に豊臣秀吉が一度は神人の権益を復活させますが、天正17年(1589)に大山崎が検地を受けると、神人による荏胡麻油の商業活動は史料上から姿を消していきます。
こうして、従来の独占的地位を失う商人集団がある一方で、競争力の高い新興商人たちがその地位を実力で奪い取るようになります。
楽市という政策は被災した市町の復興や新規の市町の振興策として採用された政策であり、戦国時代には特にそのような市町が各地に多かったということがいえるだろう。
そうした中で登場するのが、戦国大名たちによって採用された「楽市・楽座」の政策です。自由取引を促すことで商業を活性化させようとするもので、一見するとあらゆる特権を排除した自由市場政策のように見えますが、実態はより複雑で多面的でした。
「楽市」は、戦乱によって疲弊した地域や、新たに形成された市場に商人を呼び込むための施策として位置づけられます。とりわけ知られているのは織田信長による実施ですが、それ以前にも、近江の戦国大名・六角氏が石寺新市で同様の取り組みを行っており、これが先例とされることからも、楽市の導入は各地の大名が抱える経済的・統治的課題への柔軟な対応策だったことがうかがえます。
従来の市では、特定の商人に独占的な特権を与えることで、取引のトラブルを未然に防ぎ、秩序の維持を図るという側面がありました。支配者にとっては、競争の排除は治安管理の一環でもあったのです。しかし、時代が進み、経済的活力を取り込む必要が高まる中で、こうした特権構造が障壁となり、新たな市場が求められるようになります。
そこで登場するのが「新市」の設置です。たとえば石寺新市のように、既存の市の近隣に自由取引が認められた市場を新たに設け、特権的な旧市との間で空間的な棲み分けを図るケースもありました。このように、「楽市」といっても一律の制度ではなく、城下町全体の構想の中に組み込まれることもあれば、小規模な定期市として機能する場合もあり、その実態は地域や状況によって大きく異なっていたのです。
一方の「楽座」は、特権的な座の解体を通じて、旧来の寺社勢力や有力商人たちが持っていた商業上の特権を排除する色合いが強い政策でした。経済の自由化というよりも、むしろ支配の再構築、つまり権力の再配分に踏み込む政治的な意味合いが濃かったのです。
現代にたとえるならば、楽市・楽座は地域再生を狙った新興企業の誘致政策のようなものです。新しい商人を呼び込み、市場に競争原理を導入することで経済を活性化させると同時に、既存の権益構造を揺さぶり、統治のあり方そのものを変えていったのです。
グローバルな商取引を行った戦国時代の商人たちの実像
戦国時代に日本で最も急速に発展した都市の一つとして、堺を挙げることができるだろう。堺は瀬戸内海流通においても重要な港湾都市となったが、なんと言っても東アジアや東南アジアとの貿易港として発達したことが特筆される。
商人たちは次第に軍事や政治の領域にも関与していきます。多くの商人は戦国大名に対して兵糧や武器の供給、資金の貸与などを通じて軍事的支援を行い、その見返りに特権や保護を得ていました。堺においては「講」と呼ばれる商人たちの組織が都市の自治を担っていました。中でも中核をなしていたのが、「会合衆」と呼ばれる有力商人層です。彼らは武家権力の支配を受けつつも、実質的には都市の運営を主導し、堺の自治を支える存在でした。
16世紀の堺は、名目上は武家領主の支配下にあり、求められる軍事費の負担を果たすことで政治的安定を保っていました。しかし、その統治の実務は、商業の中心を担う会合衆によって担われており、財政、治安、交易の管理から対外交渉に至るまで、自治的な運営が行われていたのです。
堺の商人たちは、自衛のために武装し、都市の防衛にもあたるなど、経済共同体でありながら軍事力と政治的交渉力を併せ持つ異色の存在でもありました。彼らは単なる「御用商人」ではなく、交渉と実力によって自身の地位を確保し続けた、極めてしたたかなプレイヤーだったのです。 こうした商人たちの役割は、国内にとどまるものではありませんでした。戦国時代は、実はきわめて開かれた国際的な時代でもありました。
16世紀の日本は、グローバル化が進む東アジア経済の中で、次第に重要な存在感を示すようになっていきます。その中心にあったのが、石見銀山に代表される銀の産出です。この時代、日本は大量の銀を自国内で産出し、それを実質的な貨幣として流通させることが可能になりました。
それまでの日本は、硫黄や銅、刀剣といった輸出品はあったものの、国際市場で強い競争力を持つには限界がありました。そこに登場した石見銀山は、文字通り「宝の山」となり、日本を国際経済に躍り出させる原動力となったのです。 日本産の銀は、中国や朝鮮をはじめ、東アジアに進出していたポルトガル商人たちをも強く惹きつけました。
1540年代以降、ポルトガル人が日本へ直接来航するようになると、国内の権力者や商人たちは、その機会を逃すまいと積極的に対外貿易へ参入していきます。
本書が明らかにしているように、当時の日本には、現在のような明確な「国境」は存在しておらず、中国、朝鮮、琉球、そしてポルトガルやスペインといった西洋諸国とのあいだで、人やモノが自由に行き交っていました。とくに堺や博多といった港町には南蛮船が来航し、香辛料や火器、ガラス製品、書籍、宗教といった多様な物資や文化がもたらされました。
戦国大名にとっては、その軍事力を戦争でいかに活かすことができるかに存亡がかかっているが、それとともに、軍事力を平時にいかにして蓄え、そして維持するか。これが支配者にとっての最も重要な資質として戦国大名たちは問われることになる。では軍事力の維持のためには何が必要か。それは恒常的な財源である。
こうした国際交易の最前線で活躍したのが、新たに台頭してきた商人たちです。彼らは、それまでの特権的な商人層に代わり、政治的な保護を巧みに活用しながら、既得権益を徐々に奪い取っていきました。商業活動の自由を掲げた「楽市」の導入によって、彼らは閉ざされていた市場に参入し、自らの力で商圏を切り拓いていきます。 もちろん、そうした新興商人たちもまったくの独立独歩というわけではありませんでした。
彼らはしばしば戦国大名や有力寺社と結びつき、特権や保護を引き出すことで自らの立場を強化していきます。ただ、決定的に重要なのは、その先にある「自由」を見据えていたことです。国際的な秩序がいまだ整わず、リスクがつきまとう時代にあっても、彼らはあえて海外との交易に乗り出し、莫大な利益と影響力を手にしていきました。
無秩序の中にこそ新たな秩序が生まれてきます。そうしたダイナミズムの只中に身を置きながら、新興商人たちは、既存のルールを乗り越え、自らが新しいルールの担い手となっていったのです。彼らの存在は、戦国の時代を単なる戦乱ではなく、経済と秩序の再編の時代として捉え直す上で、欠かすことのできない鍵となります。
戦国時代の商人は、単に経済活動を担うだけの存在ではありませんでした。社会の秩序が流動化する戦国の時代において、彼らは時に権力と交渉し、時に地域の安定を支える実践者でもありました。この視点は、変化の激しい現代社会を生きる私たちにとっても、多くの示唆を含んでいます。
しかし、そうした「自由」の時代は長く続きませんでした。豊臣政権、そして徳川政権の成立により、日本社会は「安定」へと大きく舵を切ります。とくに江戸幕府の鎖国政策は、日本の商人を国際市場から事実上遠ざけることになったのです。
海外から来るわずかな貿易商人との限定的な取引にとどまり、かつてのように自由に動き回ることはできなくなったのです。 16世紀に広がっていた開かれた商業の世界は、こうして終焉を迎えます。
「楽市・楽座」に象徴されていた「楽」の精神も、時代とともに人々の記憶から薄れていきました。そして17世紀以降、日本は「天下泰平」という秩序のもとで、管理されたかたちでの商業再構築へと向かっていきます。
本書は、戦国時代をただの戦乱の時代としてではなく、経済や流通、外交といった多角的な視点から捉え直そうとする試みです。商人という切り口を通じて、揺れ動く制度や再編される秩序、地域の自立と国際社会とのつながりが、立体的に描かれています。戦国の舞台裏に、したたかでダイナミックな経済のドラマがあったことに気づかせてくれる一冊です。





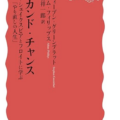
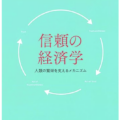

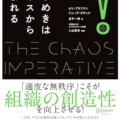


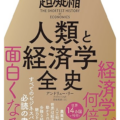

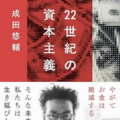
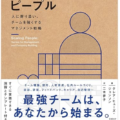

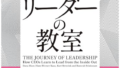
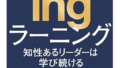
コメント