HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある
アダム・グラント
三笠書房
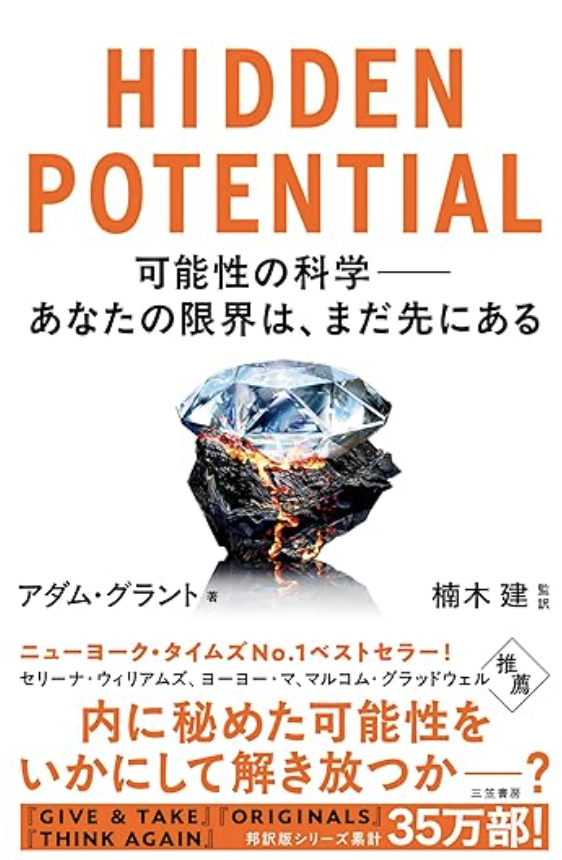
HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある(アダム・グラント)の要約
アダム・グラントは才能は生まれつきではなく後天的に育めるものだと主張します。成功の鍵は「性格スキル」であり、積極性、意志力、自己統制力という3つの特性が重要です。これらは環境と経験によって誰でも習得できます。真の成功とは到達点の高さではなく、困難を乗り越えてきた道のりにあります。個人の成長には支援する「足場」が必要であり、社会は誰もが可能性を発揮できる仕組みを構築すべきです。
成功のために才能よりも重要な要素とは?
「才能」より、「どれほど進歩できるか」(アダム・グラント)
このブログでもお馴染みのアダム・グラントが、「向上心」や「人間的成長」という普遍的でありながら見落とされがちなテーマに、真摯かつ知的なアプローチで挑んでいます。(アダム・グラントの関連記事)
HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にあるは、単なる自己啓発書ではありません。心理学の最新の知見と、弱小チームがチェス大会で勝利を収めた事例や、多言語話者たちのリアルな経験などを交差させながら、グラントは「最高の自分」に近づくための、実践的かつ科学的なアプローチを提示しています。
彼は、理論と物語を巧みに織り交ぜることで、才能の有無よりも、その後にどれだけ成長できるかが本質的に重要であるというメッセージを、読者の理性と感情の両面に訴えかけてきます。
偉大な思想家や実業家、そして指導者たちを賞賛する際、私たちはその人々の輝かしい実績にばかり注目しがちです。その結果、最も大きな成功を収めた人物ばかりを祭り上げ、最も不利な立場にありながらも多くを達成してきた人々の真価を見落としてしまう危険があります。
内に秘めた可能性を測る真の基準とは、到達した頂の高さではなく、そこに達するまでにどれほど険しく、長い道のりを歩んできたかという点にあります。どれほどの障壁を乗り越え、いかにして成長してきたかにこそ、その人の真のポテンシャルが宿るのです。
グラントは、そうした見えにくい成長の軌跡にこそ焦点を当て、誰にでも眠っている潜在能力を、どのようにして引き出し、育てていけるのかを解き明かします。
本書は3部構成で展開されます。「性格のスキル」「モチベーションをいかに高めるか」「成長の機会を増やすための体制」という3つのPartから、人がどのようにして成長し、可能性を開花させるかが丁寧に論じられています。
Part1の「性格のスキル」では、成長マインドセットの重要性が強調されます。その出発点となるのは、広範なインタビュー調査です。その結果明らかになったのは、偉大な成果を与えた人々の多くが、幼少期から「神童」や「天才」と称されていたわけではないということでした。
著名な彫刻家の中に、小学校時代に美術教師から特別な才能を指摘された人は一人もおらず、ピアニストも一部の例外を除けば、兄弟姉妹や近所の友達よりも少し上手だったという程度でした。
これらの結果が示しているのは、成功を分ける要因は多くの人が信じる「才能」ではないということです。「世界の誰かが習得できることは、ほとんどの人にも習得できる」 この結論は、本書を貫く根幹のメッセージでもあります。違いを生むのは才能の有無ではなく、環境、機会、意欲、そして成長への姿勢です。
成功をもたらす性格スキルとは何か?
人間性や性格は才能よりも重要である。
グラントは、「人格」や「性格」といった私たちが曖昧に語りがちな概念についても、新たな視点を与えてくれます。 彼は、人格や性格といった「心の力」は単なる意志の強さの問題ではなく、むしろ習得し向上させることが可能な一つの「スキル」、つまり「性格スキル(Character Skills)」であると考えるに至っています。
この「性格スキル」は、単に私たちが最高の成果を出すための補助的な要素ではありません。 それは、私たちがより高い目標を掲げ、険しい頂へと挑むための推進力そのものです。 目先のパフォーマンスを高める以上に、長期的な成長を支え、自らの可能性を押し広げる「人間のエンジン」とも呼べる存在なのです。
本書で探求される「性格・人格」とは、単なる性格傾向や気質といった表面的なものではありません。 それは、その人の「人間的な器の大きさ」や「精神的な深み」といった本質的な部分に関わるものです。
困難な状況に置かれたときにこそ、瞬間的な感情や衝動に流されるのではなく、自分自身が本当に大切にしている価値観や信念に基づいて、ぶれずに行動し続ける力。 そうした持続的な意志力、自己調整力、そして倫理的な行動を支える基盤こそが、本書で語られる「性格スキル」や「人格の力」の核心といえるでしょう。
これらはすべて後天的に磨き上げていくことのできる「心の力」であり、生まれつきのものに依存する必要はありません。
成長する意志と、適切な支援と環境があれば、誰でも、何歳からでも鍛え上げることができるのです。 著者は、性格スキルを科学的に研究するなかで、秘めた可能性を解き放つ鍵となる特性を特定しています。 それが「積極性」「意志力」「自己統制力」の3つです。
人生やキャリアにおいて、目標へ至る道は決して一直線ではなく、時に不快で、困難で、報われないように感じられる瞬間が続きます。そうしたときこそ、短期的な感情に流されず、不快感と向き合い、課題に正面から取り組む勇気が求められます。
同時に、必要なのは情報を積極的に吸収し、それを応用する力です。 柔軟な思考と好奇心を持って新しい知識を取り入れ、それを行動に移す姿勢が、進化と成長を支えます。 さらに重要なのが、「不完全さを受け入れる覚悟」です。 完璧であろうとするあまり動けなくなったり、失敗を恐れて挑戦を避けるのではなく、不完全なままでも進み続けること。 そこにこそ、継続的な努力と試行錯誤を通じた成長の道が開かれていくのです。
グラントは、これらの特性が単独で効果を発揮するのではなく、互いに補完し合いながら、「変化を起こす力」として機能していくことを示しています。 積極性が挑戦を促し、意志力が継続を支え、自己統制力が軌道を維持する。 このバランスが整ったとき、人ははじめて、真の可能性にアクセスできるようになるのです。
こうした人間的成長に不可欠なスキルは、優れた幼稚園の先生が愛情を持って育んでいます。子どもたち一人ひとりの個性を丁寧に観察し、決して急がせることなく、それぞれのペースで社会性や自己制御力、共感力などを育てていくその姿勢は、まさに教育の原点といえるでしょう。
優れた幼稚園の先生は、単に知識を教えるのではなく、子どもたちの中に眠る小さな「心の芽」に光を当て、水をやり、根気強く育てる存在です。 たとえば、ケンカをした子どもたちに対して、ただ叱るのではなく、互いの気持ちを言葉にする機会を与える。おもちゃを独り占めした子に「貸してあげなさい」と命じるのではなく、「どうすればお互いに気持ちよく遊べるかな?」と問いかけます。
こうした日々の対話と関わりの中で、「性格スキル」は確実に育っていくのです。 また、子どもが失敗したときに、結果だけを評価するのではなく、その挑戦のプロセスに目を向ける姿勢も大切です。小さな成功体験を積み重ねるなかで、子どもたちは「やればできる」という自己効力感を育んでいきます。 こうした教育環境の力は、子どもだけでなく大人にもあてはまります。
性格スキルは、実年齢に関係なく、人生のあらゆる段階で鍛えることができます。実際、ある実験では、性格スキルを集中的に鍛えた起業家たちは、たった5日間のプログラムを経ただけで、その後2年間の事業利益が平均して30パーセントも増加しました。これは、金融やマーケティングといった認知スキルを学んだグループの約3倍にも上る成果です。
彼らは、既存のチャンスを活かすだけでなく、自ら機会を創り出し、変化を先読みして新製品を次々と開発しました。経済的困難にも柔軟に対応し、強い精神的回復力(レジリエンス)を発揮して、巧みに資金を調達していったのです。
このように、性格スキルとは、私たちが目指すべき高い目標に向かって粘り強く進むための、極めて実践的かつ強力なエンジンなのです。
成長を加速させるために必要なのは、いくつかの「勇気」だと著者は指摘します。 第1に、自分にとって最適だと信じ込んでいるやり方をあえて手放す勇気。 第2に、心の準備が整っていない段階でも、あえて挑戦の場に身を投じる勇気。 そして第3に、誰よりも多くの失敗を経験することを恐れない勇気です。
不快感が生じた際、それを最小限に受け流すだけでは不十分である。驚くべきことに、人間は不快な経験を積極的に重ねることでこそ成長するのである。
本質的な成長は、安心と安定の中ではなく、不確かさや不快感の中にこそ芽生えます。 もし本気で成長を加速させたいのであれば、不安を避けるのではなく、それを受け入れ、時には自ら求め、意図的に増幅させる覚悟が必要です。 私たちはコンフォートゾーンの外に一歩踏み出すことで、初めて次のステージへの扉が開かれます。
学習とは、ただ知識をインプットすることでは終わりません。 新たに得た知識を実践し、そこで感じる不快感や戸惑いと向き合う中で、真の学びが始まります。 そして試行錯誤を重ねることで徐々に進歩し、やがてかつて不安だったことが安心へと変わっていく――それこそが学習の本質的なサイクルなのです。
さらに印象的だったのは、グラントが紹介する「人間スポンジ」の概念です。 スポンジ(海綿)は、あらゆるものを吸収し、濾過しながら、周囲の環境に柔軟に適応する存在です。人もまた、学び続ける存在である以上、変化を恐れず、吸収力を高めていくことが重要です。
この人間スポンジという比喩は、単に知識を受け入れるだけの受動的な存在ではなく、積極性・柔軟性・好奇心、さらには自分にとって不快な情報にもあえて向き合う力を備えた、能動的かつ成長志向の人物像を指しています。
最良の結果を出す人とは、情報の受け手として優れている人でもあります。すべてを無批判に受け入れるのではなく、「何を吸収し、何を意図的にスルーするか」を自ら選び取る姿勢が求められるのです。
その際の基準として、たとえば次のようなことを意識すべきでしょう。
・あなたの将来に真剣に関心を持っている人かどうか(配慮)
・その人が経験や専門知識を持っているかどうか(信憑性)
・あなたとの関係性が親密で、理解が深いかどうか(親密性)
この3つの条件を満たす相手からのアドバイスこそ、あなたの未来を改善するための貴重な知恵になり得ます。人間スポンジであるということは、自分の固定観念を一時的に脇に置き、他者の視点や未知の知見に心を開くことを意味します。 それは、自分にとって耳の痛い意見や、不快に感じる情報であっても、それが成長のヒントになるのであれば積極的に取り入れ、吟味し、自分の中に統合していく力です。
しかし、それだけではありません。 真の人間スポンジとは、得た知識や経験を自分だけのものにせず、他者にも惜しみなく共有し、貢献できる存在でもあります。学びの受け手であると同時に、与え手でもある――それが、人間としての器を大きく広げていく在り方なのです。
情報を吸収するだけでは、スポンジはいつか飽和してしまいます。 だからこそ、自分の中に溜め込んだものを外に還元する“循環”が必要なのです。人に与えることで、自らの理解が深まり、また新たな視点を得ることができるのです。その往復運動が、学びと成長を持続させる鍵となります。
このように、人格の形成もまた「才能」ではなく、「環境と経験」によって着実に育まれるのです。 この視点は、本書の全体テーマと見事に呼応しています。
著者は、建築家・安藤忠雄の歩みを通して、「完璧を目指すより、まず動くこと」の大切さを語ります。 安藤は独学で建築を学び、数えきれないほどの失敗と試行錯誤を重ねながら、世界的な建築家としての地位を築いてきました。 完璧な準備にこだわるのではなく、実践を通じて学び続ける――その姿勢こそが、成長への道を切り開いたのです。
また、「ベストを尽くせ」という言葉も一見すると前向きに聞こえますが、著者はその曖昧さに警鐘を鳴らします。 数々の研究によれば、成果を上げた人々に共通していたのは、「ベストを尽くす」という抽象的な目標ではなく、明確で挑戦的な目標を掲げていた点でした。
努力の方向が具体的であるほど、パフォーマンスも学習効果も高まるのです。 つまり、私たちに本当に必要なのは、完璧さではなく、明確な目的と高い目標です。 それこそが、私たちを確実に前進させる原動力になるのです。
成功とは。完璧さにどれほど近づけたのではなく、その過程でどれほどの困難を乗り越えてきたかなのだ。
そして何より忘れてはならないのは、失敗した自分を責める必要はないということ。 大切なのは、「うまくいかなかった理由」ではなく、「次にどう進むか」に意識を向けることです。 完璧を求めるのではなく、一歩ずつでも前へ進むことに焦点を絞る――それが、成長を持続させる唯一の道なのです。
成長には足場が重要な理由
「足場」とは、我々が独力では見出せない道を発見し、着実な進歩を遂げられるよう支えるものである。これによって、我々が内に秘めた可能性が解き放たれる。さらには、日々の退屈な業務の中で意欲を見出し、行き詰まりから脱する力を得て、困難や疑念も成長の原動力へと転換できるようになるのである。
Part2「モチベーションをいかに高めるか」では、学びや挑戦を継続するための「足場=スキャフォールディング」の重要性が語られます。
情熱の重要さは、音楽の世界に限ったことではありません。4万5千人を対象にした127の研究では、粘り強さと情熱が組み合わさることで、成功に至る可能性が高まるという結果が示されています。 では、どのような「足場」を築けば、継続的な学習や練習に情熱を傾けることができるのでしょうか。
著者が推奨するのは「デリバレイト・プレイ」という方法です。 これは、意図的な練習(デリバレイト・プラクティス)の要素と、ゲーム的な要素を融合させたもので、単調な課題にも楽しさを取り入れる工夫がなされています。スキル習得の過程で複雑な課題をシンプルな要素に分解し、遊びの要素を加えることで、モチベーションとスキルの両方を高めていくのです。
練習方法や道具、目標設定、関わる人を変化させることで、新鮮さを保ち、飽きを防ぐ。場合によっては、ロールプレイや即興などを取り入れることもあります。課題の設計を柔軟に見直すことで、成長のサイクルを途切れさせずに進めることができます。
また、「休憩」の取り方にも重要な意味があります。第1に、定期的な休憩は情熱の持続に役立ち、短時間の小休止でも疲労回復に効果があるとされています。第2に、休憩は創造力を高める。課題に熱中しているときこそ、意識的な距離を取ることで新たな視点が生まれるのです。第3に、休憩は記憶定着を促進します。学習後に適切なインターバルを設けることで、知識の定着率が大幅に向上することが示されています。
人のスキルは常に右肩上がりで伸びていくわけではなく、停滞や一時的な後退を経てから再び向上するパターンが多く見られます。山を登るために一度谷へ降りるように、進歩のためには一時的な後退や別の道への迂回も必要です。 その道が正しいかどうか、最初からわかっている人などいません。
多くの案内人から多様な視点や助言を受け取り、それらを統合して「自分にとっての最適な道」を見出すことが、モチベーションの土台となります。 また、「一つの道を極める」ことだけが正解とは限りません。副業や趣味など、一見回り道に思える活動が、結果として本業に新たな視点や活力をもたらすこともあるのです。
趣味に真剣に取り組むことで、自己肯定感が高まり、仕事にも好影響を与えるという調査結果もあります。 このように、「進歩している」という実感こそがモチベーションの最大の原動力です。
成功とは、一気にブレイクスルーを起こすことではなく、小さな前進の積み重ねなのです。 そして、自分一人で成し遂げようとせず、他者のために、他者とともに進もうとする時、私たちは思いがけない力を発揮します。障壁を「脅威」と見るのではなく「挑戦」として捉える視点、そして「成長できる」と信じるマインドセットがあれば、困難を乗り越える力が湧いてきます。
ただし、成長型マインドセットも、支える環境や文化(=足場)があってこそ効果を発揮するものです。足場がなければ、自ら築くしかありません。そのとき重要なのが「ブートストラップ思考」、つまり自らの力で一歩を踏み出す姿勢です。
さらに強力なのは、「他者と力を合わせて」足場を築く協働型のブートストラップです。チューター効果(人に教えることで自分も学ぶ)、コーチング効果(他者にかけた励ましが自分にも効く)など、「与えること」が自分を強くしていく現象が、それを裏づけています。
誰かのために頑張る、という意識は、最も強力なモチベーションとなります。困難な状況にあっても、自分が誰かの役に立っていると実感できるとき、人は想像以上の力を発揮するのです。
進歩とは、直線的に前に進むことだけを指すのではありません。後戻りも、迷いも、回り道も、すべてが「進歩」の一部なのです。 レジリエンス――困難から立ち上がる力――こそが、真の成功の証なのです。
とはいえ、私たちが前に進むために必要なのは、ただ努力を重ねることだけではありません。 周囲からの協力、そして自分自身をいたわり、楽しませるような練習――そうした“足場がけ”があってこそ、再び前を向く力が生まれるのです。
才能を育てるシステムの構築が必要
誰もが生まれ持った才能を存分に発揮し、より高い目標へと手を伸ばせる社会を真に願うならば、私たちを取り巻く「仕組み」そのものに、大胆な変革のメスを入れる必要がある。
Part3「成長の機会を増やすための体制」では、あらゆる人の潜在能力を引き出すために、どのような環境や制度が求められるのかが考察されます。 真に質の高い教育システムとは、たとえ逆境からスタートした子どもであっても、着実に進歩し、成功を掴むための「機会」が平等に与えられる場所です。
それは、限られた場所に天才を探し求めるのではなく、私たち一人ひとりの中に眠る天才性を丁寧に育んでいく、という発想の転換なのです。そうすれば、人類が持つ最も偉大な潜在能力を、余すところなく開花させることができるでしょう。
かつては、教育後進国とされたフィンランドが近年、国際的に評価される教育国家へと躍進した背景には、独自の文化的な基盤があります。著者はフィンランドの教育制度を研究した結果、その最大の成功要因は「すべての子どもには無限の可能性がある」という揺るぎない信念にあると語ります。
フィンランドの学校は、選ばれた優秀な子どもだけを伸ばすのではなく、すべての子どもに成長する機会を平等に提供することを重視しています。PISAの調査においても、学校間・生徒間の学力格差が世界で最も小さく、学力の高い生徒の割合が多いだけでなく、学力の低い生徒の割合が最も少ない国でもあります。
「一人たりとも才能を無駄にしない」――これは、フィンランドの学校でよく語られる標語です。 フィンランドの教育現場では、「子どもの仕事は遊ぶこと」という言葉がよく使われます。これは単なる理想ではなく、科学的な裏づけに基づいた教育哲学です。
イギリスの研究によれば、6歳時に学校生活を楽しいと感じていた子どもは、10年後の16歳時点での学力テストでも高い成績を示す傾向があるとされました。学習の楽しさは、知的な意欲と成績の向上に直結しているのです。
また、生徒が読む本を自ら選ぶことができたとき、読書への関心は飛躍的に高まります。読書が楽しくなれば理解も深まり、さらなる読書につながる好循環が生まれるのです。読書は、すべての子どもの学びの促進において、極めて強力な原動力となります。
集合知は個々の認知能力ではなく、むしろ向社会的なスキル(他者への配慮や協力する力)に大きく左右されることを発見した。つまり、最高の成果を上げるチームとは、 メンバー1人ひとりが優れているだけでなく、最も多くの「真のチームプレイヤーを擁するチームなのである。
集団の可能性を最大限に引き出すには、個々の能力だけでなく、それを支える仕組みが必要です。最良のチームとは、最も優秀な個人の集まりではなく、一人ひとりの中にある最高のアイデアを引き出し、活用できるチームです。研究でも、集合知は個々の認知能力よりも、協力・配慮といった「向社会的スキル」によって左右されることが示されています。
つまり、チームの力を高めるのは「真のチームプレイヤー」の存在なのです。これは、単に集団に所属している人ではなく、建設的な対話を通じて目標を共有し、互いの強みを活かし合い、弱点を補完する関係性を築ける人物を指します。
そのうえで有効なのが、従来のブレインストーミングではなく、「ブレインライティング」と呼ばれる方法です。まず個人がアイデアを練り、匿名で共有・評価するというプロセスを経ることで、心理的安全性を高め、見落とされがちな視点や発想が活かされやすくなるのです。
こうした文化は、柔軟で横断的な組織構造――ラティス型組織のような構造と相性が良い。情報が縦方向だけでなく、横や斜めにも流れることで、多様な声が集まりやすくなり、組織全体の創造性と機動力が増すのです。 私たちはしばしば、「過去の成果」と「未来の可能性」とを混同しがちです。
しかし、逆境に打ち勝ってきた人のたゆまぬ努力や、その過程で培った力にこそ、本質的な価値があります。重要なのは、困難をどう乗り越えてきたのか、その成長の軌跡を見抜ける評価システムを構築することです。
本当に優れた選考とは、単なる結果だけでなく、「その結果がどのような背景のもとに達成されたのか」に目を向ける視点を含むものです。過去の職歴や肩書ではなく、どんな環境下で何を学び、どれほど成長してきたかを丁寧に見極める必要があります。
評価されるべきは「輝きの大きさ」ではなく、「輝きに至るまでに耐え抜いた熱と圧力」である――著者はそのように訴えています。
どれほど進歩するか、どのような人物になるのかは、その人の抱く夢の大きさに大きく左右されていたのである。
壮大な夢を持つ若者ほど、多くを学び、キャリアの中でも大きな成長を遂げるという研究結果も紹介されます。その夢は、人生を方向づける羅針盤のような役割を果たすのです。
私たちが本当に目指すべき進歩とは、社会的地位や名声を得ることではありません。人格を深め、自分の価値観を貫いて生きること。そして、内に秘めた可能性の扉を開き、それを存分に羽ばたかせること――それこそが、真の成功と呼べるものなのです。
アダム・グラントは才能は生まれつきではなく後天的に育むものだと主張します。成功の鍵は「性格スキル」であり、積極性、意志力、自己統制力という3つの特性が重要です。これらは環境と経験によって誰でも習得できます。
真の成功とは到達点の高さではなく、困難を乗り越えてきた道のりにあります。個人の成長には支援する「足場」が必要であり、社会は誰もが可能性を発揮できる仕組みを構築すべきです。
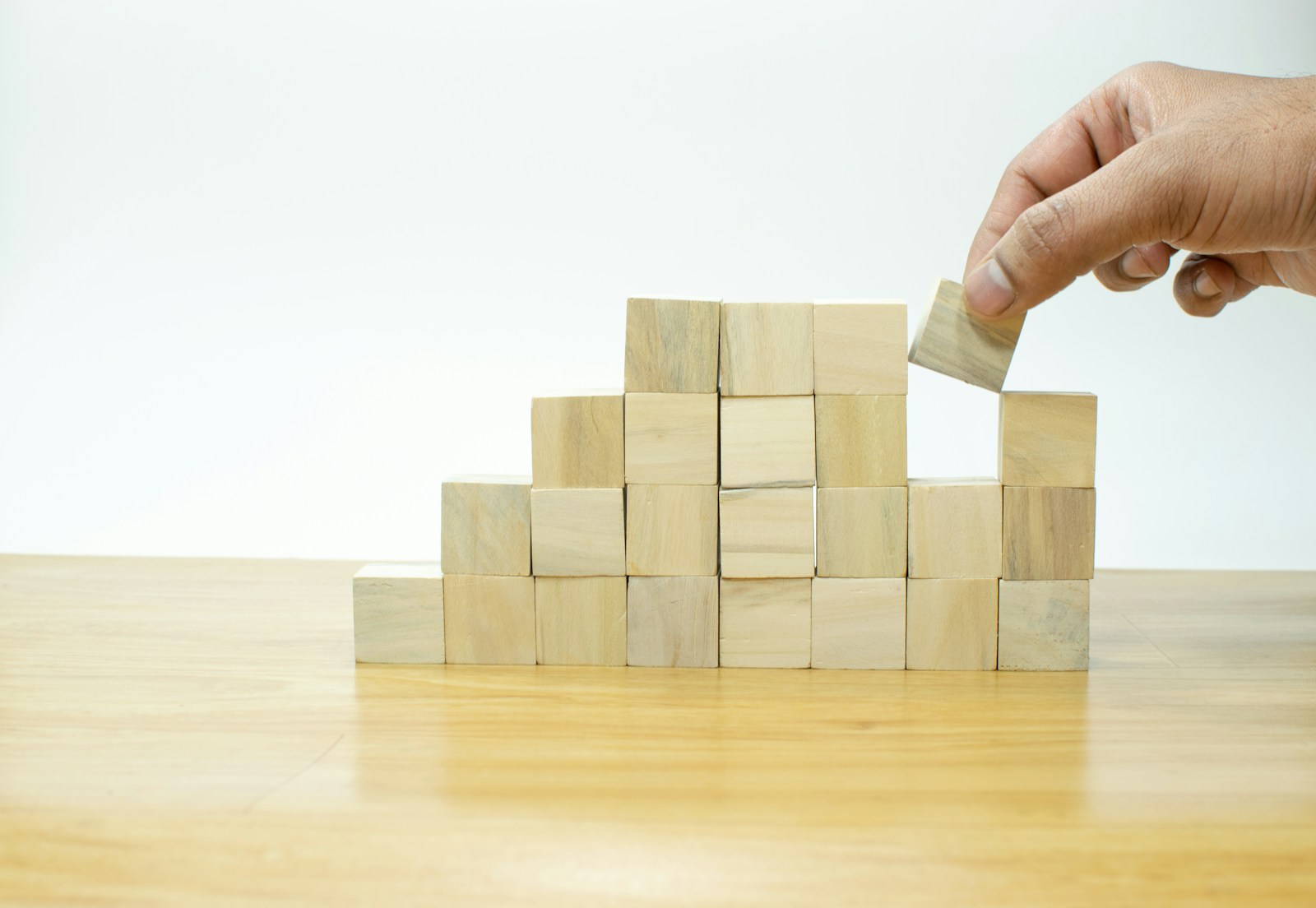




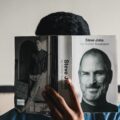












コメント