クオーターライフ 20代で知っておきたい、クライシスを生き延びる知恵
サティア・ドイル・バイアック
日経BP
クオーターライフ 20代で知っておきたい、クライシスを生き延びる知恵 (サティア・ドイル・バイアック )の要約
サティア・ドイル・バイアックは、思春期を過ぎた若者が直面する不安や迷いを「クオーターライフ・クライシス」として捉え、ユング心理学の視点からその意味を明らかにします。著者は、人生の1/4地点にあたるこの時期を「安定」と「意義」の間で揺れ動く過程と位置づけます。成長の四つの柱──「離れる」「聴く」「育む」「一つにする」──を通して、人は他者や社会の期待から離れ、自分の声を聴き、現実と理想を結び直していく。社会的成功ではなく、自分の内面と外の世界が調和した「全体性」こそが成熟の証だと、著者は静かに語りかけます。
クオーターライフ・クライシスとは何か?
若者も医療システムも、人生のこの時期に不意打ちを食らわされ、ただうろたえているかのようだ。問題は、心の病だけじゃない。根本的に、人生のこの時期に起こることへの、深い理解が欠けていることだ。思春期(もしくは青年期)のあとの20年ほどを何と呼ぶのか、世の中の合意すらできていない。私はこの時期を、「クオーターライフ・クライシス」という言葉にちなんで「クオーターライフ」と呼んでいる。(サティア・ドイル・バイアック)
10代後半から30代にかけての若者たちの間には、まぎれもない苦しみが広がっています。深刻な不安や鬱、人生への迷いは、もはや特別なことではなく、日常的なものとなりつつあります。アメリカでの自殺率の高さや薬物の過剰摂取も無視できない状況だと言います。
さらに問題を複雑にしているのは、その苦しみに対する診断や処方箋が、かえって混乱とストレスを増幅させてしまうという現実です。若者自身も、そして彼らを支えるはずの医療システムさえも、この人生の時期に直面する課題に対して準備ができておらず、まるで突然の嵐に巻き込まれたかのように戸惑っています。多くの若者が精神科医や臨床心理学者を訪ねても、的確なアドバイスをもらえずにいます。
本質的な問題は、心の病だけではありません。そもそも、人生のこの時期に何が起こるのかについての深い理解が、社会全体に欠けているのです。思春期を過ぎたあとの約20年をどう呼ぶべきかさえ、共通認識が存在しません。サティア・ドイル・バイアックは、この時期を「クオーターライフ」と名づけ、「クオーターライフ・クライシス」という概念に光を当てています。
ユング心理学を学び、若年層を専門とする心理療法士として活動している著者は、この年代が直面する心理的・社会的な課題に、深い洞察を与えてくれます。
クオーターライフとは、人が生まれ育った家を離れ、自分自身の人生へと飛び込もうと格闘し始める時期のことです。きっかけは、仕事や結婚、子育て、あるいは進学など、人によってさまざまですが、誰もが新しい世界へ一歩を踏み出そうと必死にもがいています。
ただし、クオーターライフの旅は、単なるパートナー探しやキャリアの構築ではありません。それは、自分という存在を深く探し求める旅でもあります。そしてその最終的な目標は、「全体性」に到達することです。つまり、心の内側と外側の世界が分離しているようには感じられなくなるような、生きることそのものが一つに統合された感覚を得ることなのです。
この探求の道のりは、常に「もっと何かを」と渇望し続け、足りなさに苦しむ状態から、自分自身を受け入れ、今ここにある人生に深く満足して生きる方向へと導いてくれます。
著者が掲げる「成長の四つの柱」──「離れる」「聴く」「育む」「一つにする」──は、どれもクオーターライフにおいて避けて通れない内面的な取り組みです。これらは順番に達成すべき課題ではなく、それぞれのプロセスが人生の満足度に直接的な影響を与える重要な要素です。この柱を柔軟に受け入れ、誠実に取り組むことで、私たちはより充実した人生に近づくことができます。
著者自身もまた、この問いに導かれた一人です。かつてはスタートアップで働いていたバイアックは、「この混乱の時期がいつ、どう変わっていくのか?」という疑問を追いかけ、大学院でユング心理学を学び、現在は心理療法士兼著述家として活躍しています。
本書では、著者のクライアントである4人──グレイスとダニー(意義型)、ミラとコナー(安定型)──の物語を通して、それぞれのクオーターライフの歩みを描いています。彼らは皆、それぞれに異なる個性や背景を持ちながらも、自分自身と向き合い、人生の意味を探し求めていました。
クオーターライファーの多くは、安心や安全、そして社会的な「安定」を強く望みながらも、同時に「意義」や「経験」、さらには未知なる冒険を追い求めています。堅実に生きるための確かな構造を必要としながらも、人生に温もりや親密さ、そして目的を与えてくれる神秘性や不確かさを、深く求めているのです。
クオーターライファーの多くは、「安定」と「意義」のあいだで絶えず揺れ動いています。安心や安全といった確かな基盤を求める一方で、「もっと意味のある生き方をしたい」「未知の世界に飛び込みたい」という衝動にも強く惹かれるのです。
堅実でありたいのに、心のどこかではリスクを冒してでも本当の自分を生きたいと願っている。そんな相反する思いを抱えながら生きる姿こそ、この時期を象徴しています。秩序と混沌、日常と冒険、安らぎと刺激──その両極の間で揺れ続けることが、実は成長のプロセスそのものなのです。
著者はこの内面的な葛藤を、「意義型(Meaningタイプ)」と「安定型(Stabilityタイプ)」という二つの傾向に分類しています。 まず「意義型」は、創造性や理想、内面の探求を重んじるタイプです。芸術家や哲学者、音楽家など、感受性の高い職業に多く見られ、世界の美しさや人間の奥深さを感じ取ることに喜びを覚えます。
しかし現実的な基盤を築くことが苦手で、社会の中で孤立してしまうこともあります。心の奥ではすべてとつながっている感覚を持ちながらも、自分が「唯一の存在」であるという確信が持てず、閉じこもったり、他者との関わりを避けたりすることもあるのです。
それでも彼らは、若いうちから幾度も危機を経験することで、早い段階で自らの「安定」を見出していきます。中年期を迎える頃には、すでに「意義」と「現実」を両立させる術を身につけていることが多く、彼らにとっての課題は、この二つを失わずに共存させる繊細なバランスを取り続けることにあります。
一方の「安定型」は、現実的で秩序を重んじるタイプです。法律家や金融関係のビジネスパーソン、結婚や家族を重視する人々に多く見られます。彼らは責任感が強く、社会の枠組みの中で安定を築こうと努めますが、心配性で警戒心が強く、時に他者や状況を過度にコントロールしようとする傾向があります。
特に「意義型」の親に育てられた「安定型」は、幼少期に経験した不安定さを繰り返すまいと慎重になりすぎ、自分の感情を抑え込んでしまうこともあります。 こうした人々は、外側の安定を守るために、自分の身体や感情を管理しようとします。時には摂食障害や依存的な関係性に苦しむこともありますが、それは「孤独よりも不完全な安定を選ぶ」心の防衛でもあるのです。
しかし、どれほど秩序を保っても、外側の安定だけでは本当の充足にはつながりません。最終的に必要なのは、「他者や制度を信じる力」ではなく、「自分自身を信じる力」を育むことなのです。
結局のところ、「意義型」と「安定型」は対立する存在ではなく、どちらのタイプにも成長の可能性があります。自分がどちらに近いかを理解することで、人生の選択に迷いが生じたときも、より前向きに取り組むことができます。避けがたい困難や時代の期待に振り回されずに、自分のリズムで歩むことができるようになるのです。
著者は、人間は誰しも「安定」と「意義」の両方を必要としており、その間で揺れ動きながら、自分らしさや人生の意味を見出していく存在だと語ります。その繊細なバランスを保ちながら生きること──それこそがクオーターライフを乗り越えるための最も人間的な知恵であり、成熟への第一歩なのです。
クオーターライフの正しい過ごし方
クオーターライフに自己中心的になるのをよしとしない風潮もあるけれど、私はクライアントに「自分の人生や経験に──過去にも、現在にも、未来にも──興味を持ちましょう」とアドバイスしている。ありきたりの答えを求めるのではなく、幅広い好奇心を持つことが大切だ、と力説している。
著者は、自分自身に興味を持ち、内面を丁寧に見つめることが、短期的にも長期的にも鬱や不安をやわらげ、やがて本当に探し求めていた道を見つける手がかりになると述べています。
この「自分自身を探求する旅」の最終的な目的は、複雑でストレスの多い現代社会のなかで、自分らしい生き方や人生の意味を見つけ、それを実際のかたちとして築いていくことにあります。これは決して、世間でたびたび揶揄されるような「自己陶酔」ではありません。
むしろ、古代の哲人たちも勧めていたように、生き方の本質に関わる大切な営みなのだと著者は強調しています。 「汝自身を知れ。そうすれば、神々を知るだろう」 この言葉が示すように、自分自身を深く理解することが、人生の根底にある真理へとつながる道であると、著者は考えています。
著者が「クオーターライフ」と呼ぶこの時期は、人が生まれ育った家庭を離れ、自らの人生へと飛び込んでいく重要な転換期です。きっかけは、仕事や結婚、子育て、あるいは進学など人それぞれですが、共通しているのは、誰もが自分の足で人生を切り拓こうともがいていることです。
ただし、クオーターライフの旅は、単なるパートナー探しやキャリア形成のための旅ではありません。それは、自分とは何者かを深く見つめ、真の意味での自己と向き合う旅でもあります。 そしてこの旅の最終的な目的は、「全体性」に到達することにあります。
つまり、心の内側と外の世界が切り離されたものではなく、人生そのものがひとつに統合され、調和しているような感覚を得ることです。 このような探求は、常に「もっと何かを」と求め続け、足りなさに苦しんでいた状態から、自分自身を受け入れ、「今ここにある人生」に深い満足を見出していくプロセスへとつながっていきます。
精神的に本当の意味で大人になるということは、ひとりの意識的な個人でありながら、同時にコミュニティの一員としての責任も果たせる、成熟した人間になることです。つまり、「安定」と「意義」の両方を手に入れられる、自分自身の道を見つけることにほかなりません。 それは、秩序と混乱、文明と自然、人間性と神性といった、一見相反するものが、内面でひとつに溶け合うような生き方なのです。
「安定型」は、「意義型」を「やりすぎだ」と感じているかもしれないが、豊かな感情や創造的な表現とつながっている「意義型」を、密かにうらやんでもいる。 一方、「意義型」は、「安定型」を「堅苦しい」「恵まれている」と批判しているかもしれないが、一貫性があって世の中をラクに渡っているように見える「安定型」を、密かにうらやんでいる。
「意義型」であっても「安定型」であっても、どちらのタイプにも共通して必要なのは、過去のトラウマを癒やし、人生の中で意識的にコミュニケーションや人間関係を改善していくことです。そうした取り組みを重ねていくことで、それぞれがより深く自分自身を理解し、表面的ではない「味のある自信」に満ちた存在へと成長していくことができるようになります。
そして、自分自身としっかりつながったその先には、外の世界との関わりにも、これまで以上の心地よさと豊かさが生まれてくるはずです。
クオーターラライファーの4つの柱
「離れる」「聴く」「育む」という取り組みを「一つにする」ことで、まったく新しいものが生まれるからだ。
著者は、自分らしい人生を築いていくためには、「成長の4つの柱」と呼ばれる内面的な取り組みが欠かせないと語っています。 これは、「意義型」であっても「安定型」であっても、すべてのクオーターライファーにとって、大切な心のプロセスです。自分を深く知り、人生と丁寧に向き合うための軸ともいえる考え方です。
成長の4つの柱
① 離れる
親や社会の常識、これまで無意識に従ってきた規範から距離を取り、自分自身の価値観や本音の欲求を見極めることが自分を変える始まりになります。
② 聴く「自分の声を聴く」というのは、外からの期待や評価ではなく、自分の内側から湧き上がってくる小さな声に耳を傾けることです。他人の価値観や常識に振り回されるのではなく、自分自身を信頼し、その声を真摯に受け止めていく。そのプロセスこそが、自分にとって本当に必要なニーズに応える第一歩になります。
③ 育む
望み通りの人生を「育む」ためには、表面的な努力だけでは足りません。一貫性を持って進み続けること、集中力を切らさないこと、そして、疲れや心の制限に負けずにやり抜く力が求められます。
④ 一つにする
そうして築いた人生を、日常の中に根づかせ、そこから得られる安定と充実をしっかり受け取っていくこと。
成長の「四つの柱」は、階段や段階ではなく、成長を支える柱なのだ。「離れる」「聴く」「育む」という流れは、機織りのように行きつ戻りつを繰り返すプロセスだ。たとえば、「育む」に力を入れるあまり、物事を変えることにこだわりすぎてしまうなら、自分の声を「聴く」ことに立ち戻る必要がある。同じように、自分の望みや欲求を「聴く」のが難しくなったら、何が事態を複雑にしているのかを明らかにするために、「離れる」プロセスに立ち戻り、心の声を、仲間やお世話になった人や社会の常識から分離することが大切だ。
著者によれば、「成長の四つの柱」は、順番通りにこなしていくべき段階ではありません。それぞれの柱は、人生のさまざまな場面で自然と浮かび上がり、交差し、ときに戻りながら、私たちの成長を静かに、けれど力強く支えてくれるのです。
そして何より大切なのは、この柱の取り組みが、就職や結婚などの「人生の節目」や「肩書き」といった、外側の基準に依存しないという点です。これは、他者からの評価ではなく、自分の内面から成熟していくための、まったく新しい成長の枠組みなのです。
本書では、4人のクオーターライファーたちが、それぞれの悩みや不安、夢や葛藤を抱えながら、「離れる」「聴く」「育む」「一つにする」の柱を、行きつ戻りつ歩んでいく姿が丁寧に描かれています。
ある人は「離れる」ことで、親や社会の価値観から自分を切り離し、またある人は「聴く」ことで、心の奥底にあった本音にようやく気づきます。「育む」という地道なプロセスを通じて、自分にとって意味のある人生を少しずつかたちにしていき、やがて「一つにする」ことで、「安定」と「意義」がつながる瞬間にたどり着くのです。
それは、一人ひとりが手探りで築き上げていく、自分だけの人生のプロセスです。きれいに整理された成功ストーリーではありません。迷い、立ち止まり、ときに後戻りもしながら進んでいく──そんなリアルな成長の軌跡に、私たちは胸を打たれるのです。
時間が経つにつれ、四つの柱の間には、美しい織物のように新しい模様が生まれていきます。 「離れる」「聴く」「育む」という懸命な取り組みを、「一つにする」ことで、まったく新しい価値が生まれるのです。
それは、仕事での成功かもしれません。創造的な活動が実を結ぶ瞬間かもしれません。あるいは、もう無理だと思っていた学びが実ることもあるでしょう。
すべてがひとつにまとまったとき、多くのクオーターライファーは、それがまるで魔法のようだと感じるはずです。 大小さまざまな「達成」の瞬間を通して、魂の自分と、自我としての自分が共に生きはじめ、内なる世界と外の世界に調和が生まれます。
「意義型」の自分と「安定型」の自分が対立するのではなく、支え合いながら一つの人生の中で関わり合い、共存していく。そうしたバランスが訪れたとき、人はようやく「自分も世界の一部だ」と、心から感じることができるようになるのです。 もはや、傍観者ではいられません。ただ社会の流れを眺める存在ではなく、自分自身もまた、この世界をつくる側の一人なのだと、実感できるようになるのです。
実際、私自身、20代〜40代前半まではアルコール依存に苦しみ、何度も人生に迷いました。 もしあのとき、本書に出会えていたなら、もっと早くに人生を立て直すことができたかもしれません。
今から18年前、44歳になった私は、アルコールと距離を置き、自分自身との対話を丁寧に重ねていくことで、ようやく人生が少しずつ動き始めました。過去の自分では想像もできなかったような静かな変化が、日々の中に現れるようになったのです。
そして私は、コーチのサポートを受けながら「著者になる」というビジョンを描き、それに集中して取り組むことで、そのの夢を実現することができました。
だからこそ、サティアが4人の若者たちに寄り添い、ともに歩んでいくそのやさしさが、どれほど深く、そして確かな力で人生を動かしていくのか──その意味が、今の私にははっきりと実感としてわかります。
その温かなまなざしがあるからこそ、読者である私たちも、自分の内側にある繊細な声に、恐れず耳を傾けることができるのです。そして、その静かな声にそっと従ってみること。そこから人生は、確かに新しい方向へと動き出していきます。
クオーターライファーの親という立場になった今の私にとっても、本書は大きな学びを与えてくれる一冊でした。自分自身を見つめ直すだけでなく、次の世代とどう向き合っていくかという視点でも、多くのヒントをもらえたと感じています。
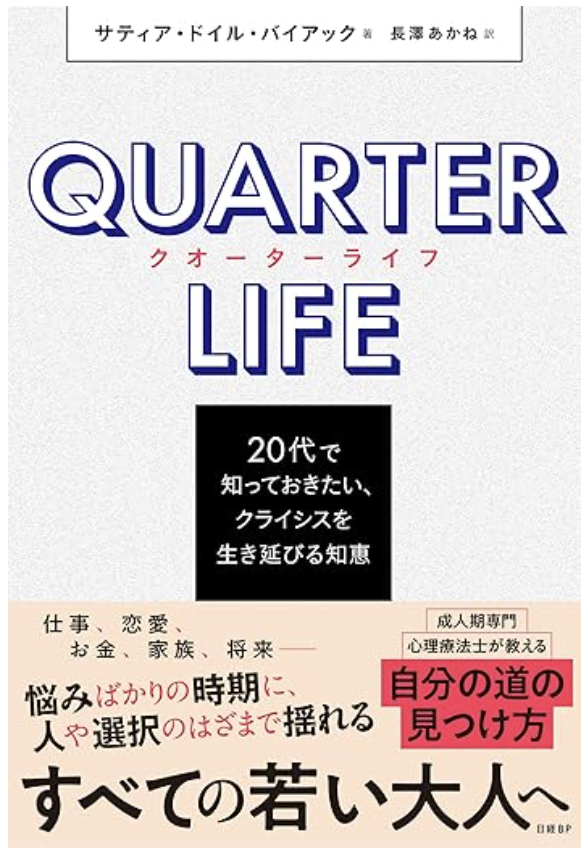













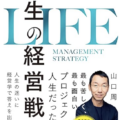
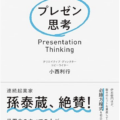



コメント