リキッド消費とは何か
久保田進彦
新潮社
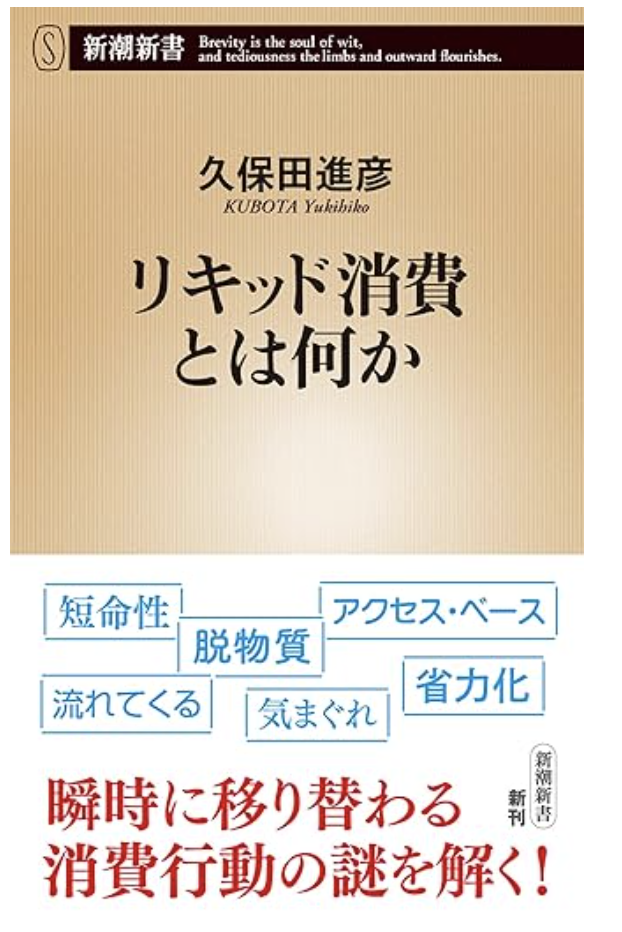
リキッド消費とは何か(久保田進彦)の要約
「リキッド消費」とは「液状化した消費」を意味し、現代社会における流動的で気まぐれな消費傾向を指します。久保田進彦氏によれば、これは①欲しいものが短期間で変わる「短命性」、②所有よりシェアやレンタルを重視する「アクセス・ベース」、③物質より経験を重視する「脱物質」の3要素で特徴づけられます。
新しいトレンド リキッド消費の特徴とは?
リキッド消費は「液状化した消費」という意味です。それは「消費の流動化」であり、「気まぐれな消費」といっても良いでしょう。 (久保田進彦)
リキッド消費とは「液状化した消費」を意味し、従来の固定的な消費行動とは異なる流動的で気まぐれな消費のあり方を表します。現代社会では、消費の形態が大きく変化し、より柔軟で一時的な消費行動が広がっています。
リキッド消費は現代の日常生活のいたるところで見られます。ファスト・ファッションの浸透により、私たちは洋服を気軽に選べるようになりましたが、同時に洋服に対してより気まぐれになりました。SNSの影響で突然注目を集める対象に「にわかファン」が急増する現象も珍しくなくなり、流行や関心事もより流動的になっています。
また、物の所有形態も変化しています。自動車を所有せずカーシェアリングを利用する人々やシェアサイクルを活用する人々が増え、旅行時にスーツケースをレンタルする習慣も広がっています。サブスクリプションの普及により、「所有しないで消費する」という行動様式が一般化しつつあります。
SNSで見た服をスマホで即座に購入し、映画はサブスクで鑑賞し、必要な時だけカーシェアを利用する。高価なブランド品より珍しい経験を重視する。こうした消費行動は現代社会における重要な変化の兆候です。
青山学院大学経営学部教授の久保田進彦氏は、このような新しい消費の形を「リキッド消費」と名付け、その特徴を分析しています。リキッド消費は、①その時々で欲しいものが変わる(短命性)、②わざわざ買わなくてもレンタルやシェアリングでよい(アクセス・ベース)、③物よりも経験を重視する(脱物質)という3つの要素で特徴づけられます。
このコンセプトは2017年にイギリスの研究者バーディーとエカートによって提唱されました。 社会変化の加速も、リキッド消費の背景にある重要な要素です。社会変化の加速とは単に社会が速く変化することではなく、変化の速度自体が増していることを指します。これは技術的加速、社会変動の加速、生活テンポの加速の3つの側面から捉えることができます。
技術の普及テンポの高まりは、人々が新技術を受け入れる習慣の加速を意味し、社会制度や慣行の変化速度の上昇を示しています。社会変動の加速は技術普及にとどまらず、衣服、食事、言語、仕事、家族のあり方など社会を構成する主要要素の変化にも及びます。かつてはこれらの変化は世代間でゆっくりと生じ、個人がその変化を実感することはありませんでしたが、現在では変化が非常に速く、数年で社会の様相が一変することもあります。
この急速な変化により、つい最近の時点が既に「過去」となり、近い将来が現在の常識が通用しない「未来」となるため、「いま」という期間がどんどん短くなっています。私たちは「現在が収縮する社会」を生きているのです。
社会変化の加速に加え、道具的合理性、個人化、リスクと不確実性、生活やアイデンティティの断片化も日常的に実感できます。現代では、容易に移動し、誰とでも簡単にコミュニケーションを取り、物の買い替えサイクルも短くなりました。
次々と新しいものを取り入れ、生活テンポも加速しています。物事に合理的に取り組み個人を尊重する一方で、将来への不安を感じ、生活が断片化し、場面によって異なる顔を使い分けるようになっています。 リキッド消費に対応するため、現代市場では消費者の負担を軽減し「手軽さ」を提供するさまざまな仕組みが発達しています。
これには、①製品選択を簡易化する仕組み、②購買・支払い手続きを簡略化する仕組み、③使用を容易にする仕組みが含まれます。①と②は買い物行動を、③は使用行動を手軽にするためのものです。
リキッド消費の特徴として久保田氏が挙げる「短命性」「脱物質」「アクセス・ベース」はいずれも現代社会を反映しています。
「短命性」はSNSの普及により常に新しい情報に触れる環境が生まれ、商品やサービスへの関心が長続きしにくくなった状況を示します。「脱物質」は若者を中心に物質的豊かさより経験や体験を重視する傾向を意味し、「アクセス・ベース」はサブスクリプションやシェアリングエコノミーに見られる、所有ではなく必要時に利用する消費形態を指します。
リキッド消費の背景には、「生活のジャスト・イン・タイム化」「興味のパケット化」「一時的所有」「不即不離」という4つの現象があります。
「生活のジャスト・イン・タイム化」は、大量の物や情報を抱え込まず、その時に必要なものだけを入手し消費する傾向です。これにより状況に応じた臨機応変な対応と欲求の即時的満足が可能になります。
「興味のパケット化」は複数の興味や関心が小分けにしていくつも存在する状態で、深く掘り下げずに多様な関心を持つことで限られた時間内でさまざまな体験を楽しむことができます。
「一時的所有」は、メルカリやYahoo!フリマなどのプラットフォームを通じて売却することを前提に購入する行動を指します。このような消費者は後日の売却価格を考慮して購入するため、価値の下がりにくい製品を好む傾向があります。二次流通システムはリキッド消費環境の拡大とともに充実してきたため、「売ることを前提に買う人」はリキッド消費時代を象徴する存在といえます。
「不即不離」は、リキッド・モダニティやリキッド消費の進展により人間関係やブランド・企業との関係が希薄化する中で生まれる、「しがらみは嫌だがひとりも嫌」という矛盾した感情を解消するための関係性です。これは密着せず適度な距離を保ちながら、多くの相手と浅く付き合う関係であり、SNSなどのデジタルコミュニケーションによって容易になりました。
リキッド消費世代のマーケティングとは?
もし「寝かせる」ことなくすぐに購入してしまえば、「好き」という気持ちを維持できなくなったときに、失敗や後悔といった感情が生まれるでしょう。こうしたネガティブな感情を避けるために、彼・彼女らは、自分の気持ちに「確信」が得られるまでの少しのあいだ「寝かせる」ようなのです。数多くの選択肢が流れてくる状況で、間違いを犯さないために確信が生まれるまで購買を控えるという現象は、理にかなった行動だと考えられます。
現代の若者の消費環境において「寝かせる」という購買前の熟考プロセスが重要な意味を持つようになっています。消費者は衝動的に購入せず、一定期間「寝かせる」ことで自分の気持ちを見極め、本当に欲しいものかどうかを慎重に判断するようになりました。この行動パターンには深い心理的根拠が存在します。
即座に購入してしまうと、後に「好き」という感情が薄れた際に失敗感や後悔といったネガティブな感情を経験するリスクがあります。これを回避するために、消費者は自分の気持ちに「確信」が得られるまで意図的に購買を保留します。
特に選択肢が無数に存在し、次々と新しい商品やサービスが登場する現代社会では、誤った選択を避けるためのこの「寝かせる」行為は非常に合理的な消費行動といえるでしょう。多くの消費者は瞬間的な買い物にはリスクが伴うと認識しています。
リキッド消費傾向の強い人には「失敗したくない」という気持ちがある。
リキッド消費の傾向が強い消費者の心理には、一見矛盾する二つの特徴があります。一方では「失敗したくない」という強い慎重さを持ちながら、もう一方では「多様な商品を試したい」という好奇心も併せ持っています。この相反する心理を理解することが、効果的なマーケティング戦略の鍵となります。
「リキッドクラスター」と呼ばれるこの消費者層は、多様な消費体験を通じて様々な商品やサービスを楽しみたいという願望を持っています。新しいものへの好奇心が強く、トレンドに敏感である一方で、選択や購入にかかる時間や労力は最小限にしたいと考えています。
そして何より「間違った選択」をすることへの不安が大きいという特徴があります。つまり、「たくさん試したいけれど失敗はしたくない」「効率的に選びたいけれど後悔はしたくない」という、一見相容れない願望を持っているのです。
このような消費者の「失敗したくない」という心理に応えるためには、商品の本質的価値を一目で理解できる視覚的な陳列が効果的です。複雑な特徴を簡潔に伝える説明文や「あなたにはこれがおすすめ」という明確な提案、商品同士を簡単に比較できる情報提示方法、用途や目的別のわかりやすいカテゴリー分類などを工夫することで、消費者は短時間で自信を持って選択できるようになります。
企業はリキッド消費者の「時間を無駄にしたくない」という意識に応える必要があります。購入までの障壁を徹底的に取り除くことが鍵となります。具体的には、ワンクリックで買い物が完了するシンプルな仕組みや、説明書なしでも直感的に使える商品設計が効果的です。
自宅や職場、コンビニなど好きな場所で受け取れる配送オプション、スマホ一つで簡単に契約・解約・変更できるサブスクサービス、面倒な手続きなしでスムーズに返品・交換できるシステムなどを整えることが重要です。こうした煩わしさの排除により、消費者は複雑な手続きにストレスを感じることなく、「本当に欲しいもの」の選択に集中できるようになります。
また「失敗への不安」を軽減するために、選択に自信を持たせる社会的証明も有効です。「みんなが選んでいる」というランキング情報や専門家による信頼できるレビュー、第三者機関からの認証や評価、実際の使用者による生の声、SNSでシェアしやすく反応が得られる仕組みなどの「お墨付き」を提供することで、消費者は自分の選択に確信を持ちやすくなります。
「慎重に選びたい」という気持ちを尊重するためには、熟考をサポートする丁寧なコミュニケーションも欠かせません。押し売りではなく検討を助ける情報提供を心がけ、商品スペックだけでなく使用感や生活への影響も伝えることが大切です。
さらにブランドストーリーや企業理念を通じた感情的つながりの構築、購入後のサポートや使い方提案も含めた長期的関係性の構築など、消費者の熟考プロセスを「無駄な時間」ではなく「価値ある選択の過程」として尊重することで、信頼関係が生まれます。
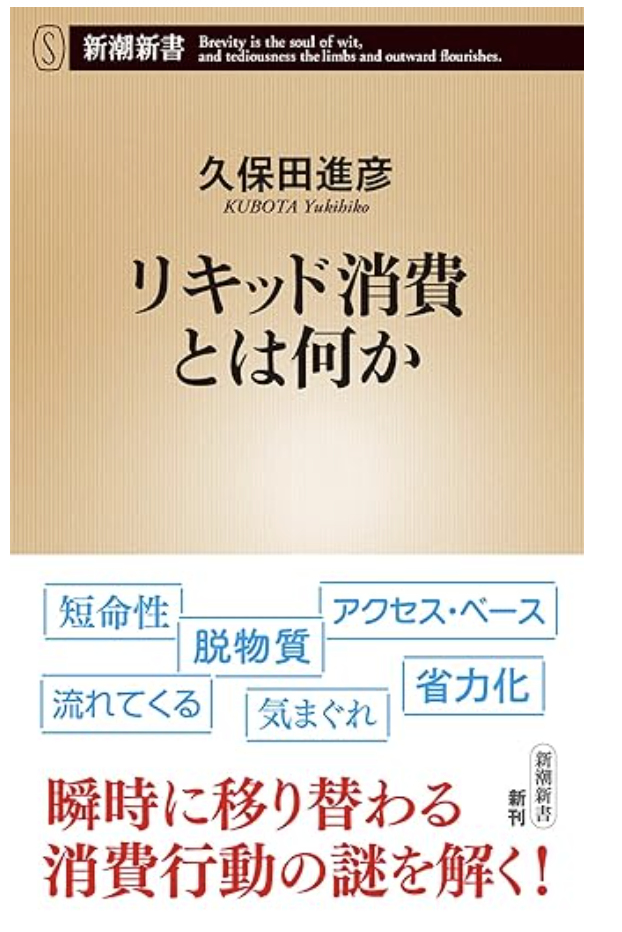







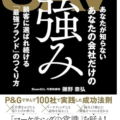



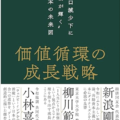






コメント