BRAIN BOOST(ブレイン・ブースト) 脳を変える究極のマインドセット
デビッド・ロブソン
二見書房
BRAIN BOOST(ブレイン・ブースト) (デビッド・ロブソン)の要約
『BRAIN BOOST』は、期待や信念が脳のパフォーマンスや健康に与える影響を科学的に解き明かす一冊です。著者は、成長マインドセット、セルフディスタンシング、セルフコンパッションという3つの習慣を提案し、脳の可塑性を活かして人生を豊かにする方法を紹介しています。これらを実践することで、ストレスに強くなり、自己成長の加速が期待できます。内面の習慣を整えることが、より充実した生き方への鍵となります。
脳の期待効果をポジティブにしよう!
脳の「期待効果」が、健康状態、体重の増減、ストレスや不眠による短期的・長期的な結果などにも影響を及ぼす。(デビッド・ロブソン)
イギリスの科学ジャーナリスト、デビッド・ロブソン氏によるBRAIN BOOST(ブレイン・ブースト) 脳を変える究極のマインドセットは、脳の可能性についての私たちの固定観念を覆す一冊です。本書では、単なるポジティブ思考や自己啓発にとどまらず、「期待」という心理的要因が脳のパフォーマンスにどのような影響を与えるかを、科学的なエビデンスをもとに明快に解き明かしています。
なかでも注目すべきは、「期待効果」に関する多くの研究とケーススタディが紹介されている点です。人が抱く信念や予測が、健康状態、認知機能、さらには日常的な行動選択にまで影響を及ぼすという事実は、自己認識が生理的なパフォーマンスさえ左右し得ることを示しています。
たとえば、不眠に関する研究では、非常に対照的な2つのタイプが登場します。ひとつは「グッドスリーパー」と呼ばれる人々で、実際には十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、「眠れていない」という思い込みによって、日中に疲労感や集中力の低下を感じやすくなります。
これに対し、「バッドスリーパー」は実際には睡眠不足であっても、不安を感じないためにパフォーマンスの低下が少ない傾向があります。つまり、「眠れたかどうか」以上に、「どう感じているか」が脳の状態に大きく影響するということです。
なかでも特筆すべきは、老化プロセスに関する研究です。高齢期をポジティブに捉えている人々は、老いをネガティブに結びつける人々と比べて、難聴や身体的虚弱、慢性的な病気の発症率が低く、アルツハイマー病のリスクも顕著に下がることがわかっています。これは、心理的な期待が生理的な健康状態にまで波及することを意味しており、「年齢は気持ちしだい」という言葉が、単なる比喩ではないことを裏付けています。
さらに、自己成就的予言の効果も見逃せません。これは、ポジティブな予測に限らず、ネガティブな思い込みも含め、知的な活動における記憶力や集中力、創造性、疲労感にまで影響を及ぼすとされています。言い換えれば、脳の働きは「客観的な状態」だけではなく、「主観的な捉え方」に大きく依存しているのです。
実際、長年にわたり固定的な能力とされてきた「知能」ですら、期待や予測によって向上したり低下したりする可能性があるという研究結果も示されています。このような発見を受けて、一部の神経科学者たちは、脳の本質的な限界に疑問を呈しはじめています。
彼らは、「適切なマインドセット(思考パターン)を育むことで、人は自身の中に眠る精神的能力を開放できるのではないか」と考えており、この視点は仕事や学習、ストレス下での意思決定といった現代人の課題にも直結しています。
心理学者ロイ・バウマイスターが提唱したこの概念は、人間の意志力や集中力は有限であり、筋肉のように鍛えることができるという理論です。日常の中で小さな自己制御――たとえば姿勢を正す、間食を控える――を意識的に取り入れることで、より大きな自己管理能力や忍耐力が養われるとされています。
しかし、著者のロブソンは、最新の研究を通じてこの「自我の消耗」という考え方を再定義しています。ウィーン大学の心理学者ベロニカ・ジョブの研究によれば、意志力の枯渇は「リソースが有限である」という信念によって引き起こされる部分が大きいのです。
実際に、「自我のリソースは限られている」と信じている人は、より早く疲労を感じやすく、「リソースは豊富にある」と信じている人は、高い集中力とパフォーマンスを持続できるという結果が示されています。
このように、「自我の消耗」は生理的な現象というよりも、認知的・心理的なものとして捉えるべきだと著者は述べています。興味深い例として、甘い飲み物を「口に含む」だけで集中力が回復するという現象があります。これは、「これからエネルギーが供給される」という期待が脳を活性化させるためと考えられています。 こうした知見は、私たちの行動選択にも応用可能です。
脳のリソースが無限である、脳には十分なエネルギーがあると信じることが、実際に認知能力や集中力の向上に寄与するという実験結果も紹介されています。このような信念が、自己成就的予言として働く可能性は十分にあります。
また、過去の体験を振り返ることも効果的です。たとえば、難しい課題を乗り越えた後に感じる達成感や、夢中になって夜更かしした読書やゲームの記憶は、意志力や集中力が尽きるものではないことの証拠とも言えます。これらの体験は、「自我の消耗」という感覚が、時に思い込みであることを教えてくれます。
人生を豊かにする3つのテクニック。脳を鍛え、心を整える習慣とは?
自分の脳は「発展途上」であることを忘れないようにしよう。
著者は、人生を豊かにする3つのテクニックを明らかにしています。
①「脳は発展途上」であることを意識する
私たちの脳は、年齢に関係なく変化し続け、成長する力を持っています。この性質は「脳の可塑性」と呼ばれ、学習や経験を通じて神経回路が組み替えられることを意味します。 この事実を知るだけでも、自分に対する見方が大きく変わります。「どうせ自分は変われない」と思っていたことが、実は脳の働き次第で改善できる。つまり、自分自身の可能性に対して希望が持てるようになるのです。
私が脳科学は人格を変えられるか?(エレーヌ・フォックス著)を読んだのは10年前のことです。それ以来、読書というインプットと、ブログというアウトプットを習慣化するようになりました。学んだことを言語化することで、より深く理解が定着し、脳が活性化される感覚を実感しています。(エレーヌ・フォックスの関連記事)
特に大切なのが、「成長マインドセット(Growth Mindset)」を持つことです。これは、「失敗しても大丈夫。それは学びのチャンスだ」と捉える思考法であり、自己成長を加速させてくれます。どんな困難にも前向きに取り組めるようになるため、キャリアや人間関係、学習や挑戦など、人生のあらゆる場面で力を発揮します。
この考え方を提唱したのが、スタンフォード大学の心理学教授 キャロル・S・ドゥエックです。彼女の著書マインドセット「やればできる! 」の研究では、マインドセット(心の持ちよう)が私たちの行動、感情、ひいては人生そのものを大きく左右することが紹介されています。キャロル・S・ドゥエックの関連記事
ドゥエックは、多くの経営者や教育現場の実例を通じて、「Growthマインドセット(しなやかマインドセット)」を持つ人々が、より高い成果を出し、持続的な努力を継続できる傾向があることを明らかにしました。反対に、「固定マインドセット(Fixed Mindset)」の人は、失敗を恐れ、挑戦を避けてしまう傾向があります。
このように、「脳は今この瞬間も発展途上である」という認識を持ち、意識的に鍛えていくことができるという姿勢こそが、自分を次のステージへと進める鍵になるのです。 人生をよりポジティブに、自分らしく生きるために。成長マインドセットを育てることは、脳と心の両面を豊かにする最初の一歩となるでしょう。
②外からの視点を取り入れる(セルフディスタンシング)
現代は、ストレス社会とも言われる時代です。仕事、人間関係、将来への不安……さまざまな要因が私たちの心を圧迫します。そんな中で注目されているのが「セルフディスタンシング(自己距離化)」というメンタルスキルです。
これは、自分自身を第三者の視点から見つめることを意味します。たとえば、自分の悩みを友人が抱えていたとしたら、どうアドバイスするかを考えてみる。その視点をそのまま自分に向けることで、過剰な感情の波から距離を取ることができます。
このテクニックの魅力は、「リフレーミング(再解釈)」が自然にできるようになる点です。つまり、ストレスや困難な状況を脅威ではなく挑戦や学びの機会として捉え直せるのです。これにより、思考がより建設的かつ柔軟になり、ストレスへの反応もポジティブに変わります。
③自分に優しくなる(セルフコンパッション)
「自分を変えたい」と願うとき、つい完璧を求めてしまいがちです。しかし、変化や成長には時間がかかります。そして何より大切なのが、「自分に対する優しさ」を忘れないことです。 これを心理学では「セルフコンパッション(自己への思いやり)」と呼びます。
自分の失敗や弱さを責めるのではなく、受け入れ、寄り添う姿勢です。これにより、自己批判からくるストレスや落ち込みを減らし、精神的な回復力(レジリエンス)が高まることが研究でも明らかになっています。 特に大切なのは、失敗を「自分だけの問題」と思わないことです。
誰もが何かしらの困難を抱えており、それは人生の一部です。他者との共通点を意識することで、孤独感が和らぎ、視野も広がります。 また、セルフコンパッションを持つことで、「自分の成功」にも素直に喜べるようになります。これは自己肯定感を高め、行動のモチベーションを長期的に保つ上で非常に重要です。
私自身、以前はミスをすると過剰に落ち込んでしまう傾向がありました。しかし、自分に優しく接する習慣を取り入れることで、リカバリーが早くなり、前向きな気持ちを保てるようになりました。
人生をより豊かにするためには、外的な要因を変えるよりも、内面の習慣や視点をアップデートすることが近道です。
・脳は常に成長できると信じること(成長マインドセット)
・自分を客観視する力を身につけること(セルフディスタンシング)
・自分に優しくなる習慣を持つこと(セルフコンパッション)
この3つを意識的に取り入れることで、日々のストレスに強くなり、自己成長のスピードも確実に加速します。そして何より、「脳は変われる」「自分は成長できる」という期待効果がポジティブに働くことで、行動の質や思考の方向性が大きく変わっていきます。
どれも一朝一夕で身につくものではありませんが、今日から少しずつでも、これらの習慣をあなたの生活に取り入れてみてください。脳と心の使い方を変えることが、人生の質を大きく変える第一歩になります。
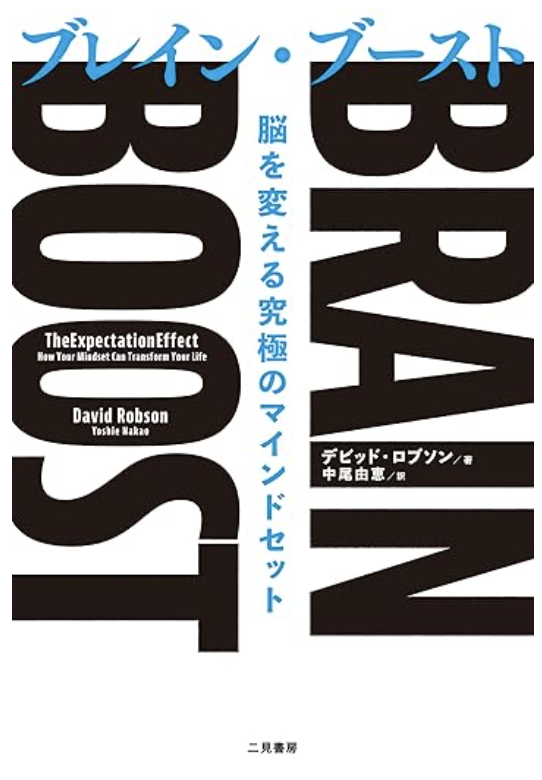


















コメント