シン日本流経営 成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」
名和高司
ダイヤモンド社
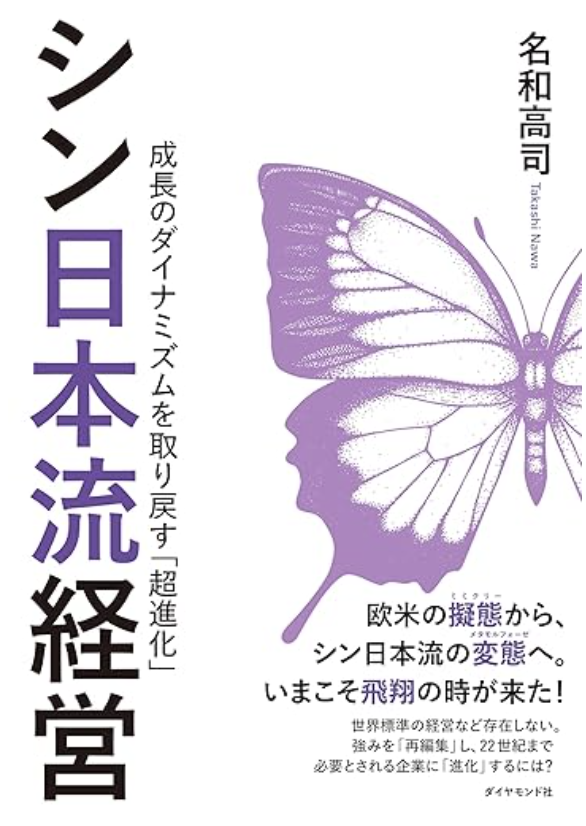
シン日本流経営 成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」(名和高司)の要約
シン日本流経営は、日本の伝統的な強みを現代的に再定義し、グローバルな文脈の中で新たな価値を創造する未来志向の経営モデルです。パーパス・プリンシプル・プラクティスの三位一体により飛躍的成長を目指し、異質な要素を結びつける二項動態によるイノベーション創出を行います。利他心・人基軸・編集力を掛け合わせながら、社会的価値と経済的価値を両立する経営が、これからの企業の鍵となるのです。
シン三位一体企業を成長させる!
パーパス、プラクティス、プリンシプルの3つのPを、筆者はエシックス(倫理)経営の「シン三位一体」と名付けている。(名和高司)
日本企業が再び世界で存在感を高めるためには、どのような経営哲学が必要なのでしょうか。名和高司氏のシン日本流経営は、平成の「失われた30年」を超え、本来の強みを再発見し、それを現代的にアップデートすることで、新たな成長軸を築く可能性を探究しています。
現在、多くの企業が「パーパス・ウォッシング」という罠に陥っています。パーパスを掲げながらも、それが実際の経営や現場の行動に落とし込まれていないため、形骸化してしまうのです。
この問題を乗り越えるために名和氏が提案するのが、エシックス(倫理)経営を基盤とした「シン三位一体」のアプローチです。すなわち、パーパス(Purpose)、プリンシプル(Principle)、プラクティス(Practice)の三要素を有機的に結びつけることにあります。 まず、企業は明確なパーパスを掲げる必要があります。
パーパスとは、企業の存在意義や未来の「ありたい姿」を描くものであり、現状の延長線上にない高い理想を示すことが重要です。掲げるだけで行動に結びつかなければ「額縁パーパス」となり、組織変革の力を持ちえません。パーパスを単なるスローガンに終わらせず、企業文化として組織全体に根づかせることが不可欠です。
このブログでも、シンギュラリティ大学が提唱するMTP(Massively Transformative Purpose)の重要性について繰り返し紹介してきましたが、著者もまた同様に、大きな志が企業変革を本質から支えると指摘しています。 日本企業もいまこそ目を覚ますべき時です。
次に、パーパスを現実に引き寄せるためには、プリンシプルを明確にしなければなりません。プリンシプルとは、どのような価値観を優先し、何を譲らないかという行動原理であり、日々の判断や行動を導く羅針盤です。現実には、株主、顧客、社員といった多様なステークホルダーの間で利害が衝突する場面が少なくありません。そんなとき、組織が迷わず善を選び取るためには、ブレないプリンシプルが必要なのです。
そして、パーパスとプリンシプルを絵に描いた餅にしないために欠かせないのが、プラクティスです。プラクティスとは、日々の業務における実践そのものです。どれほど高尚な志を掲げ、立派な行動原則を設けたとしても、現場で実行されなければ意味がありません。理念は現場での「身体知」として定着し、一人ひとりの行動にまで落とし込まれてこそ初めて価値を持ちます。
エシックス経営は、従来のコンプライアンス型アプローチとは対極に位置づけられます。コンプライアンスが「悪いことをしない」ための外部制約であるのに対し、エシックスは「正しく善いことをする」ための内発的な行動動機に基づいています。
理念と実践をつなぐ枠組みとしてのエシックスは、企業が社会の中で真の存在意義を発揮するための不可欠な基盤となります。パーパスという高い志を掲げ、それをプリンシプルという行動原理に落とし込み、さらにプラクティスという日々の実践に結びつけていく。この「パーパス・プリンシプル・プラクティス」の三位一体の循環こそが、企業の飛躍的成長を支える原動力になるのです。
私はここに、CSV経営(Creating Shared Value)の精神が重なると考えます。単なる利益追求ではなく、社会的価値の創出と経済的価値の創出を両立させる視点が、いま日本企業にとって必要不可欠になっています。社会課題をビジネス機会と捉え、持続可能な成長を目指すことが、これからの経営の大きなテーマであると確信しています。 デジタルによる分断ではなく、「あわせ」「結ぶ」という発想が求められます。
文化(ソフト)を文明(ハード)へと落とし込み、さらに海外の現地文化に根づかせていく。このプロセスこそ、シン日本流経営が目指すべき道筋です。単なる外部展開ではなく、文化的コンテクストを深く理解し、それを土台にグローバルビジネスを再構築していくことが重要です。
この「シン日本インサイド」への挑戦が、これからの日本企業に求められています。 エシックスに基づく経営、すなわちパーパスを掲げ、プリンシプルで行動を律し、プラクティスで実践を積み重ねていく循環を回していくことが、これからの企業にとって不可欠です。
それにより、CSV経営を超えた「シン日本流エシックス経営」が実現され、日本企業が世界の中で再び輝きを取り戻すことができるようになるという著者の考えに共感を覚えました。
著者は、「守破離」の精神を経営に応用することを提言しています。まず型を身につけ(守)、型を破り(破)、そして新たな創造を生み出す(離)というプロセスを、企業の進化の流れに重ね合わせているのです。私自身も、イノベーションは単なる破壊ではなく、伝統や基本を深く理解した上に成り立つべきだと確信しています。しっかりと「守り尽くす」ことで、真の創造が生まれるのです。
また、本(基本)を忘れるなという教えが、現代の企業経営においても極めて重要な指針となると著者は指摘しています。ここでいう「本」とは、利他心(Altruism)、人基軸(People-Centric)、編集力(Editing Power)を指します。私もこの考えに深く共感しています。
利他心とは、自社の利益のみを追求するのではなく、社会全体の価値創造を志向する姿勢を意味します。人基軸は、人間を経営の中心に据え、社員一人ひとりの成長と幸福を起点に組織を進化させる考え方です。そして編集力は、異なる要素を柔軟に組み合わせ、新たな意味と価値を生み出す力を指します。
これら三つの「本」を掛け合わせることで、企業は単なる部分最適を超え、全体としての革新を実現することができます。私は、利他心に根ざした人基軸経営と、編集力による価値創造を両輪とすることで、日本企業は未来に向けた持続可能な成長を確実に手にすることができると確信しています。
今こそ、基本に立ち返りながら、時代に応じた柔軟な進化を遂げるべき時です。本質を守り抜き、そこから革新を生み出していく。このアプローチこそが、シン日本流経営の核であり、次なる成長への確かな道筋であると考えます。
組織力を高めることが重要な理由
組織能力=αβΣ(P)
著者は、「統治から自治へ」と「人的資産から組織資産へ」という転換を図ることが重要だと指摘します。統治(ガバナンス)という上から目線の外圧では経営の中身は本質的には変わらず、セルフガバナンス(自治)こそが目指すべき姿だと言うのです。
そして人的資本への投資だけでなく、人財が桁違いに成長し一体となって桁違いの成果を上げる組織資産への投資が重要なのです。 この組織資産の強化について、名和氏は「組織能力=αβΣ(P=人財)」という方程式を提示しています。
この数式には、組織の成長を支える本質が、ぎゅっと凝縮されています。 まず、αはソフト要件を指します。これは組織の価値観や文化を形づくる要素であり、3つのP、すなわち存在意義を示すPurpose(パーパス)、行動原則となるPrinciple(プリンシプル)、そして日々の業務や行動様式を指すPractice(プラクティス)で構成されます。
これらは単なるスローガンではありません。組織の血肉として、社員一人ひとりの行動にまで深く浸透していなければならないのです。
次に、βはハード要件です。組織の仕組みや制度といった「骨格」にあたる部分を意味します。ここで特に重視すべきなのが、組織学習力とエンゲージメント力です。組織学習力とは、個人が持つ知識やスキルを組織全体で共有し、常に進化し続ける力。属人的にとどまらず、知見を全体の資産に変えることが求められます。
そしてエンゲージメント力とは、社員が命令を待つ存在ではなく、自らの意志で組織に主体的に関与し、貢献していく力です。意欲ある個の力が、組織の推進力を何倍にも高めるのです。経営者は個々のメンバーではなく、組織力を高めることに注力すべきです。
さらにΣ(P)は、個々の人財の総和を示します。ここで強調すべきは、単なる「人数」ではないということです。一人ひとりが持つポテンシャル、意志、スキルをどれだけ引き出し、掛け合わせることができるか。それによって、組織の総合力はまったく別次元へと進化します。 この方程式を意識的にブーストさせることで、組織は単なる直線的な成長を超え、指数関数的な成長を実現することができるのです。
本書ではさまざまなケースが紹介されていますが、ここではダイキンとカネカを取り上げます。100年企業であるダイキンは「人基軸」と「実行力」という静的DNAを基軸として「先見力」という動的DNAを起動させることで未来へとピボットすることで、飛躍的な成長を続けています。
また、ダイキンが長期にわたって成長を続けてきた秘訣は、高い先見性、実行力、そして従業員の人間力の高さにあり、ここにシン日本流経営の元型を見ることができると名和氏は指摘しています。
一方、カネカの経営改革モデルは三層構造で説明されています。上層は「経営革新力」であり、それを駆動するのが「リミットレス」という崇高なパーパスです。中間層は成長エンジンにあたる「事業構想力」と「市場開発力」の掛け合わせ。そして下層に位置するのが現場力です。この三層構造を「Xモデル」として経営に埋め込み、着実に実践しているのがカネカの特徴です。
このXモデルは、経営と現場を変革(トランスフォーメーション)しつつ、中央に2つの成長エンジンを埋め込んでクロスカップリングし、学習経験(エクスペリエンス)の蓄積を通じて進化させていく経営モデルなのです。
「二項動態」とは、名和氏が提唱する日本企業のイノベーション創出の鍵となる概念です。これは単に多様性(ダイバーシティ)を重視するだけでは不十分であり、異なる概念同士を有機的に結合させる知恵が必要だという考え方です。
名和氏は、「異」はイノベーションの宝庫であり、ダイバーシティという遠心力を十分に利かせたうえで、インクルージョン(結合)という求心力を発揮させることが、真のイノベーションを生み出すと説いています。私もまた、単なる多様性の寄せ集めではなく、異なる要素を意図的に結びつけ、新たな価値を創造する力こそが、これからの日本企業に不可欠であると確信しています。
思いもかけぬ要素と要素の組み合わせが、これまでにないイノベーションを生み出します。予測不能な出会いからこそ、次の時代を切り拓く革新的なビジネスが誕生するのです。だからこそ、異質なものを歓迎し、それらを有機的につなぎ合わせる組織文化を育むことが、未来に向けた成長戦略の中核であると考えます。
いま日本企業に求められているのは、多様性を形式的に取り入れることではありません。異質性を力に変え、意図的な融合を図り、そこから新たな可能性を切り拓いていく意志と覚悟なのです。
当然、異質なものを単に並べるだけでは十分ではありません。それらを融合させ、掛け合わせ、想像を超えた新しい世界を切り拓く。このダイナミックな結合こそが、イノベーション創出の核心であり、企業変革の原動力となるのです。
この異なる要素を組み合わせる「二項動態」の考え方は、「ずらし(差延)」から「つなぎ(融合)」への発想転換を促します。そして「有機と無機の融合」「外部と内部の融合」「過去と未来の融合」といった視点を通じて、異次元の進化を生み出す可能性を秘めています。私は、これこそが日本企業が次の成長曲線に乗るためのブレイクスルーだと確信しています。
もはや、同質性の中で最適化を目指す時代は終わりました。異なるもの同士を恐れず結びつける勇気、異なるリズムを共鳴させる知恵、そしてそこから新たな未来を創造する意志が、これからの経営に求められているのです。
シン日本流の8つの「シン」
シン日本流の「シン」を8段活用させてみる。「深」と「新」、「心」と「身」、「信」と「真」、「進」と「津」の8つである。シン日本流が、空間軸上では開放系として広く外に開き、時間軸上では非線形状に未来を拓く特性を持っていることに気づくはずだ。(名和高司)
本書のタイトルに込められた「シン」には、多様な意味が含まれています。著者はこの「シン」を8つの言葉で展開し、それぞれが日本流経営の特徴を浮き彫りにしているといえます。
まず、「深」は表面的な変化ではなく、深層からの本質的な変革を指します。量から質へ、表層から深層へという転換を通じて、組織の価値観や文化、思考様式にまで踏み込むことが、持続的成長の基盤となるのです。深層からの変革には時間と労力を要しますが、その先にある成果は極めて強固であり、企業の競争優位性を支えるでしょう。
「新」は前例のない新機軸を打ち出す姿勢を示しています。有形から無形への転換を提唱し、既存の資産や技術を活用しつつも、それを超えた新たな価値創造を志向するべきだと説かれています。私も、日本企業が未来に向けた競争力を確保するためには、無形資産、特にブランド力や組織開発力、知財への投資が鍵になると考えています。変化の激しい時代を生き抜くためには、自己革新を常態化する経営が不可欠です。
「心」と「身」は、それぞれ内面的な価値観と実践的な行動を意味し、両者が一致した「心身一如」の状態が理想とされます。理念と実践が乖離せず、価値観と行動が自然に融合している組織こそが、創造的で持続可能な進化を遂げるのです。
「信」は信頼関係の構築を、「真」は真実や本質を追求する姿勢を表します。誠実な姿勢が信頼を生み、その信頼のもとで真実を率直に語り合える組織風土が育まれます。信と真の相互強化のサイクルが、企業の持続的成長を支える柱になるのです。
「進」は、常に前進し続ける動的な姿勢を象徴しています。「静から動へ」という転換を強調し、停滞を避けて進化し続ける重要性を指摘しています。現状維持は実質的な後退を意味する現代において、常に未来を見据えた能動的な企業変革が求められます。私も、環境適応力と未来構想力こそが、これからの日本企業にとって最大の武器であると考えています。
「津」は、世界との交流拠点としての日本の位置づけを示唆しています。著者は日本を単なる出発点や終着点ではなく、世界中の知恵と技術が行き交う「寄港地」として捉えるべきだと提唱しています。私も、今後のグローバル時代においては、「日本発」や「国益第一主義」という枠を超え、異質性を受容しながら共感性を育む経営モデルが不可欠だと感じています。
利他心は「三方良し」や「自利利他」の思想に表れるように、社会全体の価値創造を志向することを意味します。人基軸は、人間中心の経営を推進する姿勢を強調しています。そして編集力とは、異なる要素を柔軟に組み合わせ、新たな価値を生み出す力を指します。
私自身、これからの日本企業にとって、異質な知の融合こそが最大の競争優位になると考えています。異なるものを受け入れ、新たな文脈を創り出す力こそが、これからの企業の未来を切り拓く鍵となるのです。
さらに著者は、「ホーリズム(全体思考)」「ダイナミズム(動的思考)」「アルゴリズム(体系思考)」というシン三種の神器を提唱しています。これら三つの思考様式を総合的に高めることが、シン日本流経営の実現、ひいては持続的成長に直結するのです。
具体的な実践方法として求められるのは、現場の技を徹底的に磨き抜き、それを仕組み化して全社に展開し、志(パーパス)と覚悟を持って内側から企業変革を仕掛けていくことです。特に注目すべきは、変革の原動力が「危機感」ではなく、「志命感」であるという点です。
私も、これまで何度も訴えてきたように、パーパスドリブンな経営こそが、社員一人ひとりの「自分ごと化」を促進し、組織の持続可能な成長を支える原動力になると確信しています。
シン日本流経営は、単なる過去への回帰ではありません。日本の伝統的な強みを未来志向で再定義し、グローバルな文脈の中で新たな成長を実現していく、まさに革新的な経営モデルです。私は強く信じています。日本企業が「失われた30年」を乗り越え、再び世界で存在感を示すためには、シン日本流経営の実践とその発信が不可欠なのです。
パーパス(Purpose)、プリンシプル(Principle)、プラクティス(Practice)というシン三位一体を軸に据え、持続的かつ倫理的な成長を目指すべき時が、いままさに訪れています。未来を切り拓くのは、危機感ではなく、志命感に突き動かされた覚悟ある行動なのです。









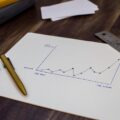






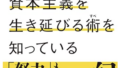
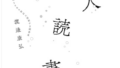
コメント