AIを使って考えるための全技術――「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法
石井力重、加藤昌治
ダイヤモンド社
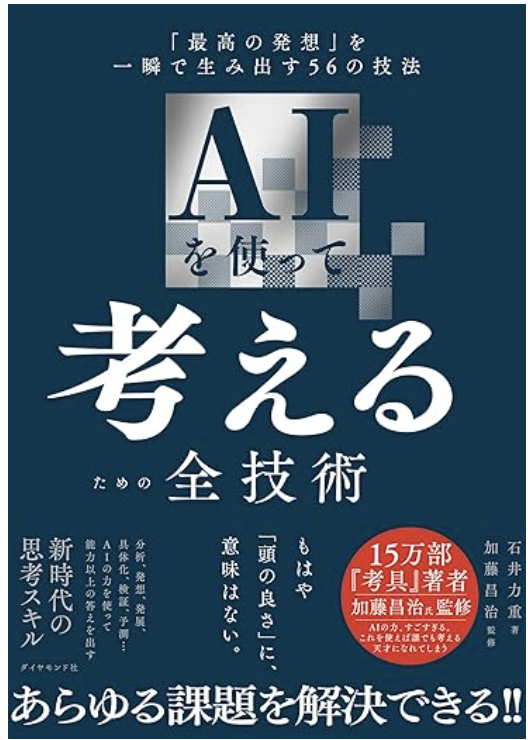
AIを使って考えるための全技術――「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法(石井力重、加藤昌治)の要約
多くのビジネスパーソンが「アイデアが出せない」と悩むなか、創造性を支援するパートナーとして注目されているのがAIです。本書『AIを使って考えるための全技術』では、AIとの対話で発想を広げる56の技法が紹介され、思考の「量・効率・質」を高める実践的なプロンプトが多数収録されています。著者・石井力重氏は、AIを思考を補完する存在と捉え、「人機共想」による創造的なアウトプットを提案しています。
AIがアイデアづくりに向いている理由
多くの「情報」を引っ張り出し、決まった「型」を用いて組み合わせる。アイデア発想の定義であるこの2つの動作は、まさにAIが得意とする作業です。(石井力重)
今、多くのビジネスパーソンが抱えている悩みのひとつに、「アイデアが出せない」という問題があります。会議での新規提案、企画書の立案、マーケティング施策の立ち上げなど、日常業務のあらゆる場面で「何か新しいことを考える」ことが求められているにもかかわらず、肝心のアイデアが思いつかない。もしくは、出てきたとしても平凡だったり、どこかで見たようなものだったりと、自信を持って提出できる案にならない。
そんな焦りや不安が、ビジネスの現場に静かに蔓延しているのが現実です。 情報は過剰なほど手元にあるのに、なぜ発想につながらないのか?その問いに対するヒントを与えてくれるのが、このブログでもお馴染みの広告業界の古典アイデアのつくり方で知られるジェームズ・W・ヤングの言葉です。(アイデアのつくり方の関連記事)
彼は、アイデアとは「既存の要素の新しい組み合わせにすぎない」と定義しました。この一文は、今日でもなお創造に携わるあらゆる職業人の指針となっています。
つまり、アイデアは何もないところから生まれるのではなく、すでに存在している情報や経験、知識といった素材をどう組み合わせるかによって生まれるのです。 そう考えると、アイデアが出せないというのは、素材が足りないのではなく、組み合わせ方が見えていないだけかもしれません。
そして、まさにこの「組み合わせる」という工程を、圧倒的なスピードとスケールで実行できるのが、AIという存在なのです。 AIと聞くと、これまで業務の自動化や分析ツールとしての側面ばかりが注目されてきました。しかし今、注目すべきは「AIを思考のパートナーとして使う」という視点です。発想の補助輪としてAIを活用することで、誰もが創造的になれる時代が訪れています。
そうしたAI活用の可能性を、実践的かつ体系的にまとめたのが、AIを使って考えるための全技術――「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法です。 著者である石井力重氏は、長年にわたり創造工学を研究し、企業や学校で発想法の研修を数多く行ってきた専門家です。本書は、そうした現場で培われた知見をベースに、AIを活用して誰でも思考力を引き出せるように工夫された一冊です。
特徴的なのは、すべての技法に具体的なプロンプト(AIへの指示文)が添えられている点です。読者はそのままプロンプトを使い、ChatGPTのような生成AIに入力するだけで、即座にアイデアの提案を受けることができます。
AIを活用する3つのメリット
「量・効率・質」の3つの面において、AIは私たちの思考を支えてくれます。AIは良きパートナーであり、相棒。AIが使えれば、誰でもクリエイティブな価値を生み出し続けることができるのです。
著者の石井氏は、AIを単なる業務効率化のツールとは見ていません。彼はむしろ、「創造性を引き出すパートナー」としてのAIの可能性を語ります。その視点は、私のように広告会社の現場でアイデアづくりの基礎を叩き込まれてきた人間にとっても、非常に納得感のあるアプローチです。
広告会社では、「アイデアは質より量だ」という考え方が徹底されていました。プレゼンが迫るタイミングになると、決まって上司から飛んでくるのは「すぐに出せ、大量に書け」というストレートなオーダーがきます。ネーミング案でも企画でも、とにかく数を出すことを求められした。大量なアイデアを出すことが当たり前という空気の中で、私は言われるまま、100本、200本というアイデアをひたすら紙に書き出していました。
最初から光るアイデアが出てくることは、ほとんどありません。むしろ、初期に出てくる案の多くは、凡庸でありきたりなものばかりです。けれども、そこに手を動かしながら、地道に要素を組み合わせ続けていくと、不思議とどこかの段階で思考のスイッチが切り替わります。そして、その転換点を越えた先に、ようやく使える発想や独自性のある構想が見えてきます。
私はこれまで何度も、自分の手と目でそのプロセスを体験してきました。初期の案の山からは想像もできなかったような企画が、あとから現れてきます。そうした経験を通して、「量から質へ」という言葉の本質が、単なる根性論ではなく、実務の現場で磨かれた確信として自分の中に刻まれていったのです。
そして現在、その「量を出す」工程において、AIの存在が極めて実用的なパートナーになりつつあります。 石井氏は、AIを創造性の代行者としてではなく、人間の思考を引き出し、補助する装置として捉えています。
そのうえで、AIを活用することの利点を3つの実践的な観点から明快に整理しています。 第1のメリットは、「大量のアイデアを簡単に獲得できる」こと。まさに、あの「まず100本書け」という広告会社のスタイルを、より負担なく、より高速に、そしてより多様性を持って再現できるのがAIです。
テーマや条件を与えれば、AIはブレることなく、迷うことなく、大量の案を生み出し続けてくれます。 しかも、その中には荒削りな中にもアイデアの種があり、意図せず発想の転換点となるような案も少なくありません。量を出しながら、その背後にある飛躍の兆しを見つけにいく。このプロセスは、まさにAIの得意分野です。
そして、まさにこのアイデアを出し続ける工程において、AIは圧倒的な力を発揮します。人間の集中力や体力には限界がありますが、AIは疲れ知らず。テーマを変えても、繰り返しても、迷わず、躊躇せず、次々と案を出してくれます。それは単なる情報の吐き出しではなく、視点や論点をずらしながら、新たな切り口を生み出す、まさに「アイデア発想機」としての働きを見せてくれるのです。
2つ目は、「時間的な効率化ができる」という点です。考える時間がない。アイデアを練る余裕がない。でもアウトプットは求められる。そんな現場は、広告業界に限らず今やどこにでもあります。AIのプロンプトひとつで、数十個の案が一瞬で出てくるという体験は、まさに発想の時短革命です。考えるべきことに集中する時間を生み出す。その効率こそ、AIを使う側の知性が問われる部分でもあります。
そして3つ目は、「アイデアを昇華させられる」ことです。どんなに良さそうなアイデアでも、それを磨き込んで仕上げなければ、提案にはなりません。ここで必要なのは、別の視点、客観的な目、そして時に挑発的な問いかけです。
AIはその壁打ちの相手として非常に優秀です。「この案の弱点は?」「もっと大胆に言い換えると?」「対極の立場から見たら?」といった質問を投げかけるだけで、次の展開が自然と見えてきます。この往来が、アイデアを深化させるプロセスにおいて極めて重要なのです。
この「量」「効率」「質」という発想の三軸は、私が理事を務める一般社団法人 妄想からアイデアを共創する協会でも中心的な考え方となっています。協会では、「妄想アイデアトレーニング=モウトレ」を通じて、質を求める前に量を出す、その重要性をあらためて言語化・体系化しています。
モウトレは、アイデア創出を飛躍させる“共創コミュニケーション”の技術を高めるとともに、既存の思考枠組みにとらわれず、自由な発想が生まれる組織づくりを支援するトレーニングプログラム群です。妄想という言葉に抵抗を感じるかもしれませんが、実はこの“妄想”こそが、誰も見たことのないアイデアの源泉になります。
実はモウトレは、Webアプリケーション「妄想商品マーケット MouMa(モウマ)」から生まれました。MouMaでは、ユーザーが19文字以内で“妄想商品”を投稿し、そこに自由に値段をつけて出品することができます。ここで大事なのは、「要素と要素を組み合わせることで、どんな荒唐無稽にも見える発想が、価値あるアイデアに転化しうる」という体感を得ること。つまり、創造のリアリティを、遊びながら鍛えるのがこの仕組みです。
モウトレは、こうした遊び心と戦略的思考を横断させる設計によって、AIの活用とも非常に相性が良いのです。大量に妄想し、組み合わせ、価値をつけ、アウトプットする。そこにAIを加えれば、思考の速度も、深度も、スケールも一気に変わってきます。 AIは考える力を奪うものではなく、思考の可能性を拡張してくれる存在です。
真夜中でも、時間がなくても、疲れていても、AIは付き合ってくれます。たった一文、プロンプトを打ち込むだけで、次のアイデアが動き出す。そこにモウトレの思考習慣を掛け合わせれば、個人もチームも、アイデア創出における共創力を飛躍的に高めることができます。 これからの時代、「一人の天才のひらめき」よりも、「多くの妄想と協働の仕組み」が価値を生む。その中心に、AIも人も並列に並ぶ未来が、すでに始まっています。
アイデアを生み出すプロンプトとは?
AIが出すアイデアの質は気にする必要はありません。いえ、気にしてはいけません。いったんAIを走らせましょう。あり得ないものも含めて、AIの力を借りてアイデアをゴソッとかき集めるのが先。獲得した玉石混交な選択肢からいいものを選んだり、ヒントを発見したりするのは、人間の方がずっとうまい。そこからが私たちの出番であり、これこそが人機共想なんです。
本書は、2023年に開発された思考支援ツール「JINCA(人機共想カード)」をベースに構成された一冊です。AIとの対話によって発想を拡張するためのカード型ツールの内容を、56の実践的な技法として体系化した本書は、アイデア創出を支えるための“問いの設計書”といえる存在です。
本書の出発点には明確な姿勢があります。それは、AIが出すアイデアの「質」を気にしすぎないということです。最初から正解を求めるのではなく、とにかく大量の素材をAIの力でかき集める。その玉石混交の中から何を選び、どう磨くか。それこそが人間の役割であり、本書が掲げる「人機共想」の本質です。
アイデアの量産だけでなく、構造化、評価、ブラッシュアップといった一連のプロセスにもAIは力を発揮します。 石井氏はこうしたプロセス全体を「人機共想」と呼びます。人と機械が思考を通じて協働し、互いに揺さぶり合いながら、発想を深めていくという考え方です。
従来は手間や時間がかかっていた思考法も、AIを使えばごく短時間で実行可能になります。これまで「面倒だったけれど本質的だった」ことを、スムーズに行えるようにする──そこに、AI活用の真価があります。
紹介されている技法の多くは、実際の創造的思考のプロセスで即座に使えるよう設計されています。たとえば、「この問題から連想できる単語を30個挙げてください。さらに、関連が薄くても構いませんので、連想できる単語を100個挙げてください」といったプロンプトは、AIが思考の材料を大量に提示してくれるきっかけになります。直接的な解決策ではなくても、その語彙の連なりが、停滞していた思考に滑走路を与えてくれます。
私たちの脳は、連想によって刺激を受け、そこから想像が広がり、最終的に創造的な発想へとつながっていきます。この構造は、アレックス・オズボーンがかつて「連想の四法則」として整理した思考の基本モデルと一致します。連想の起点が豊かであればあるほど、次の思考は飛躍しやすくなります。AIはまさにその「連想の起点」として機能します。
もう少し戦略的に視点を変えたいときには、「このテーマについて、次の6つの観点から考えてください」というプロンプトが有効です。人、モノ、プロセス、環境、意味・価値、五感。これらの異なる切り口に沿ってAIに発想を求めることで、自分自身では思いつかない角度からのアイデアを得ることができます。
思考が偏りやすいときこそ、こうした外部フレームの導入が効果を発揮します。 発想を意図的に飛躍させたい場合、「目標を10倍に設定する」という技法も紹介されています。
たとえば、1000万円の売上目標を1億円に引き上げてみる。そして、その非現実的な目標を達成する手段をAIに考えさせてみる。すると、現実的な前提から解放された思考が生まれます。常識の枠に収まっていた思考が、AIの存在によって大胆にずらされる瞬間です。
このように、本書で紹介されている56のプロンプトは、「すぐに使える」「視点をずらせる」「構造化しやすい」という明快な実践性を備えています。さらに、従来の思考技法と組み合わせることで、その効果は一層高まります。
なかでも応用度が高いのが、「異質の取り入れ」という技法です。これは、今取り組んでいるテーマから距離のある異質な概念を意図的に取り込むことで、意外性のある発想を導くものです。たとえば「この課題と距離のあるモノ・コトを7つ挙げてください」とAIに投げかけるだけで、自分の思考領域の外側から要素が引き寄せられます。創造とは既存の要素の新しい組み合わせである以上、「異質さ」は欠かせない資源となります。
さらに、「制約なき発想」も、本書の中で示される強力なアプローチのひとつです。資金、時間、人材、法律など、現実のあらゆる制限を取り払ったうえで、「理想的な手段は何か」とAIに問うことで、人間の思考に染み付いたできない前提を一時的に外すことができます。実現可能性よりも、純粋に「最善」を構想する訓練は、ブレイクスルーの感覚を養うためにも極めて重要です。 未来思考においても、AIとの共創は有効です。
本書では「先見倍歴」という技法が紹介されています。これは、15年後の未来を描くために、過去30年の社会や技術の変化を参照し、その変化量を未来に倍掛けして見立てを立てるというものです。未来は予測できませんが、過去を構造的に捉えることで、未来の仮説は精度を増します。このプロセスにAIを加えれば、仮説の具体性と飛躍性がともに高まります。
SCAMPER法や6W3H、リーンキャンバス、PPCOといった既存のフレームワークも、AIと組み合わせることで一層、有効に機能します。
私たちはAIの力を借りつつ、自らの経験や直感、そして対話を通じて、創造の深淵に挑み続けなくてはならないのでしょう。
AIが出す案に対して問いを返し、さらにそこから展開を加える。その往復運動の中に、真のアイデアは宿ります。 AIは思考を代行するのではなく、思考を引き出す装置です。問いの立て方を変えるだけで、見えてくる景色が変わり始めます。
そして私たちは、AIの力を借りつつ、自らの経験や直感、そして対話を通じて、創造の深淵に挑み続けることで、結果を出せるようになるのです。
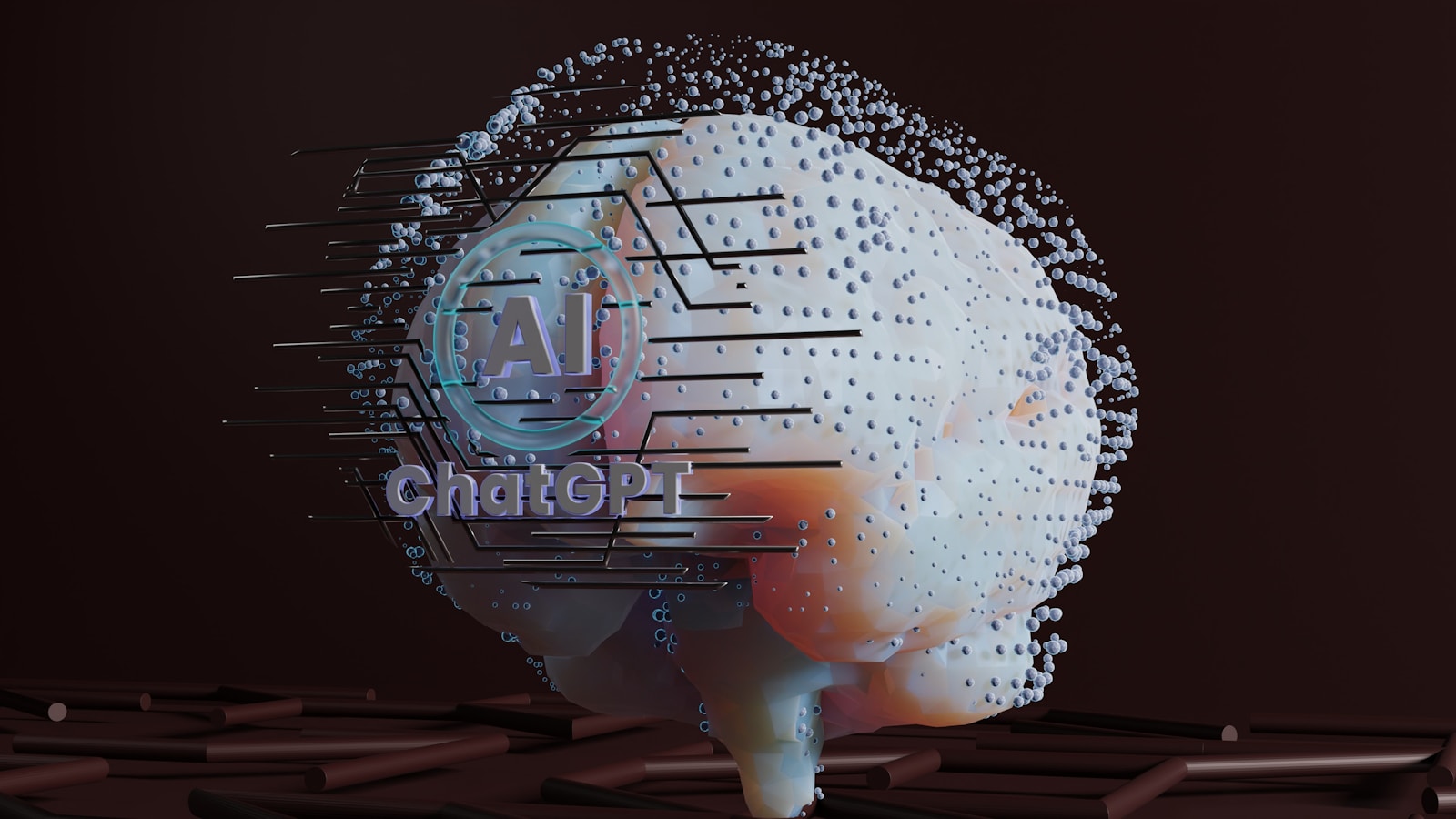









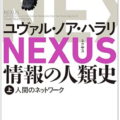
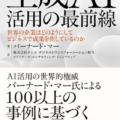
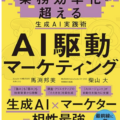
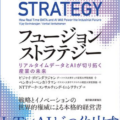



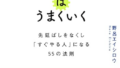
コメント