「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか
三宅香帆
新潮社
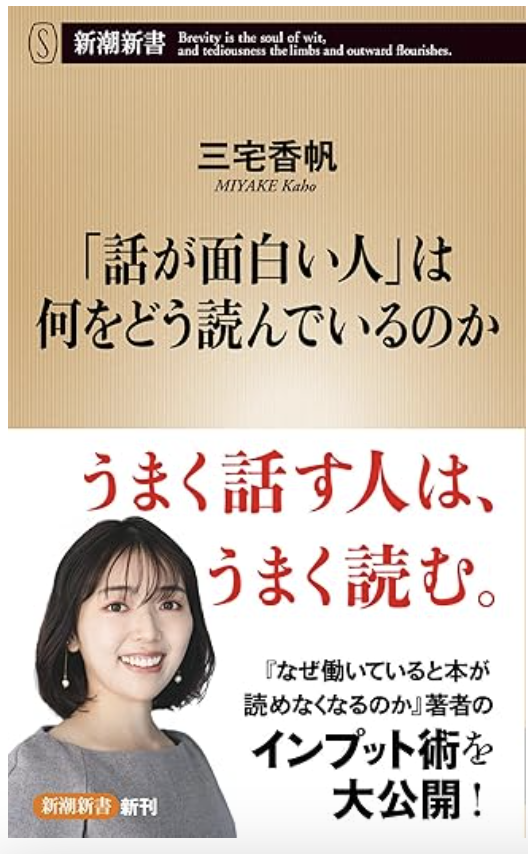
「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか(三宅香帆)の要約
話が面白い人は、特別な話術を持つわけではなく、知識や視点を仕込み、会話の場で自在に編集できる人です。本書は「比較」「抽象」「発見」「流行」「不易」という5つの鑑賞法を提示し、読書がその仕込みとなることを教えてくれます。三宅氏は多様な作品を例に、知識を素材として調理し直すことで、会話が豊かに変わる過程を描き出しています。
話を面白くするための5つの技術
たしかに、常に新しい本を読み、そしてそれをネタとして使っている人は、いつも違う面白い話ができます。それは、アップデートされたものを取り入れているから。(三宅香帆)
話が面白い人には、自然と耳を傾けたくなる魅力があります。私の周りの話し方が上手な人たちは、声に抑揚があり、例え話が巧みで、言葉の選び方にも余裕があります。そうした印象は、単なる話術の巧拙だけでなく、その人が語る世界の奥行きによって生まれているのだと思います。
彼らを見ていると、会話とは即興的なやりとりのように見えて、実は「知識」と「視点」の両軸で成り立っていることに気づかされます。 そこに気づくと、「面白い話ができる人」とはどのような人なのかが、少しずつ見えてきます。話が面白い人は、話題の裏にある「知識の仕込み方」が異なります。
人の話に耳を傾けながら「それは、以前読んだあの本に通じる」と気づいたり、「このテーマなら、こんなふうに話を展開できる」と見通しを立てたりします。
つまり、彼らは他者の話に対して“予習済み”であることが多いのです。人生の出来事や社会の構造について、すでに何らかのインプットをしていて、その材料を文脈に応じて自在に再構成できる。話しながら、頭の中で編集しているのです。
特別な話術を持っていなくても、そうした仕込みができていれば、誰でも話は面白くなります。読書、映画、記事、ドキュメンタリー、SNS。日々の中で出会う情報を、自分の中で寝かせ、発酵させ、言葉に変換する。そのサイクルが習慣化されている人は、話題の引き出しが深く、どのような会話にも厚みをもたらします。
それは教養と呼ぶこともできますが、もっと実践的で、もっと身体に馴染んだものです。話す力は、読む力の副産物として育っていくのです。
会話力や表現力といった“アウトプット”の技術を、「読む」という行為から逆算して構築していく——そんなユニークな発想に基づくのが、三宅香帆氏の「話が面白い人」は何をどう読んでいるのかです。
話すことと読むことは別物だと思われがちですが、実際には深くつながっています。読んだものをどのように理解し、どのように他者に語るか。それを意識して読書を重ねることで、語彙も視点も、語り方そのものも進化していきます。
三宅氏は、そのプロセスを丁寧に言語化しています。 とりわけ本書が興味深いのは、「話す」ための読書に必要な技術を、具体的に5つの視点で整理している点です。
〈比較〉ほかの作品と比べる
〈抽象〉テーマを言葉にする
〈発見〉書かれていないものを見つける
〈流行〉時代の共通点として語る
〈不易〉普遍的なテーマとして語る
これらの視点は、作品をより深く味わうための読み方であると同時に、それを他者に伝える際の“語りの枠組み”としても機能します。読んで終わりにせず、読んだ内容を言語化し、自分なりに咀嚼し、誰かに伝える。その循環の中に、会話力の本質があるのだと三宅氏は説いています。
実際に本書では、こうした技術がどのように実践されるのかを、具体的な作品を通して示しています。『地面師たち』『ドライブ・マイ・カー』『成瀬」シリーズ』『君たちはどう生きるか』といった、ジャンルもテーマも異なる作品を横断しながら、読解の切り口がどう変わり、語りがどのように厚みを増すのかが丁寧に解説されているのです。
また、私の好きな村上春樹にもたびたび言及があり、特に「初期三部作」の主人公たちの老後を想像するくだりには、強く共感を覚えました。作品世界の余白を読者自身が埋めていく、その姿勢こそがまさに「面白く語る」ための視点であると改めて感じさせられます。
日々のインプットで得た情報は、そのままでは素材にすぎません。下ごしらえを施し、適切に火を入れ、味付けを整えて料理となるように、知識も仕込みと調理を経て初めて他者に伝えられる表現へと変わります。会話の面白さも同様で、素材をただ提示するのではなく、その価値を引き出し、相手に届く形に編集することが求められます。
このプロセスが習慣化している人は、話題の引き出しが豊かになり、会話に安定した厚みを与えます。それは一般に「教養」と呼ばれますが、実際には知識を実践的に運用する身体化された能力です。話す力は読む力の副産物として醸成されます。読む技術はそのまま「聞く技術」でもあると著者は指摘します。
インターネット時代の小説の役割
Ⅹを見るまでもなく、インターネットそれ自体は諸行無常だ。常に形を変え、保存されない。しかし小説という形で、人々はインターネットの営みを保存することができる。Twitterはなくなっても、本は残る。書き手たちは本を書く。失われたインターネットを求めて、記憶を保存す するために。インターネットと小説は決して対立しない。相互補完的であることは、きっと可能なのだ。私たちはインターネットも小説も、どちらも楽しんでいる。
たとえば千葉雅也氏の『エレクトリック』や市川沙央氏の『ハンチバック』。2020年代の言語感覚を代表するこれらの作品を引きながら、三宅氏は、インターネット空間で育った書き手たちが小説という形式で自身のネット史を記録しようとしている動きを読み解いています。
SNSで日々更新され、忘れ去られていく言葉たち。Xのタイムラインのように、流れ、消えていく情報。その一方で、小説という形式は、書き手の視点や空気感を時間に刻印し、アーカイブとして残す力を持っています。
文学は、インターネットの儚さを補完するもう一つの言語装置として機能しているのかもしれないと著者は指摘します。私たちは、刹那的なネット文化と、残り続ける文学のあいだを行き来しながら、自分の感覚や記憶をつなぎとめているのです。
さらに本書では、障害を持つキャラクターを中心に据えた文学作品にも言及されています。村木嵐氏の『まいまいつぶろ』、加藤シゲアキ氏の『なれのはて』などがその例です。三宅氏は、これらの登場人物を「自分ではコントロールできないもの」の象徴としながら、物語が描き出す制御不能性に注目しています。
コロナ禍、終わらない戦争、震災──私たちはこの数年で「自分ではどうにもならないもの」の多さを痛感しました。どれほど努力し、貯金を積み、人生設計を描いても、現実は設計図どおりには動かない。そのズレこそが、不安や恐怖を生み出しているのです。
2024年の直木賞候補作に「制御不能な存在」が数多く描かれたのは、まさにこの社会的空気の反映だと著者は述べています。社会は私たちに「人生設計せよ」と迫りますが、現実は設計を裏切ります。小説家たちは、その恐怖を敏感に掬い取り、物語という形式に仕立てて差し出します。
読者はそれを通じて、恐怖を消すのではなく、恐怖を味わい直すことができるのです。いわば小説とは、アンコントローラブルな現実という扱いにくい素材を、調理可能な形に変える装置です。物語を味わうことで、私たちは世界を完全に支配できなくても、自分の不安を和らげる方法を学んでいるのです。
本書には小説、ノンフィクション、漫画など幅広いカテゴリーの作品が登場します。三宅氏の読書案内は、若い世代ならではの感覚を通じて、私がこれまで見過ごしてきた作品の新たな魅力を照らし出してくれます。
特に印象的だったのが、『水車小屋のネネ』の紹介です。「親ガチャ」に外れたと感じるような境遇であっても、主人公・理佐を支えているのは、今この瞬間に自分が取り組んでいる作業を「好きだ」と思える気持ちや、今いる場所に対する静かな愛着です。 人は、生まれる環境や持って生まれた能力を選ぶことはできません。
しかし、それらすべてを含めて「自分の人生」として引き受ける姿勢の美しさが、本作では鮮やかに描かれています。
私自身も、三宅さんのレコメンドをきっかけにこの作品を手に取りましたが、理佐の持つ生きる力、そのしなやかな強さに強く心を惹かれました。
面白い話ができる人は、完成品の答えを差し出す人ではありません。むしろ「わからなさ」や「違和感」という生の素材を、自分の言葉で調理し、他者と共有できる人です。その料理法こそが、相手の知的好奇心を刺激し、記憶に残る味わいとなります。
だからこそ、読書は話すことの下ごしらえになります。話し方のレシピを暗記するよりも先に、まず読むこと。そして得た素材を、自分なりの方法で調理し、語ってみること。その繰り返しが言葉に深みを与え、語り手としての力を磨いていくのです。 読書は、最も確実なコミュニケーションの訓練法であり、この本はその事実を鮮やかに示してくれる一冊です。





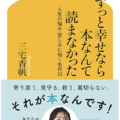











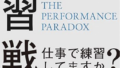
コメント