マッキンゼー リーダーの教室
ダナ・マオール, ハンス=ヴェルナー・カース,カート・ストロヴィンク
ダイヤモンド社
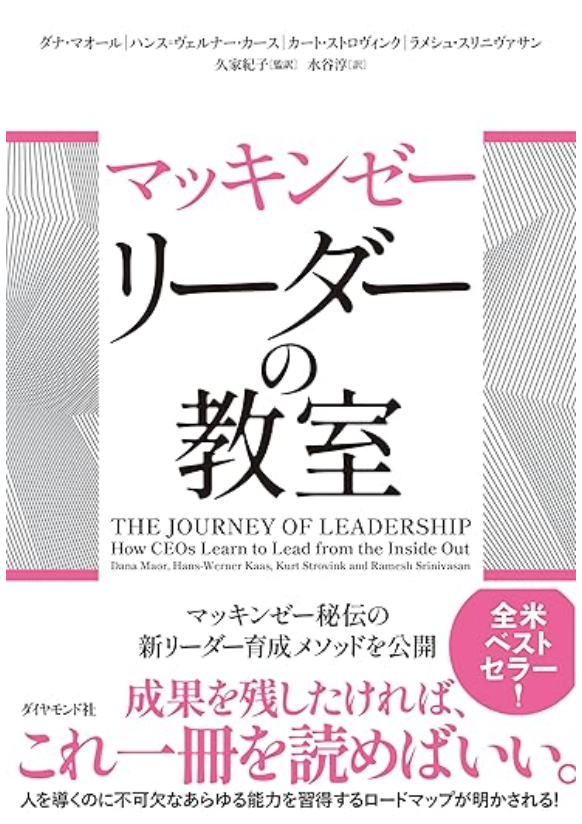
マッキンゼー リーダーの教室(ダナ・マオール, ハンス=ヴェルナー・カース)の要約
リーダーに求められるのは、スキルだけではなく人間力です。謙虚さ、自信、共感、柔軟性、失敗を恐れない姿勢など12の要素が相互に作用し、人を導く力となります。完璧を装うのではなく、弱さを見せながら信頼を築き、目的に向かってチームを動かす。これらを兼ね備えたリーダーこそ、変化の時代に求められる存在です。
リーダーに求められる12の要素
リーダーシップにとって大事なのは、優れたCEOであるために必要な無数の事柄だけではない。自分が1人の人間として何者であるかを意識し、人間としてつねに成長することも大事だ。要するに、自分自身と他者を変えることに他ならない。人間本位のリーダーシップの方法論を取り入れることに行き着くのだ。(ダナ・マオール, ハンス=ヴェルナー・カース,カート・ストロヴィンク)
チームのメンバーが思うように動かない。期待した通りの成果が得られない。リーダーとしての自信が揺らぎ始める――。 現代のビジネス環境において、多くのリーダーが直面する問題は、単なるスキルや知識の不足だけでは説明しきれない複雑さをはらんでいます。目の前の課題を乗り越えるためには、これまでの知識や経験だけに頼るのではなく、自分自身の「人間力」そのものに目を向けることが求められているのです。
どれほど高いスキルを持つリーダーであっても、「なぜ人が動かないのか」「なぜ結果が出ないのか」という壁に直面する瞬間は訪れます。こうした問題に対し、マッキンゼーは単なるノウハウの提供ではなく、リーダー自身が自己改革に取り組む必要性を強調してきました。リーダーシップとは、組織に対して何かを施す以前に、自分自身の内面とどう向き合うかが問われる営みなのです。
実は、CEOの多くがマッキンゼーが主催する「バウワー・フォーラム」のようなイベントに参加する理由の一つは、孤立とどう向き合うかという課題にあります。トップに立つということは、孤独との戦いとも言い換えられます。肩書きが上がるほど周囲との距離は広がり、率直なフィードバックや本音の対話が減っていくことがリーダーの悩みになっているのです。
そのような課題を解決するヒントを与えてくれる一冊が、マッキンゼー リーダーの教室です。本書は、マッキンゼーが世界中のリーダー育成の現場で蓄積してきた知見をもとに、再現性のあるプロセスとして体系化したものです。抽象的な理論にとどまらず、具体的な行動に落とし込むための実践的ケースが数多く紹介されており、知識の獲得を目的とするのではなく、継続的な実践を通じて自己変容を促す構成となっています。
著者たちは、リーダーに求められる内面的な12の要素を提示しています。
・謙虚さ
自分は最も賢い存在ではない。周囲の意見に耳を傾ける姿勢。
・自信
不安を抱えながらも、自分の役割を信じて行動する力。
・無私無欲の心
自分を誇示せず、正しい選択をするための心構え。
・弱さをさらけ出す
完璧を装わず、人としてのリアルを見せる。
・立ち直る力
失敗や挫折から前向きに回復する力。
・柔軟性
状況に応じて考え方や行動を変えられる力。
・目的意識
自分をはるかに超えた目的を持つ。
・大胆な一手
リスクを取ることの意味を説明し、社員に心から協力してもらう。
・権限委譲
部下たちに任せる自主性と間違いを犯す自由を与える。
・真実を語るよう促す
誰もが上司に隠し事をする。部下が安心して本音を話せる空気をつくる。
・失敗を恐れない
挑戦の中で成長する姿勢。
・共感
相手の立場に立ち、気持ちを理解する力
これらの要素は互いに関係し合い、リーダーとしての「人間力」を形づくる土台になります。
リーダーにとって、謙虚さが重要な理由
自分が一番秀でているかのように振る舞うと、恐ろしい結果につながりかねないことは、歴史が証明しているとおりである。
本書が繰り返し強調しているのは、リーダーにとって「謙虚さ」がいかに本質的な要素であるかという点です。リーダーの立場にある人ほど、自分が他者からどう見られているかを正しく理解し、耳を傾ける姿勢を持ち続ける必要があります。
リーダーシップとは、大きな声で指示を出すことではなく、沈黙の中から本音を引き出す力でもあるのです。 多くのリーダーは日々の業務に追われ、自分自身を見つめ直す時間を持てずにいます。その結果、リーダーとしての軸が曖昧になり、信頼関係や影響力が次第に低下していきます。
本書では、このような悪循環を断ち切る方法として、「意図的な内省」の重要性を提案しています。単なる反省ではなく、自分の価値観や行動の背景に意識的に向き合うことで、リーダーとしての在り方を再構築する。まさにそのプロセスこそが、持続的な成長の出発点になると説かれています。
また、本書に登場するのは、理想化された抽象的なリーダーではありません。ビジネスの第一線で成果を上げてきた実在のリーダーたちが直面した葛藤や意思決定のプロセスを通して、よりリアルな知見が語られます。たとえば、自らの限界を正しく見極めながら計画を調整する力、財務目標とステークホルダーの期待を両立させるバランス感覚、安定を保ちつつも必要なリスクを取る判断力など、いずれも現場で求められる実践的な能力です。
さらに、チームを率いるべき場面と、あえて任せるべき場面を見極める判断力、冷静さと人間的な温かみを両立させる感情のマネジメント力など、リーダーに必要な資質は多面的です。
本書では、それらを一つひとつ段階的に習得する方法が解説されています。 現代のリーダーには、相反するように見える資質を同時に持つことが求められます。
・謙虚でありながら、決断力を持つ
・弱さをさらけ出せる一方で、強さを保つ
・慎重でありつつ、大胆に動く
・寛容でありながら、高い基準を貫く
・信念を持ちながら、変化を受け入れる柔軟さを備える。
こうした二面性をバランスよく備えることが、成果と信頼を両立させる鍵となるのです。 とりわけ、CEOのような立場にある人々にとって重要なのは、単なる知識やスキル以上に、広い視野と多角的な思考です。真に優れたリーダーは、点と点をつなぎ、大局をとらえながら、異なる意見にも真摯に耳を傾け、そこから新たな洞察を得ていきます。
自らを一段上に置くのではなく、他者の声を尊重し、慎重に考え、根本的な原因と結果のつながりを深く理解する。そのプロセスにこそ、リーダーとしての成熟が表れます。
今の時代は、顧客、従業員、投資家、地域社会、そして自分自身の家族など、さまざまな利害関係者(ステークホルダー)の視点に向き合わざるを得ない環境です。そこでは、偏見を持たずに他者の声に真剣に耳を傾け、自分の使命を再定義していく力が必要です。
前述したように、優れたリーダーは、「謙虚さ」と「決断力」という一見矛盾する要素を併せ持っています。他者の助言に耳を傾けつつも、最終的には自らの責任で采配を下す勇気を持つこと。そのバランス感覚が、チームを率いる際の大きな強みになります。 リーダーの役割は、合理的な判断(頭)と、共感や信念(心)の両方に訴えかけることです。
計画に現実的な根拠を持たせる一方で、「それは本当に自分たちが成し遂げたいことなのか」「次の世代に何を残したいのか」といった問いを共有し、チームが自発的に動ける物語へと昇華させる必要があります。 著者たちがが提唱する「ポジティブなリーダーシップ」とは、他者の意見を否定せずに受け止め、建設的な対話を通じて新たな視点を引き出す姿勢です。
自分こそがすべての答えを持っていると考えるリーダーは、往々にして耳を塞ぎ、傲慢さや利己的な態度からチームの信頼を失いがちです。対して、真に信頼されるリーダーは、率直な対話を重ね、反対意見にも丁寧に耳を傾け、自らの判断を見直す柔軟さを持っています。そして、その意見に基づいて実際に行動を変えることを厭いません。
他者に頼ることは、決して弱さの表れではなく、よりよい決断に至るための重要な資源です。 本書は、そうした信念のもとに、現代に求められるリーダー像を、理論と実践の両面から描き出しています。
リーダーはあえて弱さをさらけ出せ!
弱さをさらけ出すことは弱点ではない。人を惹きつけて力を発揮するのだ。
「弱さをさらけ出す」という行為は、長らくリーダーの美徳とは対極にあるものとして捉えられてきました。強さこそがリーダーの資質だという固定観念が、無意識のうちに多くのマネジメント層を縛ってきたのです。
しかし本書は、その常識を覆します。 リーダーにとっての「弱さ」とは、無防備になることではなく、自分の限界を受け入れ、他者とつながるための入り口を開くことだと著者たちは指摘します。そこにあるのは、誤魔化しのない誠実さであり、自分らしさへの忠実さです。
つまり、弱さをさらけ出すことは、自分の価値を下げるどころか、むしろ周囲との信頼を築く力へと転化する行為なのです。 リーダーが心を開き、正直で、自分らしくあればあるほど、部下もまたあなたに対して心を開いていきます。
形式的な指示やマネジメントではなく、感情や人間性に触れる関係性がそこに生まれる。結果として、部下はより率直な意見を差し出すようになり、組織内に建設的な対話の文化が根づいていきます。
本書が強調しているのは、弱さを見せることは、実はリーダーが他者から学ぶための態度でもあるという点です。自分の殻に閉じこもらず、他者の声に耳を傾け、必要に応じて取り入れる。その姿勢があるからこそ、組織は一方通行ではない相互作用の場となり、リーダーとメンバーの関係もまた深化していきます。
優れたリーダーは、完璧さを演じる必要がないことを知っています。「わからないことがある」「今は助けが必要だ」——そう率直に口にできる人にこそ、本当の意味での信頼が集まります。なぜなら、その言葉には虚勢ではない人間らしさが宿っているからです。完璧なリーダー像を保つことに必死になるよりも、自分の弱さを受け入れ、それをオープンにできることが、むしろ強さの証だといえるでしょう。
ただし、ここで重要なのは「強さ」と「弱さ」のどちらかに偏ることではありません。リーダーには、その両方を同時に持ち合わせ、状況に応じて適切に使い分けるバランス感覚が求められます。意見が分かれる局面では、腹をくくって最終決断を下す勇気が必要です。
しかしその一方で、自分の判断に固執せず、周囲の声を受け入れ、柔軟に方向修正する謙虚さも欠かせません。 強さだけでは、周囲はついてきません。弱さだけでも、組織は動きません。人としての誠実さを軸に、「必要なときに強くなり、必要なときに心を開く」——その姿勢こそが、リーダーに求められる成熟なのです。
失敗が起こるとたいていの人はそのことを話したがらない。それは自然な反応だ。だが世界がどんどん複雑になり、変化のペースがどんどん速くなるにつれて、失敗はどんどん増えている。キャリアの中で一度か二度失敗を犯さないような人なんて、なかなか想像できない。
優れたリーダーは、失敗すらも価値に変えていきます。どんなに順調に見える人であっても、これまでに痛みや挫折を経験しています。しかし彼らは、その出来事にとらわれることなく、失敗に意味を見出し、自分を見つめ直し、次に進むための糧として活かしているのです。
立ち直りの早い人は、「なぜ自分がこんな目に遭ったのか」と延々と考え続けたりはしません。感情を消耗するのではなく、その出来事の裏にある思い込みや盲点、無意識のクセに意識を向けます。そして、そこから得た気づきをもとに、自分自身を静かに、しかし確実に調整していくのです。
本当に前に進みたいと願うのであれば、ときに立ち止まることも必要です。失敗の中から学びを確実に拾い上げ、それを次の決断に活かしていく。この地道な積み重ねが、人を内面から強くし、やがて周囲から信頼されるリーダーへと成長させていきます。
そして、自らの失敗を学びとして受け入れられる人は、リスクを恐れなくなります。なぜなら、失敗を「終わり」ではなく「始まり」と捉える視点を持っているからです。
ビジョンを実現するためには、挑戦が不可欠です。過去の失敗を受け入れ、学びを自分のものにしたリーダーは、その挑戦に対して自然と前向きになり、結果を出すために必要な一歩を、ためらうことなく踏み出せるようになります。
失敗から学ぶ姿勢は、個人の成長にとどまらず、組織全体の文化にも大きな影響を与えます。リーダー自身が失敗を率直に語り、それをどう乗り越えたかを共有することで、部下もまた安心して挑戦しやすくなります。そこに生まれるのは、恐れではなく、学びを尊重する前向きな空気です。 完璧である必要はありません。
むしろ、失敗を経験した人の言葉にこそ、重みと説得力が宿ります。リーダーとは、すべてを知っている存在ではなく、失敗の中から学び、自らをアップデートし続ける存在なのです。
優れたリーダーの資質・柔軟性とは?
優れたリーダーは3つの柔軟性を持っている。
優れたリーダーの多くは、キャリアの中で意識的に多様な経験を積み重ねています。特定の領域にとどまるのではなく、新しい役割に挑戦し、自らを未知の環境に置くことで視野を広げてきたのです。新しいことを学ぶことに常に前向きで、異なるタイプの人々と関わる中で、多様な価値観や状況に対応する力を育んでいます。
実際、歴史に名を残した革新的な人物たち──たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチやベンジャミン・フランクリンのような人々は、単一の専門性にとどまらず、複数の学問や技術領域にまたがる知識を持ち、それらを組み合わせることで、誰も思いつかなかったアイデアを生み出しました。柔軟であること自体が、創造性の土台となっていたのです。
現代のビジネス環境においても同様に、「柔軟さ」はリーダーにとって不可欠な資質となっています。地政学的リスクの高まり、テクノロジーの急速な進化、サプライチェーンの不確実性、気候変動への対応、そして消費者の意識の変化——こうした複雑で予測困難な状況においては、固定的な思考では乗り越えられません。
環境の変化に応じて自らの考え方や行動を見直し、必要に応じて進化し続けることが求められます。 本書では、その柔軟性を育てるための3つの具体的な行動指針が紹介されています。
リーダーに必要な3つの柔軟性
① 意識的に新しい地位に就く
同じ役割に安住せず、あえて未知の領域に飛び込むことで、自分の枠を広げ、自己理解を深める機会をつくります。
② 常に新しいことを学び続ける
専門外の領域や異なる視点にも関心を持ち、自分の思考や判断をアップデートし続けること。 「あらゆる問題において自分が最も賢いわけではない」と認識することが、学び続ける前提条件となります。
③ 多様な利害関係者と関わる力を持つ
顧客、従業員、投資家、社会、家族──それぞれの声に真摯に耳を傾け、橋渡しする力が、リーダーとしての信頼につながります。
この3つの柔軟性を持つリーダーは、単に変化に適応するだけでなく、組織や社会に新たな価値を生み出すことができます。加えて彼らは、自分自身をよく知り、内側から自分を導く習慣を持っています。
本書では、自分を深く理解し、そこから得た気づきをもとに「人間本位のスキル」を育んだリーダーたちのストーリーも紹介されています。彼らは自己理解を深めた上で、他者と関わり、組織に変化をもたらす実践者です。要するに、心の内側からリードする術を身につけたことで、自分自身を超えて進んでいく力を得たのです。
リーダーとして成功するために必要なのは、ひとつの正解に固執することではありません。むしろ、状況に応じて考え、動き、進化していく「柔らかい強さ」を身につけることなのだと思います。
目的を示さないと部下は動かない。
成功するリーダーは、世界の現実を冷静に見つめる一方で、自分自身の枠を超えたより大きな目的を持っています。 社会で何が起きているのかを的確に捉え、世界を少しでも良い方向に変えていくために、今この瞬間に何が求められているのかを深く理解しているのです。 そのうえで、自分が属する組織の持つ力をどう活かせば、その変化に貢献できるのかを常に考え抜いています。
単に数字や成果を追いかけるのではなく、組織という存在を通じて、社会にどんな価値をもたらせるのかを問い続けているのです。 こうした高い視座がなければ、人は本気で動きません。そして、組織全体を巻き込みながら、持続的な変化を生み出すこともできません。
リーダーに必要なのは、目の前の業績だけでなく、その先にある大義や使命とつながりながら、組織を前へと導いていく力です。 そしてもうひとつ重要なのは、「部下が人生で何を得たいと思っているのか」を真剣に聴くことです。リーダーの役割とは、そうした一人ひとりの目的意識と、会社のビジョンや戦略とをどう結びつけるかを見出すことにあります。
自分と社会、会社と個人、それぞれの目的を重ね合わせることができたとき、チームは単なる労働の集まりではなく、意味を共有する共同体へと変わっていきます。 そこにこそ、リーダーとしての本質的な価値があるのではないでしょうか。
本書は、リーダーシップを理論として学ぶだけでなく、自分自身と向き合い、組織と共に進化していきたいと願うすべてのリーダーに向けられた一冊です。
本書の核にあるのは、「ただ単に成果を出すリーダー」の育成ではなく、「人間力のあるリーダー」の育成です。自分自身の内面を変えることが、組織全体に変革をもたらす。その実感を得られる構成になっており、単なる知識の習得ではなく、日々の実践を通じて真の変化を促す設計がなされています。
読むことで思考が整理され、自分の行動が変わり、やがては、周囲の反応にも変化が現れます。。その循環を生み出すために、本書は有効なツールとなります。時代が求めているのは、人間らしさを忘れずに成果を出す、そんな「本物のリーダー」なのです。











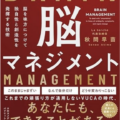


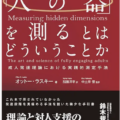



コメント