エビデンスを嫌う人たち: 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか?
リー・マッキンタイア
国書刊行会
エビデンスを嫌う人たち: 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか? (リー・マッキンタイア)の要約
哲学者のリー・マッキンタイアは、科学否定論者の信念を変える鍵はデータではなく、信頼と対話にあると指摘します。人は合理性ではなく、自らのアイデンティティを守る存在であり、説得には共感と敬意が不可欠です。対話を通じて関係を築き、理性と希望を取り戻すことこそが、今私たちに求められているのです。
科学否定論者との対話のための4つの戦略
科学否定論者の信念は、誤情報まみれのイデオロギーに何年も浸りきるなかで強化され、それが彼らのアイデンティティになっていることも少なくない。(リー・マッキンタイア)
科学否定論者の心を変えることは可能なのか──この問いは、単なる知的関心ではなく、今を生きる私たち全員に突きつけられた現実的な課題です。 コロナ禍で広がったフェイク情報、気候変動をめぐる分断、そして制度や科学そのものへの不信。理性への信頼が揺らぎ、社会がポスト真実(Post-truth)の時代に沈み込むなか、科学を信じるという行為すら、もはや政治的立場やアイデンティティに結びつく時代になりました。
哲学者のリー・マッキンタイアのエビデンスを嫌う人たち: 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか?(原書 How to Talk to a Science Denier)は、この混沌の只中で、あえて「対話」という非効率な手段に光を当てた異色の書です。
タイトルを直訳すれば「科学否定論者とどう話すか」となりますが、本書で著者は、根強い否定論者たちと地道に辛抱強く、対話を重ねていきます。 科学の正しさをただ机上で語るのではなく、著者自身が地球平面説(フラットアーサー)の国際会議に参加したり、気候変動否定論者や反ワクチン運動の支持者と直接向き合うなど、現場に飛び込み、耳を傾け、丁寧に言葉を交わしていきます。
その試みから導かれた結論は、驚くほどシンプルで、しかし深いものです。 それは、「筋金入りの科学否定論者の考えであっても、変えることは可能である」ということ。 ただし、それは証拠を突きつけて論破するという意味ではありません。
どれほど多くのデータや根拠を積み重ねても、人の信念は簡単には揺らぎません。なぜなら、人間は本質的に「合理的に思考する存在」ではなく、「自らのアイデンティティを守ろうとする存在」だからです。
著者は、反科学的な信念を抱く人々の現場に自ら赴き、時間をかけて対話を重ねるなかで気づきます。彼らは単に「誤った情報を浴びせられた被害者」ではなく、むしろ「自分が信じたい世界を必死で守っている人」なのだと。ゆえに、「足りない知識を補えば説得できる」という発想では、科学否定論者の思考を変えることはできないのです。
変化をもたらすには、まずその人のアイデンティティに触れ、変化を促す必要があります。 つまり、科学否定を乗り越えるための鍵は、情報の量ではなく、対人関係の質にあります。足りないのは単なるデータではなく、「信頼」なのです。
科学否定者の議論に共通するのは、5つの誤りだと著者は指摘します
・都合のよい証拠だけをつまみ食いするチェリーピッキング。
・あらゆる出来事の背後に意図的な陰謀を見る陰謀論。
・専門家を軽視し、偽の専門家を持ち上げる傾向。
・論理の飛躍による非合理な推論。
・科学に「完璧な証明」を求める不可能な期待。
これらはすべて、信念を守るための心理的な防衛装置として機能しています。理性ではなく、むしろ恐れや孤独が思考を支配しているのです。ここで重要なのは、科学否定を「知性の欠如」として切り捨ててはいけないという点です。むしろ、知的水準が高い人ほど、自らの信念を守るために理屈を巧みに編み上げています。これを「動機づけられた推論」と呼びます。
どれほど大量の証拠を集めたとしても、筋金入りの科学否定論者を説得することは難しいのです。なぜなら、彼らはそもそもその証拠を提示する人や制度を信頼していないからです。
私たちはいま、他者──特に、自分とは異なる意見を持つ相手と、もう一度対話をはじめる必要があります。 そしてその対話には、頭を使い、心を使い、真剣に向き合う覚悟が求められます。 これまで何度も経験してきたように、ただ情報を共有するだけでは、人の心は動きません。
信念が異なるという理由だけで相手を侮辱したり、恥をかかせたりするのは、大きな間違いです。 もし私たちの目標が、相手を説得し、否定的な立場を手放してもらうことにあるのなら、あらんかぎりの共感と敬意をもって対話に臨むべきなのです。
そうした姿勢のもとで初めて、信頼が生まれ、心の距離が少しずつ縮まっていきます。 そのとき、相手は「この人の話なら聞いてみよう」と感じてくれるのです。 その上で、対話をより実りあるものにするために、以下の4つの戦略が有効だと著者は指摘します
①グラフや図表といった視覚的な情報は、相手の理解を助け、感情的な防御反応を和らげる効果があります。
②「科学者の間では広く合意されている」という事実を伝えることも、信頼の補強につながります。
③個人的なつながり──つまり「誰が伝えるのか」は、「何を伝えるか」と同じくらい重要です。 関係性のなかで語られる言葉には、説得力と重みが宿ります。
④相手の主張に対して内容的・技術的に丁寧に反論することも、有効な手段となり得ます。 ただし、それは相手を打ち負かすためではなく、共に考えを深めるための道具として使うことが前提です。
対話とは、論破の場ではなく、理解と信頼を育てるための時間です。 だからこそ、私たちはその時間を大切にし、対話の可能性を信じ続ける必要があるのだと思います。
説得ではなく、信頼とつながりが重要な理由
私たちの認知には、自分の信じたいものを信じるよう私たちを誘惑する強い力が内在している。その力はまた、自分の信じたいものばかりでなく、周囲の人──よく知っていて、信頼もしている人──が自分に信じてほしいと思っているものをも信じさせようとする。
「誰」を信じるかを先に決めてしまえば、「なに」を信じるかも自然と決まってしまいます。ですが、その結果として、他人に操られたり、搾取されたりする危険もまた増しているのです。
だからこそ、本当に大切なのは、「常識」を思い出すことです。どんなテーマであれ、相手に考えを再検討してもらいたいと思うなら、まずその相手を一人の人間として扱うことが欠かせません。
人間として尊重し、話を聞き、彼らの現実や感情に寄り添うことで、驚くほど対話の質が変わってきます。 その際には、もちろん情報の伝え方も極めて重要になります。
単にデータを投げつけるのではなく、まず相手が信じている人や世界観を理解することで、共通の土台を探すことが大切です。そして、相手が信頼している人物や制度、背景を尊重しながら、自分自身も誠実な姿勢で関わるべきです。情報を提示する際には、「もしあなたがそう思ったら、どんな証拠があれば変わりますか?」と問いかけ、自発的な思考のきっかけを促すようにします。
そして何よりも大事なのは、「この人なら話を聞いてくれる」と相手に感じてもらえる信頼関係を少しずつ育てることです。説得を目指すというよりも、相手に再考を促すという心持ちで関わることが鍵となるのです。
マッキンタイアは、行動科学者フィリップ・シュミットとコーネリア・ベッチュの研究を引き合いに出します。従来は「否定論者を反論すると逆効果になる」と考えられてきましたが、彼らの研究はそれを否定します。信念への反論が信念を強化するとは限らない。むしろ、誤った情報を放置するほうが、はるかに危険だというのです。
反論をしないのが最悪の選択肢である。
誰かの信念を変えたいと願うなら、最初に必要なのは証拠やデータではありません。大切なのは、「関与」「信頼」「つながり」「価値観の共有」といった、人と人との関係そのものです。オンラインでのやり取りだけでは、それを十分に築くのは難しいのです。
やはり、顔を合わせて時間を共にしながら、丁寧に関わることが、信頼の土台となり、相手の考えに変化が生まれるきっかけになります。 対話を始めるときには、相手の背景や信じている人たち、属してきたコミュニティを尊重することが欠かせません。
そのうえで、誠実に向き合い、相手の立場に耳を傾ける姿勢が必要です。こちらの考えを理解してもらうには、まずは相手が安心して心を開ける関係を築くことが先なのです。 情報を伝えるときも、数字やグラフをただ提示するのではなく、「どんな証拠があれば考えを見直すきっかけになりますか?」と問いかける方が効果的です。
相手が自ら思考できるよう促すことで、対話は押しつけではなく、協働的なプロセスになります。 何より大切なのは、「この人なら話を聞いてくれる」と感じてもらえるような信頼関係を少しずつ育てることです。対話とは、勝ち負けではなく、理解とつながりを深める営みなのです。
言葉の選び方一つで、相手への敬意や覚悟が伝わるのです。 科学否定へのアプローチも同じです。知識不足が原因ではなく、信頼の欠如や価値観が脅かされる不安、そして孤独が背景にあります。だからこそ、私たちが行うべきなのは、人と向き合い、共感しながら関係を築いていくことなのです。
誰を信じるかによって、何を信じるかが決まってしまうことがあります。信じる対象を誤れば、情報に踊らされたり、搾取されたりする危険もあります。だからこそ、私たちは常識と理性を、自分たちの手で取り戻す必要があるのです。
説得すること、投票すること。信念を変えること、価値観を変えること。事実を共有すると同時に、関心の輪を広げていくこと。こうした挑戦が、いま求められている。
本書は、科学を信じるということが、ただデータを受け入れることではなく、人と誠実さを信じることなのだと気づかせてくれます。 理性を信じるとは、冷たく切り捨てるような論理ではなく、感情の中にあるまっすぐな誠意を信じるということなのです。
そしていま、私たちの社会はポスト真実と科学否定という2つの現象が、互いに火をつけ合いながら、出口の見えないフィードバックループに陥っていると著者は指摘します。
経験に基づいた事実と、政治的な価値観が混ざり合い、どこまでが現実で、どこからが信念なのかさえ、曖昧になってきています。 けれど、だからこそ希望があると著者は言います。 科学否定と現実否定。この2つの問題に、もしかしたら共通の解決の糸口があるのかもしれません。
それはつまり、対話をもう一度、取り戻すこと。人と人とが関わり直し、信頼を築き直すこと。それこそが、私たちの向き合うべきテーマなのです。
説得すること、投票すること。信念を変えること、価値観を見直すこと。 事実をただぶつけ合うのではなく、関心の輪をそっと広げていくこと。 そのすべてが、今この時代に求められている「人間らしい挑戦」なのだと思います。
私たちが目指すべきは、相手を打ち負かすことではなく、理解の糸をつなぎ直すこと。 理性と希望。その二つを手放さずに、目の前の誰かと、ゆっくりでも誠実に、対話を重ねていくこと。 それこそが、分断を越え、未来を取り戻すための、もっとも確かな一歩なのかもしれません。
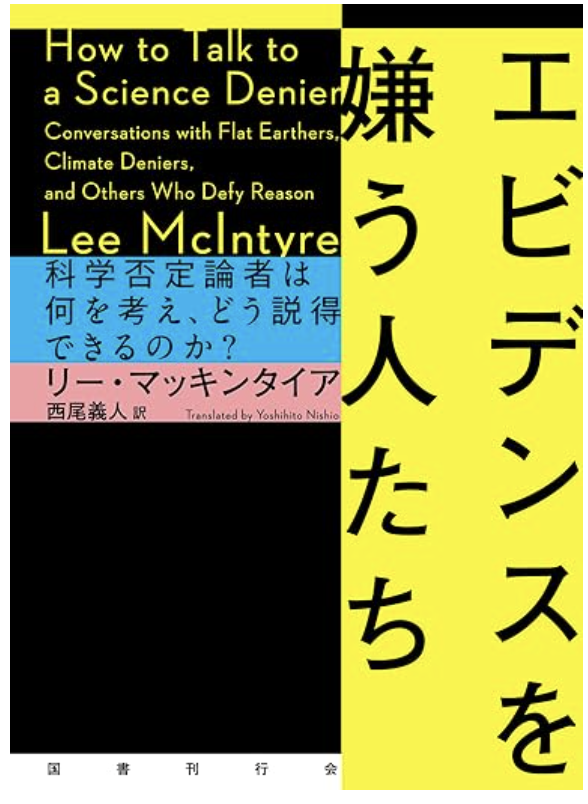













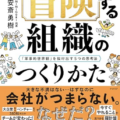




コメント