私たちは同調する
ジェイ・ヴァン・バヴェル, ドミニク・J・パッカー
すばる舎
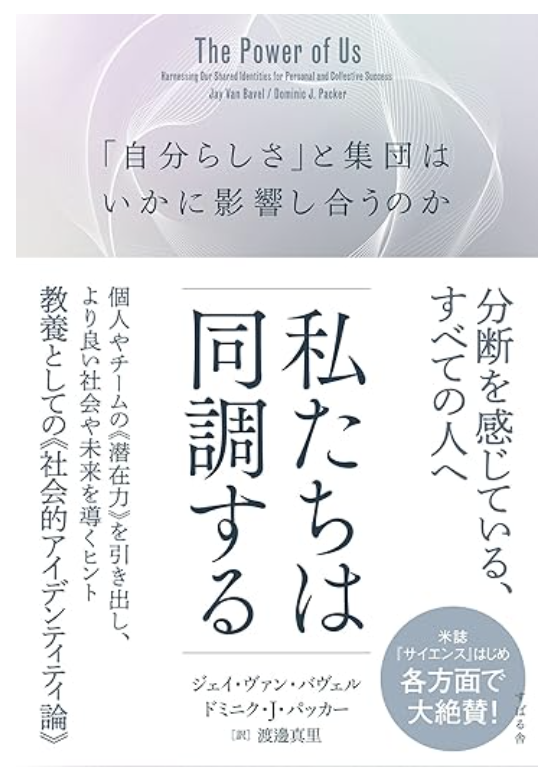
私たちは同調する(ジェイ・ヴァン・バヴェル, ドミニク・J・パッカー)の要約
ジェイ・ヴァン・バヴェル, ドミニク・J・パッカーの『私たちは同調する』は、アイデンティティが個人の行動や感覚、社会的判断に与える影響を社会心理学の視点から解き明かします。集団との関係性が自己像を形づくり、他者への見方や世界の感じ方を変える力となることを示し、分断を超えて自分と社会を再発見するヒントを与えてくれる一冊です。
アイデンティの4つの原理
私たち社会心理学者は、所属する集団について尋ねる。所属していることを誇りに思うのはどの集団か? 所属していることをひんぱんに意識するのはどの集団か? あなたの待遇に影響するのはどの集団か? 連帯感を感じるのはどの集団か?などだ。これらの問いに対する答えが、その人を知る有益な手がかりを与えてくれる。(ジェイ・ヴァン・バヴェル, ドミニク・J・パッカー)
私たちは日々、「自分らしくありたい」と願っています。しかし、そもそも自分らしさとは何を意味するのでしょうか。私たちは本当に、自分の意志で自分を形作っているのでしょうか。それとも、私たちが属する集団や環境が、無意識のうちに自分を構成しているのでしょうか。
社会心理学者ジェイ・ヴァン・バヴェルとドミニク・J・パッカーによる私たちは同調するは、こうした根源的な問いに、社会心理学と神経科学の知見をもとに挑んでいます。本書は、アイデンティティと集団の関係を手がかりに、個人の行動から社会全体の構造までを読み解くためのヒントが満載された一冊です。
まず押さえておきたいのは、アイデンティティが私たちの生活と行動にどれほど強く影響を与えているかという点です。著者たちは、社会的アイデンティティの4つの基本原則を提示しています。
1つ目に、人が所属する集団は、自己認識や「自分とは何者か」という理解の土台になっていること。私たちは個人として生きているようでいて、実は家族、職場、国家、趣味のコミュニティなど、複数の集団との関係性を通して自己を捉えています。
2つ目に、人は他者との連帯感を求め、一時的な集団や偶然のつながりでさえ、驚くほど簡単に一体感を感じるという傾向があります。たとえそのつながりが脆弱であっても、人はそこに帰属の感情を見出すのです。
3つ目に、あるアイデンティティが活性化されると、私たちの思考や目的、感情、行動にまで深い影響を及ぼすということ。つまり、「どのアイデンティティを通じて世界を見るか」が、意思決定の在り方を変えてしまうのです。
4つ目に、人は活性化されたアイデンティティに応じた規範に適応し、ときに自己犠牲を払ってでも集団に貢献しようとする傾向があるという点です。この社会的規範の内面化は、私たちの行動を非常に強く駆動します。 ただし、こうしたアイデンティティの力は、協力や連帯というポジティブな効果を生み出す一方で、集団間の境界が固定化され、硬直するときには、非常に危うい力にもなります。
「私たち」と「彼ら」の利益は両立しないという思い込みが強まると、次第に「私たちは本質的に善である」「だから彼らは本質的に悪だ」という構図が生まれてきます。こうなると、相手に異議を唱えるどころか、「敵」として排除すべき対象とみなすようになり、道徳さえ自分たちに都合よく再定義されてしまうのです。
この段階に至ると、反対意見への寛容さは失われ、グループの境界を曖昧にする存在や考え方に対して強い警戒心が生じます。敵は外だけでなく内にもいるという考えが広がり、「私たちのため」という大義のもとに、あらゆる手段が正当化される空気が強まっていきます。
社会的アイデンティティは、協同の基盤であると同時に、分断と攻撃性の引き金にもなりうるのです。 こうした危うさを含みつつも、アイデンティティは変化しうるものです。 たとえば「最小条件集団研究」と呼ばれる心理学実験では、人がコイン投げのようなランダムな方法でグループに割り振られただけで、わずか数分で新たなアイデンティティを形成し、内集団への好意を抱き始めることが示されました。
つまり、私たちのアイデンティは固定されたものではなく、文脈によって絶えず変化しているのです。 朝の通勤では生活者としての自分、会議では組織の代表、SNSでの発信者としての存在、週末には音楽好き、夜には家族やパートナーという顔を持つ。これらはすべて同じ人物の中に同時に存在し、時間とともに切り替わっていくアイデンティティです。
この「動的な自己」の仕組みこそが、人の行動や判断に深く影響を与えています。ある集団との一体感が高まると、目標や優先順位さえも変わり、自分の利益を超えて他者や社会に貢献しようとする動機が生まれます。社会的アイデンティティは、利己的な人でさえ向社会的な行動に向かわせる力を持っているのです。
私たちがオンラインで情報を目にしたとき、最初に意識するのは「それが本当に正しいかどうか」でしょうか? それとも、「誰かを驚かせたい」「仲間と共有したい」という動機でしょうか。 この問いを検証するため、研究者たちは新型コロナに関するニュース見出しを使った実験を行いました。
被験者の半数には「この見出しを共有したいか?」と尋ね、もう半数には「この見出しは正確だと思うか?」と質問しました。その結果、正確性を問われたグループのほうが、事実と誤情報を正確に見分ける力が高かったのです。
つまり、「正しいかどうか」に意識を向けるだけで、人は誤情報に騙されにくくなるのです。ところが現実のSNSでは、多くの人が情報を共有する際、真偽よりも感情や関係性を優先しているのです。 こうした動機には、社会的アイデンティティが大きく関わっています。人は自分が属する集団を好む一方で、対立する集団に対しては嫌悪感を抱きやすくなります。
実際、一部の有権者は、支持する政党への好意よりも、敵対政党への強い嫌悪に基づいて投票行動を取っています。 この分極の背景には、脳の働きも関係しています。扁桃体という感情処理に関わる領域は、社会的階層や自分の立ち位置に敏感です。
変化や平等を好む人はリベラルに、秩序や安定を求める人は保守的な思想に惹かれやすいという傾向も、脳の特性と心理の相互作用によって説明できます。
私たちの情報の受け取り方、感じ方、行動の背後には、無意識のバイアスとアイデンティティのレンズが存在しています。その事実を知ることが、情報とのより健全な向き合い方につながるのです。
アイデンティがもたらすバイアス 五感とアイデンティとの関係
あるアイデンティティを選ぶということは、世界の眺めをフィルタリングするめがねをかけるようなものである。感覚系は絶えず膨大な情報にさらされているが、アイデンティティはその情報をどう処理するかを助けている。アイデンティティは、何が重要か、どこに目を向けるか、いつ耳をかたむけるか、そしておそらく何を味わうべきかまで、教えてくれる。
私たちの感覚系は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚といった五感を通じて、常に膨大な情報にさらされています。その中から何に注目し、何を無視するのかを選別する手助けをしているのが、まさに「アイデンティティ」なのです。
アイデンティティは、「何が重要か」「どこに目を向けるべきか」「いつ耳を傾けるべきか」、さらには「何を味わうべきか」までを導いてくれます。ひとたび集団に加入すると、私たちは無意識のうちに、その集団のメンバーである「私たち」が何を大切にしているか、そして逆に何を軽視してよいかを察知します。アイデンティティは、私たちの五感すら方向づける、深層的な心理構造です。
たとえば、ある文化的アイデンティティが活性化されると、それに関わる料理への嗜好や、好ましい空間の雰囲気までもが変化します。イタリア料理の店が壁にヴェネチアの写真を飾り、韓国の焼き肉店がK-POPのヒット曲を流すのは偶然ではありません。視覚や聴覚を通じて特定の文化圏に同調させることで、その文化に属する「私たち」という感覚が喚起され、その結果として食欲や味の評価が高まるのです。
さらに、嗅覚もまた、アイデンティティと密接に結びついています。 香りは記憶と感情を強く結びつける感覚であり、特定の文化や集団に関連づけられた香りは、私たちの帰属意識を活性化させるきっかけになります。
インド料理店のスパイスの香り、フランスのパン屋から漂う焼きたてのバゲットの香ばしさ、和食店の出汁の香り——これらは単なる「におい」ではなく、文化的アイデンティティを呼び起こし、私たちの知覚全体を調律する環境要素なのです。
嗅覚はしばしば嫌悪や快といった情動と結びついて働きますが、その反応すらアイデンティティによって変化することが、実験によっても示されています。
たとえば、ある女子学生に2種類のTシャツを着てジョギングしてもらい、その後、そのTシャツを別の学生たちに手に取らせるという実験があります。一枚はセント・アンドリュース大学のロゴが入ったTシャツ、もう一枚はライバル校であるダンディー大学のロゴ付きTシャツでした。
結果は興味深いものでした。学生たちはライバル校のTシャツを手にした後の方が、自校のTシャツを手にした後よりも多くの手指消毒剤を使い、手洗いにより長い時間をかけたのです。 この現象は単なる「におい」や「汚れ」に対する反応では説明しきれません。
汗を含んだシャツに対する嫌悪感が変化したのは、そのTシャツが「誰のものか」—つまり、どの集団に属しているか—によって、嗅覚的な不快感すら社会的アイデンティティの影響を受けていたことを示しています。言い換えれば、「私たち」のにおいは受け入れられ、「彼ら」のにおいは拒絶されやすいという、人間の知覚に潜む集団バイアスの一端が見えてきます。
このように、私たちの感覚や知覚すら左右する社会的アイデンティティですが、それは単に「内集団に共感する」ことにとどまりません。
外集団に対する印象や感情、さらには「距離感」にさえ影響を与えるのです。 たとえば、アメリカの心理学者たちが行った研究では、移民に対する感情が「現実的脅威」ではなく「象徴的脅威」によって形づくられているというパターンが観察されました。現実的脅威とは、職や社会資源を奪われるといった具体的な損失への不安です。
一方、象徴的脅威とは、自分たちの文化や価値観、ひいては「アイデンティティ」そのものが侵されているという感覚を指します。
実験では、被験者にアメリカとメキシコの国境に関する異なる文章を読んでもらい、その後、メキシコシティがどれほど「近く」に感じられるかを尋ねました。すると、自国への誇りや帰属意識が強い人ほど、移民が「心理的に近すぎる」と感じる傾向が顕著に見られました。実際には遠くにあるメキシコシティが、文化的脅威の文脈では“近すぎて不安”な存在として知覚されたのです。
興味深いのは、その感覚が文章ひとつで変化したことです。国境が「世界で最も厳重に守られている」と読むと、不安感は軽減され、心理的距離も遠のきました。逆に、「国境は頻繁に越えられている」「ほとんど守られていない」と読んだ場合には、再び“近すぎる”という知覚がよみがえったのです。
このような「距離の歪み」は、文化や政治だけでなく、スポーツのような日常的な領域にも見られます。 ある実験では、ニューヨーク・ヤンキースのファンたちに、対戦相手の球場がニューヨークからどれくらい離れていると感じるかを尋ねました。
実際には、ボルチモア・オリオールズの本拠地のほうがボストン・レッドソックスの本拠地よりも近くに位置しています。しかし、ヤンキースファンの多くは、より強いライバル関係にあるレッドソックスの本拠地のほうが“近くにある”と回答したのです。 ここで注目すべきは、ヤンキースファンではない人たちは、正確にオリオールズの球場のほうが近いと回答したという点です。
つまり、敵対感情や集団対立の強さが、物理的な距離の知覚にまで影響を与えているということです。心理的な敵意がある対象は、実際よりも「迫ってくる」「近づいている」ように感じられるのです。 これらの事例が示すのは、距離の認識や空間的な判断ですら、社会的アイデンティティによって歪められ得るという現実です。
「私たち」と「彼ら」を隔てる境界線が曖昧になったり、侵されていると感じたとき、私たちは地理的な現実を超えて、感情的な地図を脳内に描いてしまうのです。
この知覚の歪みを象徴的に利用したのが、ドナルド・トランプの「壁をつくれ!」というスローガンでした。物理的な壁という施策以上に、心理的な境界を強調し、「彼らがこちらに迫ってくる」という象徴的脅威の感覚を掻き立てることに狙いがありました。
社会的アイデンティティが活性化されると、世界の見え方そのものが変わる。どこが近いか、遠いかという空間感覚さえ、内集団・外集団の感情によって再構成されるのです。 このように、どのアイデンティティが活性化されているかによって、私たちが「何を見るか」「何を聞くか」「何を食べたいか」だけでなく、「どんなにおいを心地よく、あるいは不快と感じるか」にまで影響が及びます。
五感のすべてが、社会的アイデンティティという無意識のレンズを通して調整されているのです。 社会的アイデンティティとは、単なる思想や態度の枠組みにとどまらず、私たちの身体感覚のレベルで作用し、世界の“感じ方”そのものを変える力を持っているのです。
集団思考によって人の選択は変わる?
実際、アイデンティティは私たちの思想、哲学、理論、言語を形成し、私たちが重要なことに注意を向け、私たちを取り巻く世界で何が起きているのかを自分自身に(そして他者に)説明できるように助けている。こうしたアイデンティティが社会的・物理的な世界に対する私たちの認識をかたちづくっており、アイデンティティによって、どこに目を向けるか、どう世界を解釈するかは変化している。同じできごとを経験しても、何が起きたのかについてまったく異なる結論にいたるのは、こうした選択的注意とフィルタリングプロセスが行われているからだ。
アメリカの研究チームは、警察官が麻薬や武器などの違法所持を疑って車内を捜索する際、どのような判断がなされているかを分析しました。その結果、人種によって捜索の頻度が異なるという、明確なバイアスの存在が示されました。
たとえばある地方の警察では、交通取り締まりの際に車内を調べられた割合は、黒人の運転者が9%以上、ヒスパニック系が7%だったのに対し、白人の場合はわずか4%にとどまっていました。ところが、実際に違法なものが見つかった割合は逆で、白人の運転者が18%と最も高く、ヒスパニック系は8%、黒人の運転者は14%にすぎなかったのです。
つまり、捜索される頻度は高いのに、違法所持の発見率は低いというパターンが、黒人やヒスパニック系に対して起きていたことになります。このような不均衡は、警察官が誰を捜索すべきかを判断する際に働く無意識のバイアスに根ざしています。
特に、肌の色といった視覚的情報が、状況の解釈に強く影響を与えていることが浮き彫りになっています。 こうした問題に対しては、警察組織の人種的多様性を高め、地域社会の構成に見合った警官を採用することが効果的であると考えられています。
異なる文化的背景をもつ警官は、同じ場面を別の視点=異なるアイデンティティのレンズを通して見ることができるため、曖昧な状況に対する判断や対応のあり方にも変化が生まれるのです。 これは警察に限った話ではありません。組織や社会のあらゆる場面において、
私たちのアイデンティティは、世界をどのように認識し、どんな意味づけを行うかを左右しています。ただし、アイデンティティは世界を理解する助けになる一方で、他の視点を見えなくする力も持ち合わせているという点に注意が必要です。 私たちは一つの側面に集中すると、他の情報を見落としがちです。そしてさらに厄介なのは、自分がバイアスを持っていること自体に気づきにくいということです。
他人の偏りには敏感でも、自分の見方がアイデンティティによってフィルターにかけられているとは思いにくいのです。この現象は「バイアスの盲点」と呼ばれています。 実際、661人のアメリカ人を対象にした調査では、85%以上の人が「自分は平均よりもバイアスが少ない」と考えていたことが明らかになりました。平均よりもバイアスが強いと自己認識していた人は、わずか1人だけでした。
このように、アイデンティティが私たちの解釈や判断に与える影響を理解することは、立ち止まって自分自身を見直すきっかけになります。結論を急ぐ前に、自分がどのようなバイアスを持っているか、そしてそれがどれほど見えにくいものであるかを考えることが、健全な意思決定の出発点となるのです。 さらに、アイデンティティの影響は、組織内の意思決定や社会運動の文脈でも見られます。
たとえば、人がカルト的な集団から抜け出せなくなるのは、単に同調圧力のせいだけではありません。「認知的不協和」と呼ばれる心理メカニズムも大きく関係しています。合理的に考えれば、間違いに気づいた時点でその集団を離れ、元の生活に戻るべきだと思うかもしれません。ですが、人はすでに自分のアイデンティティを深く重ねた集団から離れることに、強い心理的コストを感じるのです。
エンロンのように、高度な知性と専門性を持った人材が揃っていた企業でも、同じような現象が起きました。個人の知性が、集団の思い込みを打ち破ることは容易ではありません。 人は問題を解決する際に、自分の信念を裏づける情報を探す傾向があります。この傾向は知性とは無関係であり、むしろ集団内で共有されることで強化されることがわかっています。
心理学者アーヴィング・ジャニスはこれを「集団思考(groupthink)」と呼びました。 集団内の調和や結束を保つことが重視される場面では、人々は自分の疑念を表に出すことを避け、内心では反対していても、表向きには賛成してしまうという状況が生まれやすくなります。 特に、時間的なプレッシャーが強いときや、目上の人物の前で発言しなければならないような状況では、この傾向はより顕著になります。
結果として、人々は実際には存在しない「共有された現実」を信じ込むようになります。たとえそれが、合理的に見て誤った判断であっても、集団という枠組みの中では正しいと感じられてしまうのです。 このような事例が示すのは、私たちが現実をどう解釈し、どんな行動をとるかは、アイデンティティに強く依存しているという事実です。
スポーツの応援から警察の取り締まり、企業の意思決定に至るまで、あらゆる領域で私たちは「私たち」という枠組みの中で世界を見ているのです。 そして、その見方がどれだけ偏りうるのかを理解することが、より良い判断や共感、行動の出発点になります。
アップルの強さは「帰属欲求」と「独自性欲求」にあり!
アップル社が世界有数の企業になったのは、技術に精通していたからというだけでなく、多くの消費者に自社製品への深い愛着をいだかせることに成功したからだ、と私たちは考えている。
アップルが世界を代表する企業になった理由は、単に技術力が優れていたからではありません。もちろん、革新的な製品開発力も大きな要素です。しかしそれ以上に重要だったのは、人々にアップル製品を「ただの道具」ではなく、「自分の一部」として感じさせたことにあります。
著者たちは、アップルが構築したブランドの背後にある強力なアイデンティティ設計に注目しています。 アップル製品を選ぶという行為は、単なるテクノロジーの選択ではありません。むしろ、「アップルの世界観に共鳴し、その一員である」という帰属意識を育む行為に近いのです。
それと同時に、「他とは違う」「ちょっと洗練された存在でいたい」という独自性欲求にも応える仕組みがそこにはあります。アップルは、この所属と差異という人間が本質的に求める2つの心理的ニーズを、見事にブランドに組み込んでいるのです。
その象徴的な例が、1984年のスーパーボウルで放映された伝説的なCM、そして「Think Different」のキャンペーンです。 どちらも「私たちは他とは違う」「既存の枠組みにとらわれない」というメッセージを強く打ち出し、アップルらしさ=「最適弁別性」を鮮明にしました。 これらの戦略により、アップルはカルト的ともいえる支持を集め、世界で最も強力なブランドの一つとしての地位を確立したのです。
このように、アップルのブランドは「帰属欲求」と「独自性欲求」という、人間が本能的に持つ2つの相反するニーズを絶妙に満たしていたのです。 つまり、「仲間でありながら、少し特別」——この心理的ポジショニングこそが、アップルをカルト的な支持へと導き、世界で最も価値あるブランドのひとつに押し上げた要因だといえるでしょう。
人は誰しも、集団に属したいという気持ちを持っています。けれども同時に、「自分らしさ」や「他と違う自分」を表現したいという欲求も捨てきれません。 社会的アイデンティティの本質は、実はこのねじれの中にあります。自分が何者なのかを感じるためには、「自分はこの集団に属している」と思うことも、「他の集団とは違う」と感じることも、両方必要なのです。 そして今の時代、モノを買うという行為は、単なる消費ではありません。
買うという選択そのものが、自分がどんな人間でありたいか、どんな価値観を大切にしているかを自分自身に、そして周囲に示す「メッセージ」になっています。 乗っているクルマ、着ている服、通っているカフェ、使っているスマートフォン——それらはすべて、無意識のうちに「私はこういう人間です」というシグナルを発信しています。
もちろん、プロダクトの中にはステータスを示す記号として機能するものもあります。高級車や高級時計のように、所有そのものが社会的地位や成功の証として受け取られることもあるでしょう。 しかし、実際にはそれ以上に、「このブランドに共鳴している自分」や「このスタイルこそが自分らしい」という感覚を表現する手段としてプロダクトを選んでいる人が圧倒的に多いのです。
著者たちも指摘するように、ブランドやプロダクトが人を惹きつける本質的な理由は、それ自体の機能やデザインを超えて、「それを通じて自分がどんな人間であるかを語れる」ことにあります。
これは私自身にも深く当てはまります。アップルのプロダクトを愛用している私は、単に機能性やデザインに惹かれているだけではなく、アップルが体現している価値観や哲学に共鳴し、それを通じて「自分らしさ」を感じているのです。
製品を選ぶという行為は、自己表現のひとつ。そこには、「自分はこうありたい」という静かな意思表明が含まれています。だからこそ、私たちは“使う”という行為に、これほどまでの意味を見出してしまうのかもしれません。
アイデンティ・リーダーシップが重要な理由
人が異議を唱えるのは、その集団のことを深く気づかっているときであり、リーダーがより効果的に役割を果たすのは、フォロワー〔集団においてリーダーに従って行動する人〕とのあいだに共通のアイデンティティを築けたときだ。
本書では、リーダーシップとアイデンティティの関係にも深く踏み込んでいます。効果的な集団運営を実現するには、多様な意見を受け入れる土壌が欠かせません。反対意見から得られる価値を生かすために必要なのは、まず、メンバーが安心して異論を表明できること。そして、それを聞く側が好奇心を持って真摯に受け止めること。この2つの行動はどちらも、強く揺るぎないアイデンティティに支えられているのです。
誰が異議を唱えるかは、いくつかの条件から予測できます。その集団の規範に疑問を感じているかどうか、集団への一体感があるかどうか、そして異議を表明することによる利益がリスクを上回ると感じているか。これらすべての条件がそろったとき、人は意見を口にします。
異議を唱えるのは、組織への忠誠心がないからではありません。むしろ本当にその集団をよくしたいという願いがあるからこそ、あえて声を上げるのです。 リーダーには、こうした声を引き出すための「場」をつくる役割があります。
多くの人は、仲間から浮いてしまうのではという不安や、権威ある相手が近くにいるというプレッシャーから、口を閉ざしてしまいます。だからこそ、あらゆるレベルのリーダーが心理的な安全性を担保しなければなりません。安心して意見を言える空気、異なる意見が歓迎され、評価される文化。そうした信頼の土台がなければ、本当の対話も創造も生まれないのです。
リーダーシップは、ただ方向性を示すだけではありません。大切なのは「私たち」という共通の意識を、言葉と行動で共有することです。個人として大切にされていると感じることと、集団としての連帯感を持つこと。この両方を満たすリーダーが、人を動かし、集団を変えていきます。
優れたリーダーは、フォロワーの中にある社会的アイデンティティを言語化し、それを体現する存在でもあります。 集団の中に信頼できるリーダーがいると、他のメンバーは自分の役割に集中できます。結果として、チーム全体のパフォーマンスが向上し、利他的な行動も増え、満足度や献身度が高まる。離職率が低くなるのも自然な流れでしょう。
リーダーを信頼するという感覚は、単なる人間関係の温かさを超えた意味を持ちます。それは、集団が持つエネルギーの源そのものになるのです。リーダーに信頼が集まると、メンバーは安心して自分の役割に集中でき、互いに助け合い、創造的に動き出します。そこには命令や管理では生まれない、自然なモチベーションが宿ります。
そんな信頼を築く鍵となるのが、心理的安全性です。どんな意見でも安心して出せる場をつくれるかどうか。そしてもう一つ、フォロワーが共感できる物語を語れるかどうか。それがリーダーシップの本質であり、著者たちが語る「アイデンティティ・リーダー」の姿です。
組織や集団が前に進むには、「私たちは何者なのか」「何のために集まっているのか」という問いに対する、共有されたストーリーが必要です。その物語を言葉にし、行動で体現できる人こそが、真のリーダーなのです。
著者たちは、私たちがどんな集団に属し、どんなアイデンティティを育てていくかが、社会や組織の未来を左右すると語ります。私たちが何者かを定義するのは、環境や立場ではなく、自分自身の選択です。時にその選択は、世界を変える力にもなります。
同調は時にネガティブに捉えられがちですが、反対意見を述べることもまた、深い同調=関心の表れです。意見を言うのは、その集団に愛着があるからです。本気で関心がなければ、人はそもそも口を開きません。だからこそ、集団をより良くするための異議は、リーダーによって守られ、育まれなければならないのです。
現代では、SNSやアルゴリズムの影響で、自分の価値観に合った情報ばかりが届くようになり、異なる意見に触れる機会が減っています。それによって、対話の余地が失われ、エコーチェンバーの中でアイデンティティが強化されてしまう構造が生まれています。
著者たちは、こうした分断の時代にこそ、科学的思考をベースにしたアプローチが必要だと説きます。科学もまた人間の営みであり、完全に中立とは言えませんが、それでもなお、社会の偏見や対立を乗り越える希望を私たちに与えてくれるものです。
本書は、社会的アイデンティティを理解することが、自己と世界を見直すための鍵であると伝えています。「私たちは何者か」という問いを、「私たちは何者になりたいのか」という未来に向けた問いへと進める力を持っているのです。
人は状況や文脈に応じて、異なる自己を切り替えながら生きています。だからこそ、どの集団とつながるか、どんな価値を共有するかという選択が、自分自身のかたちを決める大切な要素になります。
過去を整理するだけでなく、これからの自分の方向性を見定めていく。その過程において、アイデンティティは単なる属性ではなく、選び、育て、再構築していく生きた要素として働いていくのです。
本書は、アイデンティティの持つ明と暗、つまりポジティブな力とネガティブな影響の両面を丁寧に描き出しながら、いまこの時代に本当に必要な自己理解と、社会的つながりの再構築に向けたヒントを私たちに示してくれます。自分を知り、他者とつながる。そのプロセスにこそ、未来を切り拓く可能性があるのです。さまざまなバイアスに惑わされず、熟考し、正しい選択を心がけたいと思います。



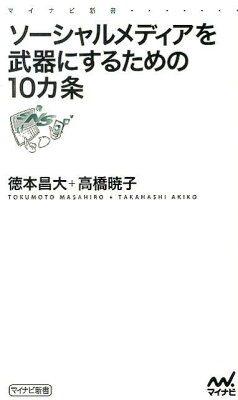














コメント