「マウント消費」の経済学
勝木健太
小学館
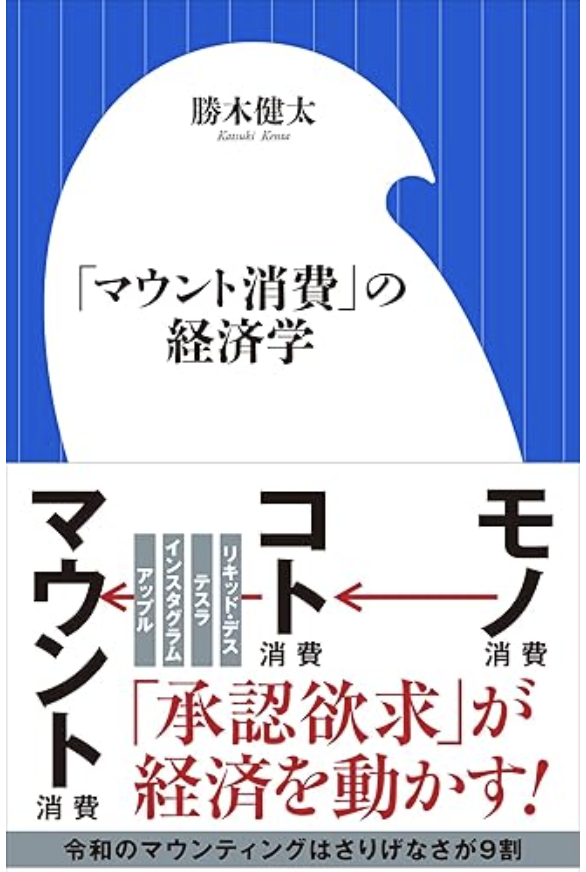
「マウント消費」の経済学(勝木健太)の要約
現代社会では、物質的な豊かさの一般化により、単なる所有価値では満足が得られなくなっています。そこで注目されているのが、「マウンティングエクスペリエンス(MX)」という新しい消費概念です。これは消費者に「特別な自分」を実感させる体験を提供し、さりげない優越感を演出する戦略です。企業はこの「マウント消費」を理解し、商品やサービスに物語性や独自の価値を織り込むことで、新たな市場機会を創出できます。
マウント消費が変える企業のマーケティング戦略
現代社会は、モノが飽和し、「コト消費」すらも当たり前になりつつある。物質的な豊かさを追い求める時代はすでに終焉を迎えつつあり、今や「誰も持っていない」「誰も体験していない」という唯]無二の価値が消費行動の新たな基準として台頭してきている。このような転換の中で、経済は次なるステージへと進化していく。その過程において、「マウント消費」は従来の消費行動を革新し、これまでにない可能性を引き出す画期的なコンセプトとして、ますます注目を集めていくだろう。(勝木健太)
SNSが普及した現代において、人々の消費行動は大きく変化しつつあります。かつては「モノを所有すること」が価値の中心でしたが、次第に「体験を楽しむこと」へとシフトし、さらに現在では「体験をいかに他者に見せるか」が重視されるようになっています。
この新たな消費スタイルは「マウント消費」と呼ばれ、自己の価値を他者と比較し、優越感を得ることを目的とした消費行動です。
例えば、高級レストランでのディナーや一流ホテルでの滞在は、単に快適な時間を過ごすためのものではなくなっています。その体験をSNSで発信し、「特別な体験をしている自分」をアピールすることが目的化しつつあります。ブランド品の購入においても、単に品質やデザインを求めるのではなく、「このブランドを持っている自分」を示すことに価値が置かれています。
こうした「マウント消費」の拡大により、消費のあり方が根本的に変化し、企業のマーケティング戦略も新たな視点を求められるようになっています。 この背景には、物質的な豊かさが一般化し、従来の「所有することの価値」が相対的に薄れてきたことが挙げられます。現代社会では、誰もが一定の生活水準を満たしており、単に高価なものを手に入れるだけでは特別感を得にくくなっています。
そのため、「他者と異なるユニークな体験」を求める動きが加速し、それが「マウント消費」という形で可視化されるようになってきました。 企業にとって、この「マウント消費」は新たな市場機会をもたらす重要な要素となっています。従来の製品やサービス提供のあり方では、消費者の深層心理に訴求することが難しくなっています。
ここで鍵となるのが、「マウンティングエクスペリエンス(MX)」という私が提唱する新たな概念である。これは特別な体験を提供するだけにとどまらず、それを通じて消費者が他者に対する優越感を実感できるように設計された体験のことを指す。言い換えれば、「自分は特別な存在である」と深く感じられる物語性や価値を織り込んだシナリオや演出を緻密に構築することである。
そこで求められるのが、「マウンティングエクスペリエンス(MX)」という新たな概念です。これは、消費者が単なる満足感を得るのではなく、「この体験を通じて自分は特別な存在だ」と感じられるように設計された体験のことを指す、著者の勝木氏の造語です。
つまり、製品やサービスを通じて「自分の価値を際立たせることができる」という要素を重視し、それを消費者が他者にシェアした際に、どのように見られるかまで計算された戦略が必要になるのです。 このMXを実現するためには、企業側が「体験のシナリオ」を緻密に設計することが不可欠です。
例えば、高級ホテルの宿泊プランにおいて、単なるラグジュアリーな空間を提供するだけではなく、そこに独自のストーリーや特別な演出を加えることで、滞在そのものが「シェアしたくなる」価値を持つものに昇華します。さらには、そのホテルに宿泊したこと自体が「洗練された選択をした自分」を演出できるような要素を盛り込むことも重要です。こうした工夫により、消費者は体験を通じて自己表現を行い、それが次なる消費意欲へとつながっていくのです。
マウント消費時代にはさりげない優越感をくすぐることが重要!
この「マウント消費」を効果的に活用することができれば、日本経済にこれまでにない活力を吹き込む起爆剤にもなり得るだろう。現代の消費者が真に求めているのは、純粋な商品の所有ではなく「自分は特別な存在だ」と実感できる体験である。その体験が自己表現の一部として意味を持ち、他者との差異を際立たせる要素を備えることで、「マウント消費」はより本質的な価値を帯びるのだ。
日本社会では、物質的な豊かさが広く普及し、単なる所有価値だけでは満足が得られにくい状況となっています。そのため、消費者は独自の体験や特別感を求め、それを通じて自己表現を行う「マウント消費」が今後もトレンドになると著者は言います。
現代のSNSにおいて、「さりげないマウント」の表現手法は一層洗練されたものとなっています。 その代表的な手法として、「自虐マウント」では疲労感を装いながら高級スパや絶景を披露し、「感謝マウント」では家族への謙虚な感謝の言葉とともに高級レストランの様子を映し出します。
また「困ったマウント」では、突然の予定として高級ホテルのスイートルームを何気なく紹介します。 これらの表現は、直接的な自慢を避けながら特別感を伝える巧みな技術です。優越感を背景に隠しつつ、子供や趣味、偶然といったストーリーを織り交ぜることで、控えめで共感を得やすい投稿となっています。このような「さりげなさ」こそが、現代のSNSコミュニケーションにおける重要な要素となっているのです。
これは、商品やサービスを通じて、さりげなく優越感を演出する日本独自の消費文化といえます。 この「マウンティングエクスペリエンス(MX)」は、欧米の直接的な富の誇示とは一線を画す、繊細で洗練された価値表現です。
現代の消費者が真に求めているのは、モノやサービスを通して得られる「さりげない優越感」である。どれほど優れた機能やデザインを備えた商品やサービスであっても、そこに他者との差異や特別感が伴わなければ、深い共感を呼ぶことは難しい。
日本の美意識と結びついたこの消費形態は、グローバル市場においても独自の魅力を持つ可能性を秘めています。 企業にとって、この新しい消費傾向への対応は、今後の成長戦略において重要な意味を持ちます。
製品やサービスに「自己の価値を高める」要素を組み込むことで、消費者の深層的な欲求に応えることが可能となります。特に少子高齢化による市場縮小が懸念される中、この概念をグローバルに展開することは、日本企業の新たな成長機会となるでしょう。
テクノロジーの進化により、モノの所有自体は容易になりましたが、人々の「特別な存在でありたい」という根源的な欲求は変わりません。企業は、単なる機能や利便性を超えて、消費者が自己の価値を実感できる瞬間を意識的にデザインすることが求められています。
このように、「マウント消費」は現代の日本社会における新たな価値創造の形として注目されています。企業がこの消費心理を的確に捉え、それに応える商品やサービスを提供することで、日本の消費文化は更なる進化を遂げ、世界的な影響力を持つ可能性を秘めているのです。
米国企業のマウント消費とAppleとテスラのケーススタディ
米国企業が世界で圧倒的な競争力を誇る理由は、技術力や資本力だけにとどまらない。それ以上に重要なのは、消費者に対して「特別な自分」を実感させるMXを緻密に設計する能力である。それらの企業は、製品やサービスを通して、「他者とは違う自分」を感じさせる体験を創り出し、 多くの顧客の心を掴むことで、強い購買意欲を引き出しているのだ。
アップルは、製品を通じて「他者とは異なる特別な自分」を演出する体験を提供しています。iPhoneやMacが持つ優れた機能性に加え、シンプルで洗練されたデザイン、直感的な操作性、そして革新的な製品発表は、すべて「アップル製品と共にある自分は特別だ」という感覚を消費者に抱かせるように綿密に計算されています。
特にアップルウォッチは、従来の高級時計が象徴してきた「ステータス競争」とは異なる価値観を提示しています。伝統的な高級時計が財力や社会的地位を誇示する道具であったのに対し、アップルウォッチは「スマートで効率的、機能性を重視する生活を送る自分」というライフスタイルを表現するツールとなっています。
さらに、高級時計市場における終わりなきマウント競争から距離を置きたい消費者にとって、「マウント回避」の象徴としても機能しています。
一方、テスラは自動車業界において、環境への配慮と革新性を組み合わせた新しい価値基準を確立しています。高級車メーカー同士の伝統的な優越性競争とは一線を画し、「環境を守りながら革新的な選択をする」という理念を体現することで、独自の満足感を提供しています。
これは「環境マウンティング」という新たな価値基準を生み出し、自動車の所有という概念そのものを再定義しているといえます。 このように、現代の企業には消費者の「現状の欲求」に応えるだけでなく、「新たな欲求」を創造し続ける能力が求められています。
それは単なる技術革新ではなく、消費者自身がまだ気づいていない潜在的な欲求を発見し、具現化する「欲求の革新」といえるでしょう。 そのためには、消費者の深層心理を徹底的に理解し、どのような体験が「自分は特別だ」という感覚をもたらすのか、どのような仕掛けが「他者との差別化」を実感させるのかを追求する必要があります。
市場調査やデータ分析に加え、人間の感情や社会的文脈を読み解く力、そして「デザインされた優越感」を創り上げるクリエイティブな感性が不可欠となっています。
アップルとテスラの成功は、単なる製品やサービスの提供を超えて、消費者に新しい価値観と自己実現の機会を提供している点にあります。この特別な体験を提供し続ける限り、両社は他に類を見ないブランドとして、その地位を確立し続けるはずです。
企業戦略において、「MXデザイナー」という新しい専門職の可能性に注目が集まっています。従来のITエンジニアが製品やサービスの利便性を追求するのと同様に、MXデザイナーは消費者が感じる優越感や差別化の感覚を専門的に設計します。
アップルやテスラのように、イノベーションを「欲求の革新」という視点でとらえることは、日本企業の新たな成長戦略として位置づけられるべきです。さらに、この概念を日本の国家戦略として取り入れることが、日本企業復活の鍵になると著者は指摘します。
日本文化に根付く「さりげなく特別でありたい」という繊細な価値観を、グローバル市場における独自の強みとして活用することが重要です。
具体的には、商品やサービスに、消費者が他者と区別化される特別感や優越感を感じられる要素を適切に組み込んでいくこと=プロダクトマウンティグフィット(商品の優越性の適合)が日本企業に求められています。これにより、消費者は商品を使用することで自然な形で優越感を得ることができ、結果として強い顧客ロイヤリティを築くことができます。




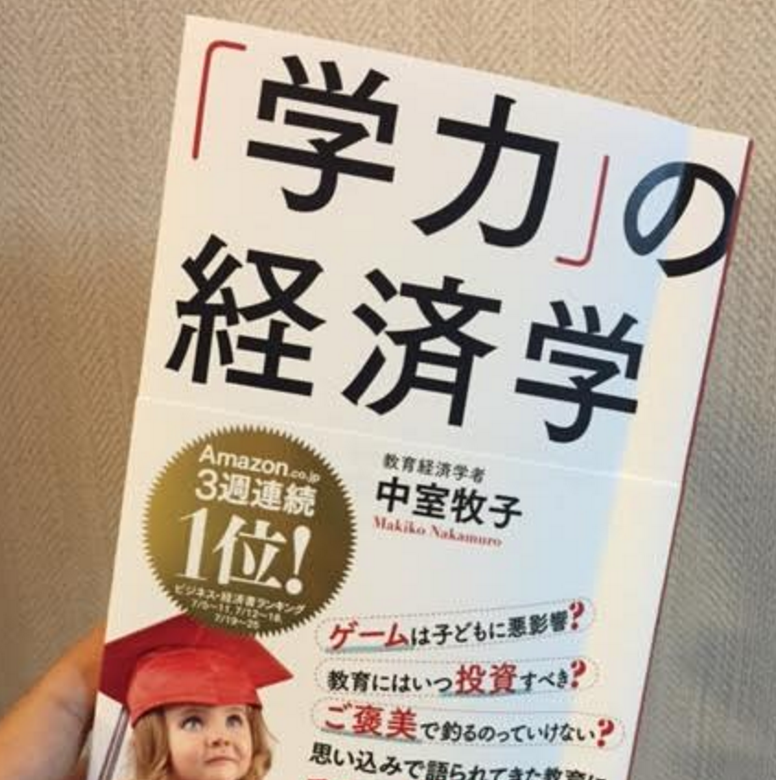


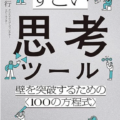
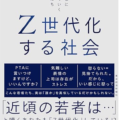


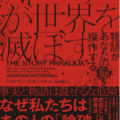

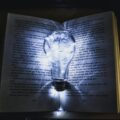


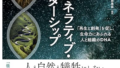
コメント