集団浅慮: 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?
古賀史健
ダイヤモンド社

集団浅慮: 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?(古賀史健)の要約
フジテレビ問題は、同質性の高い組織で起こる「集団浅慮」の危うさを象徴しています。ジェンダー・ダイバーシティの欠如、人権に関する知識不足、そして心理的安全性の欠落が、異論や違和感を排除し、誤った意思決定を正当化してしまう構造を浮き彫りにしました。本書は、空気を読むことが美徳とされてきた日本的組織文化を見直し、「尊重」と「人権」を軸にした組織変革の必要性を提示しています。
フジテレビで起こった集団浅慮とは?
集団浅慮のポイントは、組織における「凝集性」の高さにある。 凝集性(集団凝集性とも呼ぶ)とは、簡単に言うと「その集団にとどまらせようとする力」のことだ。(古賀史健)
「空気を読むこと」は、日本の組織において長らく美徳とされてきました。異論を控え、場の空気に調和し、波風を立てない態度が、協調性とみなされてきたのです。しかし、その空気に従い続けた先に、思考の停止があることに、私たちはもう気づくべき時期にきています。
空気に流された結果、誰も責任を取らずに進んでしまう意思決定。それこそが、今の日本社会の深層にある問題なのです。 いまだに昭和の論理を引きずる組織文化のなかで、その構造的な脆さをもっとも象徴的に露呈したのが、フジテレビの一連の問題でした。
優秀なはずの人々が、集団になると誤った判断を下してしまう。なぜなのか。その背景にあるのが「集団浅慮(Groupthink)」です。 社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが提唱したこの概念は、組織の中で思考停止がどのように起こるのかを明らかにしました。本来は個々に高い能力を持つメンバーが、集団としてふるまうとき、なぜ誤るのか。そのカギは「凝集性」にあります。凝集性とは、集団に人をとどまらせようとする力になります。
つまり、居心地のよさや、仲間でいたいという気持ちです。その凝集性が高まると、「この場の空気に合わせること」が優先されるようになっていきます。 フジテレビの経営陣がまさにそうでした。同質性の高い壮年男性たちによるオールドボーイズクラブが、企業の中枢に存在し、あらゆるリスクを見逃してきたのです。
第三者委員会の調査報告書が指摘するように、彼らは他の役員や専門部門に相談することもなく、内輪の論理だけで意思決定を重ねてきました。そのなかでは、異論はストレスとして排除され、議論は避けられ、「全会一致」によって誰も責任を負わずに済む空気が醸成されていきました。
こうした空気のなかでは、明文化されたルールではなく、暗黙の「あるべき姿」が力を持ち始めます。残業の常識、飲み会の出席率、育休の取り方、発言のトーンや頻度、上司への同調の仕方。どれもインフォーマルな規範にすぎませんが、それに従わない社員には、はっきりとは言葉にされない圧力がかかっていきます。
そして、その居心地のよさが守られれば守られるほど、組織は「違和感」や「異論」を排除し、「思考の省略」を正当化してしまい、クラブの常識で経営を行い、少数者の声が無視されてしまうのです。
古賀史健氏の集団浅慮: 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?は、まさにこの見えない力の構造を丁寧に言語化してくれます。そして私たちに問います。なぜフジテレビのような出来事は、今もどこかで起き続けるのか。いや、報道されていないだけで、まさに今も、無数の企業や組織の中で同じような人権侵害や不正が起きているのではないかと。
実際にフジテレビで明るみに出た一連の問題は、ジェンダー差別の構造を赤裸々に映し出すものでした。セクハラを訴えれば「面倒くさい人」とされ、飲み会への不参加は「ノリの悪い奴
」と見なされ、仕事を外されるリスクさえ伴っていたのです。女子アナウンサーに求められていた役割は、報道の担い手ではなく、男性の機嫌を損ねない“接待的ふるまい”に近いものでした。 タレントや社内関係者からのセクハラに対しても、笑って受け流すことが「大人の対応」とされ、真っ当な拒絶や抗議は「空気を読まない」と評価される。
こうした状況は、もはや過去の話ではありません。これは昭和の話ではなく、令和の日本で実際に起きていた現実なのです。
「集団浅慮」に陥らないために必要なこと
フジテレビ経営陣が 「集団浅慮」に陥ったのは、そこにダイバーシティが存在しなかったからである。
ここで見落としてはならないのが、組織における多様性の欠如、なかでもジェンダー・ダイバーシティの不足です。第三者委員会もこの点を明確に指摘しています。異なる立場や経験、視点を持つ人が意思決定の場に関わっていれば、組織の判断は変わっていたかもしれません。
ロザベス・モス・カンターが提唱する「黄金の3割」理論によれば、マイノリティが組織の3割を超えて初めて、文化や意思決定に実質的な影響を及ぼすとされます。意思決定層の同質性が崩れない限り、内部からの自浄作用は期待できません。
もう一つ見逃せないのは、人権に対する認識の問題です。著者の古賀氏は「日本人は人権意識が低いのではなく、人権に関する知識が決定的に不足している」と述べています。これは示唆に富んだ指摘です。
日本では、グローバルスタンダードとしての人権教育が十分に浸透しておらず、その空白を「善意」や「空気を読む」文化が補ってきました。その結果、「悪意がなければ問題ない」という誤解が根深く残り、差別やハラスメントが組織の中で繰り返されてきたのです。
「これは冗談のつもりだった」「ただの指導だった」「区別であって差別ではない」――こうした言い訳がまかり通る組織では、尊厳の損なわれた個人が声を上げにくくなります。人権とは、遠い国の出来事ではありません。問題は、職場という日常の中で、目の前にいる誰かの権利が守られているかどうかです。
経営陣はCSRやSDGsのスローガンを掲げる前に、まず「隣にいる人をどう扱っているか」を問う必要があります。 人権を守ることは、高潔な人格者であることとは無関係です。必要なのは、相手を「尊重する」姿勢だと著者は指摘します。
身体的・精神的・性的な自己決定権を脅かす行為は、たとえ暴力の自覚がなくとも、明確に人権侵害に該当します。それは力による支配だけでなく、立場や慣習、場の空気といった“見えない圧力”によっても成立してしまいます。 人権とは、知識の問題でもあります。
知らないことが問題なのではなく、知ろうとしない態度が組織のリスクを増幅させます。誰かの違和感や痛みに鈍感でいることは、無関心ではなく、構造的な「学習の放棄」と言い換えることができます。組織としての成熟度は、「どれだけ多くの声を聞けるか」に比例します。
そして、集団浅慮の温床となるもう一つの構造が「心理的安全性の欠如」です。心理的安全性が欠けた場では、誰もが感じているはずの違和感が表に出ることはありません。反論や異論は「空気を乱す行為」とされ、「ノリの悪い人」「扱いにくい人」というレッテルを貼られることで、自然と排除されていきます。
そうして都合のいい情報だけが共有され、組織は自らの誤りに気づく機会を失っていきます。 心理的安全性のない組織では、誤った判断が「全会一致」という名のもとに推し進められます。責任の所在は曖昧になり、結果として組織の学習機能が損なわれます。過去の過ちが記録されることなく、繰り返されるだけの閉鎖的な構造が維持されていくのです。
本来、心理的安全性とは、異なる意見や視点が自由に交わされる空間を意味します。発言が遮られず、軽視されず、真摯に受け止められる環境の中でこそ、思考の質は高まり、組織も判断を間違えなくなります。
価値観のアップデートも、社会の変革も、すべては「無知ではなくなる」ことからはじまるのだ。知らないことは恥ではない。知ろうとしない自分を、恥ずべきなのである。そしてすべての他者を「尊重」する姿勢こそが、「知ろうとすること」の第一歩になると、僕は思っている。
少数派の異論や批判は組織を壊すのではなく、強くするメッセージと捉えるべきです。 空気を読むことが美徳とされた時代から、空気そのものを問い直す時代へと変わりつつあります。
企業の和を乱さないことに価値があった時代から、異質な視点を取り込むことが求められる時代へと、確実に時代は移行しています。形式的な多様性ではなく、実質的な違いを尊重し、対話を通じて新たな知を創出する組織こそが、これからの時代に適応していく力を持ちます。
著者は、こうした組織の根本的な構造に鋭く切り込み、ボーイズクラブによる同調圧力という見えない支配の実態を言語化しました。本書の意義は、過去を批判することではなく、同じ誤りを繰り返さないために、どのような思考と環境が必要なのかを提示した点にあります。
組織文化の変革は、制度やメッセージ開発だけでは実現しません。パーパスの共有、日々のコミュニケーション、上司の問いかけの質、そして何より、誰の声も置き去りにしないという意志こそが変化の原動力になります。
異なる意見に耳を傾ける態度、多様な立場を尊重する姿勢、それらの積み重ねが、集団浅慮のリスクを小さくし、組織の知性と倫理を育てていきます。
未来は、空気の質に宿ります。問いかけの多い組織ほど、誤りに気づきやすく、変化にしなやかです。多様性・人権・対話という価値が、組織の“競争力”と“正しさ”の両方に直結する時代が、すでに始まっています。



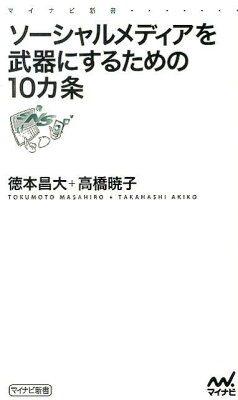











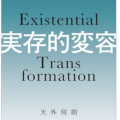


コメント