財務省亡国論
高橋洋一
あさ出版
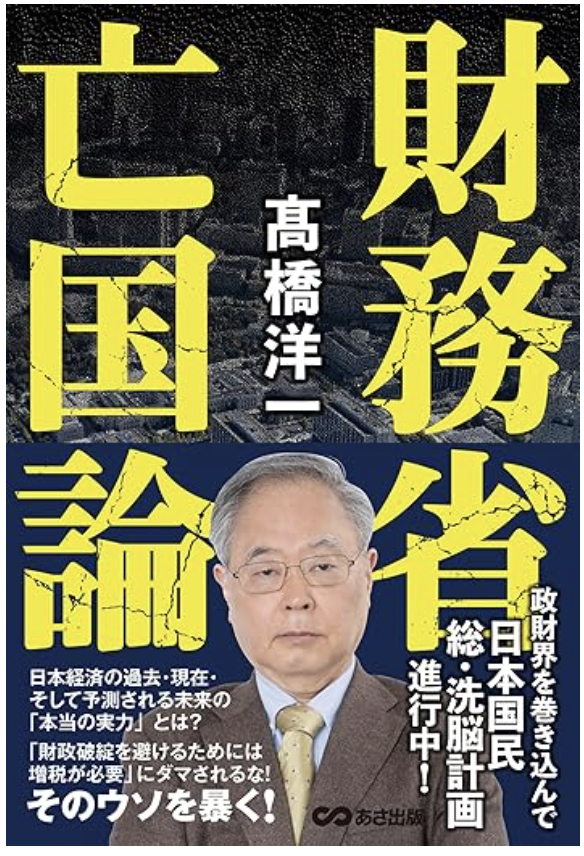
財務省亡国論(高橋洋一)の要約
財務省は増税による予算配分権を活用して、各省庁への天下りを確保するという利権構造を築き上げています。この仕組みは日本の行政システムの根本的な歪みを示しています。財務省が主張する財政規律という考え方を無批判に受け入れるのではなく、真に国民の利益となる経済政策を実現するため、政治家やメディアは財務省による洗脳から脱却する必要があります。
財務省の目的は自らの権益拡大?
財務省は「スキあらば増税したい!」人たちの集まりで、本心からは財政再建や経済成長のことなど考えていない。(高橋洋一)
財務省の組織的な行動が日本の経済成長を阻害していると高橋洋一氏は指摘します。著者の高橋氏は財務省での勤務経験を基に、その内部メカニズムを詳細に解説しています。
財務省が増税政策を推進する真の目的は、表向きの財政再建ではなく、自らの権限と影響力の拡大にあります。増税による税収増加分は「財務省の功績」として扱われ、その配分権限を通じて各省庁への影響力を強化する手段となっています。
これに対し、経済成長による自然な税収増は財務省の直接的な貢献とは見なされないため、財務省にとって望ましくない状況となります。 この構造の中で、予算配分を受けた省庁や大企業はその見返りとして、所管する法人への財務省官僚の天下りを受け入れることになります。大企業の社外取締役や顧問になることは、高級官僚の特権になっています。
さらに、増税時に設けられる例外措置も、将来の天下り先確保を視野に入れた戦略的な判断によって決定されると高橋氏は指摘します。
財務省は自らの利権構造を守るため、マスメディアを通じて経済政策の議論を意図的に複雑化しています。特に「プライマリー・バランスの黒字化」を国民経済の絶対条件のように掲げていますが、高橋氏はこれを財務省の巧妙な欺瞞だと指摘します。
プライマリー・バランスの黒字化を追求する真の目的は、財務省の権益拡大にあります。「財政健全化」を名目に増税を正当化し、その予算配分権限を通じて各省庁への影響力を強化する仕組みが巧妙に構築されているのです。 さらに高橋氏は、日本のプライマリー・バランスの計算方法自体に重大な問題があると指摘します。
海外では中央銀行も含めた財政収支を見るのが一般的であり、日本も日銀を含めたパブリックセクターバランスシートで収支を検証すべきです。この視点を用いた純資産は日本はイーブンになり、先進国に比べても遜色がなくなると言います。
また、国の借金だけを強調し、保有する資産価値を評価に入れない現在の手法は、財政状況を実態以上に悪く見せかける効果があります。経済が成長していれば、プライマリーバランスが少しぐらい赤字でも問題ないのです。
マスメディアは財務省のこうした論理を無批判に受け入れ、財政規律や増税の必要性を世論に訴え続けています。これは財務省による「洗脳」がメディアを介して国民の思考を制限している実態を示しています。
高橋氏は、このような財務省とメディアの共犯関係を明確に指摘し、その虚構性を暴き出すとともに、より実態に即した財政状況の評価方法の必要性を提言しています。
財政政策をどう変えればよいか?
財務官僚は、じつのところ、本当には財政再建のことなど考えていないのだ。歳出権という自分たちの権益を広げるために、増税を説いているだけなのである。だからそれを覆してしまう「経済成長による段階的な税増収」などもってのほかとなり、増税路線まっしぐらになる。増税なら責任は政治家にとらせることができるし、カウントされる税額が増えるぶん歳出権が拡大する。とにかく「増税」「天下り」。国民の生活をよりよくすることは二の次どころか、はなから頭にないので。
高橋氏は、経済問題は本来シンプルに理解できるものであり、不必要な複雑化を排除することで真実が見えてくると主張しています。 このような財務省主導の政策決定メカニズムが、日本の経済成長を阻害する要因となっていると考えられます。
実際、過去30年間における先進国の中で、日本だけが顕著な経済成長を遂げられていない現状は、この構造的問題と密接に関連していると指摘されています。 財務省出身者である高橋氏の指摘は、内部事情に精通した者からの告発として重要な意味を持ちます。
特に、増税政策と予算配分、天下りの連関構造は、日本の行政システムにおける根本的な課題を浮き彫りにしています。 この問題の解決には、行政システムの透明性向上と、政策決定プロセスの見直しが不可欠と考えられます。国民の利益を最優先する行政組織への改革なくして、日本経済の本格的な成長回復は困難であると言えるでしょう。
財務省の主たる関心は歳出権という自らの権益の拡大にあり、増税の推進はその手段として位置づけられています。経済成長による自然な税収増は財務省の貢献とは見なされないため、むしろ避けるべき状況とされ、その結果として増税路線が強く推進されることになります。
増税政策であれば、その責任を政治家に転嫁でき、増加する税収に応じて財務省の歳出権も拡大します。このように「増税」と「天下り」が財務省の行動原理となり、国民生活の向上という本来の政策目標は軽視されている実態が浮かび上がっています。
このような状況下で、国債発行を巡る議論について、経済政策と道徳的観点から多角的な考察が必要とされています。国債発行を単純に「悪」とする考え方は、個人の借金と国の借金を同一視する誤った認識に基づいていると高橋氏は指摘します。
個人の借金は将来の返済負担が確実に生じますが、国債発行による政府の資金調達は、適切に運用されれば経済成長と雇用創出をもたらす投資的な性格を持っています。 現在の低金利環境下では、日本銀行の金融政策だけでは経済刺激効果が限定的となっています。
このような状況下で、国債発行を通じた財政政策の活用は、雇用創出という具体的な成果をもたらす可能性が高まります。日本銀行が民間金融機関から国債を購入することで得られる利子収入は、国庫納付金として政府に還流し、これが政府支出を通じて経済全体に波及効果をもたらすのです。
公共投資に対しては「ハコモノ行政」という批判が常につきまといます。しかし、その投資が雇用を生み出し、地域経済の活性化につながるという側面も見逃すことはできません。重要なのは、単純に投資を否定するのではなく、社会的便益と費用を慎重に比較考量し、より効果的な財政支出を選択することです。
経済政策の本質は、国民生活の向上と雇用の確保にあります。低金利環境下での国債発行は、適切に活用されれば、これらの政策目標を達成するための有効な手段となり得ます。
重要なのは、財政政策の効果を客観的に評価し、真に国民のための政策選択を行うことです。 このような観点から、国債発行を通じた積極的な財政政策は、適切に運用されれば、むしろ道徳的にも望ましい選択になります。そのために、財政政策の効果を常に検証し、より効率的な資源配分を実現することです。
財務省の主張する財政規律論に安易に追従するのではなく、真に国民のための経済政策を追求していく必要があります。政治家やメディアが洗脳から抜け出すことが重要だと思います。





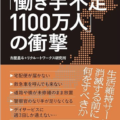


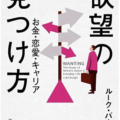









コメント