底が抜けた国 自浄能力を失った日本は再生できるのか?
山崎雅弘
朝日新聞出版
底が抜けた国 自浄能力を失った日本は再生できるのか? (山崎雅弘)の要約
日本社会は、自浄作用を失い、完全に「底が抜けた」状態に陥っています。政治の腐敗、財界との癒着、軍備拡張、メディアの機能不全が連鎖し、民主主義の基盤が揺らいでいます。説明責任の欠如や不正の放置が常態化し、国民の無関心がそれを助長しています。私たちはよりよい未来のために、問題を直視し、社会の健全性を取り戻す努力を重ねる必要があります。
完全に底が抜けた日本の政治
権力を持つ者が、公益にも配慮してその力を抑制的に使うか、それとも私益だけを追求してフルに自分のためだけに使うかは、文明国と野蛮国の違いでもあります。 今の日本は、その意味では完全に野蛮国の領域に入ったと言えます。(山崎雅弘)
現代日本の社会は、自浄作用を失い、あらゆる分野で深刻な問題が複雑に絡み合う「底が抜けた」状態に陥っていると山崎雅弘氏は指摘します。政治の腐敗、大企業偏重、軍備の増強、報道機関の劣化、さらには国民の無関心といった要素が連鎖的に作用し、社会全体の健全性が著しく損なわれています。
著者は、この状況を歴史的観点から読み解き、公的記録やデータを基に分析し、警鐘を鳴らしています。 現在、日本では自民党政治家の裏金問題、それに伴う脱税、軍備偏重、統一教会問題、貧富の格差拡大、自己責任論の浸透など、多くの課題が山積しています。これらは一見すると個別の事象のように見えますが、実際には密接に関係し合い、社会全体の機能不全を引き起こしているのです。
特に、専守防衛の放棄と軍備拡張を推し進める政府の動きは、「戦争ができる国」へと日本を変貌させる大きな要因となっています。かつて日本が掲げていた「平和国家」としての姿勢は、ここ十数年の間に急激に変容し、戦後日本の基本方針が揺らいでいるのです。
さらに深刻なのは、政治家の汚職や不正が発覚しても、実質的な責任を取らず、問題がうやむやなまま終息してしまうケースが常態化していることです。かつては、政治スキャンダルが発覚すれば議員辞職や逮捕といった形で何らかの責任を問われることがありましたが、近年ではそうした事例が減少し、権力を持つ者が責任を逃れる構造が確立されつつあります。
その結果、政治の透明性は低下し、不正行為がエスカレートしても問題視されにくい社会になってしまいました。 このような腐敗構造が深刻化する要因の一つに、権力を監視するべき機関の機能不全があります。民主主義国家において、検察とジャーナリズムは特定の権力者やその取り巻きの「私益」ではなく、国民全体の利益、すなわち「公益」を守る役割を担っています。
しかし、現在の日本では、検察による自浄作用は大きく失われており、ジャーナリズムも本来の役割を果たせていません。検察が特定の権力層に対して甘い姿勢を取り続け、権力犯罪を厳正に裁かない状況が続くことで、法の公正性が損なわれています。
同時に、ジャーナリズムも政治的圧力や経済的利益によって独立性を失い、政府のプロパガンダを垂れ流す機関へと変質してしまったのです。
この構造の根底には、政界と財界の癒着があります。企業献金や政治資金パーティーを通じて、財界から政界に多額の資金が流れ込み、それと引き換えに政府は大企業や富裕層を優遇する政策を推し進めています。その結果、企業経営者や株主の利益が優先される一方で、一般国民の生活向上は後回しにされ、格差が拡大していきます。
このような政財界の利権構造は、発展途上国ではよく見られるものですが、日本も同じ道をたどりつつあると言えるでしょう。 さらに、この癒着構造にはメディアも深く関与しています。もはやこの観点から言えば、悲しいことに日本は先進国とは言えません。
ジャーナリズムも底がぬけた?
記者会見における誰弁の常態化は、自民党政権の責任であるのと同時に、本気で権力者に「説明責任」を求めなくなった報道記者や報道企業の責任でもあります。「説明を差し控える」と言われて黙って引き下がるような、報道人としての責任感も職業的衿持も持たない政治記者ばかりになったことで、権力者は自分に不都合な事実については、どこまでも説明を拒絶できるようになってしまいました。
新聞やテレビ局などの大手メディアは、政府の意向に沿った報道を行い、政権にとって不都合な情報を十分に伝えなくなっています。政治的圧力だけでなく、経済的見返りとして広告費や消費税の優遇などから、本来の監視機能を果たせなくなっているのです。
その結果、国民は重要な情報を得る機会を奪われ、知らぬ間に政府の意図する方向へと誘導されています。民主主義国家ではメディアが「第四の権力」として政府を監視し、健全な議論を促す役割を果たしますが、現在の日本ではその機能がほぼ消滅していると言っても過言ではありません。 このような状況が長期化することで、政治報道の現場でも大きな変化が生じました。
かつては記者が厳しい質問を投げかけ、政治家が説明責任を果たすことが求められていましたが、現在では「説明を差し控える」というフレーズが常套句となり、政府が情報を開示しないまま終わるケースが増えています。政治家は記者の質問を軽視し、まともに答えなくても問題にならないという風潮が蔓延しています。
本来であれば、報道記者はそのような態度を批判し、厳しく追及するべきですが、現在ではそうした機能が完全に失われています。その結果、国会での議論の質も著しく低下し、論理的な討論が成立しなくなっています。 こうした現状に危機感を持つ人は決して少なくありません。
しかし、政治や社会の構造は簡単に変わるものではなく、多くの人々が「何をしても無駄だ」と感じ、諦めのが広がっています。しかし、歴史を振り返ると、権力の腐敗が極限に達したとき、必ずそれに対抗する動きが生まれ、大きな変革をもたらしてきました。重要なのは、社会の健全性を取り戻すために、少しずつでも声を上げ、問題に向き合う姿勢を持ち続けることです。
山崎氏は、日本の現状を歴史的な視点から分析し、過去の教訓を忘れずに未来を見据えることの重要性を説いています。歴史の中で、多くの国々が権力の暴走によって社会の機能を失い、重大な過ちを犯してきました。戦前の日本においても、軍部の暴走とそれを抑えられなかった政治、メディアの責任放棄が国を破滅へと導きました。
まさにこの10年で日本の民主主義は後退しています。同じ過ちを繰り返さないためには、歴史を学び、現在の問題を直視することが不可欠です。 私たちは、今の日本社会を見渡して「このままではいけない」と感じています。
倫理が崩壊し、権力が暴走し、不正が常態化した国を次世代に引き継ぐわけにはいかないと著者は言います。手遅れになる前に、失われた自浄作用を取り戻し、社会を健全な状態へと再生させるための取り組みを始めるべきです。国家の衰退を防ぎ、より良い未来を築くために、私たち一人ひとりができることを考えていく必要があります。まずは、権力者を監視し、しっかりと選挙に行くことが重要です。
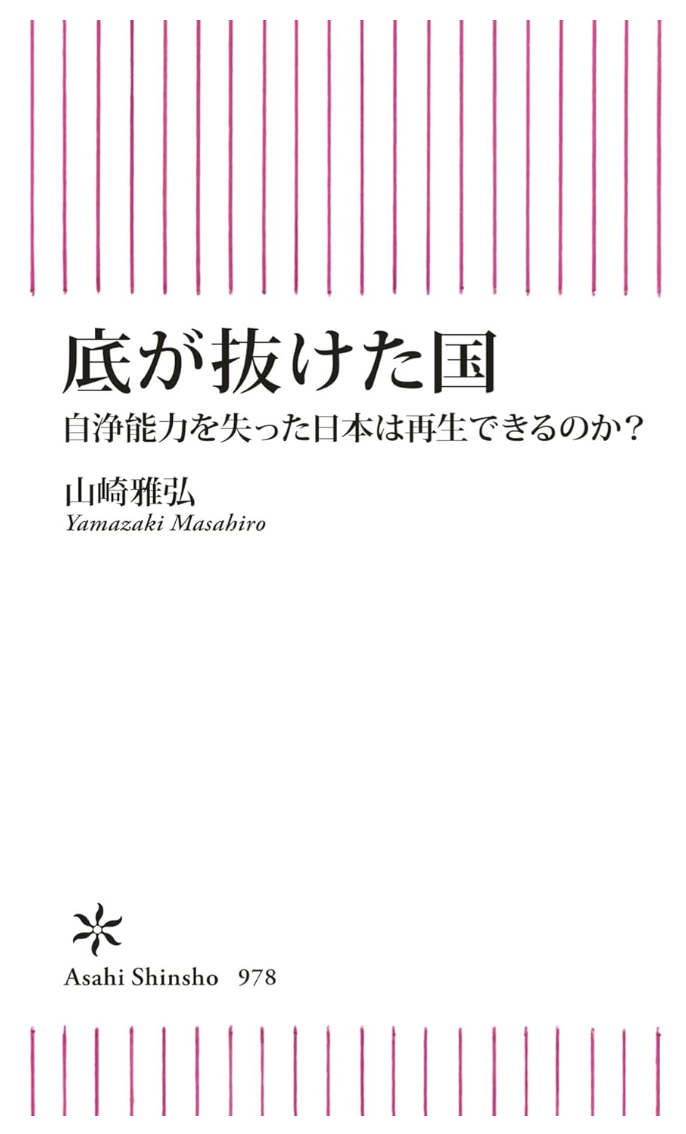










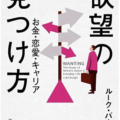
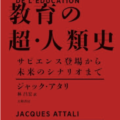





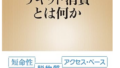
コメント