失敗できる組織
エイミー・C・エドモンドソン
早川書房
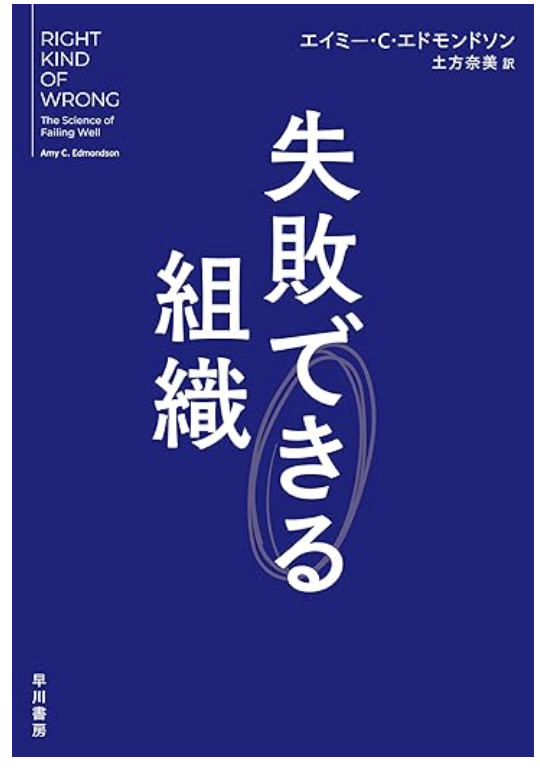
失敗できる組織 (エイミー・C・エドモンドソン)の要約
失敗はすべてが悪ではなく、学びや成長の契機となるものです。「賢い失敗」「基本的失敗」「複雑な失敗」と分類し、適切に向き合うことが重要です。心理的安全性や質の高いフィードバックが、失敗を共有し活かす土台となります。自己認識・状況認識・システム認識を磨き、前向きに失敗と共に歩む姿勢が、個人と組織の進化を支えます。
失敗できる組織がイノベーションを起こせる理由
上手に失敗に対処して、その恩恵を享受する。そしてもう一つ重要なこととして悪い失敗をできるだけ回避する。そのための第一歩は、失敗はどれも同じではないと理解することだと私は考えている。(エイミー・C・エドモンドソン)
失敗は、できれば避けたい——これは多くの人に共通する本音でしょう。私たちは無意識のうちに、失敗=マイナス評価という図式に縛られています。特に、成果や効率が重視される社会では、「失敗」は計画のズレや能力の欠如として扱われがちです。
しかし皮肉なことに、変化が速く、不確実性の高い時代においてこそ、私たちは失敗とどう向き合うかを問われているのです。 実際、真に価値のある学びや革新は、成功の連続からではなく、試行錯誤の過程から生まれます。
挑戦には必然的にリスクがつきものですし、そのリスクが「失敗」というかたちで現れることは避けられません。だからこそ、失敗を排除するのではなく、「活かす」ことにシフトする必要があります。そこにこそ、持続的な成長への道筋があるのです。
「心理的安全性」という言葉を有名にしたエイミー・エドモンドソンは失敗できる組織の中で、失敗を「望ましい結果から逸脱した結果」と定義しながらも、その背景にあるコンテクストと、そこから得られる学びに注目します。すべての失敗が悪いわけではありません。重要なのは、その失敗が何を意味し、どのような形で次に活かせるのかという視点を持つことです。エイミー・エドモンドソンの関連記事
著者は、失敗を「賢い失敗」「基本的失敗」「複雑な失敗」という3つのタイプに分類します。この分類によって、私たちは失敗の性質や原因、そして対処法をより深く理解することができます。
まず、「賢い失敗」とは、予測が難しく、新たな知見や発見をもたらす失敗です。これは、新しい挑戦やイノベーションの過程で避けがたく発生するものであり、長期的な成長には不可欠な要素です。
次に「基本的失敗」は、既知のルールや手順からの逸脱によって生じる、回避可能な失敗です。これは個人の注意不足や準備不足に起因することが多く、再発防止のためには仕組みづくりや教育が求められます。
「複雑な失敗」は、複数の因果が絡み合い、予測しづらい状況下で起きる失敗です。チームや組織全体の構造やコミュニケーションのあり方が影響しており、全体最適の視点で見直す必要があります。 これらの分類は、失敗を単なる結果ではなく、改善と成長の素材として扱ううえでの道しるべになります。
そして、それを可能にするのが「心理的安全性」の高い組織環境です。 心理的安全性が確保された場では、人は失敗を恐れずに発言し、実験し、フィードバックを受け取ることができます。失敗は隠されるのではなく、共有され、次なるステップの糧となるのです。
新しいことに挑戦する際には、私たちは意識的に困難を選び取ることになります。当然、そこには失敗のリスクが伴います。しかし、挑戦と失敗を重ねるうちに、私たちは「失敗に慣れる力」を身につけていきます。リスクを取れば取るほど失敗はむしろ増えますが、そこには2つの重要な効用があります。
そこには2つ利点がある。第1に、恥ずかしい思いをしたところで死にはしないと気づくことだ。第2に、失敗筋が鍛えられ、失敗をするたびに痛みは和らいでいくことだ。多くの失敗を経験するほど、それでも問題ないと気づく。問題ないどころか、成長できる。
この姿勢を体現しているのが、イノベーション企業IDEOの文化です。同社のモットーは「早く成功するために速く失敗しろ」。です。元CEOのデビッド・ケリ氏は、社員に対して「早く失敗しよう」と明るく声をかけていました。これは、失敗を排除するのではなく、価値ある学びとして組織の中に組み込もうとする姿勢の表れです。
実際、どれほど才能ある若手であっても、失敗に対する不安や恥の感情によって行動が制限されることは少なくありません。IDEOのアプローチは、こうした心理的障壁を取り払い、挑戦のハードルを下げることに重点を置いています。
リーダーに求められるのは、失敗を排除する姿勢ではなく、それを前進のための自然なプロセスとして受け入れる企業文化を育てることです。失敗を許容するだけでなく、そこから学びを引き出し、次の挑戦につなげる空気をつくること。そうした環境からこそ、本質的な創造性やイノベーションは芽吹いていきます。
失敗に対するマインドセットを変えよう!
心理的安全性は上手に失敗する技術においてとても重要な役割を果たす。心理的に安全な環境であれば、手に負えない状況に陥ったときに助けを求めることができる。それは未然に防げる失敗をなくすことにつながる。ミスを報告し(その結果、ミスを認識し、修正することができ)、さらに悪い結果を回避することができる。また新たな発見を生み出すために、熟慮のうえで実験することが可能になる。
失敗に対する恐れが、組織文化において大きな障壁となることもあります。失敗を報告できない雰囲気があると、小さな問題が見過ごされ、やがては大きなトラブルに発展します。私たちは失敗を恥と捉えるとそれを隠そうとします。しかし、それでは、失敗を改善できません。だからこそ、透明性とオープンな対話を可能にする文化の構築が不可欠です。そこには心理的安全性が欠かせないのです。
「私はミスをした」と素直に認めること。そして、そのうえで「次に同じミスをしないために、今回の失敗から何を学ぶべきだろう」と自問してみる。たったそれだけで、私たちと失敗との関係は、驚くほど健全なものへと変わっていくと著者は言います。
また、質の高いフィードバックも欠かせません。フィードバックは、具体的で実行可能であること、そして経験やデータに裏打ちされた信頼性が重要です。単なる感想や評価に留まらず、行動につながる知見として機能させるためには、双方向のコミュニケーションが欠かせません。
失敗を犯すのは、私たちの本来の姿だ。自己受容は勇気ある行為と見ることもできる。自分に対して正直になるのは勇気が要ることであり、それは他者に対して正直になる第一歩だ。失敗は人生の一部なので、失敗するかどうかではなく、「いつ」「どのように」失敗するかが重要だ。
失敗は人生において避けられない現象です。重要なのは「失敗するかどうか」ではなく、「いつ」「どのように」失敗するかです。私たちは今、上手に失敗する技術を学ぶ必要があります。基本的な失敗は可能な限り予防し、複雑な失敗には備えを。そして、賢明な失敗には意欲的に取り組む姿勢が求められます。
失敗から学ぶためには、以下の3つの認識領域を意識的に磨くことが大切です。
・自己認識
自分の強み・弱み、価値観、思考や感情のパターンを理解する力。なぜその選択をしたのか、どんな思い込みが影響したのかを省みることが、失敗の本質的理解につながります。自らの至らない部分を認める力をや姉妹なしょう。
・状況認識
自分を取り巻く環境や状況を正確に把握する力、状況を認識する力を身につければ、リスクコンロールができるようになります。状況に応じて、警戒心を高めたり、リラックスできるようことで、正しい選択ができるようになり、失敗を防げます。過去の失敗を振り返ることで、より良い意思決定が可能になります。
・システム認識
システム思考は私たちに、品質、安全性、あるいはイノベーションといった組織の目標を実現するのに役立つシステムをデザインする力を与えてくれる。
システム認識を習得する第一歩は、部分に集中しがちな人間の自然な傾向に抗い、意識的に「全体を見る視点」を養うことです。たとえ一瞬でも視野を広げ、思考の境界を引き直し、より大きな全体像と構成要素同士の関係性に目を向けることが重要です。
しかし、現在の教育や職場環境は、専門性の習得や部分の分析に重きを置く一方で、部分と部分のつながりや相互作用に目を向けることの重要性は見過ごされがちです。だからこそ、システムに目を向け、その構造を理解し、活用することで回避可能な失敗を減らそうとする姿勢は、今こそ意識的に学ぶべき能力といえるでしょう。
また、システム思考は私たちにとって心理的な支えにもなります。なぜなら、身の回りで起きるすべての失敗が、自分一人に責任があるわけではないと気づかせてくれるからです。これは決して責任逃れを意味するのではありません。むしろ、自分が複雑なシステムの一部であり、その中には予測もコントロールもできない要素があるという現実を受け入れることが大切なのです。
この視点は、近年の「患者の安全性向上」ムーブメントでも大きな役割を果たしてきました。医療従事者がミスを犯したとき、あるいは何か異常を感じたときに、すぐに声を上げる文化が定着しつつあるのは、システムとしての現場を理解する姿勢が広まった成果ともいえます。
システムを正しく理解することは、失敗を防ぐだけでなく、品質や安全性、さらにはイノベーションといった組織の目標を実現するための基盤にもなります。システム思考は、私たちにより良い仕組みをデザインする力を与えてくれるのです。
このように失敗が当たり前だという姿勢を持つことで、逆境からの回復力が高まり、創造性やイノベーションが促進され、失敗から深い学びを得られるようになります。そして、自分の弱さを受け入れられる人は他者にも寛容になり、信頼関係の構築にもつながります。
成功だけでなく失敗も含めて自分を受け入れることで、外部の評価に左右されない安定した自己価値感が育まれるのです。 直感に反するようですが、失敗はしばしばチャンスを引き寄せます。なぜなら、失敗は自分に足りない能力を明確にし、本当に情熱を注げる対象を再確認する機会にもなるからです。
失敗は終わりではなく、新たな問いと挑戦の始まりです。私たちが失敗から目を背けず、そこから学び、再び立ち上がるとき、未来への扉は大きく開かれるのです。
失敗を前向きに捉えるマインドセットは、子ども時代にこそ育むべきものだと著者は言います。完璧を求めすぎると、子どもは失敗を恐れ、新しい挑戦を避けるようになってしまいます。しかし、転ばずに自転車にすぐに乗れる子どもはほとんどいません。
失敗は成長のプロセスであり、避けるべきものではなく学びのきっかけです。親や教師が「失敗は恥ずかしいことではない」と伝え、安心して挑戦できる環境を整えることで、子どもは健全な自己肯定感と成長マインドセットを身につけていきます。
私自身、大学で失敗の重要性を学生に伝える立場にあるため、著者の主張には深く共感しています。 本書の結論は明快です――失敗は避けるべき過ちではなく、適切に扱えば学びと成長の源になるということ。
大切なのは、すべての失敗を一括りにせず、「意味ある失敗」と「避けられる失敗」を見極め、その違いを理解したうえで前向きに活用する姿勢なのです。「失敗を讃える」という文化を作れる組織が、真に強い企業であることを本書で実感できました。





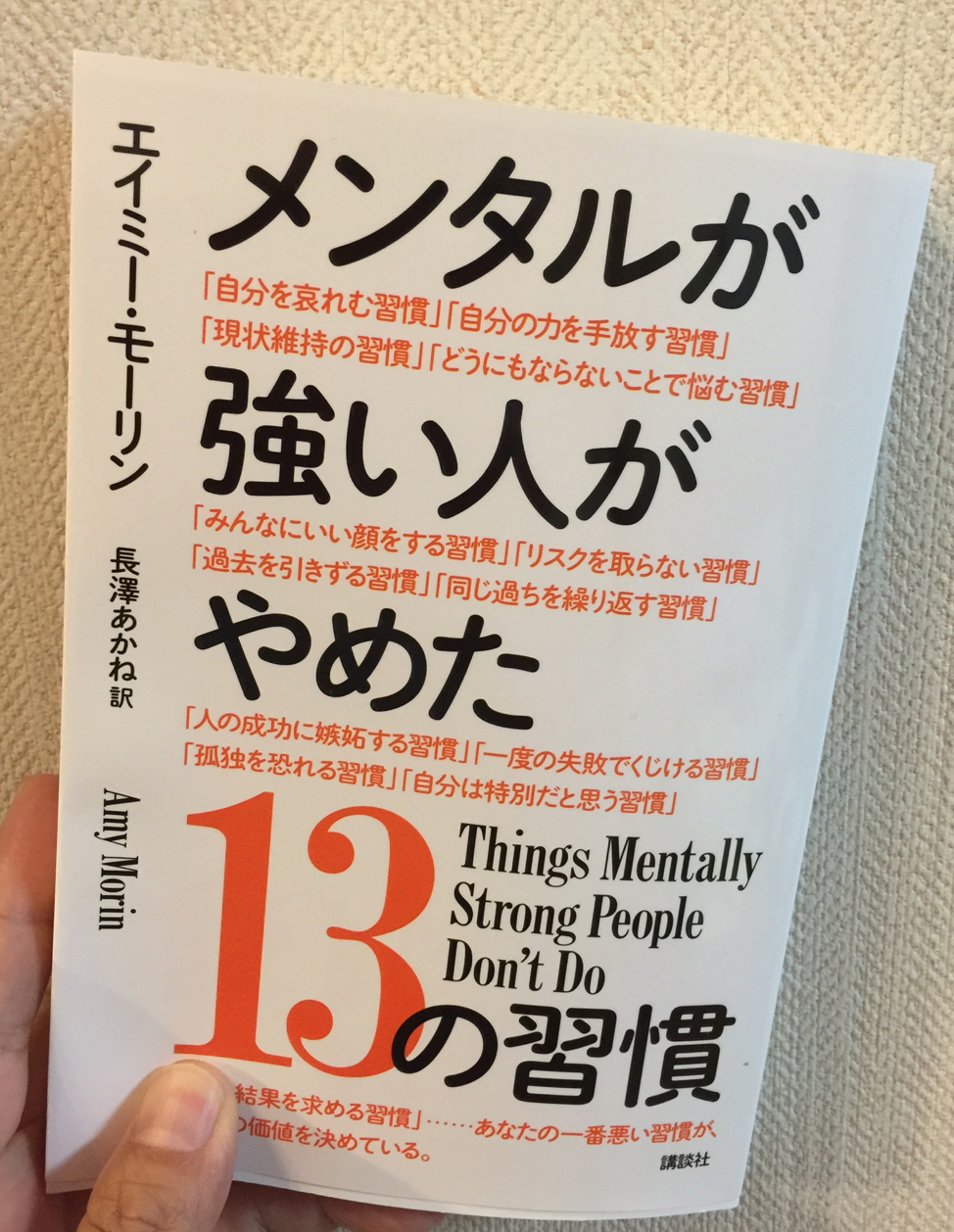








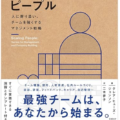



コメント